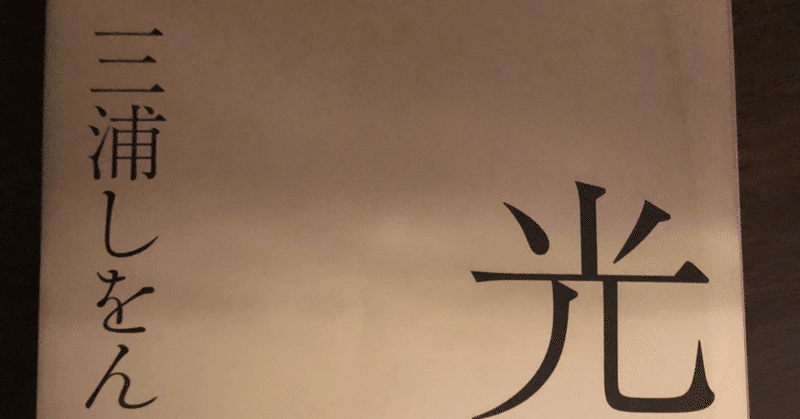
【読書レビュー】三浦しをん『光』
通勤電車で本を読むのが日課だ。片道45分程度、往復で1時間半の道のりを毎日読書にあてていることになるから、一般的な社会人よりも本に触れる時間は長いはずだ。
noteを使い始めて何回か自分の体験や考えていることを投稿はしてみたが、人様に披露できるだけの大した経験や思考は持ち合わせていないので、既にネタ不足に悩んでいる。そこで、どうせ通勤時間に本を読むのなら、中でもいいと思った本を自分なりにアウトプットしていろんな人に見てもらうのもいいかなと思うので、これからは自分のペースで細々とレビューをしていきたいと思う。
(誠に勝手ながら)三浦しをんの代表作は、箱根駅伝を題材にした青春小説『風が強く吹いている』だろう。高校時代に読んで面白かった記憶があるが、その後いろいろあって陸上競技にトラウマを抱えるようになって以来「陸上=風が吹いている=三浦しをん」という我ながらよくわからないアナロジーをつくり出し、彼女の作品からはかなり距離を取っていたのだ。また彼女の作品を読むきっかけがほしかったところだが、ちょうどある読書家の友人が最近『光』を私に薦めてくれたので読んでみたものである。
さて、『光』のあらすじである。ある離島に生まれ育った信之は、中学の同級生で美しい容姿を持った美花と交際していた。同じく島には小学生の輔が暮らしていたが、彼は父親からの酷い暴力を受けていた一方で、信之を強く慕っており、行く先々に付いて来るのだった。
ある日、大地震が発生し、それに伴う津波の被害で、信之、美花、輔、輔の父、観光客のカメラマンの男と長く島に住んでいる老人の6人を残して島民は全員が死亡してしまう。復旧活動が続く中、とある日の夜に美花がカメラマンの男に犯されている現場を信之は目撃し、美花の目の前で怒りの末に殺してしまう。しかし大災害をきっかけに島から人間は消え、信之の罪はうやむうやのままに終わってしまったのだ。
時間は進み、信之は妻と一人娘とともに真面目に社会生活を送っていた。美花は篠原未喜と改名し、女優として活躍してた。一方の輔は工場で肉体労働をして生計を立てていた。3人は三種三様の生き方をしており、互いの関係性も失われていた。ただ、輔は信之の殺人の証拠となる写真を秘密裏に現像し、ずっと所有していたのだ。輔は写真の存在をちらつかせながら再び信之への接触を図る。
…ここまで書いてしまったが(wikipediaをちらちら見ながら)、この後は盛大なネタバレになる気がするので、あらすじはここまで。実際は輔を虐待していた父も大きく物語に関わってくる。
この小説の一番の良さは、通奏低音として流れる人間の「闇」だ。感情に任せてカメラマンを殺し、その後は平然と日常生活を送る信之、それを冷たく傍観する美花、二人の過去という弱みをもって信之に迫る輔、それぞれに「闇」が潜んでいる。個人的には輔が最も恐ろしい。何をするかわからない不気味さがあり、読者側としても本人の思考をうまく汲み取ることができない。「何を考えているのかわからない人」というのは、いつ何時でも怖い。
恐らく三浦氏はこの小説を通して「人間の闇・怖さ」を描きたかったのだろうと思う。人は時として殺めておきながら「バレなければいい」という魂胆で日常生活を送れる冷静な面、目の前で人が殺されるのを傍観できる無関心、表向きはいい顔をしながら裏では人の弱みをしっかり握っている二面性など、人間は様々な闇を抱えているが、それはなかなか日常生活で自覚することがなければ、あるいは人から指摘されることも極めて少ない。『光』はそういった人間の深部に存在する闇を、『光』の中の登場人物にそれぞれ憑依させることによって読者に示しているのではないか。『光』というタイトルに関して、本当は人間の闇を描いているが、闇とは真逆の『光』という言葉を採用している点も、人間の表と裏という二面性を暗示しているように思われる。『光』は映画化もされているのだが、例えば離島の自然を写しながらアップビートでテンポのいい音楽をBGMに使うなど、映像と音楽のミスマッチが所々に見られる。映画のBGMを選択する際も、小説のテーマである「人間の二面性」を表現するため、このような音楽の選択に至ったのだろうと勝手に推察している。
ここまで書いてわざわざ繰り返す必要もないかもしれないが、『光』を読んで心が晴れ晴れすることはまずありえない。読んだ後に苦い疲労感と、心の疲労が蓄積するような負のエネルギーを大量摂取させる小説といえるだろう。読書に心地よい読了感を求める人には絶対にお勧めできない。(私にとっては結構好きな小説だったので、私に勧めてくれた読書家の友人には深く感謝したい)
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
