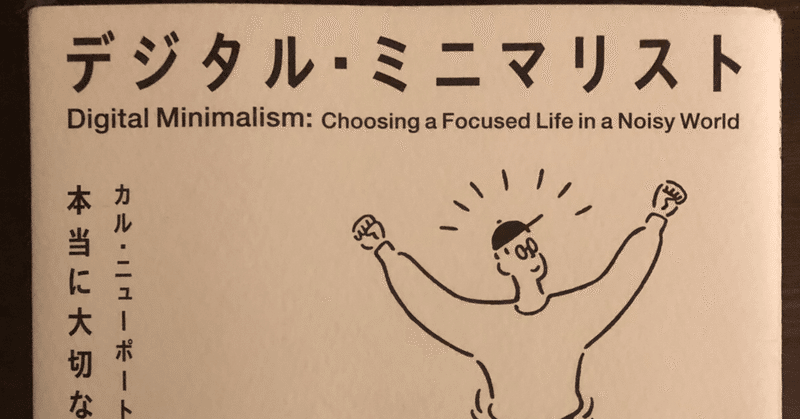
【読書レビュー】カル・ニューポート『デジタル・ミニマリスト』
私が携帯電話(当時はガラケー)を持ち始めたのは、高校入学のタイミングだった。それまで家のパソコンで友人たちとメールのやり取りをしていたのが、ポケットサイズの小さな端末からできるようになり、離れた友人とも常につながっている感触を得たのだった。
高校を卒業し、大学に進学した時にはすでにスマホが世に出始めていたが、実際に私が初めてスマホを手にしたのは大学1年の夏だった。メールのやり取りができるのはもちろん、TwitterやLINEといった各種SNSの利用もスマホの購入を機に始めた。特にTwitterでは、わざわざ連絡を取り合うまでもなく友人や有名人たちの日常が画面上に展開されており、不特定多数の人間の日常生活が共有されている不思議な感覚があった。
スマホの利用を始めて今日まで、SNSの利用を辞めたことはない。社会人になった今は忙しくて見る頻度は減ってしまったが、毎日の生活の中には必ず一定量のSNSを利用している時間がある。そんな私は『デジタル・ミニマリスト』を読むまで、毎日のSNS利用時間はせいぜい1時間程度だろうと高を括っていた。
『デジタル・ミニマリスト』中の調査報告によると、SNS利用者の多くは1日の2時間以上をSNS利用に費やし、スマホの持ち上げ回数は計80回を数えるとのことだ。自分の場合はそこまで多いはずはない、と思ってiPhoneのスクリーンタイムを見ると、残念ながらSNS利用時間は1時間半、持ち上げ回数は60回以上を数えていた。
『デジタル・ミニマリスト』は、現代の情報社会においてソーシャルメディアが人間に与える(あまりにも大きすぎる)悪影響を挙げ、SNS等と適切な距離感を保つためにはどうするかを述べている。SNSは広告で収益を上げる特性上、ユーザーにより長時間かつ高頻度で当該アプリを利用させるために様々な工夫を施している。一見してSNSは離れている人とも連絡を取り合える画期的な発明物に思えるが、その裏では人間の脳幹(無意識の注意力)を乗っ取り、それをお金に換えているのに過ぎないのだ。それだけではない。SNS利用者はオンライン(テキストメッセージ)上のコミュニケーションに慣れてしまい、現実の対面の会話コミュニケーション能力を著しく低下させてしまうのだ。本書はこの点を非常に危惧しており、ここではとても書ききれない量の具体例、研究結果を示して危険の有様を生々と説明している。
上記のような現状を打破するために、題名にある通り、本書では「デジタル・ミニマリズム」というスタンスを提案している。ミニマリズムとは平たく言うと「少ないほど良い」という立場のことだが、「デジタル・ミニマリズム」とは、スマホ利用を極限まで制限し、本当にオンラインでのコミュニケーションが必要な場合にのみ限って利用を許すということである。これはSNSの他ニュースアプリ、ゲーム、天気予報などあらゆる機能をいくつもスマホに求めるようなマキシマリスト的な立場と対極にある。
デジタル・ミニマリズムによると、例えば今まで一日あたり3時間以上もSNS等を利用していたユーザーは、その3時間以上の無益な時間を、他の有益な活動に充てることができる。運動や読書、家族との会話などがその一例だ。日々忙しい毎日を送る現代人にとって、デジタル・ミニマリズムに立つことによって生まれる3時間はあまりにも貴重である。
『デジタル・ミニマリスト』を読み終えたのはこの記事を書く1週間ほど前なのだが、それまで1時間半ほど費やしていたSNSの時間は10分程度に激減した。具体的には、スマホ上からSNSアプリを消し、すべて自宅のパソコン、wifi環境のあるところでしかネットが使えないiPadからしか閲覧できないようにしたのだ。デジタル・ミニマリズムによって私にもたらされた1時間半は、何かと忙しい毎日にゆとりを与えてくれている。
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
