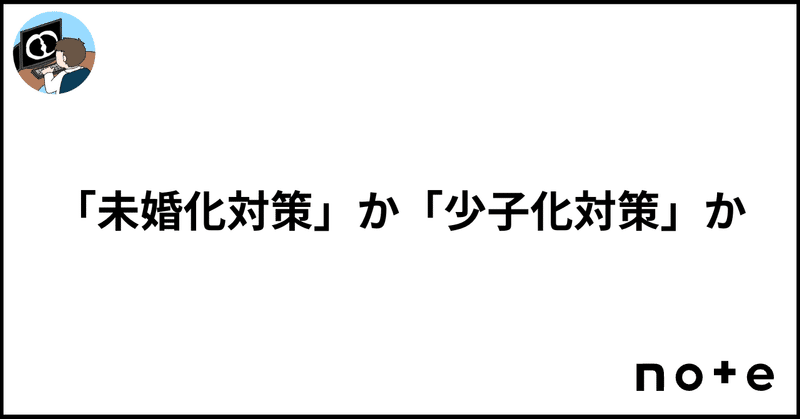
「未婚化対策」か「少子化対策」か
今日は前回の山田昌弘『日本の少子化対策はなぜ失敗したのか?』の感想の補論です。メインの話ではないけれど、ぜひディスカッションしておくべきところかなと思い、回を改めて語ってみます。
山田の主張の特徴は「未婚化」を少子化の主因として指摘されているところです。この少子化トレンドの中でも既婚者家庭の子どもの人数は変わっておらず、既婚者が子どもを産む人数が減ったから少子化になったわけではない。婚外子に寛容でない日本社会においては、このことはすなわち未婚化(非婚化と言うべきかもですが)が少子化の主因であることを示唆するものとなります。
「だからこそ未婚化対策が大事である」という主張は非常に重要で、江草も賛同するものです。
ただ、ちょっと気になったのは「未婚化対策」の重要性を訴えるあまり、山田が時々「少子化対策」の方を無意味であるかのように語ってしまっている場面が見られることです。
つまり、保育所が不足していようが、育児休業がなかろうが、夫が家事・育児を手伝わなかろうが、 2005年くらいまでは、既婚女性は平均 2人、子どもを産み育ててきたのである。
一方で、たとえ保育所を増やし、育児休業制度を作り、夫が家事を手伝うようになっても、「結婚していない女性」にとっては何の意味もない。
これらの事情があるために、欧米型の少子化対策が「空振り」に終わってしまうのである(同じように、東アジア諸国でも空振りに終わるであろう)。
つまり、親の愛情と、世間体意識、そして、リスク回避意識の三者が結合して、少子化がもたらされていると考えられる。
その状況に対して、欧米型の少子化対策、つまり、女性が働きに出られればよい、とにかく子どもが最低限の生活を送れればよい、という形での支援は「無効」なのである。
これが本章の、いや、本書の結論である。
こうした「少子化対策」無意味論は、山田だけでなく独身研究家の荒川和久も同じような語り口の主張をされていたりと、時々目にするロジックです。
書きました。子育て支援政策は少子化対策にはならないという事実を提示しています。そもそも予算をつければ出生数が増えるという簡単な問題ではない。政府といい、この事実を頑なに報道しないメディアといい、まさに戦前の空気に似てきたと感じる。https://t.co/uCIP8YeGQb
— 荒川和久/独身研究家/コラムニスト (@wildriverpeace) January 6, 2023
両人に共通する論拠は、(子持ち家庭を支援する意味での)「少子化対策」が行われてきたが効果がなかったという事実なのですが、これは必ずしも「少子化対策に意味がない」という論理的帰結を導き出せるものではありません。
にも関わらず「少子化対策に意味がない」「少子化対策にならない」かのように語ってしまっていることは、重大なミスリーディングであると考えます。
なるほど、このたび「少子化対策」という介入をしてみたが結果として「少子化が止まらなかった」とした場合、この「少子化対策」に意味がないという仮説は確かに成り立ちますし、検討すべき可能性のひとつであることは否定しません。
しかし、介入したけれど望んだ結果が得られなかった場合、その介入が十分条件でなかったとは言えても、必要条件でなかったとまでは断定できないのです。
めちゃくちゃ極端な例を出しますが、「卵焼きを作ろう」としていて「フライパンを火にかける」という作業をしたけれど「一向に卵焼きができない」という事態を観測したとします。フライパンに卵を溶き入れてないんだから、当然卵焼きはできません。
この時「卵焼きを作りたい時には卵を割って溶き入れる作業こそが重要で、フライパンを火にかける工程は無意味だ」と結論づけられるでしょうか。「いや、卵を溶き入れることもフライパンを火にかけることもどっちも要るでしょ」とツッコミたくなりませんか?
確かに、卵焼きを作る時に卵を溶き入れることも必要ですし、その重要性は誰しも認めます。フライパンを火にかけるだけでは卵焼きができないこともみな賛同するでしょう。その上で、「フライパンを空焚きしたのに卵焼きができなかったから」といってそのフライパンを火にかける工程を無用扱いするのも早計であることも明らかです。
つまり、「フライパンを火にかけること」は卵焼きを作る上で必要条件ではあるけれど十分条件ではないだけなので、フライパンを空焚きした人が憤慨して「フライパンを火にかけること」を否定してしまうのは頭に血がのぼった早とちりなわけです。
もちろん、少子化問題はもっと複雑で不透明ですから、卵焼き作りのように必要条件や十分条件がはっきりと分かるわけではありません。
だから、確かに今までの少子化対策がうまく行ってない事実を踏まえると、少子化対策が真に無効である可能性はあります。
しかしながら、「やってみたけどうまくいかなかった」からといってそれが必要条件である可能性を捨ててしまうことは、「フライパンに火をかけること」を否定するぐらいの早計であり、妥当な主張とは言えません。
医療界では"Absence of evidence is not evidence of absence."という名言がよく語られ(「有効とするエビデンスが存在しないことはその有効性が存在しないことのエビデンスにはならない」的な意味)、何かの介入(治療法)を「無効」とすぐさま断じることには慎重な文化があります。
その医療界の端くれの江草から見ると、両人の「少子化対策は無意味だ」と言わんばかりの語り口には危ういものを感じざるを得ません。
そもそも、山田の提示している「日本型の少子化モデル」は、「結婚と出産育児が直結してる」という日本独自の文化的特徴を重視するものです。「日本では出産後の子どもの経済的安定の保障まで見据えているからこそ若者も結婚に慎重になり未婚化するのだ」という理路だったはずです。
そんな「結婚と出産育児が直結している」のが日本文化であるならば、「未婚化対策」と「少子化対策」も日本においては直結しているはずですし、その両者をことさらに区別する必要も少ないと言えるでしょう。
もちろん、現状、少子化抑制が思うように進んでないことからすると、確かに「未婚化対策」的な早期介入をより強化していくという案を出すのは妥当ではあります。
しかし、その「未婚化対策」の必要性を強調したいがあまり「少子化対策」の部分をわざわざ否定するような言い方をするのは、「未婚化対策」と「少子化対策」が直結している日本においては、「蛇が自分の尻尾を食べている」ようなものでしょう。
山田の少子化モデルを踏まえるならば、「未婚化対策」も「少子化対策」もどっちも強化しましょう、と帰結するのがむしろ自然だと感じます。
もっとも、実を言うと、両人とも文中で「少子化対策も不要であるとは言ってない」というエクスキューズも記してはいるんですよね。
だからといって、保育所整備や育児休業の充実、男性の育児参加促進が不要と言っているわけではない。それだけでは、不十分ということを言いたいのだ。
別に、家族関連支出をなくせと言っているわけではない。それはそれとして必要だが、少子化対策には何も寄与しないという現実をまず知るべきだ。
荒川の方は結局「何も寄与しない」と踏み込んでしまっていて、ちょっと擁護しきれないのですが、山田の方は「不十分」と述べ「あくまで十分条件として否定しているだけであること」を理解されているようにうかがえます。
しかし、ならばこそ、前述の引用部分のように「何の意味もない」「空振り」「無効」という、必要条件であることまで否定するかのようなミスリーディング的表現で「少子化対策」を語ってしまうことには慎重であるべきであったのではないでしょうか。
『日本の少子化対策はなぜ失敗したのか?』は、大筋は同意できる内容であっただけに、こうした表現の違和感はちょっと気になってしまったポイントでした。
「未婚化対策」か「少子化対策」か。
細かいところですが意外と重要なディスカッションと思うので、以上、私見を記してみました。
江草の発信を応援してくださる方、よろしければサポートをお願いします。なんなら江草以外の人に対してでもいいです。今後の社会は直接的な見返り抜きに個々の活動を支援するパトロン型投資が重要になる時代になると思っています。皆で活動をサポートし合う文化を築いていきましょう。
