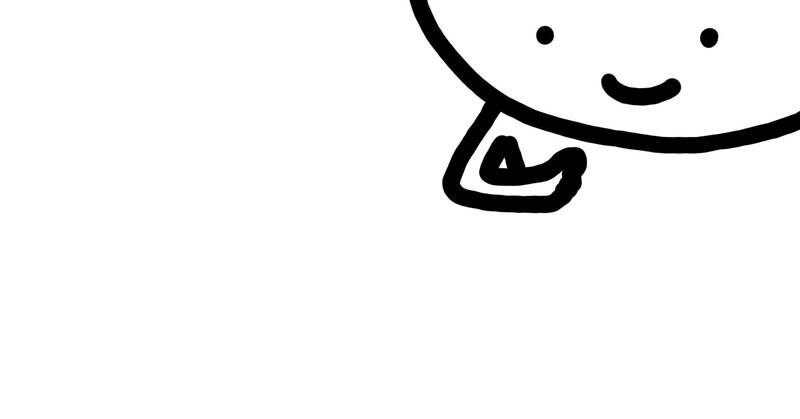
私とは他者である(アルチュール・ランボー)
詩人としてのランボー
アルチュール・ランボーは19世紀のフランスの詩人です。多くの人が名前くらいはご存じなのではないでしょうか?
早熟、天才、神童と言われたものの、詩を書くのをパタッとやめ、その後放浪に出たりとなんだか凄い人です。
私はランボーの詩はちょっとのぞいたことがあるくらいで、よく知りません。読んでも「うーん、何言ってんだかさっぱりわからん」って感じでした。
「私とは他者である」とは詩ではなく、ランボーが書簡に記した言葉です。
私はこの言葉をある方の文章の中で知り、その文章を書かれた方をとても尊敬していたこともあって、これはきっと深い意味があるに違いない、そう思って、長い間心の中にとどめてきた言葉です。
"suis" ではなく "est"
「私とは他者である」この言葉を、心の中にとどめるだけではなく、私はかなり長い間その意味するところを考え続けました。
フランス語では
”Je est un autre"
Jeは”私”、estは英語でいうbe動詞なのですが、実はこれ英語で言うと
”I am(アイ アム)" ではなく”I is(アイ イズ)"となります。
英語で”I am a student .”とは言っても、”I is a student.” とは言いません。
フランス語では1人称のJeに続くbe動詞は本来”suis"となるはずなのです。ところが3人称につくべき”est"というbe動詞が使われている。
つまり、ランボーが言いたかったのは、私=ランボー自身、ではなく私=普遍的で誰にでも存在する私、という意味だったのだと私は解釈しています。
えー、ややこしい話は置いておいて
なんていうんでしょうか、”私”、”あたし”、”ボク”、“オレ”等々なんでもいいのですが、なんだか知らない間にそんな自我を持ってしまってますよね。
性別にしろ、人種にしろ、利き腕にしろ、もうありとあらゆる属性はなんだか知らないうちにそうなっていて...
例えば性別に関していうと、LGBTの方たちって、性別に関してはこの辺の事情に関してとても意識的で立派だなぁと思うんです。
「私は女性に生まれてきたけれど、まぁそれはそれとして」みたな。ちょっと自分の持って生まれた属性を突き放しているような。
これ「私とは他者である」という言葉の意味の一つの面を表していると思うんです。「私は女性で、世間一般では女性という性の概念というのは決まっているみたいだけど、たまたま生まれてきたら社会がそう位置付けていただけで、あたしにはあんまりフィットしないのよね」みたいな感じ。
ランボーは同性愛的嗜好もあったようで、同じ詩人である男性と過ごしていた時期があります。そんな背景を知っているからか、私は今のLGBTの方々とランボーの言葉とを重ね合わせてしまうのかもしれません。
「太陽と月に背いて」の中のランボー
ランボーを描いた映画を2本見たことがありますが、なんといってもデカプリオがランボーを演じた「太陽と月に背いて」がおすすめ。女性の監督の作品だったと記憶しています。なんかこう全体に繊細な感覚が貫いていました。
確かこの映画の中だったと記憶しているのですが、デカプリオ演じるランボーが「詩なんか書いても世の中何も変わらなかった」とつぶやくシーンがあります。
そう、詩を書いたくらいで世の中簡単に変わりません。
現代においてTwitterでリツィートして自身の主張を拡散したり、ネット上で炎上させることはできても、世の中を実質的に変えるのはそうたやすいことではありませんし。
ただ、「私とは他者である」という人間にとって普遍的とも思える命題を、あの若さで見出したのはすごいことだと、そう思います。
なんて言うんでしょう、若くして真理にたどり着いた者が抱く、強烈なもどかしさと孤独といったようなものを感じます。
だから、「詩なんか書いても世の中何も変わらなかった」というのは映画のセリフではあったにしろ、詩をあっさり見限ったランボーの本心ではなかったのか?とそんな風に思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
