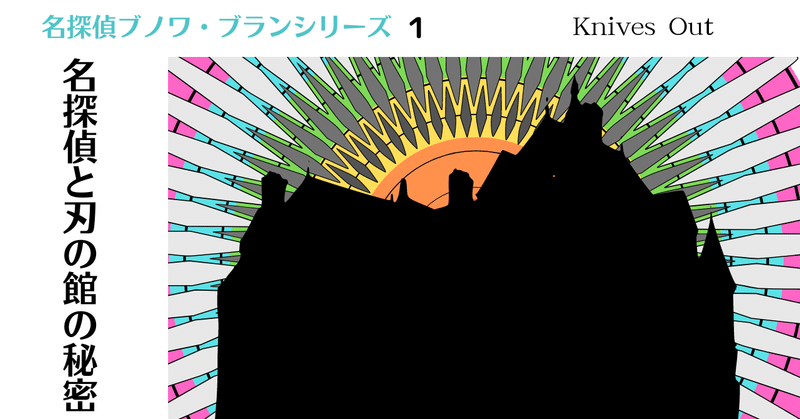
ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密【映画感想】
この記事に興味を持って頂きありがとうございます。まずネタバレなしの感想はこちらです。
■どんな映画?
殺された大富豪と胡散臭い被害者遺族。謎に挑む変わり者で思わせぶりな名探偵などクラシックなミステリーへの愛が溢れた一作。
主人公の名探偵をジェームズ・ボンドでお馴染みのダニエル・クレイグが演じる。
■良いところ
クラシックミステリのお約束を上手にに映画化していること。
そしてそのお約束を利用した演出と見事な結末。
■良くないところ
良くも悪くもお約束ありきなので、その辺に多少理解がないと退屈かもしれない。
意図的にツッコミどころを作っていて、そこを面白いと取れるかどうかも課題になりそう。
■あらすじ
大富豪にして著名なミステリ作家ハーラン・スロンビーが自宅の書斎で死亡した。自殺と思われたが、ある日彼の看護師であり友人でもあるマルタは館に呼び出され、怪しげな男ブノワ・ブランからの尋問を受ける。聞けばこの男、匿名の依頼人から多額の依頼金とハーラン氏の死亡記事の切り抜きの入った封筒を受け取って事件の解明に乗り出したという。マルタには一つ不安な事があった。実はあの夜、鎮痛剤と間違えてハーランにモルヒネを大量注射してしまったのだ!解毒薬も何故か見当たらず焦るマルタにハーランは完璧なアリバイ工作を提案する…なんとか尋問を切り抜けたマルタだったが、ブノワに事件捜査の助手として任命されてしまう。未だ疑いの目を向けられ不安に感じるマルタはなんとか証拠を隠滅しようとするが、この事件には更なる秘密があった…現代最後の名探偵ブノワ・ブランが初登場。クラシックミステリに映画ならではの魅力が組み合わさった傑作。
■感想など
クリスティ作品の裏表紙にあるあらすじ書きを少し意識して書いてみたんですがどうでしょう?それっぽかったかな?
オホン。それはともかくとして、いやともかくではないか。本作を簡潔に言うならば「アガサ・クリスティへのラブレター」なんていう言葉がいいんじゃないかと思う。まずなんといってもダニエル・クレイグが演じる名探偵が最高だ。
この男、なんとも珍妙で、切れ者のように見せて隙だらけ。とそれ自体がブラフで壮絶な切れ者。詩的な言葉を使いたがるところなんかも、どことなくエルキュール・ポアロを彷彿とさせる。
劇中で語られるところによると「あのテニス殺人事件を解決した現代最後の名探偵」だそうで、ポアロの二作目は「ゴルフ場殺人事件」だし、クリスティ自身も85歳で亡くなっているところからもリスペクトが伺えるね。
上に書いただけではなく、親族の中にぐれてる放蕩者がいたり、職務に忠実な弁護士が死の少し前に変更された遺書の開封をしたり、探偵の意見に反発する刑事がいたり、被害者の遺産相続人が親族以外の人物(作品の語り部でもある)だったり、それで少し前まで家族同然だと宣っていた親族が一気に手のひらを返し相続を放棄させようと躍起になったり、家政婦が重要な事実を見ていたり。
とまぁこんな感じで、凄まじい量の「お約束」が詰め込まれていてミステリー小説をよく読む人はニヤリとできるはず。私が気づいていないものもきっとあるんだろうな。とはいえ、お約束を詰め込んだだけの映画というわけではなく、そのお約束を時に効果的に、時に面白おかしく、現代的に料理していてとてもいい印象を受けたね。
だからこそ、こういったお約束が通用するか、理解できるかどうかというのが本作の評価を分ける分水嶺になってくるんじゃないかと思う。そもそも根幹にある「大富豪が死に、遺族のほとんど全員が動機を持つ中、遺族ではない少女が相続人に任命される」という設定が古典的というか荒唐無稽なのは否めない。
更に本作にはもう一つ、かなり荒唐無稽な要素があるね。というのも、あらすじでも書いた本作の語り部マルタは「事実に反した事を口に出すと反射的に嘔吐してしまう」というなんとも都合の良い特異体質を持っている。アナ・デ・アルマスのゲロシーンが見れるのはきっと未来永劫本作だけだろうし、そういう意味でも見る価値は…まぁこれ以上はノーコメントで。
ミステリというのは虚像の中から事実を掘り返すジャンルなわけで、これが肝要であると同時に映像化という点では足を引っ張る点でもある。あまり捜査や事情聴取に長らく時間をかけてしまうと冗長になるし、かといってそこに時間を使わないと登場人物にスポットを当てられず薄っぺらくなってしまう。このバランスを尺の中でどう調整するかが難しいね。
人間ウソ発見器、というかウソ発見器人間とでも言えるマルタの特異体質は、この部分をコンパクトに纏めるためのギミックとして上手く機能している。その点で言うと、探偵以外の人間を語り部にするのも同じ目的だと思う。これは小説でもよく使われるやり方で、探偵を物語の裏で動かすことで地道な捜査の場面を省略しつつ、事件の当事者である語り部視点で物語に集中できるようになっている。
体質はともかく、このように本作ではミステリー小説のお約束を盛り込みつつ、証拠となる情報を上手く見せるように工夫したり、結末に辿り着くまでに専門的な知識を要しないようにすることで敷居が高くならないように配慮されているように感じた。
ミステリー系の映画やドラマというのは、尺やテンポの関係から視聴者が知らない情報を使って真実に辿り着いてしまうということも多くて、どうしてもアンフェアに感じてしまうこともあると思うから、こういった配慮は気楽に見る分にも探偵気分に浸るにしてもありがたい。
もっとも、こういう視聴者には見えない部分や、語り部の視点から見ているからこその勘違いを使ったアンフェアなトリックというのもある意味ではミステリ小説の醍醐味でもあると思うから、塩梅が難しいんだけど。
本作で言うなら「私見たんだよ…」のくだりがそれにあたるだろうか。いやそんなまさかぁと思って見直してみたら、確かに「見たんだヒュー…」にも聞こえるから勘違いや決めつけって恐ろしいね。その他にもマルタが証拠の隠滅に悪戦苦闘するシーンはこのアンフェアを逆手に取ったユーモアとも言えるんじゃないかと思う。
ちなみに吹き替えで見てたから、一応原語に切り替えてみたけど何言ってるかよく分からず。「You did this」と「Hew did this」みたいな感じかな?英語リスニングできる人がいたら、ぜひ初見時になんて言っていると思ったか教えてくださいね。このくだりの為か英語字幕もない作品みたいだし。
ただこの「あだしみだんだひゅょ…」に関しては、犯人告発のシーンではっきりと言い換えられていて初見の流れで見たときにはかなり滑稽というか、んな馬鹿な!?って感じた。実際に先のシーンを見直したらまぁ言ってるかもなぁってなるんだけどね。
その他、そもそもスマホがある時代なのに監視カメラの録画はVHSってそんなことあるか!?とか、色々と突っ込みたいところも多くて、それを許容できないと一気に陳腐に感じられてしまうかもしれない。
ただ、私達日本人はこういうミステリ特有のツッコミどころとかに関しては割りと免疫あるんじゃないかと思う。クリスティ作品は日本でもドラマがやっていたし、影響を大きく受けている横溝正史作品や、お約束の塊である二時間サスペンスなんかもあるもんね。まるっとお見通しだ!でお馴染みのトリックも横溝正史のパロディみたいなものだし。
そしてそんなお約束をフル活用した本作のクライマックス、先にも触れた犯人告発のシーン。これは凄かった。
実はこの映画が配信された時期、個人的にクリスティブームが来ていて、だからポアロものをよく読んでいたんだけど、クリスティ作品って悲劇の語り部と一族の中の放蕩者のロマンスというパターンが多いと感じていたので、マルタとランサムもてっきりそれのオマージュだとばかり思っていたんだよね。
ところが実際にはこのお約束を逆手に取ったランサムが犯人という展開で、これにはちょっと面を食らったと同時に良い意味で期待を裏切られた。確かに「また戻ったんだね」とか口論していた割りにやけに余裕ぶっていたりと不審な点はあったんだけども。大抵の場合、不審なやつは犯人じゃないというのもお約束だから本当に油断してた。
そしてそこからの流れが本当に秀逸だと思う。まず、これまで活用されてきたマルタの「嘘をつくと嘔吐する体質」というギミックがランサムの嘘を暴く決め手になるというのがいい。これは彼女の強い想いの表れで、探偵の勝利であると同時に語り部の勝利でもあるなんて風に感じた。これまでの緊張から堰を切ったかのようなカタルシスがあるね。まぁ放流されたのはゲロだったんだけど。
そこからの犯人逆上、これまで存在感だけすごかった椅子のナイフを掴み取りマルタを刺すも…という展開も良い。爺さんのことを一番理解していると自負していた孫が、椅子の背後にあるナイフが模造刀であることに気付いていなかったというのが良い意味で滑稽だ。ちなみに初見時はたまたま取ったナイフがびっくりナイフだなんて…と思っていたけど、多分被害者の性格を考えるに全部模造刀なんだろうね。
そしてそこから気だるげなBGMとともに彼ら一族のあらゆる嘘が暴き立てられていき…そしてブノワ・ブランがなぜ現代最後の探偵と言われるかその所以が示されると、最後の最後に出てくるのが最初に登場した
My House
My Rule
My Cofee !!!
のコーヒーカップというのがまたなんとも最高なんだ。
■まとめ
本作を簡潔に言うのなら「アガサ・クリスティーへのラブレター」なんて言葉が似合うかと思います。筋書き、劇伴などの演出、そして物語の中核を担うトリックと結末、様々な部分からクラシックミステリーへの愛と情熱が感じ取れる一方、映画化にあたり冗長化しないように、またアンフェアでないようにも注意されていると感じました。
しかし配慮こそされているものの、こういった様式美的なお約束は時代錯誤的な側面もありますから、あまりそういった作品に触れたことがない人にとっては荒唐無稽に感じられてしまうかもしれません。とはいえ本作は小説や映画という垣根を越えて、無駄がなく非常によく出来たミステリであることは疑いようがありません。
もしも、これから本作を視聴する方がいれば、映画だからと油断せずに、劇中に散りばめられた様々なヒントや違和感を見逃さないように注意してみてください。そうすれば、投げた石が放物線を描くように真実にたどり着けるはずです。
■余談
ところでこの「ナイブス・アウト(Knives Out)」という作品名、どういう意味なのだろう。と思ってググってみると解説してくれているブログがあって、そこの出典元の辞書にあった長めの文章を翻訳にかけてみると「恨み節」という単語に行き着きました。アーナルホドネ…
ついでに今回のヘッダー画像の話もしてしまいますか。一言でいうと「ハヤカワ文庫」ってところで、ハヤカワ文庫から出版されているクリスティ作品の表紙をオマージュしました。白い領域に邦題とシリーズ名、右上に原題という構成ですね。
絵の部分は本作の冒頭に出てきた館の全容をゴニョゴニョにして作ったシルエットに象徴的な椅子をイメージした多重の円とナイフを模した図形を重ね、背景は作中で語られた「重力の虹」をイメージしたものを用意。
何故外側が紫かというと「重力の虹」という単語から、なんとなく宇宙から見た地球の虹を想起して、もしも宇宙から虹を見たら天地が逆さまになっているように色も逆さまなんじゃないかっていう意味不明の発想がでてきたからです。
あくまでも空想のものだから、実際の理屈はどうかは知りませんし、重力の虹って単純に放物線の事なんでしょうけどね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
