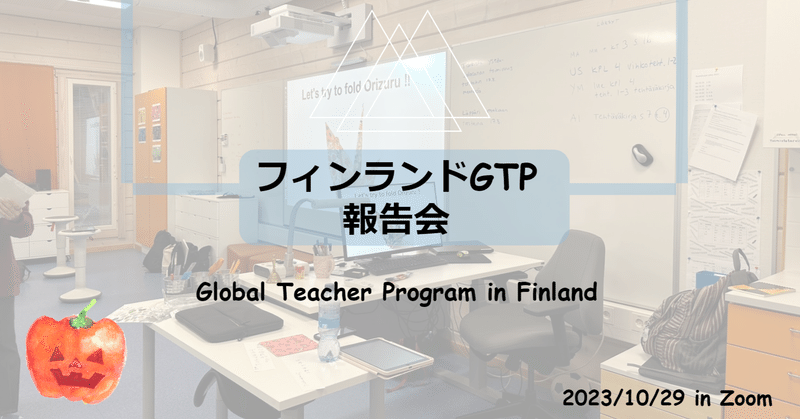
vol.8 なぜフィンランドの学校はソファを置けるのか?
今回からは「学びを社会につなげる」というテーマで、今までの学びを振り返りながらアウトプットしていきます🌱
今回は、去年の8月に参加した「フィンランドGTP(Global Teacher Program)」を通して探究したことを書いていきます。
詳細は省きますが、現地の小学校で日本文化のワークショップとして「パステルアート」の授業もしました!
なぜフィンランドの学校はソファが置けるのか?

・問いの背景
「学習環境」というキーワードに関心があり、フィンランドの教室環境をリサーチする中で、小学校の教室などでは、ソファやバランスボールやマット、イヤーマフなどバリエーション豊かなアイテムが導入されつつあり、多様な学び方をサポートすることで、柔軟な個へのサポートを保障していることが分かりました。
このような教室環境の根底には、「子どもたち一人ひとりには、それぞれに合う学びのスタイルや過ごし方があること」
その上で、「子どもの実態に合わせて創意工夫を行うことが重要である」という認識がフィンランドの教師たちの間にあるのではと推測しました。
・問いの目的
もちろん、フィンランドの教室内にソファに置くことを可能にしている背景を解像度を高めることもありますが、
それだけではなく、それをどのように日本の学校現場に還元することができるのかという実践的側面も含んでます。
日本、フィンランドの区別なく、
「だれもが学びやすい環境はどのような環境であるか?」
という問いから、すべての子どもたちを受け止めるために、学校教育の枠組みそのものを見直すインクルーシブな視点が浸透しつつあります。
しかし、インクルーシブな教室環境を「理念」として語ることはそれほど難しくはありませんが、
それを「行為」として可能にすることは難しいです。
(理念と行為が切り離されている本質的な問題があると思います)。
「だれもが学びやすい環境」という理念を、環境として実現しつつあるフィンランドの現場から探究したいと思いました。
・探究の動機
・教室環境の整備や工夫が、広く子どもたちの学びや育みにいかなる作用を及ぼしているのかを現場を見て考える。
・そのような教室環境のデザインを可能にしている教師や行政による仕組みには、どのようなものがあるのかを明らかにする。
・子どもたち一人ひとりに合う学びの形を日本の教室内でも十分に実現するためには何が必要なのか。
・そして、何が障壁となるのかを明らかにして、来年度から学校現場に入る自分に何ができるのかを考える。
この動機を起点にしつつ、「フィンランドにあって日本の教室にないもの」という観点を加えて、今回の探究ではフィンランドの教室内に置かれているソファという具体物に焦点を当てました。
「なぜソファを置くことができているのか?」の理由を探究する中で、教師の認識や、学習環境のデザインの考え方、現場と行政の関係性などの学校現場を取り巻く様々な観点につなげて探究することを目指しました。
なぜソファは必要?
ところで「ソファを置くことで、どのようなメリットがあると思いますか?」みなさんはどう考えますか?
ぼくもぱっと考えてみてみました。
・自分に合った環境を選ぶ力って大事かも…
・人によって学びやすい環境は異なる
・居心地がよくて長時間過ごしたくなる空間の方が学習意欲も高まる?
・話しながら勉強できるリビングのような学習空間
・動きながら勉強するのが得意な子にピッタリ
「これって大事だよね」が現場で形になる

「1人ひとりに合わせた学びを実現する環境って大事だよね」
理想を謳うことに終始するのではなく…現場で着実に対話が重ねられ、実際に形になっている
これが実際にフィンランドの教室を見たときにぼくが感じたことです。
「メリハリが大事!」とよく言われるが…
その一例を紹介したい思います。
勉強や仕事をするときに「メリハリをつけることが大事だよ!」と言われることがとても多いと思います。
さて、日本の学校の職員室はメリハリが付けられる環境でしょうか?
現職の先生方の話を聞く限りでは、職員室は騒がしく、集中して作業などに取り組める環境とは言えないそうです。
フィンランドの職員室は、環境としてメリハリをつけた設計になっています。


上記の2枚の写真はどちらも職員室ですが、部屋が2つに分かれています。1つは仕事に没頭する部屋。教材などが置かれているため、日本の職員室と外観は近いですが、シーンとしていることが一番違いでした。
一方で、2枚目はソファが置かれた部屋で、基本的に教材などの仕事に関するものは置かれていません。
そして、コーヒーを飲みながら、「あの授業はどうだったか?」「あの子はどうだった?」というゆるやかな授業のリフレクションが行われるそうです。
「何が自然なの?」という問いの大切さ
もう1つは、自分の固定観念が揺さぶられたエピソードです。

こちらは英語の教室。実際に教室にソファが置かれているのを発見した僕は、イヤーマフと同じように、落ち着かない子のための場所なのかな?と思い、先生にどのような目的で、このソファを使用しているのかをインタビューしました。

この返答を聞いてハッとしました。当たり前ですが、固いイスよりも、やわらかいソファに座って本を読みたいですよね。
ぼくたちは、いかに無意識に不自然なことを子どもたちに強いていたのかに気づかされました。
「一体なにが自然なのだろうか?」という問いは、教室環境から授業づくり、学級経営などの様々な場面において、自らの教育観を見直すきっかけを与えてくれると思います。
日本の教室環境に視点を移してみる

そこで、教室環境に関して創意工夫を凝らしている現職の先生方にインタビューを行いました。
・現状教室にかけられる予算は公立では0だと思います。
・教室環境を充実させようと思ったら、日本では自腹で用意するのが普通だと思います。
・地域によって差はあるが、環境整備は一部のアンテナ高い人が自腹を切ってやっている感が強い。揃える文化は根強い。
「どうせむり…」を乗り越える「だったらこうしてみよう!」

お2人とも「残念ながら…」というトーンでしたが、厳しい現実を知れたことも僕にとっては、この探究をしなければ気づけなかったことです。
最後に#どうせむりではなく、#だったらこうしてみようで可能性も探ってみたいと思います。

この事例のように、揃える文化を乗り越えるためには、まずは学校のみんなが使う公共的な場(図書室や廊下のスペース)から、徐々に始めていき、子どもたちの具体的な事実を集めていきます。
そこから、学校全体に「子どもたちが学び方を自ら選択する」という文化を育んでいくことが可能性のある道筋だと今のところは考えています。色々と乗り越えるべき壁もありますが💦
これからの探究
「この探究をすることは、あなたの人生や仕事、あるいは社会にどのようにどのように活かすことができますか?」
プログラムに参加した動機でもありますが、来年度から学校の教員になるため、探究の成果を現場に還元したいと思っています。
教師の役割は、直接的に教えるという従来の在り方だけではなく、学習環境を整えることにより間接的に学びを促し、支援する在り方が求められると考えています。
自分自身にとって、環境による教育を、フィンランドの事例も含めながら探究できたことは、
子どもたちが潜在的に求める様々な学びの機会を柔軟に提供するための視点を育む点で、自分の人生、社会に大いに活かせると思います。
フィンランドと日本。どちらが優れているではなく「よりよい教育」をみんなで創る感覚を大切にしていきます🌱

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
