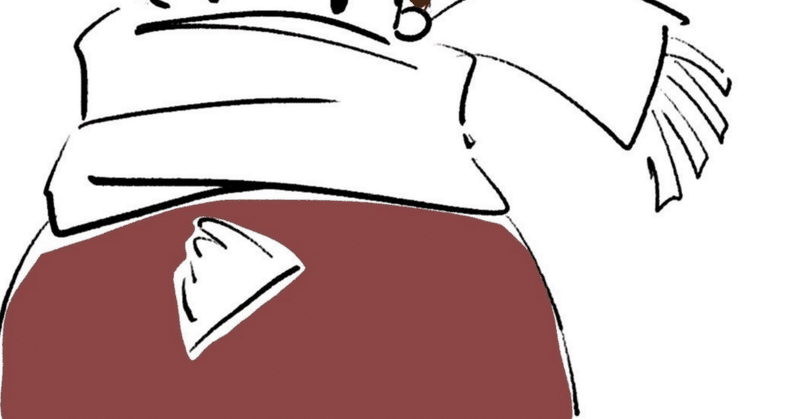
推し(小説)
細野くんが今日もかわいい。線の細いからだ、尖った白い顎、さらさらと風になびく髪……。細野くんが今日もかわいい。
細野くんは同じ学科の男の子である。大学一年生のときから推していて、四年生になった今でも推している。細野くんとは、話なんて合わない。いつも彼の好きなゲームやアニメの話をただ聞いているだけだ。でも細野くんは顔がいい。細野くんはとてもかわいい。だからあたしは細野くんの話を聞いている。
あたしがあんまりにも推すものだから、友人たちは呆れた様子でその様子を見ていた。そんなに好きなら、付き合っちゃえばいいのにって。分かってないなあと思う。推し活動と恋愛は全くの別物なのにさ。あたしは、細野くんみたいな、儚さ・かわいさ・あざとさ全開みたいな男じゃなくて、もっとひょうひょうとしたタイプの男が好きだ。背が高く、細い腰から下半身にかけて、おわんのような凹みがある人が好きだ。一度、そんな男を好きになってしまって、でも結局ふられて、仕方がないので当時かわいがっていたサークルの推しと付き合ってみたが、やっぱりうまくいかなかった。推しは、恋人にするとよくない。推しは推しすぎると、王様みたいに振る舞うようになることを、あたしは元カレから学んだ。王様になった推しは、まったくおもしろくない。態度が大きい推しなんてもう推しじゃない。おどおどしていて、カップを両手で持って、寒そうにからだを縮めて、ときおり笑う顔がとんでもなくかわいくないと、それは絶対に推しなんかじゃない。そういう意味で、細野くんはどんぴしゃだった。あたしは細野くんの小さなからだを愛したし、彼がぬいぐるみを好きなところも、甘いスイーツが好きなところもきちんと受け入れ、彼の行動をちくいちSNSのアカウントにしたためていった。
〈今日も推しが尊かった。帰りに手振ったら照れながら振り返してくれてしんどみ深い。話しかけてくれてありがとう……〉
推しは、かれこれ四代目だ。といっても、推しというのは、一人に絞るんじゃなくて、何人かいて同時並行で推すものなので、四代目も何もないかもしれない。バイト先やサークルの先輩にも、推しはいた。けれどもやはり細野くんは最推しという認識だったし、四年生になってバイトもサークルも辞めた今、直接会って拝めるのが細野くんだけだったのである。そういうわけであたしの細野くんへの熱は、今まで以上に大きくなっていったのだった。
だから、就活が終わって、細野くんの友達から打ち上げに誘われたときは、二つ返事で了承した。
「細野くんも来るの!? 絶対行く!」
細野くんの友達は、友也という。友也は細野くんと似たような背格好をしているが、細野くんよりも陰キャで不細工だ。甲高くてキリキリとした声質と逆三角形の顔が、なんだかカマキリを思わせる。
要は、友也と細野くんと、友也の彼女とあたしで、飲みに行こうと言う話だった。なぜあたしが選ばれたのか? それはあたしが細野くんを推しているからである。もともと細野くんと友也で打ち上げをしようと思っていた所、メンヘラと名高い(と、学科の男子が言っていたっけ)友也の彼女が乱入してきた。三人で遊ぶのも間が持たないので、細野ファンであるあたしが呼ばれた、というわけである。
「なんだかそれ、ダブルデートみたいだね」
フルーツタルトに切り込みをいれながら、長い髪をゆっくりと肩の後ろにはらって、さゆりが言った。あたしの隣に座るみき子は、もくもくとモンブランを頬張っている。大学でいつも話している友人だ。そうなのよ、とあたしは頷く。
「せっかくお出かけするんだから、細野くんと二人きりになれたらいいね」とさゆり。
「まあ、二人になっても大した話はしていないんだけどね」
あたしはそう言ってショートケーキの鋭角のところを頬張った。ほのかなクリームの甘味が広がっておいしい。二年前からある大学近くのこのカフェは、人通りの少ない路地に位置しているからか、客もいなかった。こんなにおいしくて安価なケーキセットが売っているのに。昔ここで働いていた男の子も頼りない感じで、好きだったっけ。もういないのかな、と厨房をちらりとふり返る。厨房ではアルバイトの女の子たちがつまらなそうに働いている。
「沙耶は、細野の見た目が好きなの?」
それまで無言でケーキを食べていたみき子が、私に尋ねた。
「顔が好き」
「そんなに顔、いいっけ?」
「失礼すぎ!」あたしが笑ってみき子を軽く小突くと、
「中世的な感じだよね」
とさゆりが間に入って笑った。さゆりは綺麗で、みき子はお洒落だ。あたしは女の子が好き。あたしはかわいい女の子が好き。ううん、たぶん、あたしは自分に優しくしてくれる女の子が好きなんだ。こういうふうに仲のいい女の子とおいしいものを食べているだけで、幸せな気持ちでいっぱいになる。
「お出かけしたら、感想教えてよ」
さゆりの言葉にあたしは頷く。もちろん! 友也の彼女とはこれまでよく話したことがないから、仲良くなれればいいんだけどね。そんな、思ってもいないことを口にして、あたしたちは解散した。細野くんがいなければ、絶対に参加しないような飲み会。かと言って細野くんしか来なかったら間が持たないから、友也たちがいてくれることは助かるのだけれど。
〈今日は学校の子とケーキ食べた!色々話して楽しすぎたな、推しのこと話せて良かった~〉
九月の初旬でも、夏本番のように暑かった。胸の間をじくじくとした汗が伝わって、気持ちが悪い。普段使わない駅のロータリーで、腕時計をちらりと見る。この駅につくまでは、かなり時間がかかった。もともと大学の最寄りに集まろうと言う話だったのに、友也と細野くんが、それでは遠いと言い始めたのだ。仕方なく彼らの自宅に近い駅を待ち合わせ場所にし、そこで飲むことになった。十七時。外は明るいが、人はまばらだ。この時間だからなのか、もともと人が少ないのかはわからない。あたりは淋しく、しんとしていた。
そんな景観に三人の姿を見出すのは容易だった。細野くんは秋口ということで薄い身体に長めのカーディガンを羽織っていて、爪の先しか見えていない右手であたしに手を振った。あたしは跳んで行って彼をいろいろな角度から長め、「かわいい」と繰り返した。細野くんは今日もかわいかった。推しは今日も尊かった。かわいいと言えばいうほど細野くんは嬉しそうにするから、あたしはたくさん声をかけてしまう。友也にも「その服良いね」「似合っているね」と声をかける。テキトーに。そうすると彼もその彼女も得意げになるのでおもしろい。
あたしたちは友也に導かれて個室つきの安い居酒屋に入った。友也がソファ席の方にどかりと座り、彼の恋人もそれに続く。あたしと細野くんは余った椅子の席に着き、彼らと向かい合うかたちで座る。
それでは就活、お疲れさまでしたー。かんぱーい。何品か注文したのち、直ぐに届いたジョッキで友也が音頭をとった。乾杯が、あたしは嫌いではない。「かんぱい」というなんともばかげた音の響きがあたしは嫌いではない。ただ、ビールは好きではなかった。というか、お酒が好きではなかった。飲めないわけではないのだが、おいしいとは感じなかった。どうしてこれを好き好んで飲めるのかが分からなかった。あたし以外の参加者はお酒がだいすき。こうした飲みの場でなくても、自宅で楽しむ機会が多いようだ。細野くんは薄い唇に重いジョッキを当てて、少しずつすすっている。うっすらと見える頬骨のへこみを、あたしはぼんやり見ていた。やっぱりかわいい。
「マジで他のやつら、内定貰えたのかなー」
友也の一言から始まり、話題はうわさ話に移っていく。いつもそうだ。友也は細い体型に似合わず、酒が入ると声が太くなる。同じ学科の子やサークルの子がどんな内定をもらったか、誰が院に進むのか、公務員試験は……。友也の情報が、あたしの情報になってゆく。ときどき彼の恋人からいくらか媚びの込められた茶化しが入り、場が和む。あいつにあの中小企業は役不足だって。あいつ、バカなのに仕事できるの? ああいうやつが社会に出て足を引っ張るんだろうな、俺、足並みそろえるって言葉大嫌いだよ。それでも社会は弱者を軸にして廻っていくからなあ、やりきれないよな。政治家もバカばっかだし。友也の話は止まらない。役不足の使い方が違うよ、とは言わず、あたしはぼんやりと聞いている。細野くんは「そうだよねー」といつものトーンで頷いている。
あたしは友也の、いわゆる「友也節」が好きではなかった。ふだんから毒舌キャラを豪語する彼だが、それが毒舌だと感じられたことがなかった。むしろ嫉妬か愚痴のたぐいだろうと思っていた。それでも彼の恋人は、彼のそんなところに惹かれているのだろう――甘やかな表情でテーブルの一点を見つめ、頷いていた。あたしは薄気味悪さを覚える。女の、それも女友達のこういうところを見るたびに、あたしは自分の喉元を搔きむしりたくなるのだった。男はいい。あたしにとって男とは、セックスをするか、愛でるか、どちらかの存在だから。でも、女は。女は信頼関係(共犯関係と言った方がいいかもしれない)で結ばれているのだ。それなのにこういった一面を見せられると、あたしのこころの中の壁紙がぺらぺらと剥がれていってしまう。あたしはこの人間の全てを把握することができない! もしみき子やさゆりのそういう、〈おんな〉のところに気付いたら、あたしはとうとう幻滅して、孤独に気づいてしまうだろう。それだけは怖かった。そういうのを見てしまうくらいなら、見ないふりをしている方がマシだと思うのだ。いつの間にか友也の話は終わり、今度は彼の恋人が口をとがらせている。
「私ん家、親が毒親でさあ」
彼女は家庭の事情について流れるように話し始めた。日本酒がどんどん空いていく。あたしはとうにビールからジンジャエールへ飲み物を変えている。最初のときよりも、なんだか友也と彼女の距離が近いような気がする。細野くんは頷いて聞いている。親に流されるように生きて来たんだよね、本当は心理学がやってみたかったのにこんな学部に入ってさ。大学で勉強していることも全然好きじゃないし、親は干渉してくるくせに兄しか可愛がらないし、本当に早く家から出たいんだよね。でも大人になりたくはないし、働きたくないし、怒られたくないし。あーあ、私も院に行きたいなあ。私立中高一貫校出身だという彼女の、ぽってりとした唇をあたしは見つめる。
友也とその彼女は、付き合っていることを、誰にも知らせていなかった。知っているのはあたしと細野くん(とみき子とさゆり)だけである。最初、あたしは二人が関係をあからさまにアピールしないことを、好ましく感じていた。あたしだって、もう二十二だ。恋愛が見せびらかすものでないからこそ、二人の心に閉まっておくものだからこそ、甘やかに発酵することくらい、知っている。それなのに二人から感じられるのは、そんな高尚なものではなかった。言わないでね、と言いながら、伝えてほしそうにこちらを見ている。噂が広まって「あの二人、付き合っているんだって!」と伝わる瞬間を夢見ている。あたしはこういうふうにして、人から都合よく求められるたち。あの物欲しそうな眼を見るたびに、吐き気がするのだった。人が与えてほしいものを与えるのは簡単だ。実際これまでも、そうしてきた。推しを飼っていたとき。推しの望んでいることをあたしはやってやる。人と話すとき。彼ら、彼女らが欲しい言葉をそのままかけてやる。そうすることであたしは馴染んできた。馴染んで、馴染んで、ときどきストレスになって。そのどろどろとした人間模様の中でわかったのは、純粋に美しいものを、あたし自身が好むと言うことだった。美しい男や女。美しい友人関係。美しい日本語、などなど。邪悪さのない本物の美。だから、細野くんが好きだ。顎から耳にかけて美しいラインを描いている、細野くんという実体が好きなのだ。
毒親の話が終わると、ようやく細野くんに話す順番が回ってきた。細野くんは、最近見ているアニメのことを話した。細野くんは小首を傾げて話すのがくせだ。自分なりの言葉でアニメの話をして、それから噛み締めるようにうんうん、と頷く。あたしもだいたいのアニメは知っていた。けれども細野くんの好きなアニメは美少女系のものだったので、よく分からなかった。細野くんは楽しそうに話す。あたし以外の参加者は、その話にもついていけるのか、前のめりになって聞いている。あたしが細野くんの推しキャラについて尋ねると、彼は袖から指をのぞかせて、恥ずかしそうに顔を覆った。ネコみたいに丸い背中、細いのに角ばった手の甲、全てがあたしを好ましい気持ちにさせる。かわいい。庇護したい。この綺麗な実体に、良いものをたくさん与えたい。
それからあたしも元カレのことを一言、二言話して、飲み会はお開きになった。何だかずいぶん長い日だった。友也とその彼女は日本酒をどんどん入れていたので、結構な値段になった。細野くんも飲んでいて、顔がうす赤くなっていた。大きめの服に着られたかのような小さな彼は、うす赤くなると、余計に女のようだった。ぼんやり眺めていると、友也があたしに手を差し出す。
「ほら」
「なに?握手?」
「握手なわけねーだろ、一人七千円!」
あたしは驚いて細野くんを見たが、細野くんは何でもなさそうにお金を渡していた。あ、そうか。細野くんもそれなりに飲んだのだしな。三人がつぎつぎに紙幣を出すので、あたしも慌てて友也に手渡す。こういうとき、みき子だったら「何で飲んでないあたしが払わなきゃいけないの?」って、強く言うのだろう。あたしには、そんなことできなかった。だってそんなことしたら、推しに誘われなくなってしまう。それに払わなかった場合の気まずい雰囲気について考えるだけで、とても面倒くさくなるのだ。
支払いを終え、外に出ると鈴虫の声が響いていた。鈴虫は羽をすり合わせて音を出す。これは、昔好きだった男が言っていたこと。あたしがほんとうに好きで、好きで、でも好きになってもらえなかった、ひょうひょうとした男が言っていたこと。虫なんて、どうでもよかった。どうでもよかったのに、その男が言うだけで、どんなに甘やかな響きに感じられたことだろう。身体中にじんわりと溶け込んでいくあの感じ。彼の言葉を、彼の声を、あらゆる細胞に浸み込ませていこうとしていた、あの頃のあたし。細野くんは鈴虫に気付かない。もし気付いたとしても、きっと肩をびくりとさせて、袖を口に当てて驚くだけだ。
あたしたちは駅で分かれた。彼らは下りの電車で、あたしは上りの電車で帰っていく。人のいない車両の中で、細野くんの話を懸命に思い出していた。家で飼っている犬のこと、最近ハマっているゲームのこと、一人で横浜に食べ歩きにいった日のこと……。忘れてしまいそうだった。反芻しなければ、忘れてしまいそうな話だった。
〈色々あったけど推しくんが近くに座ってくれたので満足。また行こうって言われた~尊いんじゃ~〉
「さいってーだね」
みき子がのけぞるようにして、そう吐き捨てた。あたしは彼女の贅肉のついていないすっきりとした顎を見やり、それからガレットに乗せられたバニラアイスクリームを小さな銀の匙で押しつぶした。割り勘って! そんなことある? 好きなだけ飲んでおいてさ。そう言って、みき子もアイスクリームを口にいれた。みき子おすすめのこのカフェは、紅茶と共にガレットも売りにしているのである。
「でも、あの場で払わなかったら変な空気になっていたと思う」
「まあね。でもあんたも意思表示するべきだよ」
「意思表示か」
あたしがぼんやりしたまま、そう繰り返すと、みき子は大きく頷いた。
「それに、その友也と彼女の距離が近いっていうのもくそキモイ」
「正直目のやり場には困ったよ。まあ仲が良いのはいいことだけどね」
「いちゃいちゃするのは他所でやってほしいわ、頭悪すぎるよね」
「うん、まあ分かるけどね、気持ちは」
みき子が少し表情を曇らせて、あたしを見た。あたしは気付かないふりをしてガレットを丸めて口に入れる。
「沙耶は、優しすぎるのよね」
結局、それからはみき子のバイトの話や、大学のレポートの話、ゼミの話などをして解散した。助かった。いつものように、みき子が喜びそうな返答ができたと思う。そうだよね、わかるよ、みき子が正しいよ、みき子しかできないよ、と。なるべく細野くんの話題にはしたくなかった。口にすれば細野くんを否定されるに決まっている。細野くんの悪口を、みき子に言ってほしくなかったから。推しについて、他人にとやかく言われたくなかったのだ。
お会計の際、みき子が片眼をつぶって「自分の食べた分だけ払おう」とおちゃらけたので、あたしは思わず笑った。「お会計はどうされますか」「別々にしてください」「かしこまりました」学割にこだわるみき子の後ろ姿を見ながら、財布の角をいじる。他人に、正確に気持ちを伝えるのは難しい。あたしの語彙力が乏しいせいで、うまく話すことができない。確かに嫌な思いはした。でも、うまく言えないけど、細野くんのことも友也のことも嫌いじゃないんだよ。そして、あたしはきっと細野くんを良いと思っているんだよ。それは恋愛とはまた違った感情で。もしかしたらそれはペットに対する愛情と似ているかもしれないけど。
「学割使えなかったわ、けちな店!」
みき子がぶつくさ言いながらあたしに耳打ちしてくる。店員が次に支払いをするあたしの顔を見ている。次はどこ行く? 服でも見る? みき子の声にあたしは頷く。みき子はいい子。あたしを大切にしてくれるし、あたしに降りかかった嫌なことを全否定してくれる。みき子のことが好き。みき子もあたしのことが好き。でも彼女が誘うところには、なぜか、いつも、さゆりはいない。
みき子にはそういうところがある。みき子にはそういうところがあると、あたしは思う。
〈今日は大学のかわい子ちゃんとカフェ‼ たくさん話せて嬉し~。愛しかねえ〉
二週間が過ぎた。講義後、一人で帰ろうとすると、珍しくさゆりが声をかけてきた。さゆりはいつものように髪を耳にかけてから話す。彼女の顔周りで舞う細い指を目で追い、さゆりは可愛いねえと呟くと、彼女ははにかんで首を横に振った。
「この前沙耶に教えてもらった映画、とっても良かった」
「見てくれたんだ!」とあたしは目を輝かせる。
「もちろん。切なかったな、和解すると思ったのに最後は別れちゃうんだね」
「エモいよね、ああ、なんだかこんな言葉を使うと俗っぽく成り下がってしまうけど……」
「エモーショナルと言えば、セーフかも?」さゆりが悪戯っぽく笑うので、あたしも声を出して笑った。あたしたちは教科書を片づけ、二号館の階段をゆっくりと降りる。
二人で帰るのは久しぶりだった。いつもはみき子と三人で帰るか、さゆりが学校に残るかのどちらかだったので、久しぶりのさゆりに、あたしは少し緊張した。さゆりはあたしよりも少しだけ背が高い。いつも花のような香りがする。それはさゆりが好きな香水で、あたしが褒めるとさゆりはまた照れ臭そうにはにかむのだった。
「もうすっかり秋だねえ」あたしは呟く。
「あっという間だね、この前まで夏みたいだったのに」とさゆり。
「大学もあと半年もないと思うと、実感ないね」
「そうね、何だかさ……」
さゆりがそう言い、言葉を止めた。あたしは先の言葉を待つ。さゆりはよく、言葉をつまらせる。一年生の頃、彼女が打ち明けてきたことがあった。言葉がうまく出ないときがある。鈍臭いので、イライラさせてしまうかもしれない。あたしはその時、何て返したのだっけ。あたしだって、鈍臭いから、大丈夫と笑ったのだったか。みき子が何も言わなかったので、話はそこで打ち切られたけど、美人でも生きづらいことはあるのだなあとのんきに思ったものだ。さゆりは「ああそうだ」と言い、深呼吸をして話した。
「小学生の時に感じた四年間と、大学で感じる四年間、同じ年月なのに、どうして今の方が短く感じるんだろう。時間の密度といえばいいかな……どうしてそれが異なるんだろうって、よく考えるの」
「時間の密度か」あたしは言う。「いい言葉だね」
「植物の匂いひとつでも」
と、さゆりが足を止めた。あたしも立ち止まる。見ると、深い緑色の葉のあいだに小さな星の集まりがあって、かぐわしい香りをさせていた。金木犀だ。
「あの頃は毎日のように感じていたのに、今では数日で散るように感じちゃう」
あたしは金木犀も、やはりどうでもよかった。ただの花だ。鈴虫と一緒。仲良しのさゆりが話すから、耳を傾けるだけ。それでも友也やみき子の話を聞いているより、いいと思った。思えばさゆりは、細野くんと会う前に玉砕した男と少し雰囲気が似ているのだった。
「でも、二十二になった今でも、一日が長いなと思うことはあるよ。嫌なことばかりだけど」とあたしは言う。
「嫌なこと? 何かあったの」
さゆりはそこまで尋ねた後、察したように唇を噛んだ。あたしは頷く。
「前話していた飲み会のこと。楽しかったんだけどさ、ちょっともやもやすることがあって」
あたしが話し始めると、彼女は食べ物でも消化するように、ゆっくりと噛みしめて聞いていた。その柔らかな受け止め方に、あの日の自分の感情が溢れてしまいそうになる。細野くんが近くに座ったこと、細野くんが話したこと、細野くんが着ていたカーディガンのこと、細野くんが飲んだビールのこと。細野くんが可愛かったこと。細野くんが自分の家の近くの駅に集合させたこと。細野くんが……。
細野くんが思っているような人間ではないかもしれないこと。
細野くんもあたしにお金を出させた――
推しは、いつでも弱々しくほほ笑んでいなければならない。身体に合っていない大きめの洋服を身に付けていなければならない。長い前髪を気にして触らなければならないし、甘えたでスイーツが好きでなくてはならない。品が無ければならない。ましてやお酒なんてがぶがぶ飲んではならない。
「……きっと、どちらの細野くんも細野くんだと思うな。可愛い細野くんも、沙耶をモヤモヤさせた細野くんも」
しばらくの無言ののち、さゆりはそう呟いた。確かに、とあたしは頷く。
「いい所だけを見て行けばいいのかな」
「そう思うよ」
「そう言えば、さゆりはあまり細野くんたちと話さないよね」
うん、とさゆりが遠くを見ながら言った。その不自然な間に、問い詰めずにはいられなかった。
「なにかあったの?」
「うーん、あのね」
あたしはさゆりを見る。今から。今から本当のことが言われる。あたしの見たものの、答え合わせが始まる。おへそのあたりがきゅっと締め付けられて、呼吸が浅くなった。どくんどくんと胸が鳴った。
「わたし、日によってバッグを替えて使っているじゃない。でもそれは……豪遊しているからというか……つまり、いかがわしいことをすることで得たものなんじゃないかって、言われたことがあって。それから毎日、通りすがりに言われてるんだ。だから、あんまり得意じゃないんだよね」
からだが静かに冷たくなっていった。
推しのくせに、とあたしは呟いた。
カマキリを道で見つけた。コンクリートの藍色と、緑の色鉛筆のようなカマキリのコントラストがはっきりしていたので、気づいたのだった。カマキリは大きかった。いやもしかしたら、もともとこれくらいの大きさなのかもしれない。いつもだったら素通りしてしまうものだったが、しゃがんでじっと見てみた。
カマキリは美しいかたちをしていた。けっこう近くで見たものだから、瞳がこちらを向いているのが分かった。なんだかエヴァンゲリヲンみたいだな、とあたしは思った。エヴァの瞳にあたしは映っているのだろうか――触ろう――あたしが手を伸ばすと、エヴァは臨戦態勢になった。威嚇している。ああ、生き物だ。この生き物でさえ、命を掛けて生きているのだ。あたしがいま踏みつぶしてしまえばうす緑色の液をぶしゃ、と放出して蟻にたかられてしまうようなこの生き物でさえも。
友也、全然カマキリになんて似てないじゃん。カマキリのがよっぽどイケメンじゃん。鞄から下敷きを出して、エヴァをそっと端に寄せた。立ち上がって、金木犀を探す。鈴虫を探す。秋と言うのは目まぐるしい速さで過ぎ去っていくのだった。秋はもう、そこにはなかった。
「時間の密度」
あたしは呟いた。時間には重さがある。
大学に着き、二号館の階段を上ると、見知った友人たちが楽しそうに喋っていた。挨拶をして教室に入る。いつもの、前から六番目の席に進む。いち、に、さん、し……四番目の席に友也と細野くんが座っていた。
「よお」と友也が言った。
「よお」とあたし。
細野くんを見る。細野くんは待っている。あたしに可愛いと言われるのを今日も待っている。しかし彼の顔も、髪も、身体も、もうあたしに働きかけなかった。あたしにはもう、ボランティアをやる気力などなかった。だって、秋はこんなにも短いのだから。
素通りした。細野くんがふり返ったのが、気配で分かった。一番後ろの席に座るさゆりがこちらに気づき、手を振る。これから銀杏が落ちるだろう。紅葉もきっと色づくだろう。ひとつひとつのことを心に留めて、生きていかなければならない。秋が終わるのはとてもとても、早いのだ。
あたしがほほ笑むと、さゆりもにっこりと笑った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
