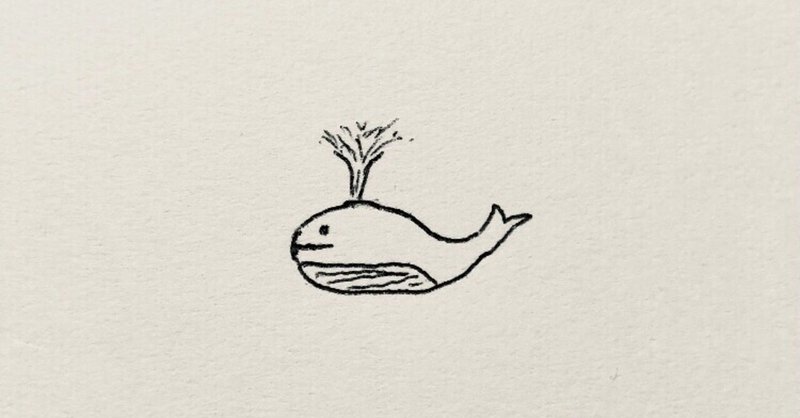
掌編小説(9)『スイング・バイ』
観客席を埋め尽くすヒューマンたち。彼らの発する数万人分の怒号やヤジが空間を埋め尽くす。彼らが睨みつけるリング上では、二体のアンドロイドが死闘を繰り広げていた。両者ともに傷だらけで、黒い機体のアンドロイドに至っては片腕を失っている。それでも、相対する王者の表情に余裕はなかった。
全戦無敗。絶対王者であり、身につけた最新鋭の外躯殻と、その流麗な戦闘スタイルから【白銀姫】と呼ばれる現チャンピオンが今、かつてない窮地に立たされていた。対戦相手は本戦初出場の新機体。といっても、本来ならとっくにバラバラにされているはずのプロトタイプで、彼女自身のA・Iにもまた、この試合では「程よい好試合の末に負けるように」とプログラムされているはずだった。
素早く白銀姫の背後に回った黒鉄のアンドロイドが、片脇に頭を潜り込ませ、片方しかない腕で相手の腰をがっしりと抱え込んだ。
会場にいる誰もがみな、息を止めた。俺は拳を強く握った。
人口減少に伴うヒト種保護の観点から、危険を伴うあらゆるスポーツの主役が人間からアンドロイドになり数世紀が経つ。
こんな地下闘技場で開催される興行プロレスもその例外ではなく、団体の下っ端整備士の俺は、何百というパーツに分解された何体ものアンドロイドを修理する仕事に明け暮れていた。
まだ小さな妹を養うために、毎日、油まみれの腕で汗を拭う。両親が俺たちを団体に売った金と同じ額を返すまでは、自由な生活を望めもしない。手先が器用で数も少ない人間の子は、貴重な労働力として高値で取引されている。俺たちのように身売りされた【抵当孤児】は、文字通り掃いて捨てるほどいた。胸糞の悪い話だ。
「ニケ! 飯にするぞ」
食卓がわりのキャビネットにパンを置いて、倉庫の奥にある作業部屋に向かう。
俺たちのような孤児が成り上がる手段は一つしかない。競技用アンドロイドを使って賞金を稼ぐことだ。俺は整備士の立場を利用して少しずつくすねたパーツを組み上げ、一機のアンドロイドを完成させていた。
戸籍情報のない俺たちが正規戦に出場することは不可能に近い。だから、俺が身を置く団体のような非合法で非正規な試合に出るしかない。それでも勝たせてもらえるかは分からない。アンドロイド競技の世界は、オッズと金と主従関係で支配されている。
目の前に横たわる黒鉄の機体は俺たちの未来そのものだった。
パーツの盗難は最悪のタイミングで見つかった。
泳がされていただけだった俺は、完成した機体をまんまと取り上げられた。
「こいつで一発当てようってか。健気なもんだぜ。おい! 今日の姫の相手はこいつだ。準備しとけ。仕込みも忘れんなよ。盛り上がらなきゃ金にならんからな」
プロモーターがこめかみを指さした。
呆然とする俺のそばを離れるとき、確かにあいつはこう言った。
「大丈夫ですよ。マスター」
ベアリングを軋ませながら、白銀姫を抱えた黒のアンドロイドが後方に身を反り投げる。
鮮やかに決まった『ベリー・トゥー・バック・スープレックス』で、白銀姫は外躯殻ごと真っ二つに折れてしまった。場内が静まり返る中、よろよろと立ち上がったあいつは高く拳を突き上げた。俺には彼女が笑って見えた。
次の瞬間、鼓膜が破れそうになるほどの歓声が上がった。賭け札を放り投げるもの。頭を抱えながら立ち尽くすものもいた。
一緒に観戦していたニケが、倒れかかる彼女の足を抱き支える。
「頑張ったね! アテナ」
ニケの頭を撫でる黒鉄のアンドロイド。機体はひどく損傷している。
「アテナ?」
「ほら、これ」
ひび割れた大腿フレームに刻印された文字の一部が削れている。そこは確かに“a The na“とあった。
試合は無効になった。団体が摘発されてしまったからだ。それでも、アテナの奮闘は無駄にはならなかった。白銀姫を負かすほどの機体とその整備士という触れ込みで、正規団体に入ることができたからだ。
アテナはまさに、俺たちの救いの女神となった。
***
このお話は2月19日「プロレスの日」にちなんで、「プロレス」をテーマに書きました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
