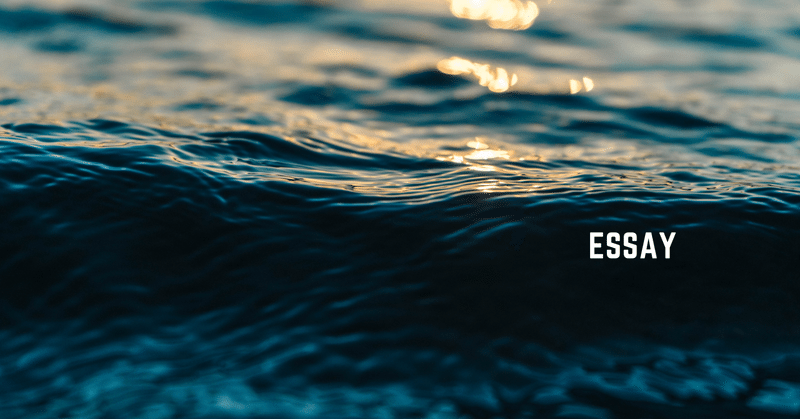
使い捨てをやめたこと。
のどが渇いたら自動販売機でペットボトルの水を買う、スマホは新機種が出たら買い替えてる、だってその方がお得だし、快適、毎朝コンビニでコーヒー買ってから仕事に行く、最近のコンビニのコーヒーも結構いける、なんて今の私達にとっては珍しくない、当たり前の生活です。
しかし、このような日本人の生活を、世界中の人々全員がしたらどうなるのか?
地球は1つでは足りなくて、2.8個も必要になるのです。
そんなにすごい贅沢ではない普通の暮らしを何気なくしていても、地球上の貧しい国の人々や、将来世代の分まで地球の資源を消費しているのです。
国際シンクタンク、グローバルフットプリント・ネットワークは毎年、人類による自然資源の消費が、地球が持つ1年分の資源の再生産量と二酸化炭素吸収量を超えた日を「アース・オーバーシュート・デー(地球の使いすぎが決定した日)」として発表しています。
これによれば、実に8ヶ月で1年分の資源を使い果たし、残り4ヶ月は借金生活だったのです。
地球の全人類全体の資源を賄うのに地球は1個では足りず、1.7個必要だといわれ、全人類がアメリカ人と同じ生活をしたときには地球は5個も必要になります。
しかし、平均的なインド人と同じ生活をすれば必要資源は地球0.7個となり、地球1個で十分賄える計算になります。
今のまま行けば毎日カレーの生活になるのです(それは悪くない!?)
このような人口増加と大量消費、工業投資による地球資源の枯渇は1970年代から指摘されてきましたが、具体的な策は施されることなく先延ばしにされてきました。
1992年にはじめて地球サミットで環境問題が人類共通の目標と認識されるようになり、「持続可能な開発」に向けて世界が1歩を踏み出し、日本においても温室効果ガス削減に向けた政策や様々なリサイクル法が成立しています。
しかしながら世界に目を向ければ、まだまだ日本人の危機意識は低く、政府主導による介入も少ないと言わざるを得ない状況です。
今回は世界の取り組みをご紹介しながら、まずは自分の身の回りでできることは何かを考えてみたいと思います。
レジ袋を減らす
環境庁の資料によると、プラスチック製のレジ袋1枚(Lサイズ)は原油換算で8.2mlの天然資源を消費し、原料採掘から処分まですべてのプロセスで二酸化炭素33gの環境負荷を生じるとされています。
また、プラスチック製の袋は自然界で分解しないため、海洋生物をはじめとする生態系に深刻な影響を与えたり、川の堰に詰まって水害を引き起こしたりします。
打ち上げられたクジラの胃の中から大量のレジ袋が発見されたといった報告はショッキングで、削減の必要性を直接的に訴えます。
デンマークでは早くに「包装税」が導入され、容器包装の製造業者に対して素材、重量に応じて課税されます。
そして、その課税によるコストの増加は消費者に転嫁するために包装の有料化を実施し、結果的に60%ものレジ袋削減効果があったそうです。
イタリアではプラスチック製袋が使用禁止になり、お隣韓国でも法律でプラスチックおよび紙製の使い捨て買い物袋の無償配布を禁止しています。
大量消費の国、アメリカでも自治体ごとにプラスチック袋の禁止と有料制が急速に広がっており、ハワイでは全米で初めて州全体でプラスチック製レジ袋の使用が禁止となりました。
遅ればせながら、日本でも2020年の7月よりレジ袋が有料化され、マイバックやマイカゴを持ち歩いて買い物するのがやっと当たりまえになってきました。
私個人も常にマイバックを持ち歩いており、服を買うときも包装は断るようにしています。
まずは自分のできることがからやっていく、個人の意識の変容が大切だと思います。
ペットボトル飲料を減らす
ちょっと喉が乾いたときについ買ってしまうのがペットボトル飲料です。
英国の市場調査会社の報告によれば、2016年に世界で生産されたペットボトルは約4880億本であり、1年で3.9%の勢いで増加し続けているそうです。
日本における清涼飲料ペットボトルの出荷本数は227億本、2004年は148億本でしたので12年間で1.54倍に増えています。
もちろんペットボトルはポリエチレンテレフタレート(PET)というプラスチックでできています。
各国でも徐々に脱ペットボトル飲料の動きが広まっており、例えばアメリカの大学ではペットボトル飲料の自販機が撤去され、水筒を安価で販売し、その売上金で大学構内に水筒用の冷水機や、ボトル給水器が設置されています。
また、グランドキャニオン国立公園内でもボトル入り飲料水の販売が禁止され、公園内では湧き水を利用した給水ステーションを多数設置して来園者には水筒の持参を呼びかけているそうです。
またヨーロッパでも公共の場所にボトル給水ステーションが設置されたり、Refill(給水)スポットを増やし、Refillアプリでスポットを探したり、参加するカフェに水筒を持参すれば無料で水を入れてくれるサービスもあるようです。
そして、各議会や省庁でもペットボトル飲料を禁止する動きが広がっています。

日本ではペットボトル消費のうち、水とお茶がその大半を占めており、7割がペットボトルで販売されています。
また、日本は人口、面積あたりの自動販売機の設置台数が「世界一」となっており、自動販売機での販売が非常に多いといった特徴があります。
日本の自治体でも水道水や湧き水の美味しさをアピールするため、省庁内でリユースの瓶とガラスのコップで提供したりするところもありますが、わずかであり、ほとんどがペットボトル飲料での提供となっています。
国の状況を紹介しながら日本においてもペットボトルなどの使い捨て容器入りの飲料の消費を減らし、水道水を選択することで、環境負荷の低減をめざす「水do!キャンペーン」が2009年から始まりました。
各地で自治体と協力しながら、情報の提供と普及啓発活動がされています。
私個人としては2016年にハワイに行った際に、現地の人がみんなマイボトルを持って歩いているのがとてもかっこよく見え、水筒のデザインも日本にあるものよりとても「クール」だったため、現地でそれを購入して、日本に持ち帰り、それから水筒生活が始まりました。
それまでは大量に買い置きしたペットボトルを持っていっていたので、かなりペットボトルの消費量は減ったように思います。
2013年の家造りでの節約をきっかけに家族ででかけるときも全員の水筒を持っていき、なるべく行った先でペットボトル飲料を買わないようにしています。
職場においてもゴミの廃棄コストだけで年間500万円程度かかっています。
職員がペットボトル飲料を持ち込まない、買わないだけでもこのコストを下げることができます。また、下がったコスト分で各部署に給水器をつけたりすることもできますので、こうした提案もしていければと思います。
使い捨て品を減らす
ファーストフード店、スタンドカフェ、各イベントやスポーツ観戦、それらの場所で提供される飲み物や食べ物の容器は基本的に使い捨て容器が使われています。
また、出張でホテルなどに泊まれば使い捨ての歯ブラシや歯磨き粉、アメニティグッズがあるのが当たり前かと思います。
もっといえば生理用品や紙おむつ、ホッカイロなども使い捨てですね。
使い捨て品は清潔で洗う手間も省け快適な分、資源やエネルギーも使われることになり、当然ゴミは増えることになります。
多くの国で経済成長とともに、使い捨て品が増えることになります。
お隣韓国では「資源の節約とリサイクルの促進に関する法律」によって、様々な使い捨て品を包括的に規制しています。
例えば使い捨て買い物袋、ホテル・旅館・銭湯における使い捨て剃刀、歯ブラシ等で使用の抑制や無償提供の禁止が義務付けられています。
飲食店でも割り箸が使われることはなく、また2003年1月からは一定の面積以上の店舗内においては、使い捨てカップ等を使用せず、多回用品(マグ、グラス、リユース容器)に切り替えること、テイクアウトの使い捨て容器にデポジット制を導入することなどが実施されるようになりました。
(テイクアウト容器のデポジット制は後に廃止)
アメリカのバークレーでは2020年から店内ではリユースできる容器のみを使用すること、持ち帰り容器はすべて堆肥化可能なものにすること、持ち帰りカップを1個25セントの有料制として客に容器の持参を促すことが条例として可決されました。
これは世界的にも最も先進的であり、環境負荷の低減に寄与する制度といえると思います。
日本において使い捨て品の使用を抑制するために国の制度はまだありませんが、各地のイベントやフェスでリユース容器の使用が徐々に広がっているようです。
しかし、私のいる札幌では大通り公園で多くの飲食を主体としたイベントが開催されるものの、容器は使い捨てが主でリユース容器の使用は広がっていないように思います。
子供を預けていた保育園では紙おむつではなく布おむつが使われており、きちんと布おむつの使用方法を学んだことによって家でも布おむつを使用するなどして、なるべく紙おむつを使用を減らすようにしていました。
現在は出張の際に使い捨て品のアメニティは使わない、連泊の場合は掃除は不要、割り箸はもらわない程度のことしかできていませんが、リユース容器の飲食店やスタンドカフェがあれば積極的にそうした店舗を利用するなどしていきたいと考えています。
長く使えるものを大切に使う
買い物をするときに、一見した値段だけで判断せず、どれだけ長く使えるかを考えて購入することを考えています。
これは家造りの際の家具の選び方や外壁、塗装、内装などすべてに共通してあったテーマの一つでした。
多少高くても大切に使い、メンテナンスをすることで長く、そして味わい深くなっていくものが好きです。
新しいものは確かに気持ちがいいし、流行の色や形の移り変わりも早いのでファストファッション的に安価なものをどんどん買い替えていく方法も確かに理はあるように思いますが、経年変化を楽しみながら、ものや素材を育てていくことも一つの楽しみと言えます。
家を建てた後に買った家具は椅子ぐらいですが、最後に購入したリユース品の一人がけの椅子は、構造素材に無垢のナラの木が使われており、15年以上も前に製造された椅子でしたが、クッションと布地を新しく張り替えて構造体はそのまま再利用されて売っていました。

新品なら10万以上する椅子が半額以下で買えたのです。
またクッションや布が古くなり、擦り切れたりしても、構造が問題なければ、また張り替えるだけで使用することができます。
こうやって大切に長く使用することでモノに対して愛着が湧き、いずれはお気に入りのものだけに囲まれて暮らしていけるようになると思います。
最後に
最近ではシェアリングエコノミーという言葉があるようにものをシェアして使うことも当たり前になってきました。
日本では食品のロスも大きな問題となっており、大手コンビニでは今季から消費期限間近の品物の割引も容認する動きになってきているとの報道もあります。
そうした活動が身を結ぶためには消費者である私達がどのような選択をするかによると思います。
消費者が過剰とも言える鮮度へのこだわりで消費期限の新しいものから選ぶことや形の良い野菜を選ぶことなどの行動が変わらなければ、小売店は「売れる」もの、「売れる方法」を選択せざるを得ません。
私もそうですが、多くの人は「気づかずに」そうした選択をしており、道徳やモラルのしっかりしている日本人はゴミをきちんと分別して捨てているし、もともと慎ましく、質素な生活をしている地球でもエコ寄りな民族だと思っていると思います。
しかし、世界に目を向けてみますと日本における地球資源の消費量は少なくなく、また、国を挙げての取り組みも一歩遅れているように感じます。ほとんどの人は「やっているつもり」であって「気づけていない」だけなんだと思います。
日本人が本気を出せばこの分野でも日本は世界のトップに立てる資質があり、世界をリードしていけるのではないかと思っています。
こうした活動が「普通」の文化になるようになっていくためには、それが「かっこいいこと、クールなこと」といった発信をしていくことも大事だと思います。
アメリカのレッドカーペットで俳優がプリウスに乗って登場したように、インフルエンサーと呼ばれる人たちはぜひ率先してこうした活動を「クール」に牽引してもらえたら、もっとみんなが当たり前にそうなる空気ができあがると思います。
自分にできることを無理せずに、少しずつ。
こうした人が増えればやがてはその「少し」が積み重なり、やがて大きな波になり、文化になります。
「私だけがやっても意味ない」ことはありません。
まずは気づくことが大切です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
参考図書:
#SDGs #脱使い捨て #生活 #生き方 #持続可能 #地球資源 #推薦図書
サポートいただけたら今後の活動の励みになります。 頂いたサポートはnoteでの執筆活動費、参考図書の購入に使わせていただきます。
