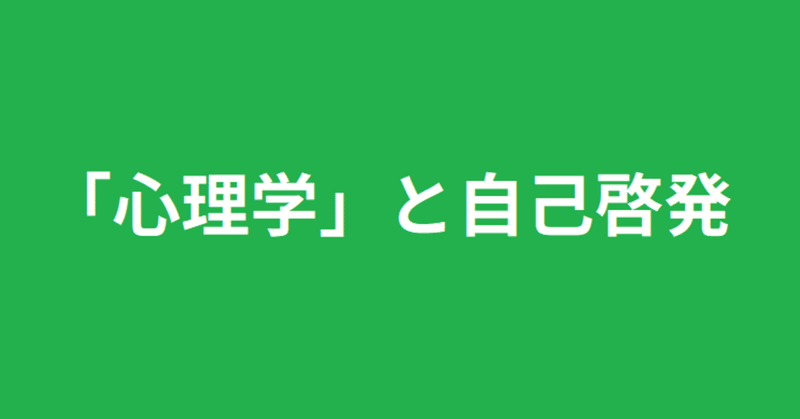
マインドフルネス:今ここを生きる【アドラー心理学とは何か"臨床心理学と自己啓発を整理する"#9】
今ここを生きる、そんなことを言わなくてもみんな今以外では生きられないよと思うかもしれません。しかし、この言葉が生まれるということは、人には「今を生きていない」と言えるような状態がある、ということです。
人間は多くの時間、未来への不安を感じたり、過去を思い出し辛くなったりしています。多くの悩みや辛さは現在よりも、変えられない過去やまだ訪れていない未来に焦点が当たっている、これをマインドレス(mindless)な状態といいます(文献①)。
今まで見てきた原因論も劣等コンプレックスも、マインドレスな状態といえます。今ここを生きるは、今までと地続きの話です。
また食事の際にスマホが気になるなど、気が散ってしまう状態もマインドレスです。マインドレスでは行動に集中もできなければ、心身を休めることもできない。今ここ(here and now)に焦点を当てられている状態、またそのための方法をマインドフルネス(mindfulness)と言います。
1.マインドフルネス 思考が"今"から離れていると気づく
定義は色々ですが、マインドフルネスの考案者カバットジン(1994)はこう記しています。
Mindfulness means paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally.
マインドフルネスは、今この瞬間に、 判断を加えることなく能動的な注意を向けることを意味する。
出来事を価値づけるのは人間であるという考えは、認知行動療法と共通ですね。前回は思考のクセに気づくでしたが、今回は思考が過去未来や別のことに向かってしまっているのに気づきます。
ただ、前回は思考のクセに気づき困っていれば修正するアプローチでしたが、マインドフルネスは「判断を加えない(non-judgmental)」を強調します。思考と自分を同一視せず、雑念は浮かぶものだと受け入れつつ距離を取り、今に集中し直します。
ただ「放っておけ」ではありません。放置できるのだったら、最初から悩みません。当然そのための訓練を行います。マインドフルネスとして最も行われているのが瞑想(meditation)です。
瞑想といっても「無になりましょう」ではなく、むしろ無にはなれないと気づく練習です。意識を向けるものは呼吸です。雑念が浮かぶことを感じ、それを価値づけず呼吸に意識を戻します(文献④)。マインドフルネスにも色々あって食事とか歩行とか集中する対象が違うものもありますが、呼吸は普段していることですから追加の行動をする必要がなく、気づきを得やすいのかもしれません。
2.マインドフルネスと瞑想 宗教、エビデンス
マインドフルネスは元々仏教の禅から構想されました。1979年慢性疼痛患者のためにマインドフルネスストレス低減法(MBSR:Mindfulness-based stress reduction)を開発したカバットジンの著書が、90年代に大流行。研究も盛んになり、様々な定義や様々な方法が生まれている(文献⑤)他、自己啓発など商業分野でも様々な方法が生まれています。
基本的には、地域的宗教文化の要素が取り除かれることで、世界で誰もが実践でき科学的効能が実証される方法・道具になったとされます(文献⑥)。ただし、仏教側からマインドフルネスが論じられることもありますし(文献⑦)、商業的広まりの中で宗教的意義の再確認・再意味づけが起こることもあります(文献⑥)。
また、仏教はもちろん、1970~90年代頃のニューエイジ運動の瞑想ブームなど、マインドフルネス以外の文脈でも瞑想は色々行われてきました(文献⑤)。情報の中には文脈がぐちゃぐちゃになっているものもあるのでご注意ください。マインドフルネスの中でエビデンスがある方法があっても、マインドフルネスを標榜する全てがそうとは限りません。心理療法の範疇でないものも多数ありますし、心理療法にしても膨大な数あることは最初の回で述べた通り、絶対の方法はありません。
一方で、マインドフルネスが効果を生む構造を科学的に解明しようとする研究が多数あるのも事実です。例えば、脳では現在の行動と異なる意識していない思考「マインドワンダリング(MF)」時に働くデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)が注目されています。MFは記憶の整理などの役割はありますが、過剰になると集中力低下やネガティブ思考を生みます。
瞑想などマインドフルネスの取り組みはDMNの活動を低下させること、このプロセスを訓練することでDMN活動の制御を脳が学習していくことが示されています(文献④・⑧)。切替上手になるんですね。
ただどんな人・どんな場合でも瞑想すれば頭すっきりとは限りません。呼吸に意識を向けるとか感覚的な部分が多いのでやり方はどうしてもバラつきますし、向き不向きもあるでしょう。イギリスのオンライン調査ですが、定期的に瞑想をしている人の25.6%が瞑想により恐怖や不安など不快な経験をしたという論文もあります(文献⑨)。1度の経験で合わないとは断じれませんが、無理してやるようなことではありません。
3.感情を冷静に捉える "RAIN"
瞑想の他には、怒りや衝動など感情に対処する4ステップ「RAIN」はよく使われます。
(1)Recognize(認識する):「自分は怒っているな」と心情をメタ視点で捉えます。
(2) Accpet(受け入れる), Allow(許す):自分が怒っている事実を価値づけずそのまま認めます。
(3)Investigate(検証する):身体の変化を観察します。眉間にしわが寄っている、歯を食いしばっている、汗をかいているなど。その上でなぜ怒ったのか、自分が何を求めているのか考えます。
(4)Non-Identification(同一視しない), Not personalize(個人化しない):冷静に見たことで怒りと距離を置きます。ただし、Nに何を位置づけるかは識者により様々です。Nurture(育てる):検証を通して見えた自分と向き合う、Note(言葉にする):短文で状況を総括する、というバージョンもあります。
自分の感情を冷静に見て、身体の変化を観察する所が特徴です。
一部表現には揺れがありますが、頭文字をとった標語とは概して複数の解釈が生まれるものです。例えば挨拶のオアシス運動というものがあります。60年代から文献に残っているのですが、「し」の解釈は昔から「失礼(します)」と「親切」の2通りあるのが確認できます。
いま、ある小学校では「オアシス運動」というのをやっているそうだ。オハヨウ、アリガトウ、シツレイ、スミマセンの頭文字をとってオアシス運動。
一方、工場でも、人の和を保つため、明るい職場作り運動を三十八年から進めている。その一つに”オアシス運動”というのがある。
オハヨウ、アリガトウ、シンセツ、スミマセンの頭文字をとったものだ。
話をRAINに戻すと、原典は瞑想講師のマクドナルドが90年代に考案した方法で、瞑想講師のブラックが広めたそうです(文献⑫)。2人でもNは違いますが、こちらの通り他の識者も違いがあります。

細かい違いはともかく、感情が沸き上がった際に身体の感覚に目を向けてみる、ということですね。表現はお好みに応じて取り入れましょう。
4.アドラーは「今ここを生きる」とは言ってないけれど
アドラー心理学とマインドフルネスは世界観から親和性が高いことが指摘されています(文献⑬)。過去じゃなく、今ここを生きる、『嫌われる勇気』の青年が最後に感動していました。
青年:わたしは変わったのか、そしてそこから見える世界は変わっているのか、わたしにはまだ分かりません。けれど、一つだけ確信を持っていえます!「いま、ここ」は強烈に輝いていると! そうですとも、明日のことなど何も見えないくらいに、強く!
ですが、アドラーは「今ここ」とは言っていないと『嫌われる勇気』著者も言及しています。
「どうすれば人は幸せになれるか」に関する三つめのポイントは「今ここを生きる」ということです。アドラー自身はそんな気の利いた言い方はしていませんが(笑)。彼はそれを「ザッハリッヒ(sachlich)」というドイツ語で表現しました。これは「現実的」といった意味で、私は「即事的」という訳語を使っています。平たく言うと「地に足が着いている」という感じでしょうか。
では、元となったドイツ語sachlichはどう使われているのでしょうか。例えば、褒められる認められることへの依存が劣等コンプレックスに繋がるような話で、否定形unsachlichが出てきます。
Ein solcher Mensch muß unsachlich werden, weil er den Zusammenhang mit dem Leben verliert, weil er immer mit der Frage beschäftigt ist, was er für einen Eindruck macht und was die andern von ihm denken.
そのような人(認められようと努力する人)は、自分がどのような印象を与えるか、他の人が自分をどう思うかという問題を常に気にしているため、人生とのつながりを失い、現実との接点を見失うに違いない。
認められるかどうかばかり気にしていると、自分が今している行動そのものに集中できない。確かにこれは今ここを生きていない、マインドレスな状態と言ってもいいでしょう。
「今ここ」の語が取り入れられているのは、マインドフルネスの考えが、現代のアドラー心理学に影響を与えていると言えるのかもしれませんね。影響の方向性はどちらにしても、「今ここを生きる」価値観は共通していると思います。
(次回へ続く)
【参考文献】
①熊野宏昭「マインドフルネスはなぜ効果をもつのか」『心身医学』52(11)、pp. 1047-1052、2012年
②J. Kabat-Zinn "Wherever you go, there you are" Hyperion, 1994
③杉浦義典「マインドフルネスにみる情動制御と心理的治療の研究の新しい方向性」『感情心理学研究』162、pp. 167–177、2008年
④久賀谷亮『世界のエリートがやっている 最高の休息法 ―「脳科学×瞑想」で集中力が高まる』ダイヤモンド社、2016年
⑤齊尾武郎「マインドフルネスの臨床評価:文献的考察」『臨床評価』46、pp. 51–69、2018年
⑥砂田安秀「マインドフルネスと倫理」『心理学評論』643、pp. 363–383、2021年
⑦伊藤雅之『現代スピリチュアリティ文化論――ヨーガ、マインドフルネスからポジティブ心理学まで』明石書店、2021年
⑧山本彬貴・渡辺明日香・木村一志「慢性疼痛とマインドフルネス―注意機能に関わる脳内ネットワークの観点から―」『北海道文教大学研究紀要』45、pp. 1–11、2021年
⑨M. Schlosser, T. Sparby, S. Vörös, R. Jones & N. L. Marchant "Unpleasant meditation-related experiences in regular meditators: Prevalence, predictors, and conceptual considerations" PLOS ONE, 145, p.e0216643, 2019
⑩長野県警察本部警務部教養課『旭の友』368、1977年
⑪中央労働災害防止協会『安全衛生のひろば』10(2)、1969年
⑫T. Brach "Radical Compassion" Random House, 2020
⑬M. Bluvshtein, S. Saeedi, N. DeBruyn, K. L. Gillespie "Mindfulness, Therapeutic Metaphors, and Brain Functioning in Adlerian Therapy: Gemeinschaftsgefühl at Work" The Journal of Individual Psychology, 77(4), pp. 409-426, 2021
⑭岸見一郎・古賀史健『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』ダイヤモンド社、2013年
⑮岸見一郎「過去も未来もない。『今ここを生きる』のが幸せの条件」ダイヤモンド・オンライン、2018年:https://diamond.jp/articles/-/186658 (参照 2023年7月6日).
⑯Alfred Adler "Menschenkenntnis" Anaconda Verlag, 2022(初出版:Alfred Adler "Menschenkenntnis" m S. Hirzel Verlag, 1927)
⑰岸見一郎「未来を生きるアドラーの教え 第6回 承認欲求からの脱却」ミライノマナビ WEBサイト、2019年:https://mirainomanabi.up-edu.com/column/theme04/1219/ (参照 2023年7月6日).
★アドラー心理学とは何か"臨床心理学と自己啓発を整理する" 一覧はこちら
<前回>#8 認知行動療法 ~行動・考え方の癖に気づく~
https://note.com/gakumarui/n/n89e55aaeeed7
<次回>#10 ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)
https://note.com/gakumarui/n/nff5de4e271e3
専門である教育学を中心に、学びを深く・分かりやすく広めることを目指しています。ゲーム・アニメなど媒体を限らず、広く学びを大切にしています。 サポートは文献購入等、活動の充実に使わせて頂きます。 Youtube: https://www.youtube.com/@gakunoba
