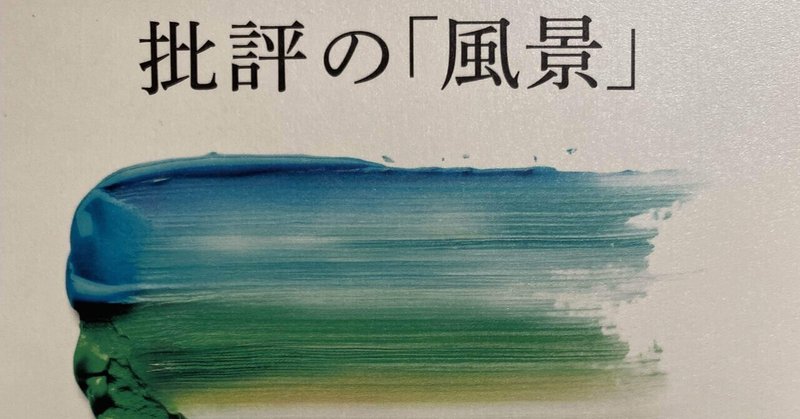
読書記録(2024年 2月分)
脳みそが崩壊しかけた2月。リハビリとしてよく図録を読んでおり、単著をそこまで読んでいないですが、いいものをいくつか。
文芸書
①オクタビオ・パス『鷲か太陽か?』
メキシコを代表する詩人の散文詩の最近の翻訳。パスの詩は、繊細を超えて病的な透明さへ向かう近現代詩とは異なり、骨太で豊饒なイメージの世界を湛えています。
シュルレアリスムの影響が色濃いのですが、そこに安住しない野性的な表現も、中南米的な極彩色も、パス自身の力強さに収斂しており、勇気づけられるところもありました。
解説も簡潔ながら要点が分かり、面白いものでした。
②ジョン・バージャー『批評の風景 ジョン・バージャー選集』
英国を代表する美術批評家の論集から精選されたものが並んでいます。いくつも既に日本語訳されていますが、このような形で決定版として刊行されたことを寿ぎたいです。碩学トム・オヴァートンが編集したのも凄いなと。
ただの批評としてではなく、古くはラスキンからの「文学としての批評」の良き伝統がここに宿っています。「キュビスムの瞬間」や「理想的な批評家と闘う批評家」など、異なる分野を取り上げたものが楽しめて、アンソロジーの醍醐味がここにあります。
美術書・専門書
①ハンス・ブルーメンベルク『神話の変奏』
「現実」が人間生活の一切を無慈悲に奪っていきますが、人類はそれに物語を投影して意味づけをすることにより、衝撃を緩和してきました。それこそが神話の起源であり、その役割は時代によって宗教や神学、そして芸術へと「変奏」していったという巨大な動きを書いている本です。
文化とは何かなど、巨大な問いに真正面から向かい合ったスケールの大きさが魅力的です。ただ、ドイツ人としてゲーテという存在を媒介して色々語ったりするので、根拠に偏りがあるのは否めませんし、西洋の神話や古典を理解していることを前提に進むので気楽に読めるものではありません。
②フィリップ・ラクー=ラバルト、ジャン=リュック・ナンシー『文学的絶対』
なぜ大学で文学(芸術)を学べるのか。それは娯楽ではないのか。つまり文学は学問の殿堂にのせるべき価値があると誰かが主張したわけですが、そのイデオロギーの起源を19世紀初頭のドイツ・ロマン主義の面々に見る、という本です。
イェーナという小さな町に集った文学者が『アテネーウム』という雑誌を創刊し、理論的な洗練が行われた小さな点に解剖学的なメスをいれて、その価値を明るみに出すというものです。彼らの文献のそのままの翻訳もあって、本の分厚さの割にはスッキリしています。
③椹木野衣『感性は感動しない 美術の味方、批評の作法』
現代美術についての軽い入門書。批評家はどのように作品を見ているかといったことなどから、思い出といった個人的なところまで書いてあります。難易度的にも誰でも読めるものです。知識以前の「態度」といったところを掴みたい場合、参考になることが多いです。
かなり挑発的なことが書けるのも、入門書的な自由さ故に思います。価値ある内容は上にあげたようなゴツイ専門書にあると考えがちですが、アカデミックな作法と先行文献で縛られているため、入門書的な本の方が刺激のある中身の場合がありますが、本書もこれに当てはまる例です。
④D.M.ロペス、B.ナナイ、N.リグル『なぜ美を気にかけるのか:感性的生活からの哲学入門』
芸術作品からではなく広く美的経験を対象に平易な言葉で考えてくれます。読みやすく、かつそれだけで終わらないのが特徴で、読者側も思索の現場に歓待してくれるような本です。
若手の気鋭の美学者がそれぞれの立場からアプローチしてくれているので、「これはそう思う」「ここは違うのでは」と色んな美学的思索の叩き台になってくれます。ポップな割に奥行きのある本でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
