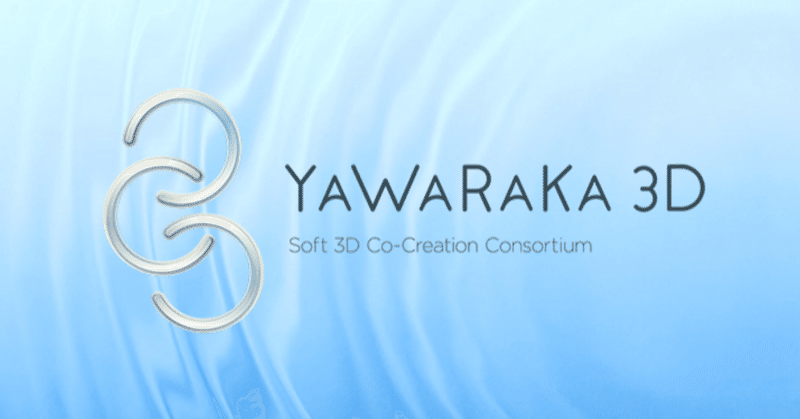
3Dプリンターの普及の壁は何か?
やわらか3D共創コンソーシアム 会長の古川ヒデミツです。
海外に比べて、日本での3Dプリンターの普及が遅れているといわれています。そのヒントになりそうな、新しめの記事をクリップしてみました。
日本AM協会が進める「日本で3Dプリンターが普及しない問題」への打開策
2022.10.05
『澤越氏:設計開発を進めるうえで、形状や一部機能の確認をする際に3Dプリンターを使うのは、日本でも中小企業を含め実施しています。しかし、それをもって「日本が3Dプリンターを活用している」というのは大きな間違いです。私たちの身の周りで使っている製品で使える形にするには、品質保証や法定管理といった複雑な要素が絡んでくるからです。』
『――今までの作り方からAMに変えると、様々な要因に対して保証や検証をしなければいけなくなるということですね。
澤越氏:はい。ものづくりに関わるすべての工程の方々、設計から部品管理、製造管理、あとの保証や品質管理の方々など全員が、AMのために今まで学んできたことと違うマインドを持ち、AMに準じた生産ラインなど新たなものを構築しなければいけないということです。
つまりこれは、大手企業になればなるほど莫大な時間とお金がかかることを意味します。 海外では既に取り組んでいるこれらの事柄を、「いずれやらなければいけない」というのは、日本の製造業に携わるの皆さまの共通認識としてあります。
ですから、展示会やセミナーには多くの方が情報収集に来られます。でも、同じ状態を目指して行動を起こすかというと、「今はそのメリットがないから」という話になるわけです。結局は、AMに対してコストをかけても、それを取り返せる見通しが立たない、自信を持ってスタートを切るだけのビジネスが描けないんです。ここが一番の要因ですね。』
『大企業になればなるほど、行動管理・作業管理は厳しくなりますから、会社が認めないテストや作業に時間をかけるのは難しいです。昔は「それ面白そうだから、ちょっと隠れてやってみなよ」という流れがあって、そこからウォークマンやVHSテープなどの商品が生まれました。でも今はそれをやらせてもらえないのが実情です。』
「AMに取り組まない3つの理由」を乗り越えるためにはバリューの理解が必要ー日本3Dプリンティング産業技術協会(J3DPA)
2022.11.01
『シェアラボ編集部:なるほど。そういう意味では「試作分野ではもう活用が進んでいる」という実際の実態はあるということですね。
三森氏:はい。その認識でシェアラボ編集部さんが先ほどおっしゃった「じゃあなんで日本は弱いのか」、試作を3Dプリンターで取り組んでいるのはわかった上で、製造業でどうして弱いのという話になってくると思いますが、私は原因が3つあると思っています。
1点目が国産3Dプリンターが育っていないために製造技術情報が不足している点。
2点目が何に使ったらいいかという設計的・商品企画的な理解が不十分である点。
3点目が製品や部品の単価にとらわれすぎてプロセス全体のコストを検討できていない点です。』
【起爆剤になるのは動作原理まで知り抜いた専門家との対話】
『三森氏:私は、日本で3Dプリンターが最終部品の製造で活用されない阻害要因としてはやっぱり動作原理を深く知り説明責任をきちんと果たせる、良質な3Dプリンターの装置メーカーや造形を行う加工業者がまだ育って来てないというところだと思います。やっぱり日本人はしっかり技術的に全てを把握しながら行きたいのだと思います。製造環境を相談しながら活用をすすめていける体制や、ぐんぐんモノづくりの深い議論に入っていく会社やチームが必要だと思います。』
日本の3Dプリンター活用を阻む3つの壁と闘う!群馬積層造形プラットフォーム(GAM)の挑戦
2022.10.19
『GAM小川氏:大きく3つあると思います。
1つ目の壁は、「中小企業にとって3Dプリンターの導入は少なくない設備投資になる」ということ、そして2つ目の壁は「3Dプリンターがあるだけでは、積層造形ができない」ということです。
AMには前工程や後工程があるため、それらを含めた設備投資をすると、相当な予算が必要となるでしょう。
そして最後の3つ目の壁は、「ノウハウを学ぶ機会がない」点です。
日本ではAM教育の場がほとんどありません。実践しているサービスビューロなどに外注しても作業過程を見ることができませんので、やり方はわかりません。自社の知見として蓄積できないため、3Dプリンターを活用したものづくりができる技術者の養成にはならないんですね。』
海外と日本の決定的な違い。日本のAM活用推進に必要なたった1つのポイントーひょうごメタルベルトコンソーシアム
2022.10.19
『柳谷氏: 一方で海外を見たら、決してそうではないんです。面白かったのは、海外の方に話を伺った際に、『アルミを材料にした3Dプリンター造形に取り組んでいます』というので『何に使ってるんですか?』と聞いたら、『飛行機に使ってる』っておっしゃるんです。『じゃあ飛行機のどこに使ってるんですか?』と聞くと『客席の脚』とお答えになるんですね。『強度計算して、従来工法よりラティス形状の脚の方が軽いから燃料代が減る。飛べば飛ぶほどコストダウンになる』と。そういうところとか、あるいは電車の運転席の部品とかね。めったに出ない部品だからコストダウンにつながるということで、3Dプリンターで作ってしまうんです。』
『だから別に、3Dプリンターならでのすごい部品性能を目指すわけではなく、上手に使いどころを見つけているんですね。『とにかく1回使ってみよっか』と、『少量でもいいから、とにかく1回これ作って使ってみよう』とうまく初めの第一歩を踏み出している。自動車でも所有者のサインを3Dプリンターで造形して車のエンブレムに使う、とかね。そういう使いどころを見つける発想がうまいんですよね。
日本人は真面目なんで『疲労寿命がどうだ』とか『レーザーによる急速凝固で新たな金属組織を目指す』とか、ひたすら性能面で突き抜けた向上を目指そうとする感じです。だから、ハードルがものすごく高くなっているんです。欧米の展示会に行ったら、すごいものばかりではありません。遊び心のある、小さな取り組みもいっぱいあります。
ShareLab編集部:実際に使って効果が出る使い方を見つけるのがすごく上手ってことですね。
柳谷氏:そうですね。やっぱり海外の人って発想や考え方が違うなという気が本当にしますね。こんなところに使ってこれ儲かるんですか?って、日本人だとそんなこと言いたくなるんですけど。一旦これで使ってみたとか、作ってみたという挑戦をしています。』
第一次ブームから10年 3Dプリンターは流行から社会実装へ
2023年1月 (有料記事)
『2012年~2013年頃にかけて、日本では3Dプリンターの第一次ブームが起こった。熱溶解積層(FDM)方式などの樹脂系3Dプリンターの基本特許が切れたことで、アメリカや中国のスタートアップが3Dプリンターを続々と発売。安価かつ小型のプリンターが登場し、個人がものづくりに参入する「メイカーズムーブメント」が脚光を集めた。これにより樹脂系3Dプリンターは市民権を得たものの、企業での活用は試作品を作るためのラピッドプロトタイピング(RP)が中心であった。
それから約10年で、造形速度の高速化、樹脂以外の金属やセラミックなどの印刷材料の普及、プリンターの低コスト化などが進み、RPだけでなく、3Dプリンターで最終製品や実用的な部品・治具を作る「ダイレクト・デジタル・マニュファクチュアリング(DDM)」の時代が訪れつつある。』
3Dプリンティングの現状と将来展望
*本稿は『カレントひろしま』2018年11月号(発行:一般財団法人ひろぎん経済研究所)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載。
『【デジタル化との相性が良い】
Cyber Physical Systems(CPS)やドイツのIndustrie 4.0、米国のIndustrial Internetなどが広く注目されだしたのも、AMのブームが巻き起こった2013年頃であった。これら第四次産業革命の要素の1つとしてAMが位置づけられている点にも注目すべきである。日本政府はSociety 5.0を、そして経済産業省は目指すべき産業のあり方としてConnected Industriesという概念を提唱しており、ここでもAMは重要なツールの1つとして意識されている。Society 5.0のもと様々な施策が打ち出されており、今後のものづくりにおけるAMの活用拡大に期待したい。』
『本稿ではAMの夢を語ることを極力避け、AMの特徴を示し、現状の課題とその対処方法について詳しく述べた。AMは工作機械の一種であるため何に使うのかはユーザー次第であるが、アイデアを生み出し技術革新を起こす可能性を大いに秘めた技術である。先に良いアプリケーションを思いつけばマーケットを大きく獲得することが可能かもしれない。
反面、海外でアプリケーションが出てくるのを待っていては手遅れになってしまうだろう。装置の導入まではいかなくても、サービスビューロの利用でAM製品を作ることも可能である。多くの企業がAMの活用に取り組み、我が国発の技術革新が数多く生まれることを期待してやまないところである。』
いろいろなプレーヤーが大きなうねりを起こしつつあります。
やわらか3D共創コンソーシアムでは、3Dプリンターの社会普及に取り組んで参ります。今後ともよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
