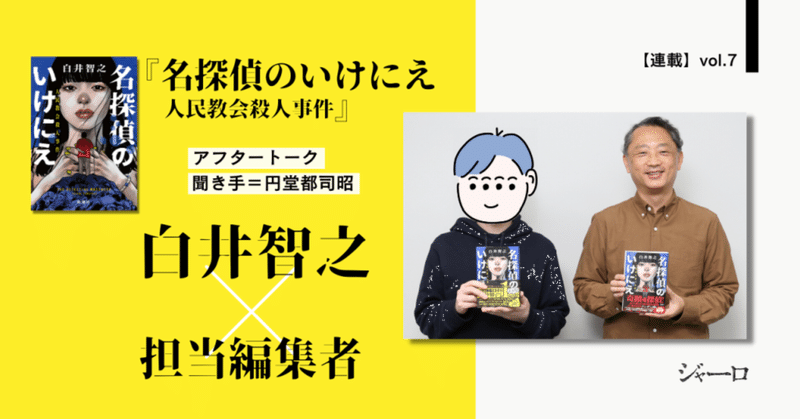
『名探偵のいけにえ 人民教会殺人事件』(白井智之)・2022年の各ランキングで軒並み上位に!【著者×担当編集者】アフタートーク 第7回
対談=白井智之(作家)× 新井久幸(新潮社)
聞き手・構成=円堂都司昭

二○二二年十一月三十日、光文社にて収録。撮影/近藤陽介
※対談はソーシャルディスタンスを守り、マスクをつけて行いました。
『本格ミステリ・ベスト10』第1位、『このミステリーがすごい!』第2位、『週刊文春ミステリーベスト10』第2位など、二〇二二年末のランキングで軒並み上位となった『名探偵のいけにえ 人民教会殺人事件』。カルト教団を舞台にした同作は、奇蹟を信じる人の集まりという特殊条件で多重解決がなされる、企みに満ちた内容で高く評価された。作中で信者たちが粉末ジュースのクールエイドを飲んだことにならい、アメリカから取り寄せた実物で乾杯してから(※作者の提案)、本作の成り立ちをふり返る取材はスタートした。
設定の一貫性をどう表現するか
――新潮社での白井さんの担当は、最初から新井さんだったんですか。
新井久幸 いや、小社での前作『名探偵のはらわた』は別の者が担当で、自分はデスクとして背後霊的に関わっていました。僕は長いこと単行本の編集をやってから「小説新潮」編集部へ移り、今は再び単行本の編集部に戻ってきています。基本はデスク業務ですけれど、プレイングマネージャー的に時々本を作る、そんな感じです。
白井智之 『名探偵のはらわた』の仕上げの段階のころに新潮社でご挨拶したのが、新井さんとの最初の出会いですね。
――津山事件、帝銀事件、阿部定事件など実際にあった事件をモデルにして作中要素とした『名探偵のはらわた』の後、『名探偵のいけにえ』の企画はどのように始まったんですか。
白井 前作ができた時、次もよろしければといっていただいて、前任の担当者と打ち合わせを始めていました。その段階では、同作の直接の続編か、違う方向性を目指すか、二つのパターンを考えていました。幸い『名探偵のはらわた』は増刷もしたし、良い評価をいただけたので、次もトーンダウンしないようにしたい。ただ、前作は人殺しがいっぱい蘇る内容だったので、普通の続編だと同じような内容になってしまいそうだから、それに縛られずゼロベースで考えましょうという話になりました。その方向で最初のプロットを作ったくらいの段階で担当の変更があり、新井さんと相談するようになりました。
新井 今ここに、最初にもらったプロットがありますけど、けっこうページ数があって、かなりかっちりした構成になっています。最終的な作品では人物名、固有名詞が変わったので、原稿を読んでみて、これ誰? みたいな部分もありましたが、全体の骨格は早くにできていたんです。だから、けっこう長い間、細かく考えを詰める期間があったんじゃないかと想像しました。
――名前が変わっても、物語で役割を果たす人数は、最初から揃っていたわけですか。
白井 そうです。細かいキャラクターは実際に話を作るなかで増えましたけど、大筋に関わる人物や設定は、決まっていました。
――多重解決もできていたんですか。
白井 プロットの時点でできていました。この話のメインのアイデアは登場人物の世界観というか、世界のとらえ方によって解決が変化するところ。それ自体は前から考えていて、書けたら面白そうだなとメモしていました。それを、実在の事件をモデルにしてとりこむこのシリーズのやり方と掛けあわせたらさらに面白い話ができそうだと思ってプロットを作ったので、順番として多重解決はむしろ構想の一番初めからあったんです。架空の宗教があって信者と信者じゃない人がいて、という設定も以前から考えていて、その構造的なアイデアに肉付けをしてこの話にしたという順番です。
――カルト教団が舞台ですが、なぜ人民寺院をモデルにしたんでしょうか。彼らがガイアナで集団自殺したのは一九七八年。白井さんが一九九〇年に生まれるよりかなり前です。
白井 集団自殺したとされる教団はブランチ・ダビディアンや太陽寺院などほかにもありますが、人民寺院を選んだ理由はトリックとの兼ねあいや、場所のふさわしさですね。スケールの大きい事件ですし、南米で集落を作った点も本格ミステリの題材として魅力的なので、時間をかけて調べました。連続殺人をめぐるダブルバインド(二重拘束。二つの矛盾したメッセージによって混乱した状態)や多重解決の流れから、より大きな規模の集団自殺に至る展開を思い描いていたので、プロットから必然的に人民寺院がモデルとして必要になった感じです。
――プロットを読んだ時点で新井さんは、作品の方向性をどうとらえていたんですか。
新井 たまたま、特集したテレビ番組を見ていて人民寺院事件は知っていました。カメラマンが、死ぬ最期の瞬間まで撮っていた映像が残っていたりするので、エグいやつテーマに選ぶんだなと感じつつ読みましたが、もうプロットの段階で、何をやろうとしているのか、ある程度できあがっている印象でした。原稿にならないとわからないことはいっぱいあるので、この段階でなにかいっても仕方ないとわかりつつも、とりあえず気になるところについて聞いておこうと思いました。いつもそうなんですが、とにかく聞くだけ聞いて、そういう風に感じる読み手もいるんだと書き手に知ってもらい、それによって内容がわかりやすくなるならいい、という考えです。
最初に気になったのは、ある人物の行動の動機です。そこは肝だと思ったので上手にやらないと、それはないだろうと読者に思われるから、説得力を強めたほうがいいとお話ししました。
あとは、奇蹟について、信者たちにはどう見えているのかという点です。例えば、病気も怪我も存在しないという教団に腕のない人がいて、信者たちはどうとらえているのか。部外者には腕がないように見えるけれど、信者たちは腕がないとは認めない。彼らは、そういうものだと頭で納得してただ概念として受け入れているだけなのか、本当に腕があるように見えているのか。その辺の見え方はすごく気になったので、けっこうクドく聞きました。
白井 厳密にいうと今回は特殊設定ミステリとは違うんですが、そのようなタイプの小説で毎回悩まされることの一つが設定の作りこみ、納得度の高め方なんです。作中での一貫性をどう持たせるかが大事だから、そうだよな、と思いながら新井さんの話を聞いた記憶があります。
新井 全部を作中で説明してもらう必要はないんですが、設定をかっちり作ったうえで書かれていれば、安心して読めると考えています。

「特殊設定」ではなく「特殊条件」
――作家によっては、編集者に意外性を味わってもらいたいからと、ラストについては話さないまま原稿を渡す方もいますけど、白井さんのプロットは全体が書いてあったんですね。これは白井さんにとっては通常のやりとりなんですか。
白井 そうです。
新井 僕は、書きたいものを書くのが一番いい作品になると思っているタイプなので、プロットなしでもいいんです。相談があればもちろん乗りますけど。プロットだけ先に読んじゃうと、初読の人がどこで驚くか、内容をちゃんと理解してくれるかわからないから、不安との戦いはありますよね。
――プロットを出した後は、実際に原稿を書いて、途中でいったん見せるんですか。
新井 いや、それは最後までできてからでしたね。
白井 ……最後まで書きましたね。編集者から途中で見せてといわれれば見せることもありますが、基本的に最後まで書きます。途中で見ても……。
新井 ミステリの場合、記述がおかしいのか伏線なのか、最後まで読まないとわからない。それに、いったん書きあげても、最初のほうへ遡って直したりすることもありますから。
――第一稿が書きあがるまで、期間はどれくらいだったんですか。
白井 他の仕事もやりつつでしたが、一年まではかかっていないと思います。でも、自分の本のなかで、一番時間がかかったことは間違いない。
――第一稿を受けとってからの修正のやりとりは。
新井 原稿になってからのやりとりは、一回だったと思います。こちらが気づいたことをメモしてお渡しして、修正していただいたものを入稿しました。
――例えば、いくつかの推理の順番を入れ替えるような、大きな改稿はありましたか。
新井 ないです。この作品はそんな風にいじれないというか、いじると崩壊してしまう。前作より百ページくらい増えて四百ページくらいあるんですけど、紙も値上がりしているし定価が高くなるから「参ったな、短くできないかな」と最初は思ったんです。削れるところはないかと探しましたが、ないんですね。本番の事件が始まるまでに前日譚があって、それが事件には直接関係ないように一瞬思えたので、ここを短くできないかと考えましたが、最後まで読むと削れないとわかる。これが物語の土台になっていて、後で効いてくるから。もう、削れる部分を探すのはやめようと思い直しました。
――結果的に『名探偵のいけにえ』は、ミステリランキングで好成績を記録しました。
新井 ランキングがすべてではないとはいえ、やっぱり嬉しいです。白井さんもおっしゃっていたんですけど、主戦場は『本格ミステリ・ベスト10』だと思っていたんです。前の本より上の順位になったらいいな、そうなってしかるべきだと思っていたので、そこで1位をとれて他のランキングも上位になったのは、嬉しかった。みんな、ちゃんと読んでくれて、本格が好きなんだなって。
――『本格ミステリ・ベスト10』で白井さんは、二作目の『東京結合人間』(二〇一五年)の8位以来、ずっと10位以内が続き、『名探偵のはらわた』(二〇二〇年)の3位がそれまでの最高でした。そのシリーズの次作だから、ランキングは意識していましたか。
新井 駄目だったらショックが大きいので口には出しませんでしたが、今回は3位より上を狙っていました。引き継いで最初の本ですから、担当が変わってつまらなくなった、なんて最悪じゃないですか。だから、結果にホッとしています。

――白井さんの作品の場合、二〇一四年に『人間の顔は食べづらい』でデビューして以来、結合人間とか人面瘡とか特異な設定の内容が多かったですから、ランキングの順位と同時に、今度の内容はどこまでグロテスクかということにも関心が持たれがちです。
白井 そうですね。
――その点、『名探偵のいけにえ』はかつてほどグロテスクじゃないというか……。
新井 みんな、グロじゃないというんですけど、もう絶対麻痺してますよ(笑)。相対論で語るから大したことないって話になるんですけど、作中で九百人も死んでいますからね。これまでで、たぶん一番死んでいます。切断死体も出てくるし、グロかどうかはわからないですけど、ひどいことにはなっていますよ。
白井 ただ前作も、ひどい人がたくさん出てきてひどいことをして回るような話ではなかったので、今回も同程度に揃えてはいます。また最近は、作品ごとにミステリ的なアイデアがどういう書き方なら一番活きるかを考えています。バイオレントな世界観のほうが活きるトリックやアイデアもあれば、逆にそうではないように作りこんでいったほうがいい場合もあると思うんです。『名探偵のいけにえ』で読者に一番ギョッとして欲しいのは、やっぱり九百人が毒を飲んで一夜にして死んでしまう場面です。そこが活きるように書けるかが、この話の大事なところだと思ったので、それ以外は登場人物がやたらと乱暴なことをしたりはせず、普通のキャラクターに造形したつもりです。
――本の帯に「多重解決」と「特殊条件ミステリ」とありますが、「特殊設定」ではなく「特殊条件」としたその微妙さが重要かと思いました。
新井 そこを拾っていただいたのは嬉しいですね。
白井 世界そのものの前提や法則が変わってしまった特殊設定ではなく、あくまで一部の宗教を信仰する人の認識が歪んでいる話です。帯のコピーの提案で最初に「特殊設定」と書かれていたことに対し、そう話したら、新井さんも「実は僕もそう思っていたんです」と。
新井 その時、なにか他の言葉を考えます、思いつかなかったら特殊設定でそのままにさせてくださいといったんですが、意外とすぐに「特殊条件」が思い浮かんでメールしたら「それいいですね」となりました。そんなやりとりもありつつ、悩んでひねり出したんですけど、ネットの感想をみると普通に「特殊設定」と書いてあって(笑)。でも、本格ミステリで、条件づけ、言葉の定義、どういう背景かにこだわって書かれた作品ですから、紹介もこだわってやるべきだと考えました。
――『名探偵のいけにえ』では、作中の地図の絵柄にも味わいがありますよね。
白井 僕が作ったものを元にして、プロの方に、イラストに起こしてもらったんです。そうしたらお墓とかキッチンになっている車とか、僕のラフになかったものまで本文を読みこんで絵にしてくださった。感激です。僕が死んだら棺桶にこの地図を入れてください(笑)。
新井 ちなみに冒頭にある英文の遺書は、白井さんの手書きの字です。
――『名探偵のいけにえ』は、前作『名探偵のはらわた』と関連はあっても直接の続編ではない。位置づけとしては。
新井 公には姉妹編と呼んでいます。続編といって、前作を読んでいないといけないと思われるのは困るし、順番に関係なくこれはこれで読んで欲しいので。



本格スピリットが強い二人
白井 変な宗教が支配するコミュニティへ行って、事件に巻きこまれる。その構造に関して最初に思いついたアイデアがあったのですが、それをどう料理していくか、自分では良いアイデアと思いながら不安もありました。「あぁ、なるほど」とパッと理解できるトリックとは違うし、だいぶ頭でっかちというか、多重解決や特殊条件についてああじゃこうじゃ考えた先に生まれた着想なので。自分はすごく好きだけど大丈夫かなと思ってプロットをお渡ししたら、これがやりたいんだよなと思っていたところを、新井さんが「ここがいいよね」とリアクションしてくれて、本当? ああ、良かった、と思った記憶があります。
新井 だったら良かった。僕もそうですけど、本格スピリットが強い二人なので、そうじゃない人たちはどうかという不安はありました。『名探偵のいけにえ』は、これだけ複雑なことをやっているのにわかりやすく書いてあるので、読者がめくり返してチェックしなくても大丈夫。そこもすごいところですし、ロジックの積み重ねだけでも素晴らしいのに最後の最後に一本背負いが待っていて、まだやるんだという点も上手い。
白井 フーダニットやハウダニットに分類される謎解きに関しては、手がかりの解釈から導き出される論理的な推理で展開していきますが、ある人物の動機については手がかりに基づく推理とはやや推理の性質が違う。そこは新井さんにも指摘されたところで上手に見せないといけないので、初稿の後、要素を足し引きして今のバランスに持っていきました。
――お話を聞いていると、本格スピリットで結びついた二人が和やかに作り上げた印象ですが、意見の違いや衝突はなかったんですか。
新井 細かい部分を色々と「ここはどうなってるんですか?」と聞いたくらいでしょうか。ただ、物語の終わらせ方として、動機を断言しない、決めつけないほうが絶対いいと思うというのは、しつこくいったかもしれません。
白井 初稿の後、伏線の強弱みたいな話をすごくした記憶があります。自分の他の本と比べても細かい情報の量が多い話なので、読み手が一つひとつの情報を全部覚えているわけはない。そのへんの強弱について、ここはもっと書いておいたほうがいいとか……。
新井 最初のほうでちょっとだけ出てくる話は途中でおさらいしてください、絶対ばれないからもうちょっと伏線をわかりやすくとか。全部についていうわけではないですが、何ヵ所か指摘すると、白井さんが読み返しながら判断してバランスをとり、他にも修正が増えていく。削ったり増やしたり改稿するうちに伏線だけが残っているとか、その逆とかが出てきて大変でした。読者がちゃんと驚いてくれるか不安だったから、会社でミステリが好きそうなやつに読んでもらって感想を聞き、それを反映したりしました。
あと最初、こんなに大怪我した人がずっと喋るだろうかという場面があって、そこは怪我の程度が軽くなりました(笑)。
白井 僕が『人間の顔は食べづらい』でデビューする時、KADOKAWAに呼ばれてここを直してくださいと最初にいわれたのが、「腹から腸が出る描写があるんですけど、出たら普通、人は死んでしまうので出さないでください」ということでした。自分はずっと同じことをやっている。過度に人を傷つけすぎている(笑)。
――シリーズ三作目の予定はどうですか。
新井 この次はみんなのハードルが高くなりすぎて、おいそれとはできないですよね。と、僕も無駄なプレッシャーをかけていますが(笑)、白井さんから次の大枠の構想をチラッと聞いたら面白そうなんです。
白井 『名探偵のいけにえ』を作った時と同じスタンスというか、ミステリ的にやりたいことを第一に考えて、それ以外の部分は柔軟に調整していく感じで次もできたらいいなと思っています。
――その本はいつくらいに出るんでしょうか。
白井 ……来年ではないですね。
――すごい小声(笑)。
白井 『名探偵のはらわた』では殺人鬼たちの蘇り、『名探偵のいけにえ』では宗教的な設定を使った多重解決というように、次作もまず作品の核となるところを構想しなければならないので、それを考えているのが今の段階です。
新井 僕としては『名探偵のいけにえ』が文庫になる前に新作を出したい気持ちはありますが……。今回の作品は、本当に最初のプロット段階から物語がかなりできていたので、僕がとやかくいう余地はなかったというか、細かいところをいじったら全部に関わってしまうということもあった。『名探偵のいけにえ』の多重解決は、他の多重解決とはちょっと違う。他は、探偵による材料の選び方や並べる順番を変えたりで事件の見方が違ってくる、勝手に事件が複雑になる話じゃないですか。でも、この作品は根本的に違う。謎を解く人ではなく、事件を見ている人たちの立ち位置によって解決が変わるわけです。いうのは簡単でも、物語で読ませるにはめちゃくちゃ難しいことをとてもわかりやすくやっている。だから、本当に純粋に楽しませていただきました。簡単にいうと、白井さんが勝手に頑張っただけで、僕はこの本に関われて良かった。そういう感じです。
(おわり)

《ジャーロ No.86 2023 JANUARY 掲載》
■ ■ ■
▼ジャーロ公式noteでは、皆さんの「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。
いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!
