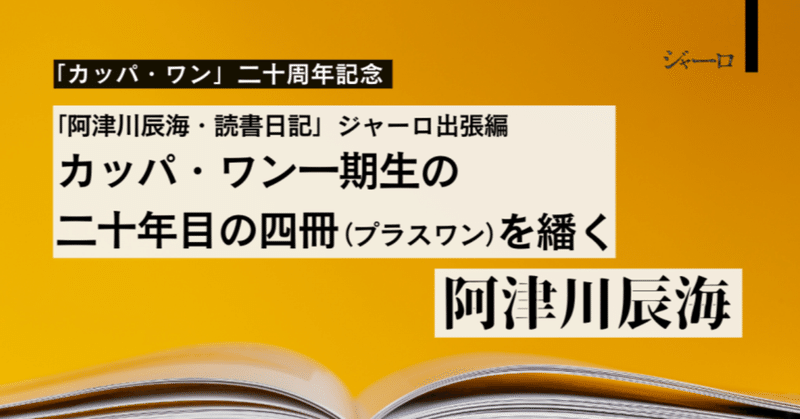
阿津川辰海|カッパ・ワン一期生の二十年目の四冊(プラスワン)を繙く【「阿津川辰海・読書日記」ジャーロ出張編】
▼「カッパ・ワン」第一期四人の特別座談会はこちら
はじめに
カッパ・ワン二十周年、おめでとうございます!
石持浅海、加賀美雅之、林泰広、東川篤哉(敬称略・五十音順)の四名が揃い踏み、華々しいデビューを飾った日から二十年。それぞれがそれぞれのスタイルで本格ミステリーを追求してきたからこそ、この二十年があり、石持浅海・東川篤哉の両氏が選考委員を務める「カッパ・ツー」の創設に繋がり、その第一期生として私が選ばれた……そう思っております。この四氏は私がミステリー読みたての中学生の頃から慣れ親しんでいた四人であり、多大な影響を与えられた方々でもあります。
そんな四人の新刊が、カッパ・ワン二十周年を記念して、この二〇二二年に揃い踏む……そう聞いた瞬間から、私のワクワクは止まりませんでした。
そして、四作品を読んでみると、この二十年で、四人がそれぞれ変わったこと、あるいは逆に、変わらず貫いたことが、如実に見える四作品になったのではないかと思いました。そこで今回は、ジャーロHPにて私が連載しております「阿津川辰海・読書日記」の出張編として、この四人の新作を全て紹介させていただこう、という企画です。よろしくお願いします。
石持浅海『高島太一を殺したい五人』
さて、トップバッターは石持浅海です。石持作品には、超合理主義を体現したような登場人物たちが多く登場します。登場人物たち(犯人、あるいは探偵たち)が合理性を重視するがゆえに、彼らが組み上げた論理は、時に倫理を超越してしまうのです。
こうした世界観の中で、石持浅海は犯人の視点から事件を描く、いわゆる倒叙ミステリーを数多く著してきました。『扉は閉ざされたまま』などの〈碓氷優佳〉シリーズが代表的な作例ですし、雑誌「紙魚の手帖」では、犯罪に手を染めるべきか悩んでいる人の相談を聞くNPO法人を描いた、トリッキーな倒叙連作〈犯罪相談員〉シリーズを連載中です(おそらく本にまとまったらユニークな傑作になることでしょう!)。倒叙に限らずとも、テロリストの視点から描いた「日常の謎」と言える『攪乱者』や、殺し屋が依頼人にまつわる謎を解いていく『殺し屋、やってます。』に始まる〈殺し屋〉シリーズなどでも、石持は犯人視点の謎解き小説を追求してきました。
本書『高島太一を殺したい五人』は、この石持倒叙ミステリーの系譜に連なる一作であり、新たな到達点を示した傑作です。と同時に、非常にアクロバティックなプロットを導入した作品でもあります。
塾のサマースクールに集まった五人は、それぞれに高島太一を殺したい、という動機を抱えている、というのが最初のシチュエーション。この「動機」というのが、さすが石持作品の登場人物と言いたくなるほど一人一人歪んでいるのがミソ。その昔、『君がいなくても平気』のノベルス版に「捕まらないでくれ。僕と別れるまでは。」という主人公の心情を捉えた帯文が掲載されていましたが、石持作品の登場人物は、徹底的に合理主義であるがゆえに、時折その言動がとても身勝手で利己的に見えるのです。こうした歪みが五人それぞれに見えるのがまず面白い。
そして、事件は早々に、意表を突く展開を見せます。事態が変なところにもつれていき、それと同時にこの「五人」のディスカッションも加速していくのです。二百ページという短さながら、起伏のある展開で楽しませてくれるところは、さすが石持ミステリーというべきでしょう。短い作品ですし、序盤の展開にもトリッキーなひねりがあるので、ここから先の展開をあまり書くわけにはいきませんが、やはり終盤のロジックの跳躍に驚かされました。石持本格は、自在です。
二十年経っても変わらぬ企みの妙と、よりしなやかになった手さばきの巧さで読者をもてなす傑作です。
加賀美雅之『加賀美雅之未収録作品集』
本書は、二〇一三年に、五十四歳の若さで亡くなった加賀美雅之の未収録作品をまとめた画期的な短編集です。各種アンソロジーに発表した短編や、デビュー前に連名で文庫の公募雑誌アンソロジー「本格推理」「新・本格推理」に発表した短編を集成しています。
これまで本になった加賀美作品は、シャルル・ベルトランという探偵役を主人公とした本格ミステリーでした(私は『双月城の惨劇』の塔の密室とホワイダニット、そして『監獄島』の盛り込みすぎなところが大好きです)。もし、これまで加賀美作品を長編やベルトランものの短編集『縛り首の塔の館 シャルル・ベルトランの事件簿』でしか読んだことがないという方がいたら、『加賀美雅之未収録作品集』で、著者のもう一つの側面を知ることが出来るでしょう。
それは、史実と記述を巧みに織り上げるパスティーシュの名人、という顔です。
ここで「史実と記述」というのは、「史実」は歴史を指し、「記述」は参照元となる一次作品……加賀美にとっては、カーの〈アンリ・バンコラン〉シリーズや〈ギデオン・フェル博士〉シリーズ、あるいは鮎川哲也の〈鬼貫警部〉シリーズなどを指します。こうして並べると、これはパスティーシュに伴うものなので、「史実―歴史」は唐突に感じるかもしれませんが、カーの「パリから来た紳士」や山田風太郎の「黄色い下宿人」を思い出してもらえればニュアンスが伝わると思います。史実、歴史の中で「あったこと」と、尊敬する作品の中で「書かれたこと」との空隙に、「あり得たかもしれない」歴史と創作の交錯を幻視する……これこそが、「パリから来た紳士」や「黄色い下宿人」に潜む感動の核心で、この核心は、『加賀美雅之未収録作品集』の良さにそのまま繋がってくるのです。
鬼貫警部の満州時代の事件を描く「凍夜に死す」では鬼貫らしいアリバイ崩しの短編に、ある人物との出会いというくすぐりを織り交ぜ、ある短編では語られない名前というフックを巧みに忍ばせながらラストの一行の感動に繋げ、ある短編では不可能犯罪がアナスタシア皇女の歴史へと接続する。より典型的なのは、「ジェフ・マールの追想」という掉尾を飾る中編で、ここではアンリ・バンコランを主人公とした推理の冒険が描かれるのですが、この中編の結末に、思わず膝を打つような歴史と史実の交錯が語られるのです。ありそうでなかったその「組み合わせ」に唸り、あったかもしれないという幻想を語る加賀美本人による「好事家のためのノート」にも、ニヤニヤさせられてしまいました。
もちろん、常にトリックをメインに据えて読者に挑む作風も素晴らしい……素晴らしいのですが、この『加賀美雅之未収録作品集』を通じて、歴史と記述の空隙で、無邪気に自分の想像のタペストリーを織り上げていた、作者の姿を知ってほしいと思います。重厚さはもちろんですが、この軽やかさも、同時に加賀美雅之だったのだ、と。
林泰広『魔物が書いた理屈っぽいラヴレター』
デビュー作『The unseen 見えない精霊』で、奇術師にして小説家の泡坂妻夫から「久しぶりに活字による大マジックショーに出会った」と称された林泰広。確かに『見えない精霊』では、大胆な伏線と逆説が繋がった瞬間に現れる、意外な真相がキモになっていました。
しかし、林本格の魅力はそのイリュージョン性だけではありません。『見えない精霊』以前に「本格推理」に採られた「二隻の船」「プロ達の夜会」「問う男」、あるいは二〇一七年に十五年ぶりの新作として発表された短編集『分かったで済むなら、名探偵はいらない』は、その独特な会話劇が特徴となっていました。短文を積み重ねながら、会話文の途中でも改行を繰り返すことで、林作品には独特の文体が生まれています。その会話劇から生まれてくる登場人物たちのズレが魅力的な短編ばかりでした。林本格とは、会話劇の魅力でもあったのです。
あるいは、長編『オレだけが名探偵を知っている』のように、独自の名探偵論も作者の特徴の一つです。名探偵とは何か、「オレだけが」「知っている」と言えるのはなぜか、という、この挑発的なタイトルの理由が明かされる終盤が魅力となっていました。
では、『魔物が書いた理屈っぽいラヴレター』はどんな作品か。本書もまた、林流の名探偵論を切り口にした作品であると同時に、その独特な会話劇について、新たな冒険に挑んだ作品でもあるのです。
あらすじはこんな感じ。名探偵の「君」と相棒の「俺」が逃げ込んだのは、中世の古城に隠された五つの部屋「空中牢獄」。十六世紀の貴族・ドウによって恐ろしい不死身の魔物が召喚された場所で、次々に人が襲われる。治療不能の毒を食らって苦しむ「君」を抱えながら、「俺」はこの地獄から逃げられるか。
ある意味、近年流行の「特殊設定ミステリー」の文脈を感じさせる作品とも言えます。魔物の動きや制約についてはしっかりルール化されており、その範囲の中で謎を解き明かさなければいけないのです。「名探偵」物語という意味では、互いに異様な信頼を寄せあう名探偵―ワトソン関係を描き、『オレだけが名探偵を知っている』とはまた違った層の物語となっています。
そして、会話劇、という点ですが、これは書簡形式で書かれているということもあり、作品全体が、コミュニケーションの物語であると言うことが出来ます。林泰広はここで新たな冒険に挑んでいて、真相をぼかしながら言えば、今回は特殊設定ミステリーの文脈を借りて、究極のディスコミュニケーションの物語を描いたのではないかと思います。四人の中で、この二十年の変遷が大きいのが、林泰広なのではないでしょうか。
東川篤哉『スクイッド荘の殺人』
さて、最後の一人、東川篤哉の登場です。乱れ打ちのように繰り出されるギャグの中に隠された伏線が魅力の一つ。ギャグで笑ったために印象に残ったシーンが、そのまま謎解きの快感に繋がるという、ユーモアミステリーとして理想的な設計になっています。本格ミステリーが備えるべき稚気と精緻さを両立させる作家、それが東川篤哉です。
この原稿では、カッパ・ワン一期生の「変化/あるいは変わらないもの」をテーマに書いてきましたが、この「変わらない」という点では東川篤哉は四人の中で急先鋒であると言えるでしょう(もちろん、良い意味で!)。その「変わらなさ」こそが、東川本格の最大の武器であり、魅力と言えるのかもしれません。いつだって、東川本格は温かく読者を迎えてくれるのですから。
では『スクイッド荘の殺人』はどうか。これもまた、いつものゆるい雰囲気を守りつつ、本格ミステリーのあるテーマについて、新たな挑戦をした作品と言えます。〈烏賊川市〉シリーズ十三年ぶりの長編となりますが(そしてファンはご存じの通り、これは東川長編の刊行自体が十三年ぶりと同義です)、膨らんだ期待にしっかり応える一作と言えるでしょう。
あらすじはこうです。小峰三郎という男からの依頼は、彼がスクイッド荘というホテルに滞在する間、ボディーガードを務めてほしいというものだった。かくして鵜飼杜夫と戸村流平は、温泉とお酒を求め……いやいや、あくまでも、小峰氏の命を守るために、スクイッド荘に繰り出すのだが……。
このなんともトボけたあらすじから想像される通り、今作もまた、ゆるい雰囲気で楽しませてくれます。遂に事件が起こると、これがどんなテーマの長編かが明らかになるのですが、それだけで話は済まず、砂川警部たちが脇筋で追いかける二十年前のバラバラ殺人が絡んでくるというところがキモ。ユーモラスなやり取りの中に隠された伏線が一撃で事件の構図を明らかにしたとき、そのクリーンヒットぶりに、思わず快哉を叫んでしまう作品です。愛嬌のあるエピローグが好み。
東川篤哉『仕掛島』(東京創元社)
さて、東川篤哉は二〇二二年もう一作、刺激的な快作を発表しています。東京創元社から刊行された『仕掛島』がそれです。カッパ・ワン一期生の四人が光文社から発表した四作をここまで取り上げてきましたが、せっかく最新刊なので、ここでは「プラスワン」枠で取り上げてみたいと思います。
『仕掛島』は、二〇〇五年に同じく東京創元社の叢書「ミステリ・フロンティア」から刊行された『館島』に続く作品になります。「シリーズ」と呼称していいか分かりませんが、『館島』で探偵役を務めた小早川沙樹の縁者が出てきますし、続編なのは間違いありません(名づけるなら、〈小早川〉シリーズとでも呼称するしかないのかしら。舞台となる館も島も違うので)。
『館島』は作品の年代を一九八〇年代に設定し、タイトルに館を冠していることからも分かる通り、「新本格ミステリー」の文脈に真っ向から挑んだ作品でした。本格ミステリーには、「いやいや、こんな大胆不敵な館、誰が建てるんだよ!」とツッコミを入れたくなるような館が数多く存在しますが、もしそういう館でランキングを組むとすると、この『館島』は個人的にかなりの上位です。発想そのものには唖然とするのですが、ぬけぬけとした伏線で真相を支えているので笑ってしまいます。
一方の『仕掛島』は二〇一八年を舞台として、小早川沙樹の息子である二世探偵、小早川隆生の冒険を描きます。何を隠そう、本作は横溝正史へオマージュを捧げたといえる作なのです。瀬戸内海の孤島を舞台に、名士の一族を集め、遺言状を開封、隠された兄弟の出現に始まり、庭には顔を血まみれにした鬼が闊歩すると来れば、これはもう横溝正史の世界です。とはいえ、そこは東川篤哉。おどろおどろしさには流れることなく、横溝的な主題・要素をカリカチュアして用いることで、自分のユーモラスな世界を損なうことなく、横溝的な謎解きミステリーを志向しているのです。
『館島』の姉妹編にふさわしいような、大胆な仕掛けももちろん用意されています。なにせ『仕掛島』などという、大胆不敵極まりないタイトルを使っているのですから。個人的には、そのアイデアと使い方にもシビれたのですが、思わず、「ああっ!」と口に出して叫んでしまった、二つの効果的な伏線に唸らされました。不可解・違和感の取っ掛かりとなる「気付き」と、「いやいやいや」と読者が承服しかねた瞬間に差し出される「原理」の提示に、やはり東川本格は飄々としながら精緻なのだと唸ってしまったのです。
まとめ
これまで、石持浅海・加賀美雅之・林泰広・東川篤哉の四氏について、カッパ・ワン二十周年記念作品プラスワンを読み、その変化と「変わらなさ」を辿ってきました。四人それぞれに個性があり、楽しい作品ばかりです。ぜひ、読み比べてみてください。
そして、カッパ・ワンの次に生まれた新人育成プロジェクト、カッパ・ツーにもどうぞご注目を。私もカッパ・ツーの第一期生として、二十周年の時には先輩方に胸を張れるように頑張っていこうと思います。
また、「阿津川辰海・読書日記」は、ジャーロHPにて連載中です。こちらもよろしくお願いいたします。
それでは、また次の日記でお会いしましょう。
《ジャーロ No.85 2022 NOVEMBER 掲載》
阿津川辰海(あつかわ・たつみ)
二〇一七年、石持浅海、東川篤哉が選考委員を務める本格ミステリ新人発掘プロジェクト「カッパ・ツー」第一期に選ばれた『名探偵は嘘をつかない』でデビュー。他の作品に『星詠師の記憶』『透明人間は密室に潜む』『入れ子細工の夜』『阿津川辰海・読書日記 かくしてミステリー作家は語る〈新鋭奮闘編〉』『録音された誘拐』『紅蓮館の殺人』『蒼海館の殺人』がある。
現在、ジャーロHPにて「ミステリ作家は死ぬ日まで、黄色い部屋の夢を見るか? ~阿津川辰海・読書日記~」を連載中。
■ ■ ■
▼ジャーロ公式noteでは、皆さんの「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。
いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!
