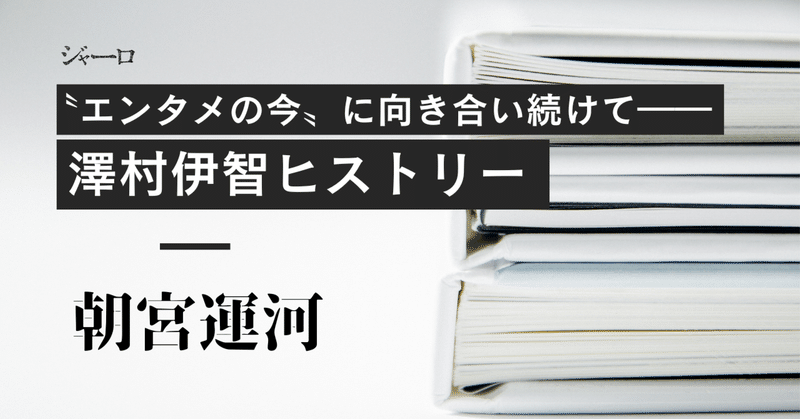
【解説】〝エンタメの今〟に向き合い続けて――澤村伊智ヒストリー|朝宮運河
澤村伊智さんの最新長編『斬首の森』(ジャーロNo.84掲載)と合わせて、お楽しみください。
文=朝宮運河
今、日本のホラー小説シーンは未曽有の活況を呈している。
二〇一〇年代後半から二〇年代にかけて、ホラーに意欲を燃やす新鋭が日本ホラー小説大賞(二〇一九年に横溝正史ミステリ&ホラー大賞と改称・リニューアル)などから相次いでデビュー、野心的な作品を相次いで発表しているのだ。たとえば最東対地、阿泉来堂、芦花公園、新名智らはこのジャンルの次代を担う頼もしい作家といえる。
かれらの動きと呼応するようにベテラン・中堅作家勢も超自然的恐怖を扱った力作を相次いで上梓。三津田信三、宮部みゆき、辻村深月、小野不由美らの人気作家がそれぞれ魅力溢れるホラーを手がけている。
『ミッドサマー』(二〇二〇年日本公開)に代表されるホラー映画のヒットや、動画配信サイトにおけるホラー・心霊系コンテンツの急増、各地で開催されている怪談イベントなどの人気も相まって、恐怖を楽しむという行為は身近なものになった。そうした状況も追い風になり、国内のホラー小説をめぐる状況は日々賑やかなものになっているのだ。
しかし――もし二〇一五年に澤村伊智が『ぼぎわんが、来る』で第二十二回日本ホラー小説大賞・大賞を受賞していなければ、あるいは澤村がホラー以外のジャンルを志していたとしたら、今日のホラー小説をめぐる状況は大きく変わっていたはずである。
澤村は二〇一〇年代後半以降のホラーシーンにおいて重要な役割を演じ(主演の一人だったといっても過言ではないだろう)、当時やや退潮気味であった国内のホラーシーンを活性化させて、多くの読者と書き手にホラージャンルの可能性をあらためて呈示してみせた。澤村が『ぼぎわんが、来る』によって起こした波紋は、やがて大きな波となり、ホラージャンルのみならず日本のエンタメ文芸に影響を与えていく。
本ヒストリーではその作家的軌跡を三つの時期に分け、代表作とともにあらためてふり返ってみたい。
1・『ぼぎわんが、来る』の衝撃
澤村伊智は一九七九年大阪府生まれ。府内で何度か転居をくり返した後、小学三年からは兵庫県宝塚市で暮らす。子どもの頃より怪談やホラーに親しみ、怪奇作家・佐藤有文の児童向けオカルト本『絵ときこわい話 怪奇ミステリー』に夢中になった。フレデリック・マリヤット「人狼」など、英米怪奇小説のリライトが収録されていた同書を、澤村はしばしばホラーの原体験として語っている。
大阪大学を卒業後、上京して出版社に就職。雑誌編集やライターの仕事に就く。澤村作品でしばしば出版業界が舞台となるのは、こうした経歴の影響だろう。友人の影響で小説の執筆を始め、仲間内の講評会のためにさまざまなジャンルの小説を執筆。初めて書き上げた長編が『ぼぎわんが、来る』の原型「ぼぎわん」だった。同作で第二十二回日本ホラー小説大賞・大賞を受賞。作家になるつもりはなく、受賞の報せを受けた際には驚いたと語っている。
『ぼぎわんが、来る』の予備選考会での評価は異例の〝オールA〟。最終選考会でも満場一致で大賞受賞が決まったという。同賞の最終選考委員だった綾辻行人、貴志祐介、宮部みゆきの評価はそれぞれ次のようなものだ。
「過不足のない平易な文章で語られるストーリーはスピード感抜群の展開を見せ、読み手をまったく飽きさせない」(綾辻行人)、「選考をしながら早く先を読みたくてならない作品は稀有であり、著者は天性のストーリーテラーと言える」(貴志祐介)、「小説的な遠近法が効いているので、読み手も登場人物たちと一緒に、『ぼぎわんがやってくる』恐怖を現在進行形で味わうことができます」(宮部みゆき)。
三氏ともリーダビリティの高さに着目している。また文芸評論家で予備選考委員の一人でもあった東雅夫は、「この世ならぬ存在を描きだす怪異描写の巧みさという点でも、本書は群を抜いている」(「本の旅人」二〇一五年十一月号掲載の書評)と、ホラー小説としての特徴を指摘した。
『ぼぎわんが、来る』の〝ぼぎわん〟とは作中に登場する化け物の名だ。会社員・田原秀樹の周囲で気味の悪い出来事が相次ぎ、秀樹は彼の祖父が怖れていたこの怪物のことを思い出す。家族の命を守るため秀樹は伝手をたどり、女性霊能者・比嘉真琴に救いを求める。
右の各氏がそれぞれ評価しているとおり、『ぼぎわんが、来る』は〝得体の知れない化け物に家族が襲われる〟というシンプルかつ力強いストーリーを、非凡な描写力と人物造型、トリッキーな構成によって語った作品だ。そしてそれら大小の技巧は、すべて読者を怖がらせるという的に向けられている。
刊行当時、私が『ぼぎわんが、来る』を読んでもっとも感銘を受けたのが、この著者の潔いスタンスだったように思う。『ぼぎわんが、来る』は当時のホラー小説において手薄になっていたジャンルの中心部分を、〝怖さ〟に特化したストロングスタイルの長編で射貫いたのだ。
ちなみに作中でもっともらしい由来が記されている〝ぼぎわん〟だが、実は架空の存在だ。著者は民間伝承や古典に登場する妖怪のイメージを流用することなく、あえてオリジナルの化け物で読者を怖がらせることを選んだのである。この点について澤村自身がデビュー直後のインタビューでこう語っている。
「おばけのどこが怖いのか。僕の仮説は、名前が怖いんじゃないか、ということなんです。由来でも実害でもなく、名前とそれが怖いものだという認識こそが怖い。(略)『ぼぎわん』が怖いものになっていたら、僕の立てた仮説は正しかったことになります(笑)」(「本の旅人」二〇一五年十一月号掲載のインタビュー)
たとえ名前しかない空疎な化け物であろうとも、それを物語る言葉がもっともらしく真に迫ってさえいれば、読者を心底震え上がらせることができる。ホラーにおいては何を語ったか以上に、どう語ったかが重要となる――。『ぼぎわんが、来る』にはその後の澤村作品を特徴づける、こうした小説観・恐怖観がすでにはっきりと打ち出されていた。
2・エンタメ作家としての足場を固めた第一期
衝撃のデビューから約九か月、二〇一六年七月には第二長編『ずうのめ人形』が刊行される。
オカルト雑誌編集部のスタッフがある原稿を読んだことで、次々と命を落としていく。編集者の藤間は〝ずうのめ人形〟の呪いから逃れるために奔走するが、タイムリミットは刻一刻と迫っていた。
都市伝説でおなじみの〝伝染する呪い〟をメインモチーフにしたこの作品は、いくつかの重要な意味をもっている。ひとつは『ぼぎわんが、来る』の霊能者・比嘉真琴を再登場させることで、〈比嘉姉妹〉シリーズの開幕を読者に宣言したこと。刊行時のインタビューによれば「ゼロから作ってもよかったんですが、ちょうどいいキャラクターがいるので再利用しようと」(「ダ・ヴィンチ」二〇一六年九月号掲載のインタビュー)くらいの軽い意図だったそうだが、結果として澤村は名刺代わりの人気シリーズを持つことになった。
もうひとつは澤村作品の大きな特色であるメタ・ホラー性を明確に打ち出したことである。ミステリ評論家の千街晶之がいみじくも「いい意味で『ホラーやミステリや怪談を読みすぎた人の小説』」(『ぼぎわんが、来る』の文庫解説)と評した澤村作品は、先行作への言及や参照を数多く含んだマニアックな作風で知られるが、中でも〝伝染する呪い〟をテーマに扱った鈴木光司『リング』(一九九一年)を作中で俎上に載せ、そのモチーフを変奏してみせた『ずうのめ人形』は、とりわけそうした傾向が色濃い。ジャンルへの知識と批評性に裏打ちされた『ずうのめ人形』は、多くの読者と新しい書き手に刺激を与え、ホラーブームの呼び水となった。
翌年、澤村はもう一冊の長編を上梓している。デビュー版元以外から初めて刊行された『恐怖小説 キリカ』だ。
正直に告白するが、初めてこの作品を読んだ際には少々困惑した。超自然的恐怖を扱った〈比嘉姉妹〉シリーズとは異なり、〝人間が一番怖い〟系のサイコサスペンスだったからだ。主人公は澤村伊智本人。日本ホラー小説大賞を受賞し、愛する妻と順風満帆の生活を送っていた澤村のもとに、何者からか誹謗中傷の手紙が届き始める。
五年後の今日、あらためて読み返してみると『恐怖小説 キリカ』が実験作でも異色作でもないことが理解できる。澤村がホラーと同じくらいミステリへの志向を秘めていたこと、ジャンルへの義理立てよりも「怖くてびっくりして面白い小説を目指して」(若林踏『新世代ミステリ作家探訪』掲載のインタビュー)いることなどが、明らかになってきたからだ。
この創作姿勢はたとえばスティーヴン・キングを思い浮かべると分かりやすいだろう。キングは『呪われた町』『シャイニング』などホラーの傑作を執筆するかたわら、『ミザリー』など超自然要素のないサスペンスも好んで手がけており、どちらのジャンルでも高い評価を獲得している。「『ミザリー』に挑む」と単行本の帯に記された『恐怖小説 キリカ』は、キング同様にホラーとミステリを往還しながら、恐怖を主軸にしたエンターテインメントを執筆していくという意思表明だったのではないか。
同年には〈比嘉姉妹〉シリーズの第三弾『ししりばの家』(KADOKAWA)が登場。大量の砂に侵食された異常な家に、比嘉姉妹の姉・琴子が立ち向かうという長編で、ホラーの王道である〝幽霊屋敷もの〟に新機軸を打ち出した野心作だった。
デビュー作から『ししりばの家』までの活動期間を、仮に第一期と呼ぶことにしよう。この三年の間に澤村は新世代エンタメ作家としての足場を固め、当時停滞気味だったホラーシーンに新風を吹き込むことに成功した。そのことが第二期以降のさらなる飛躍に繋がっていく。
3・大きな飛躍を遂げた第二期
二〇一八年十二月には『ぼぎわんが、来る』が『来る』のタイトルで映画化され、全国公開された。
監督は『告白』などで知られる中島哲也。ライターの野崎を岡田准一、比嘉姉妹を松たか子と小松菜奈が演じるという豪華キャストで制作された『来る』は、正体不明の化け物と霊能者たちのサイキックバトルをメインに据えた、祝祭的ホラー大作だった。『来る』のスマッシュヒットは、普段ホラーを読まない層にも原作者・澤村伊智の名と〈比嘉姉妹〉シリーズの存在を知らしめることになる。
映画公開に先立ってシリーズ初の短編集『などらきの首』が刊行されている。物理トリックを含んだミステリ要素と、〝などらき〟と呼ばれる化け物をめぐる超自然ホラー部分が見事に融合した表題作や、雑誌の夢野久作特集のために執筆された怪作「居酒屋脳髄談義」など、著者の引き出しの多さをあらためて感じさせる六編を収録している。悲痛な学校怪談ものの「学校は死の匂い」は二〇十九年、第七十二回日本推理作家協会賞(短編部門)を受賞、たびたびアンソロジーに収録されるなど著者の短編の代表作となっている。
この頃から澤村は短編作家としての才能を開花させ始める。本誌「ジャーロ」に発表された「ありふれた映像」「宮本くんの手」などを含む二〇一九年刊行の作品集『ひとんち 澤村伊智短編集』は、著者の短編巧者ぶりをあらためて印象づける一冊だ。ゴシックテイストの異形ホラー「闇の花園」、未確認動物をめぐる謎を〝不穏な名前イコール恐怖〟という澤村メソッド全開で描いた「シュマシラ」などの収録作はいずれもハイレベル。私見ではこの十年間に書かれた怪奇幻想系の短編集の中でも、上位にランクインするほどの完成度を誇っている。
また同年には〈令和元年最恐SF〉と銘打たれた『ファミリーランド』を上梓。これは近未来社会での恐怖や絶望を先端テクノロジーやSF的ガジェットとともに描いた短編集で、しばしば澤村作品のテーマとして取り上げられる家族関係の危うさが、全六編の中でそれぞれ浮き彫りにされている。作中のジェンダー表現が評価され、同書は第十九回センス・オブ・ジェンダー賞・特別賞を受賞した。
一方で、二〇一九年には力作長編『予言の島』が刊行されている。瀬戸内海に浮かぶ孤島を訪れた天宮|
淳とその旧友たち。その島はかつて一世を風靡した霊能者・宇津木幽子が、最後の予言をした島としてオカルトマニアの間では有名だった。奇妙な風習や怨霊伝説の残る島で、関係者が次々と命を落としていく。
横溝正史の『獄門島』にオマージュを捧げたという『予言の島』は、閉鎖的な集落での連続殺人という本格ミステリでおなじみのプロットをなぞりながら、霊能者の予言に翻弄された人々の悲劇を描いていく。著者が「そこ(横溝正史ミステリ&ホラー大賞)に応募しても大賞を獲れるくらいの作品、という意気込みで書いた」(『本の旅人』二〇一九年三月号掲載のインタビュー)と語る同作は、よくある土俗系ホラーミステリを期待して手に取った読者を大いに戸惑わせ、驚愕させる。
予言とは何か、呪いとは何か。言葉に翻弄される人間という『ぼぎわんが、来る』以来のテーマにあらためて向き合ったこの長編は、『2020本格ミステリ・ベスト10』で八位、『このミステリーがすごい!2020年版』で十九位を獲得。澤村は本格ミステリの俊英としてもあらためて注目を集めることになる。
エンタメ作家としてさらに一回り大きく成長したこの時期を、第二期と呼ぶことにしたい。
4・さらに作家性を研ぎ澄ませた第三期
続く第三期は二〇二〇年から現在まで続く時期である。
この三年に発表された作品をふり返ってみると、これまで以上に大胆な着想・手法によって書かれたホラーやミステリが目立つ。第一期、第二期の活動によってエンタメ文芸シーンに確固たる地位を占めた澤村は、その作家性をさらに研ぎ澄ませ、他の書き手には真似のできない作品を相次いで発表しているのだ。
不気味なおまじないが不幸の連鎖を招く学園ホラー『うるはしみにくし あなたのともだち』(二〇二〇年)、駆け出しライターが怪事件に遭遇する『アウターQ 弱小Webマガジンの事件簿』(同)、巨大な化け物と比嘉姉妹の対決が描かれる表題作など、五編を収録した〈比嘉姉妹〉シリーズ短編集の『ぜんしゅの跫』(二〇二一年)、寂れたニュータウンにはびこるカルト教団の闇を扱った『邪教の子』(同)、人を恐怖と絶望に陥れる謎めいた女性の〝仕事〟を描く連作集『怖ガラセ屋サン』(同)、小説ならではの怪談を追い求めた野心的短編集『怪談小説という名の小説怪談』(二〇二二年)――。
もちろんこれらの作品の執筆時期は分散しており、二〇二〇年代以降の問題意識がダイレクトに反映されているわけではない。むしろデビュー以来、澤村が抱えてきたホラー観や小説観が多彩な作品によって、より明確になったということだろう。いずれにせよ第三期に書かれた澤村作品はすべてが刺激的だ。
中でも注目すべきは、ホラーや怪談と深い関わりをもつ外見的美醜の問題を、おまじないが引き起こすおぞましい事件とともに描いた『うるはしみにくし あなたのともだち』だろう。クラスメイトを呪っているのは誰なのかというフーダニットの興味に加え、醜さがなぜ恐怖を喚起するのかという問いについて鋭く思考した同作は、現代におけるホラーのあり方を真剣に模索しているように思われる。
価値観の変化から目を背けることなく、同時にホラー特有のいかがわしい面白さを手放すこともしない。そのぎりぎりのせめぎ合いが『うるはしみにくし あなたのともだち』を二〇二〇年代以降の世界に開かれた作品にしているのだ。
短編集では『怖ガラセ屋サン』に目を瞠らされた。幽霊なんか全然怖くない、やっぱり人間が一番怖い、と主張する男女が思いも寄らない恐怖に見舞われる「人間が一番怖い人も」、ホラーとは実は相性がよくないスピリチュアル業界を舞台にした「救済と恐怖と」など七編の収録作はいずれも、恐怖とは何か、私たちは何を怖がるのか、という根源的な問いを含んでいる。
恐怖について語ることで読者を恐怖させる。そんなアクロバティックな試みに挑んだ『怖ガラセ屋サン』は、澤村の理知的でテクニカルな小説作法がよく表れた連作になっていた。
では、澤村伊智はこれからどこへ向かうのだろうか。『怖ガラセ屋サン』刊行時のインタビューにおいて、著者は次のように語っていた。
「やっぱり読んで面白いと思っていただけるのが一番ですから。日々更新される面白さに向き合いながら、エンターテインメントを書いていきたいと思っています。今回恐怖論をやりきったことで、新たなステージに進めたような気がしています。今後はもう少し肩の力を抜いて、ストレートに怖い話が書けそうです」(「ダ・ヴィンチ」二〇二一年十一月号掲載のインタビュー)
来たるべき第四期は、よりストレートな怖さを志向したものになるのか。それとも挑戦的な作風の第三期がまだしばらく続くのだろうか。その答えは本誌に前半部が掲載された長編『斬首の森』を読んで、皆さんそれぞれが考えていただきたい。
ただひとつ確かなのは、澤村伊智はこれからも変化を止めないだろうということだ。先に「怖くてびっくりして面白い小説を目指して」という発言を紹介したが、この面白いという感覚は普遍的である一方、社会の変化にともなって「日々更新される」。恐怖の感覚にしてもそれは同様だろう。澤村はその変化を見逃さない。
『ぼぎわんが、来る』から『怪談小説という名の小説怪談』にいたる軌跡には、〝エンタメの今〟に向き合い続けてきた澤村の作家的スタンスが刻まれている。澤村の作品は日本ホラー小説史における重要作として、この先十年、二十年と読み継がれていくだろう。
しかしその魅力をもっとも味わうことができる読者は、間違いなく今を生きる私たちだ。これからも澤村の活躍をリアルタイムで追いかけ続けたいと思っている。
《ジャーロ No.84 2022 SEPTEMBER 掲載》
▼ジャーロ公式noteでは、皆さんの「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。
いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!
