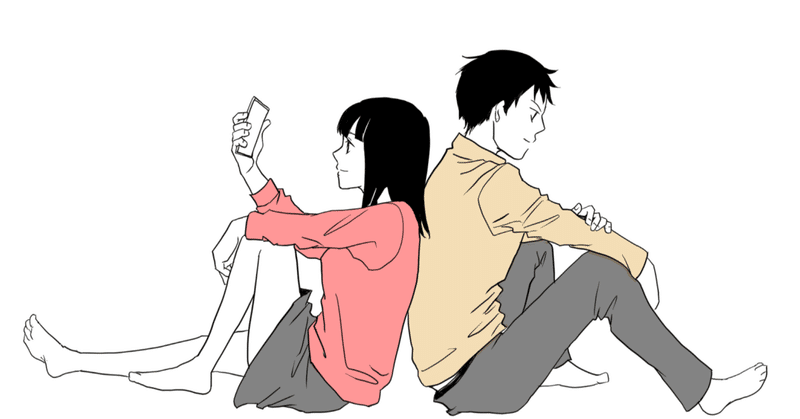
【連作短編】先輩ちゃんと後輩君 その7
第7話 先輩ちゃんは「生」について真剣に考える
塾のバイトの帰り道。高田 春人のスマートフォンが軽やかに鳴った。ダウンジャケットのポケットから取り出してアプリを起動。青山 陽葵から送られてきた内容を一瞥して考え込むような表情となった。
『今日は私の給料日! 駅前商店街の北口に午後六時に集合だ!』
以前にも似たようなメッセージを目にしたことがある。給料日を声高に主張していながら一文のどこにも「奢る」の言葉が見つからない。その時は割り勘になった。
「……またですか」
冷ややかな目で呟いて顎先を撫でる。冴えない顔のまま踵を返した。一時の感情で相手の機嫌を損ねて「生活環境抜き打ちチェック」と称した行動を起こされては堪らない。一人分の飲食であっても頻度によっては家計を圧迫する。一人暮らしの大学生に余裕はなかった。
十数分後、春人は待ち合わせ場所で陽葵を見つけた。白いコートのポケットに両手を突っ込み、上体をゆらゆらと揺らしている。通り掛かる人には素早く反応。目をやる度にボブカットの髪型が崩れた。
春人はゆったりとした状態で近づく。気付いた陽葵はにっこり笑う。親からはぐれた子供のように嬉しそうに走ってきた。
「後輩君、急いで移動するぞ」
「わかりました」
二人は並んで商店街の中を歩く。赤い提灯がぶら下がった居酒屋は早い時間帯に関わらず、賑やかな声が外まで漏れていた。春人は横目で見ながら陽葵に言った。
「今日は給料日ですね」
「そうだ。待望の日で、もちろん、大人である私の奢りだ」
「割り勘ではないのですか?」
「自分から誘って、それはない。立派な社会人が学生の後輩君と割り勘など、格好悪いにも程がある」
陽葵は笑顔で言い切った。過去は振り返らない主義のようだった。
敢えて蒸し返す必要はないので、そうですね、と春人は控え目に答えた。
連れて行かれた先は小ぢんまりとしたラーメン屋だった。良い感じに古びていて高級感は全くない。納得した表情の春人を他所に陽葵は勢いよく引き戸を開けた。
「味はいいぞ」
陽葵は親指を立てて無邪気な笑顔を見せた。春人は目を細めて、期待しています、と穏やかな調子で返した。
店内は細長い。ウナギの寝床の状態でテーブル席はなかった。
常連客なのか。陽葵は気にする様子はなく平然と突き進んで、一番、奥の席を選んだ。隣に春人が座ると、にかっと笑う。
「トイレが近いから便利だぞ」
「ラーメン屋で呑むつもりですか」
「もちろんだ。生中、二つ」
陽葵はカウンターの向こうに大きな声で注文した。
「いいよな、生中で?」
「注文する前に訊いてください」
春人は出されたおしぼりを広げた。両手を丁寧に拭うと男性店員が二人分のジョッキを持ってきた。
「これだよね」
陽葵はジョッキを上から覗き込む。ふんわりとしたキメ細かい泡に尖らせた唇を差し込んで豪快に傾けた。一気に半分を呑み、笑顔で息を吐き出した。
「やっぱり生だな」
「瓶ビールも美味しいですよ」
冷静に返す春人に白い髭を生やした陽葵が詰め寄る。
「いや、そこは生だろ。なんでもそうだが、『生』の一字には抗えない魅力がある。餃子四人前で」
「ですから、注文する前に」
春人の文句を陽葵の言葉が遮る。
「例えば今の季節に牡蛎がある。生食用と加熱用、選ぶとしたら私は『生』の方だ。鮮度と美味さが違う」
「鮮度は同じですよ。栄養価が高いのはむしろ加熱用の方ですし、味も上ですね」
「え、本当に?」
目を丸くした陽葵は白い髭で呆けた。周囲に他の客はいないものの自然に目がいく。春人はおしぼりの一部を使ってさりげなく拭いた。
「あ、ありがとう。その、さっきの話なんだけど」
「本当ですよ。栄養豊かな海は菌も多いので加熱が必要になります。生食用は綺麗な海に限られていて、その分、栄養が不足しがちで身が細くなって味にまで影響を及ぼします」
「知らなかった。しかしだ。私の『生』の主張は変わらないぞ。生野菜は特別なイメージがある。ただの足よりも生足の方が魅力的だ。そう思わないか?」
男性店員が苦笑いの状態で餃子を差し出す。受け取った春人はカウンターに皿を手早く並べる。手前の小皿を取って醤油とラー油を入れた。陽葵も同じようにして最後に酢を注ぐ。
「生中、おかわり!」
「急に生々しい話になりましたね。あと、わかっていると思いますが酔っ払って脱がないでくださいね」
「脱ぐか! そう簡単に生乳を見せる私ではないぞ!」
「あまり店内で強く主張しない方がいいですよ」
春人の囁く声を受けて陽葵はカウンターの奥に目をやる。店主が腕を組んだ状態でぎこちない笑顔を向けてきた。
二人は無口となって餃子を食べる。おかわりの生中を半分ほど呑んだ陽葵が思い付いたように話題を振ってきた。
「スーパーで売られている袋麵の『生』は美味しいよな」
「それには同意します。乾麺にはない弾力とコシがあって良いですね」
「そうなのだが、簡単に作れないところが難点だな。深夜に小腹が空いた時は特に手順が面倒で困る」
「そうですか?」
春人は羽根つき餃子を齧る。口をさっぱりさせるように透かさずビールを呑んだ。
餃子を一口にした陽葵が目を怒らせて頷く。
「スープ用のキャトルに麺を茹でる寸胴が必要だ。数分で沸騰した湯に生麺を解すようにして入れる。フライパンでは入れる具を炒める。これを同時にして最後に合わせるとようやく完成だ。時間も掛かるし、すぐには食べられないじゃないか」
「その工程を省くことができますよ」
「どうやって? 絶対に無理だろ」
「電子レンジを使えば簡単にできます」
春人は柔らかい笑みを浮かべた。残りの餃子を一口にしておしぼりで口を拭う。
「麺の茹で汁をスープに使うのはダメだぞ。ドロッとして味が悪くなる」
「少量の茹で汁は使ってもいいと思いますが、今回は違う方法になります。まずラーメン鉢にスープの素を入れます」
「キャトルの湯を注ぐのだな?」
「いえ、水を使います。そこに煮え難い具を入れてレンジで加熱します。その間に麺を茹でて合わせれば完成です」
春人は残りのビールを呑んで軽く息を吐いた。
「その方法ならキャトルやフライパンを素っ飛ばせる。麺を茹でる時間で作れて時間の短縮にもなるんじゃないのか!」
「そうなりますね」
「よし、今から私のアパートに行くぞ! 生麺は近くのスーパーで買って実践だ!」
陽葵は伝票を手にしてレジへ向かう。
「あの、ここのラーメンは……」
その声は耳に届いていない様子で陽葵は会計を済ませた。早々に引き戸を開けて笑顔で振り返る。
「急ぐぞ!」
春人は諦めて立ち上がる。横目で見た店主は何とも言えない表情を浮かべていた。
「……餃子、美味しかったです」
軽く頭を下げた春人は猫背となって店を出るのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
