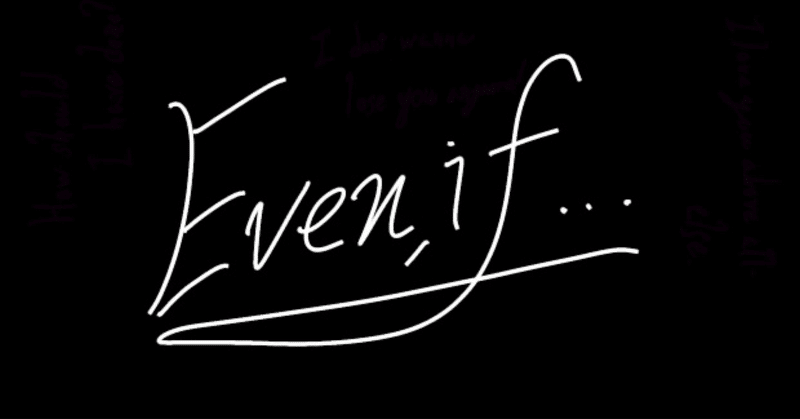
EVEN, if... <「彼」の手記Ⅰ>⑤
僕は自分を落ち着かせた。何もできない非力な俺自身を無視しようとして。しかし僕は無視する以外に自分を落ち着かせる方法を知らなかった。僕は彼女のことを思い浮かべた。だが、俺は突然吐き気に襲われた。これは彼女に対する嫌悪感などではなく、どうしようもない俺自身の愚行と、ここ最近の俺自身のストレスによるものだった。
しばらくして激昂をする心を収めると、再びかつての記憶のアルバムを箱から取り出そうと瞼を閉じた。心の奥底に隠した、あの懐かしい日々を記録したアルバムを。この恋心が周りの人間に気付かれないよう生きるために日の当たらない場所へやった、埃をかぶってしまっているそれをもう一度開く。この心内を、秘密を守りたければ、自分自身にも隠しておかなければならないことを、天性の道化、詐欺師の僕は知っていたからだ。
林間学習から少し時間は飛び、季節は秋になった。二学期になり、みんながこのクラスに大分慣れた頃合いだ。もうかれこれ五年も前の記憶なので曖昧になってしまっているのだが、この二学期のどこかで、電磁石に関することを理科で習ったはずだった。これはその時の記憶だと思われるものだ。
僕は随分と手先の器用な人間で、ちまちました作業や気の長くなるような反復作業、繊細で細かい指の動きが必要とされる作業も正確に、しかも幾分か他人より早くこなすことができるのが自慢の一つだった。そしてこの時、簡単な電磁石を用いた大型のモーターを搭載した車のラジコンのようなものを作る理科の授業があったのだ。もちろん1時間で終わるような内容ではないので3、4時間を使っての取り組みとなった。僕は例によって初めの2時間ですべての作業を終わらせ、暇を持て余していた。それを見かねた先生が僕に他の生徒を手助けするよう命令を出したため、僕は渋々そうすることにした。席に座って、隣の席の生徒がぐしゃぐしゃに絡まった銅線を四苦八苦しながら解こうと試みる様を眺めるのが楽しかったというのに。何より、斜め前の方にいる、目の前の組立途中のラジコンと自分の手元を交互に見て、白黒の無機質な説明書とにらめっこをしながら深く集中している彼女を眺めるために早く終わらせたというのに、大して仲良くもない人間のために歩いて回らないといけないというのは、なかなか気の悪いものだった。
そんなこんなで不貞腐れながらも僕はせっせと手を動かしてラジコンを組み立てている生徒の席と席の間を進んでいった。僕が本当に仲良くしていたのは彼女と親友である彼だけだったので、他の生徒の席の間を歩いている時には何とも言えない違和感を感じたものだ。僕と彼らの間には何か深い溝のようなもの、底の見えない谷があった。橋をかけることも出来ない。向こうの様子はあまりにも遠すぎてぼやけて見える。しかし、親友とはそんな雰囲気の谷、僕と彼とを完全に隔てるものは存在していなかった。橋が架かっているような、あるいは大地がつながっているような、お互いのことをよく知り、いつでも渡っていくことのできるような感覚だ。一方で彼女はそんな安い雰囲気ではなかった。陸がつながっているなど、橋が架かっているなど、そんな容易い方法では彼女の許に行くことはできない。彼女はいつも、荘厳な風格を漂わせている威厳に満ちた巨大な宮殿の、正面、地上からずっと高くにあるベランダから、優雅にこちらを見おろしていた。僕はその絢爛とした、大きさのせいか、あるいはその存在感のせいか、ずっと遠くにあるのに近くにあるように感じる宮殿の前に跪き、そして彼女の言葉を待った。月の光のように繊細で、森の中を悠々と流れる大河のような美しさと畏れに満ちた、心休まる子守唄のような言葉を。もちろん、彼女もまだ小学生だ。発言の一つ一つが警句になっている訳でも、的確にものを言う指摘などでもない。しかし、彼女の言葉、それを発する声の波長が非常に美しかったのは事実だ。慈愛に満ち、優しさを感じ、心震わせるにはあまりにも十分すぎる唄だった。
この時間のことをわざわざ書こうと思ったのは、結果的にこの時間のおかげで彼女と休み時間外でも話すことができたからだ。この時の僕はこの時間がどれほど貴重なのかを分かっていなかったため、一々の会話内容を深く覚えていない。あまりにも大金持ちな富豪が自身の口座の預金額の下7ケタをこれっぽっちも気にしないように、それが当たり前になると人間というものはありがたさとやらを忘れてしまうようだ。
あの頃は楽しかった。だが、戻りたいとは思わない。記憶の中で黄金のように輝き、二度と戻れないからこそ、この思い出は、彼女と過ごした日々は、僕にとって非常に価値のあるものになっているのだ。結局のところ過去というのは、今を生きる僕たちにとって今を彩る絵の具のようなもので、その一つ一つを羨んだり呪ったりするものではないのだ。
時は無情に流れてゆく。たとえ目を隠してその変化を観なかったとしても、耳を閉じて世界の聲を聞かないようにしたとしても、時というのは総てのものに等しく終わりを運んでくる。私と彼女とのこの一年も、この無情な時間の手によって締めくくられようとしていた。
2学期も終わり、冬休みを終え、終わりを感じる3学期に突入した。日を追うごとに温暖になってゆき、葉を落とし色彩に欠けていた木々は青々とした葉の衣を再び纏いはじめた。やがてその緑の衣に点々とピンク色の蕾がみられるようになったと思えば、あっという間に葉と葉の間に美しい桜の花が現れる。それは葉の生き生きとした緑を殺し、その身を強く主張する。競争と風に負けた花は散り、最後の足掻きとでも言おうか、煩いほどに地面を塗りつくしてゆく。上ばかり見る人間に散々踏まれた挙句、茶色く変色して、栄華に満ちたその一瞬を終える。もはや原形すら留めていない花弁は時の運んだ結末の前で己の無力を呪いながら、今もなお咲き誇る仲間を羨むように見上げている。
気付けば3月だった。満開の桜が道を彩り、春の到来の、その嬉々とした雰囲気を通行人に一々伝えていた。僕もその雰囲気を楽しみ、〝終わり〟たるものの存在を見ていなかった。刻一刻と、それは僕の首を絞めつけていたのに。
郵便局員はすぐそこに来ていた。手に終わりへの招待状を持ちながら。僕の郵便受けの前に立っている。
こうして、僕の栄華に満ちた永遠は終わった。
今思い出したのだが、僕は五年生の時に自分の本棚に並ぶほんの数々をすべて読み果たしてしまい、たいそう暇だった。こうして僕は母親の本棚から小説をくすねて読むという考えに至ったのだった。そしてその時、初めて読んだ小説というのが、伊坂幸太郎という作家の〝死神の精度〟だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
