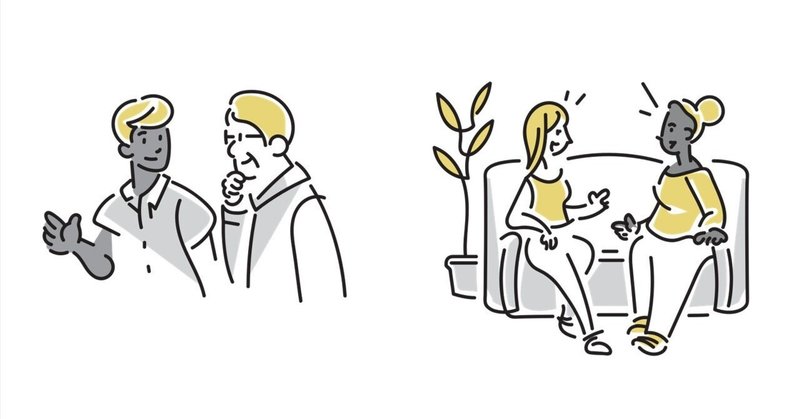
「私は対話可能な人間だ」と訴える試み
こんにちは。ぎんじろうです。
このnoteは、同日に公開した『「#大学生の日常も大事だ」とは何だったのか』の注釈的な立ち位置のものです。
良ければこちらもご覧になってください。
まず簡単にこのnoteを書いた背景を説明します。
2020年、新型コロナウイルスの影響で大学は授業をオンラインで実施するようになり、その結果、大学生(特に新1年生)は対面の居場所や出会い・交流の機会を奪われました。彼ら彼女らはその不満と疎外感を世間に訴えるために「#大学生の日常も大事だ」というハッシュタグを使用し、SNSで様々な投稿を行いました。当時の私はオンライン授業にそれほど不満を感じていなかったため、そのハッシュタグに寄せられた投稿に完全に共感することはできませんでした。
このような内容を書いたものが上で紹介したnoteなのですが、私はそのnoteに「※私は冷笑主義ではありません。」という注釈を入れようとしました。
しかしよく考えてみると、このことを証明するのは非常に困難です。
取り合えず「私は冷笑主義ではない」という説明を思いつくままに書いてみると、字数がとてつもなく増えました。そして、証明と呼ぶにはあまりにお粗末なものが出来上がりました。
そういうわけで、執筆中のnoteを二つに分けて、こちらを『「私は対話可能な人間だ」と訴える試み』と題しまして、「私の対話スタンス」(「広義の政治的スタンス」と読み替えられるかもしれません)について書こうと思いました。
私の対話スタンスを構成する5つの要素
それでは、私の対話スタンスを構成する5つの要素を紹介したいと思います。
1つ目は、共感・理解・賛成は違うということです。
同一視されてしまいがちな三つですが、それぞれの違いに自覚的であることは大切だと思っています。
例えば、
・テロリストの犯行動機に共感できる部分はあるがどうして実行に移したのか理解できない
・原発再開のメリットデメリットはあまり解らないが反対する人の気持ちに共感できる
のようなケースはよくあるのではないでしょうか。
これらの区別については、下のnoteがとても参考になります。
2つ目は、他人の痛みを蔑ろにして人の正義を上から目線で笑う「冷笑主義」は、私が最も拒否するものの一つだと言うことです。
私の考えでは、冷笑主義とは、「単に共感・理解が無い」状態を指すのではなく、「他者を自分と対等な存在として尊重する態度に欠ける」あるいは「共感・理解しようとする意志を持っていない」状態が関係するように思います。
「対話」の対義語を考えたときに「暴力」という単語が思いつきます。これは「外交vs軍拡」と似たものを感じます。
しかし私は、「冷笑」も「対話」の対義語になり得るのではないかと考えています。問題や対立を直視せずに自らの立ち位置をあたかも中立であるかのように振る舞う冷笑主義は、「暴力」と同じかそれ以上に「対話」を阻害します。
そして、「暴力」よりもその悪質性が可視化されにくいところに「冷笑」の陰湿さと毒々しさがあります。
3つ目は、他人の声に耳を傾けるのと同じように、自分の心の声をよく聞いてあげることが大切だということです。
自分と異なる意見を取り入れようとして他者の声を全て受け入れようとすると、自分の存在が不安になったり、かえって自分の意見が抑圧された気分になることがあります。その状態は「自分と他者が対等な存在である」とは言えないので明らかに不健全です。
これは逆もまた然りで、自分の心の声しか聞こえていない利己的な人は、他人の声に耳を傾けることが重要になってきます。
4つ目は、自分の心の声や共感などの「情動」の領域は、ある程度「そう感じちゃったなら仕方ないか」と割り切る必要があるだろうということです。
「恋人を好きだと思う気持ち」も「同性愛者は変だと思う気持ち」も、どちらも非常にプライベートなものであり、かつ、他者はおろか自己でさえ容易に操作できないものです。(ここで挙げた2つの気持ちの良し悪しについてはここで論じません。)
その前提に立てば、他者の意識を変えたい(賛成を得たい)と思ったときには、思考や理解などの「理性」の領域に上手くアプローチする必要があるだろうと思います。逆に「情動」のみに働きかけて賛成を得ようとする勢力には注意するべきです。
5つ目は、対話の際は「表現」に気を配る必要があると言うことです。ここでの「表現」とは「アウトプットの手段全般」を指すもので、「共感・理解の促し方」や「賛成/反対の示し方」と言い換えることも可能でしょう。
表現方法を間違えると、相手に誤解を与えたり相手を傷つけたりしてしまいます。また、「自分の心の声を大切にする」ということは、何を言っても許されるということではありません。それはヘイトスピーチ解消法がなぜ存在するのかを考えればよく分かると思います。
一方で、「表現」の揚げ足ばかり取って、論点をずらし、他人の言葉の内容や行動の意味を矮小化する行為は冷笑主義の典型的な行為です。
以上が、私の対話スタンスを構成する5つの要素でした。
おわりに
実は、6つ目に加えようとしてやめたものがあります。
それは、「私に絶対的な信念があるとしたら、それは『絶対的な信念はない』ということだけ。」というものです。
なんというか、私はこういう「一見意味ありげな言葉」や「対句になっている言い回し」が好きなんですよねw
絶対的な信念を持っていないということは、自分の意見を変える柔軟性を持っているということです。そして、自分の意見を変える柔軟性を持っていることは、良い対話を始めるための条件の一つだと思います。
『「私は対話可能な人間だ」と訴える試み』と『「#大学生の日常も大事だ」とは何だったのか』の二つのnoteを書いて気づいたのですが、私はきっと「柔軟性」が好きなんですね。この気づきは私にとって予期せぬ収穫でした。
ここまで読んでくださりありがとうございました。今回のnoteはこれでおしまいです。
ぜひ次回作にもご期待ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
