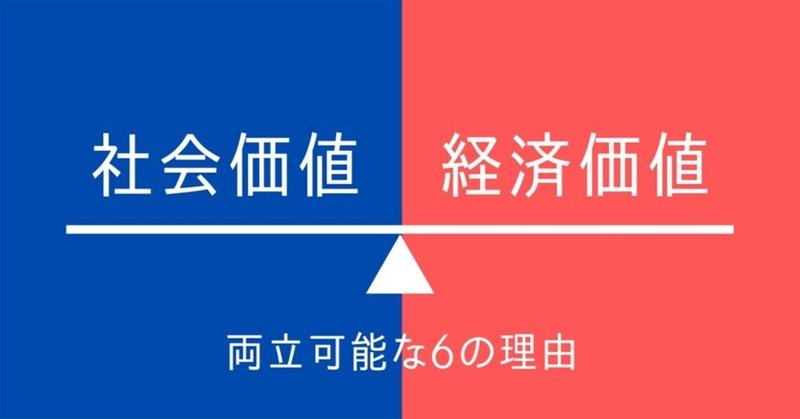
いま社会価値と経済価値が両立できる6つのワケ
これまで「社会にとってよいこと」と「利潤」の両者はトレードオフの関係にありました。
しかし今、社会が利潤を中心とした「利潤資本主義」から人にとって良いことを判断基準とする「倫理資本主義」へのシフトが進む中で、社会価値と経済価値を両立した企業経営が現実的なものになりつつあります。筆者が代表を務める GOB Incubation Partnersでは、そうした新たな経営モデルを「見識業」と呼び、その実現に向けたプロセスを事例や社会背景を踏まえながら考察。本連載で、数回にわたって私たちが目指す見識業について解説しています。
前回は、利潤資本主義から倫理資本主義への社会の移り変わりと、見識業の全体像を紹介しました。
第2回となる今回は、見識業が求められる=その実現を後押しする社会の流れを「6つの潮流」として見ていきます。
筆者:山口高弘(GOB Incubation Partners株式会社 代表取締役社長)社会課題解決とビジネス成立を両立させることに挑戦する事業支援を中心に、これまで延べ100の起業・事業開発を支援。社会に対する問い・志を、ビジネスを通じて広く持続的に届けることに挑戦する挑戦者を支援するためにGOBを創業。自身も起業家・事業売却経験者であり、経験を体系化して広く支援に当たっている。
前職・野村総合研究所ではビジネスイノベーション室長として大手金融機関とのコラボレーションによる事業創造プログラムであるCreateUを展開するなど、個社に閉じないオープンな事業創造のための仕組み構築に携わる。内閣府「若者雇用戦略推進協議会」委員、産業革新機構「イノベーションデザインラボ」委員。
主な著書:「いちばんやさしいビジネスモデルの教本」(インプレス)、アイデアメーカー(東洋経済新報社)
見識業の定義
では、まず見識業の定義から確認していきましょう。前回、「人にとってよいことが儲けを生む」企業経営へとシフトすることで、倫理資本主義の広がりが加速するとして、その経営モデルを見識業と定義しました。
見識業は「見識」と「業」の2つから成ります。「見識」とは社会的価値の創造に必要な「時間空間を超えたモノの見方・考え方」を提示するものであり、人と社会にとってよいことを見抜き、その実現に向けた影響を高い想像力で捉え、最適でありかつ正しい解を見出す力量です。「業」は社会的価値という通常そのままでは利潤に結びつかない価値を利潤に結びつけるための方法論を指しています。
社会価値を生み出すには、「今この瞬間はよいかもしれないが、将来の悪影響を生むからやり方を変えよう」「今は影響は小さいが将来好影響が拡大するから重視しよう」といったような時間的なモノの見方・考え方(時間軸)と、「自分にとってはよいが、顧客にとってはよくない」(顧客視点)や「顧客にとってはよいが、ステークホルダー(生産者や環境など)にとってはよくない」「ステークホルダー(生産者や環境など)にとってもよい効果を与えうる」といった顧客/ステークホルダー社会価値を見抜く空間的なモノの見方・考え方(空間軸・関係軸)が求められます。
今回は、そんな見識業の実現を後押しする時代の潮流を6つに整理しました。
潮流1:「人にとってよいこと」と「儲け」のトレードオフ解消が現実的に
これまで社会性と経済性は両立しがたいトレードオフの関係にありました。社会的な価値を重視すれば、コストがかさみ経済的な損失がかさみ、経済的な価値を重視すれば、環境に配慮した原材料を敬遠して安価な原材料を選択するなど社会的な価値を減らしてしまう────。どちらかを重視すればどちらかを諦めなければならないという天秤のような関係にあったのです。

そのため、経済価値を重視する組織と、社会価値を重視する組織は、それぞれ別の場所で発展してきました。つまり前者は主に企業が、後者は主に非営利団体が担ってきたのです。そして両者は、寄付やCSRなど必要に応じてつながりを持つことで、社会全体の経済価値と社会価値の総和を増大させてきました。しかし、それがトレードオフを前提とした社会における“限界”でもあります。
しかし、今や社会的価値をミッションとしながら、同時に経済的な価値を確保して持続性を実現する事例も増えています。前回紹介したパタゴニアやフィリップスはその典型です。
日本国内で言えば、フィットネスクラブの「カーブス」が、社的価値と経済価値を両立した経営を実践していると言えるでしょう。カーブスはフィットネスクラブの事業を通じて、「そこで友人をつくり、地域における孤独孤立を解消する」という社会価値を提供しています。
そのために、運動不足を解消したいけれどハードな運動は嫌いな人や、運動は好きだけど苦手だと感じている顧客のインサイトを捉え、「体操のようにラクに体を動かせる」「恥ずかしい思いをせずに運動を楽しめる」といった顧客にとっての経済価値(お金を払ってでも得たい価値)を提供。さらに、そうした経済価値を利潤に変換するために、入会金や月謝、フランチャイズビジネスによるロイヤリティ収入といったビジネスモデルを構築しているのです。
潮流2:流通する情報の解像度とスピードの拡大
SNSの勃興に代表されるように、現代は情報が流通するスピード、解像度ともに格段に向上しました。そしてそれは人をより「倫理的」にさせます。
多くの人は、目の前で誰かが困っていれば、助けたいと思うでしょう。しかし、困っている事実を知らなかったり、隠されたりすれば、その手を差し伸べることはできません。知ることのハードルが格段に低くなった現代、人々はより「倫理的」であろうという流れが加速し、同時に企業に対しても倫理的であることを求めるようになります。
2018年、イタリアの有名ファッションブランド「ドルチェ&ガッバーナ」(以下、D&G)は、上海でのショー向けに制作した動画が原因で、SNSを中心に多くの批判を受けました。動画には、箸を使って不器用にピザを食べるアジア系モデルが出演。それが「伝統的な箸文化を馬鹿にしている」「侮辱的、人種差別だ」などの批判を受けました。
結果、予定していたショーは中止に。また中国の小売り各社が同ブランド商品を撤去したり、有名芸能人がブランド商品の不買を発信したりとさらに炎上は拡大。調査によると、D&Gの2019年第1四半期のSNSにおけるエンゲージメントは前年同期比で98%減少、2019年3月期(2019年度全体)の収益は全世界合計では増加したものの、中国を含むアジア太平洋市場の売上が占める割合は前年の25%から22%に縮小しました。
潮流3:顧客が反応できる価値の「深度」が深まった
従来のマーケティングでは、顧客に対して、分かりやすく直感的に理解できる価値を訴求することが重要だと言われてきました。今でもそれは間違ってはいませんが、少し潮目が変わってきています。これまではごくわずかの人しか価値を感じていなかった「社会を良くする」「環境負荷を下げる」といった企業努力が、購入の大きな決め手になってきているのです。
そもそも製品の価値には2種類あります。「体験しなくても想像できる価値」と、「体験してはじめて深く理解、体感できる価値」です。
前者は価格や使いやすさなど、後者は製品を購入することで環境に貢献できるといった価値を指します。これまで、購入する決め手の多くは前者でした。後者は購入時点ではまだその価値を感じられないのですから、当然です。
しかし、米国の調査によると、似たような製品であれば「社会や環境によい製品を購入する」と回答した人は83%で、ミレニアル世代の若年層は87%とその傾向は一層顕著です。顧客が、これまで想像しづらかった深い価値(社会価値)を重視し、購入の決め手とする傾向が見えてきます。こうした潮流を見ても、社会的価値を生み出しそれを顧客へと伝えることは今後ますます重要になると言えるでしょう。

こうした価値を訴求している企業として、シューズブランドのTOMS(トムズ)があります。TOMSでは、靴が1足売れるごとに、靴を買えない子供たちに1足を寄付する「ワン・フォー・ワン」モデルを採用。これまで約9300万足を子供たちに届けています。現在では寄付先の国での雇用創出や、病気の治療支援や予防教育など、支援の輪を広げています。
潮流4:社会性がなければ人や顧客が集まらない
これまでの企業は、顧客に経済的価値を届け、それを自社の利益に還元してきました。言い換えると、ステークホルダーの力を借りながら、自社の利益確保のみに関心をもっていたわけです。
しかし本来、事業は、社員やパートナー、地域社会、環境などさまざまなステークホルダーとの関係の上で成立しています。こうしたステークホルダーとの持続的な関係を構築できなければ、顧客も社員も集まってはくれません。
Googleは2018年、AI技術をペンタゴン(米国防総省)のドローン用軍事技術に使用していたことが明るみに出て、社内で4,000人が反対の署名運動を起こし、十数人が退職する騒動となりました。社会的価値を重視する人は、企業の倫理性にも敏感になっている今、それを損なえば、人は離れていきます。
実際、米国民を対象としたJUST Capitalによる調査でも「給与水準が10%低下しても、より公正な企業を選択する」と回答した人が74%、さらに66%は「給与水準が20%低下しても」同様の回答をしました。資本主義大国の米国でもこうした意識が高まっていることがわかります。

離れるのは社員だけではありません。社会価値を重視しないことで、顧客も離れていく可能性が高まっています。世界最大手のPR会社エデルマンが日本を含む世界8カ国で実施した購買者意識調査「2018Edelman Earned Brand」によると、「社会的・政治的な問題に対するブランドの姿勢いかんによって、そのブランドの製品やサービスを購入するかボイコットするかを判断している」と回答したのは64%(日本では60%)で、前年から13ポイントも増加しました。
例えば1997年にスポーツ用品大手の米ナイキはインドネシアなどの工場で就労年齢に満たない少女らを低賃金で強制的に働かせていたことが発覚すると、これが世界規模での不買運動につながりました。不買運動が同社の売上に与えた影響をデロイトトーマツが試算したところ、売上損失は1998年〜2002年の5年間で約121億8000ドル(日本円で約1兆4000億円)にも及ぶそうです。人権侵害によって、企業にとって致命的な損失を被ったのです。
なお、その後Nikeは企業経営を大きく見直し、現在ではCSRやサステナビリティの分野で高い評価を受ける企業の1つに成長しました。実際、3BLマガジンが1999年から発表する「企業市民ベスト100」(米の時価総額上位1,000社を対象に、気候変動、従業員との関係、環境、財務、ガバナンス、人権、ステークホルダーの8つのカテゴリーから企業を評価した)の2020年版では、全体19位、Consumer Durables & Apparel(耐久消費財・アパレル)分野のトップにランクインしています。
潮流5:限界費用の低減で、社会性を重視した事業を営みやすくなった
これまで多くの企業は「スケールメリット」を利用して事業の効率化を図ってきました。もっともわかりやすいのは、資源調達コストの低減でしょう。原材料などを大量に仕入れることで、製品1個あたりの仕入れコストを下げることができます。しかし、小規模事業者にとって大量の仕入れが難しいように、スケールメリットを活用するには、まず規模を拡大するための利益が必要です。つまり、社会性を重視するためには、逆説的に、まずは経済性を優先して規模拡大を図らざるを得なかったのです。
しかし今や資源調達コストはかなり低くなりました。その理由を「第3次産業革命」の理論的主導者で、独メルケル首相のアドバイザーでもあるジェレミー・リフキン氏は3つのテクノロジーの出現で説明しています。
経済活動をより効率的に管理・運営する新たなコミュニケーション技術
より効率的に動かす新しいエネルギー源
より効率的に移動するための新しい交通・物流技術
これらによって、資源調達コストは劇的に低くなり、「社会性」を重視する起業家たちが、事業を起こしやすくなりました。同時に、資源調達コストの低減は、事業活動が引き起こす環境負荷の低減へもつながります。事業活動によって環境負荷を拡大させたくないと考える人にとって、社会性を重視した事業創造の機会が拡大していると言えるでしょう。
潮流6:経営者や組織の「統合」に関する研究が進展
前回、社会性の高い事業を生み出すためには、その主体である「人」と「組織」もまた社会性を高めなければならないと説明しました。ここで言う「社会性」とは、顔の見える他者が求めることを、自分ごととして捉える力のことです。
現代は、価値観や個性を重視するあまり、反対に自己中心性も拡大しています。そのため、多様な価値観や個性を尊重しながら、自己中心性を克服し、個性を統合、調和できるか、組織のあり方が問われています。経営者や組織が社会性を高めるために考えなければならないのは、成長ではなく統合なのです。
統合とは、「自己中心性を解放し、他者を想像し、他者と自分を重ねて捉えること」です。社会性とは「顔の見える他者が求めることを、自分ごととして捉える力」だとすると、統合はその第一の条件だと言えます。
しかし、概念として理解していても、人や組織における「統合」を実態としてはイメージしづらいでしょう。実際、これまで経営者や組織に対して最も多く適用されてきたのは「成長」の理論でした。「統合」のための方法論は、精神的、宗教的なニュアンスを含むものとしてビジネスシーンでは少なからず敬遠されがちだったのです。
しかし近年では、「統合」を経営に活かす研究が形になり始め、ビジネスシーンにも広く流通するようになってきました。ビジネスと内面の変容を関連づけた「U理論」や、組織と精神の発達を結びつけた「ティール組織」などがその代表です。
「統合」の重要性を正面から扱えるようになってきたことで、これまで顧みる機会が少なかった「自分の内面」の社会性を問えるようになってきたこと、その実態を可視化されたことで、こうした統合に関する議論が進展を見せています。
連載の続きはこちら>
みなさまからのご意見、ご感想もお待ちしています。
本連載を通じて提言している「見識業」は、豊富な実践例があるわけではありません。GOB Incubation Partnersでも、新規事業開発の支援やコンサルティング、さまざまな企業や起業家との実践、歴史的な背景などを踏まえて少しずつその解像度を高めているところです。ぜひ、皆さまの率直なご意見も聞かせてください。
