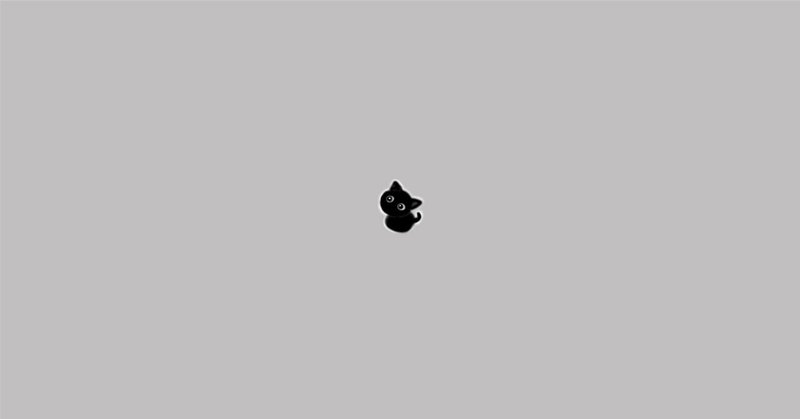
(掌編小説)くろねこ春子の日常#002拾われた春子
満月の夜に黒猫に変身する女の物語

ぼーっとしてたら満月の夜。気が付けばくろねこ春子に変身していた。このまま部屋にいても仕方ないにゃん。徘徊するとするか。私は窓から外に出て(いつも少しだけ開けてるんです。本当です)蒸し暑い夏の夜に繰り出した。コンビニの明かりが魅力的だが入る訳にもいかず、うろうろしているうちに公園に。そういえばここには公園があったんだな。あまりなじみがない。とても小さな公園の、ひとつだけあるベンチに座っている白髪のおじいさんが、街灯の明かりにうすぼんやりと浮かんでいた。片手に缶チューハイ、膝の上にさきいか。私はその匂いにつられて、ふらふらとおじいさんの足元へ。
「にゃーん」
おじいさんは私の目を見るといきなり抱き上げた。強引にゃん。
「さきいかの匂いにつられちゃったのか。でも猫が食べると腰を抜かしちゃうからだめだよ。家においで、ちゅーるあるから」
私はおじいさんに抱かれ、拉致された。でも優しそうだから、ついつい。おじいさんのアパートは公園のすぐそば、いつから建ってるのかわからない木造の1階だ。おじいさんは部屋に入ると窓を全開にした。
「暑いなあ。エアコン買わないとダメかなあ」
私は畳の上に寝そべりながら、テレビの台風情報を見ていた。今週は台風か、通勤がちょっと面倒だにゃん。ふと気が付くと私はおじいさんのあぐらの上に抱かれ、目の前にちゅーるを差し出されていた。
「ほら、お食べ」
「にゃーん」
私はちゅーるを舐めた、おいしい!ぺろぺろ舐め続けていると、おじいさんは缶チューハイを飲みながら話し始めた。
「昔飼っていた黒猫のラビちゃんにそっくりだな。人懐っこくて、もしかしたら生まれ変わりかな?」
おじいさんはそう言いながら私を抱きしめ、頬ずりした。酒臭いし、無精ヒゲが当たって痛いにゃん。私の気持ちを察してか、おじいさんはそっと私を膝の上に置いて、頭と背中を撫でながら話し続けた。
昔は家族がいて、みんな猫好きでいつも家に猫がいたこと。会社を辞めてから離婚して、それからずっとひとりでいること。私は撫でられているうちについウトウト。気がついたら夜が明けていた。いけない!もう変身が解けちゃう!私は慌てておじいさんの膝から離れると、外に向かって窓から飛び出した。
「ラビちゃん!おい!待って!」
後ろでおじいさんが叫んでいるのが聞こえたけれど、私は全速力で走った。自分のマンションに戻った頃には半分変身が解けていて、しっぽが消えていたのでとりあえずパンツを履いた。自分の手を見るとまだ黒いモフモフのままで、我ながらかわいい。今朝は仕事だ。ほとんど寝てないけど頑張らないと。ふぅ…。

仕事帰りになんとなく気になって公園に行ってみると、おじいさんは公園でちゅーる片手にウロウロ。
「ラビちゃーん」
私を探しているのか。しかし私はラビちゃんじゃないんだよ。おじいさん…。それからもつい気になって、たまに公園に立ち寄ってみると、やはりおじいさんはちゅーる片手にウロウロ。はー、仕方ない、次の満月の夜、待ってろおじいさん!
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
