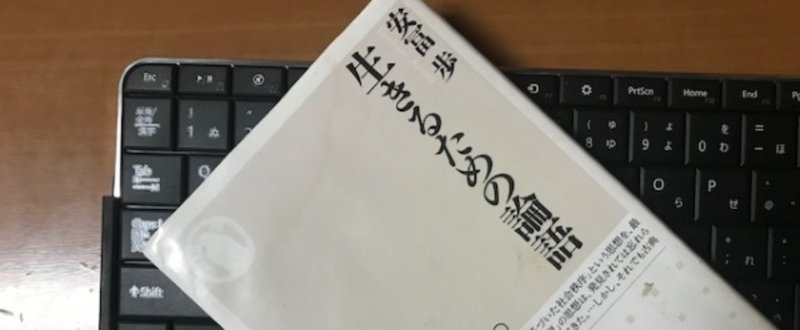
残酷な書
前回は最後に論語を引いて話を締めましたが、今回はその論語について。
まず、お断りしておきますというか、断るまでもないんだけど、ぼくは論語のすべてに精通しているわけではありません。そのような知識を蓄える能力もなければ時間もない。下敷きになっているのは、安冨歩著の『生きるための論語』という本です。
論語は残酷な書です。
昨今の科学的な研究は、遺伝が残酷なものであるという事実をあきらかにするようになってきています。才能は遺伝によってあらかた決まってしまう。遺伝が6割、環境が4割。
ぼく自身は、このような科学的な見解は受け入れるにしても、受け入れ方については大きな違和感を持っています。
「才能」とは何を指して言うのか?
短距離走の能力が遺伝で決まるいう言ならば、違和感はない。特定の身体能力の優越が遺伝で決まるのは事実そうだろうと思うし、短距離走の能力という才能の解釈については、解釈の仕方に多様性は皆無と言っていい。スポーツといったような世界は、才能に恵まれた者たちが才能を競って努力をして、勝者がすべてを持っていく世界でいいと思う。それはあくまで社会のなかのほんの一部分のことだから。
が、社会全体がそうなっては困る。
ホモ・サピエンスの遺伝的な社会性はそのようにはなっていないはずだから。
才能の解釈こそ多様でなければならない。
才能を社会が定義してはならない。
才能は個人が定義するものでなければならない。
社会が才能の定義を個人から奪ってはならない。
ばらばらの個人がばらばらに才能を定義して、そのばらばらが社会全体として才能の定義の多様性になるようでなければならない。
才能というと、どうしても「できること」を想定してしまうけれど、果たしてそれだけが才能定義の方向性なのかというと、そうではないと思います。
「できないこと」が才能になることだってあります。大いにある。
生まれたばかりの赤ん坊は何もできないけれど、何もできないからこそ大人から能力を引き出す。能力を引き出す能力において赤ん坊に優る存在はないし、能力を引き出す能力を才能と定義するなら、赤ん坊は偉大な才能を持っていると言える。そして、そうした定義はまったく不自然なものではない。才能の方向性を「できること」に限定してしまうことこそが、むしろ不自然。
論語が残酷な書である所以は、その不自然の原因を指摘してくれているからです。指摘するだけに留まっているわけではないけれども、でも、不自然はどうしようもないと言ってのけてしまう。
論語の冒頭、学而第一は有名です。
子曰
學而時習之不亦説乎
有朋自遠方來不亦樂乎
人不知而不慍不亦君子乎
有名なわりにはうまく解釈できないのがこの学而第一だっりしますが、その点『生きるための論語』の解釈は筋が通っています。
先生が言われた。何かを学び、それがある時、自分自身のものになる。よろこばしいことではないか。それはまるで、旧友が、遠方から突然訪ねてきてくれたような、そういう楽しさではないか。そのよろこびを知らない人をみても、心を波立たせないでいる。それこそ君子ではないか。
大抵の解釈はこのように一貫して解釈することが出来なくて、ことに最後の一文は独立した解釈になってしまっているのが一般的です。
偉そうなことを言ってしまいますが、ぼくは最近、この解釈でも納得いかないと感じ始めています。“君子”にバイアスがかかってしまっているように思うから。「立派なもの」というバイアス。なるほど字面からしても立派そうですが、「ふつうのもの」だという解釈でもいいのではないか。
そう考えると、四段目の“不知”はよろこびのことを指すのではなくて、学習そのものことだと読む方が筋が通る。学習を知らない者にも心を波立たせない。それはむしろ自身の能力を発揮させる好機だと見る。赤ん坊を抱いてこの子を守るのに全力を発揮しようと思うのが「ふつうのこと」であるように、未だ学習を知らない存在に対しても「ふつう」でいられる「ふつうの者」が“君子”だという解釈でいいのではないか。
“君子”が「ふつうの者」であり、論語が説く“仁”が「ふつうのこと」であるとするならば「ふつうのこと」ではないこととは「不自然なこと」ということになります。では、その不自然はどこから生まれるのか。
論語の論理によると、それは“孝”です。
親孝行の“孝”。
論語といえば孔子であり、儒教であり、儒教といえば親孝行という連想が生まれますが、この連想は間違ってはいません。ただし、ほとんどは歪んでいます。
儒教は“三年之喪”ということを言います。親が死んだら「3年間は喪に服しなさい」と言っている。でも、論語によれば、孔子はそんなことは言っていません。3年間も喪に服したくないのなら、しなくていいと言っている。
宰我という人が孔子に三年之喪などいやだと言った。孔子は嫌ならそれでかまわないと言った。そして、宰我はかわいそうなやつだと言った。
三年之喪は強制ではない。自然にそうなるものだと。親から三年之愛をもらっていたなら「ふつうに」そうなるのが三年之喪であり、それが孝だと。宰我が三年之喪を嫌がるのは三年之愛をもらうことができなかったためであって、だからかわいそうなのだ、と。
今風の言葉で言えば「親ロスから立ち直るのには3年くらいかかるのがふつうだ」といったようなところでしょうか。「親ロスのない人は、親に愛してもらえなかったんだね、かわいそうに」
当人がいかに努力をしても取り返しの付かないことを指摘するのは、残酷なことです。
儒教はその後、その残酷さを見ない方向で進みます。したくてもしたくなくても三年之喪に服すように社会制度を整えた。社会制度にすることによって残酷さと向き合わなくて済むようにした。三年之喪を「強いて勉める」ようにした。
残酷というならば、こっちの方がもっと残酷だったかもしれません。が、そのように社会制度を整えた人たちは、残酷さから目を背けられるようにという優しい心遣いのつもりであったのかもしれません。
その心遣いは、あったとするならば、かの「大審問官」のそれと恐らくは同じでしょう。
このまま続けると長くなりそうなので端折ります。
残酷なことですが、残酷な事実は残酷なまま受け取るしかありません。受け止めきれないのなら逃げるのもいいけれど、生きづらい。
不自然な生きづらさの中に生きて、そのことをオノレの才の源として努力をするのもいい。でも、努力の成果でのみ評価されるなら、生きづらさが再生産されてしまう。
生きづらさの再生産を阻むには、やはり、もともとの残酷な事実に向き合うしかないのだろうと思います。才能を「できること」の方向性へと縛ってしまう不自然の源。「できないこと」が「できること」を引き出すという「ごくふつう」へのところへと立ち戻るために。
感じるままに。
