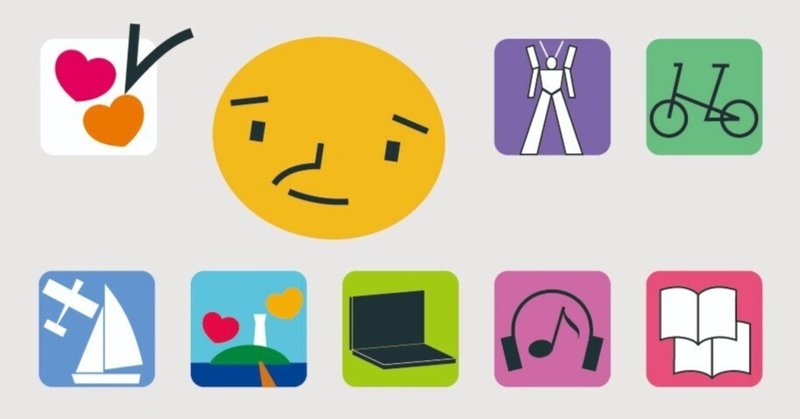
笑って老年 不良講師お花見デート作戦 [体験記]
私は2000年から2013年までの13年間、東京都下にある某デザイン専門学校の非常勤講師をつとめていた。私の58歳から70歳の期間である。
この話はその教師時代のエピソードである。
今回投稿のため再読してみて、教師の風上にも置けない不良講師だったと改めて自覚した。
しかし過ぎ去ったものは変えられない。老後の愉しい思い出になった。
生きがいは狂い咲き!
六七歳になったこのごろ、今のわたしの生きがいはなんだろうかと考えることがある。
専門学校の教師をしているので、これはひとつ大きな生きがいである。
二十歳前後の大勢の若い学生たち(多くは女性である)と、日々接していられるのは単純にうれしい。この歳で幸せな毎日をおくっていると思う。
教師でなかったら典型的な老人生活になっていただろう。
仕事以外では私は一人遊びの趣味が多くて、自転車、音楽、ラジコン、読書、パソコン、軽登山、そして酒など、色々ある。
仕事と趣味の中間ぐらいの気持で時々デザインコンペに応募する。専門のプロダクトデザインやマーク、ロゴなどのデザインである。
若い頃はけっこう入選、入賞したこともあったが、最近はめったに入選しなくなった。
しかし応募するときは本気モードで、徹底的にアイデアを考えベストをつくす。短い期間に全力投球するので頭も体もけっこうくたくたになる。
結果発表までの期間はかなりドキドキときめきの日々である。もしや、万一、という思いである。
そのため落選の通知を受け取ったときのショックは大きい。がっくり落ち込み自己嫌悪におちいる。
しかし、落ち込みの日々がすぎて気がつくとまた、新しいコンペを見つけてアイデアをこねくりまわしている。
コンペは私にとって唯一のギャンブルなのである。
酒と弁当を買って、近所の公園の池でラジコンヨットを走らせると、半日楽しめる。
また天気のいい日、早朝家を飛び出して、三崎漁港などへ遠路サイクリングすることもある。そこでマグロの漬け丼など食べて夕方戻ってくるのもそれなりに楽しい。
読書も子供のころからの楽しみで、ファンタジーなど読んでいると、一晩で一気に読んでしまうこともある。
しかしこれだけでは人生何かが足りない。
ときめきがないのだ。わくわくしないのだ。
男がときめくもの、いくつになってもそれはやっぱり女である。しかも若い娘である。
中年の狂い咲きというが、私の場合は老年の狂い咲きになるのだろうか? 普通の老人は狂い咲かないものなのだろうか?
たまたまチャンスがないだけなのだろうか?
みっともないからなにもしないのだろうか?
あるいはもう興味がないだけなのだろうか?
どうなのだろう・・・・?
どちらにしても老後の最後のあがきなのである。いい歳をして接近するチャンスを、若者のように常日頃考えている。
作戦計画である。これがまた楽しい。
頭脳と心身の活性化にも有効だと思う。血行がよくなり体温も暖かくなるような気がする。
たとえば朝教室に行ったときでもチャンスはつくれる。
たいてい一人二人早く来ている子がいるものである。
その子と最初は挨拶をかわすだけでいい。
そのうちちょっとした会話ができるようになる。通勤途中の出来事の話題でも、天気のことでもよい。
だんだん親しくなって、家のこと趣味のことなどお互いに話しだすようになったら、第一段階はクリヤーしたことになる。
ここまできたらあとは楽である。
おいしいものが大好きな子だったらどこか食事に誘えばいいし、本が好きな子だったら好きそうな本を貸してあげたり、逆に貸してもらってもいい。
女の子と親しくなるのは頭脳的知的作業である。無から有を生み出す創造作業なのだ。
いつも同じ手口ではすぐに飽きられてしまう。たえず新鮮な驚きを提供していかなければならない。
実行に移すときはわくわくする。誘いのメールを送る時、生きている実感を感じる。
正直なところ、本音のところ、これが現在のわたしの一番の生きがいかもしれない。
ひところ、〈不良中年オヤジ〉、〈ちょい悪オヤジ〉、という言葉がはやった。
ちょっと悪ぶって、服装などもすこしくずして着る、まあ見た目そういうファッションのオヤジということらしいが、さしずめわたしは、〈不良老年オヤジ〉を志向しているのかもしれない。
あの「失楽園」で一世風靡の、渡辺淳一の小説「あじさい日記」の文中の一節に、
「男の幸せは、秘密の多さで決まる」
咄嗟に、わかりかねていると、村瀬がきっぱりという。
「秘密のないような一生では、面白くないだろう」
というのがあった。いたく同感である。心がけたい。
渡辺先生はまた、「年甲斐もない老人になりなさい」ともけしかけてこられる。
これも同じく同感である。がんばりまーす。
もうこの歳になると、「マイウェイ」の歌の文句ではないが、おのれの心の命ずるままに生きていこうという気持ちが強くなってくる。
したいことだけし、したくないことはなるべくしない。「品格」など気にしない。ってゆーか、もともとなかったか。
世間や他人の評価、期待される高齢者像などどうでもいいのだ。
まだ準サラリーマン的立場なのでおのずと限界があるが、気分としては「マイウェイ」路線である。
城山三郎の随筆集「この日、この空、この私」に、
六十代に入ったころ、「これはいい、これで行こう」と思ったのは、
「残躯楽しまざるべけんや」
という伊達政宗の言葉であった。
もっと日常的な言い方では、
「今朝酒あらば 今朝酒を楽しみ
明日憂来らば 明日憂えん」
といった生き方である。
そこで先に述べた「この日、この空、この私」と、つぶやくようになった。
とあった。これなども同じような気持ちである。
USB大作戦
つい二、三日前、近くの中山駅で女子学生のKさんと会った。
彼女がパソコンのデータを欲しがっていたので、USBに入れて渡したのである。メールで日時、場所を約束して届けにいったのである。
最初わたしはCDに入れて渡そうかとおもっていた。
しかし考えてみるとCDでは渡したらそれっきりである。そこでUSBに変更した。
USBなら返さなくてはならない。もう一回出会いのチャンスが増えるのである。
出会いにも周到な計画をめぐらす〈ちょい悪不良老年オヤジ〉なのであった。
中山あたりは、わたしの手近な自転車散歩コースである。
行った先で女の子に会うとなると気分が全然違う。いつもはふうふういう長い坂道を、軽々と走ってしまった。
ときめきがあるのだ。なにかわくわくしてくるのだ。
Kさんとは、教室で普通に話はするが特別親しい間柄ではない。
きちんとした言葉づかいの清楚な感じの女の子で、黒目がちの目が白い顔に印象的である。
メールの文章もていねいな敬語が美しく、服装もいつも落ち着いたものだった。
駅の改札口で彼女にUSBを渡した。
データの取り扱いについて簡単に説明した。
もし時間があったら、お茶か食事でも誘おうかと思っていたのだが、時間がなさそうだったので、そこで別れた。
出会いの時間はものの五分ぐらいだった。
しかし女の子に会った興奮の余韻で、帰り道はうきうきしていた。
女の子のパワーは絶大なのだ。大の男の一日を真っ赤なバラ色に染めあげてしまうのだ。
ときめき感は、老年オヤジのくたびれた全細胞を刺激し、活性化し、血行を良くし、若返らせ、健康の向上に寄与する。
考えてみると、彼女はわたしに対してなにもしていないのであった。
わたしが一方的に彼女に愛情をそそぎ、勝手に一人で満足しているだけなのだった。
しかし、これでいいのである。わたしはこれで幸せになったのである。
相手に愛情をかけたからといって、相手から愛情を期待するのは、愛情の押し売りである。身勝手というものである。
好きなものを愛するだけで人間は幸福になれるのである。
わたしは椿の小さい鉢植えを育てている。一本の小枝を挿し木にして、花が咲くまで育ててきたのだった。
もう何年になるだろう。毎年、大輪の美しい花を咲かせてくれるようになった。
今年は、こんな小さな木からと驚くくらいたくさんの花を次々に咲かせてくれている。
真夏、真っ白に乾ききった鉢を見てあわてて水をかける。強風にとばされて鉢が割れ、椿がごろんと横たわっていたこともあった。
長い年月をかさねて、わたしと椿の彼女は共に生きてきたのである。
わたしは大輪の美しい彼女を愛し、彼女はそれに応えて毎年美しい花を咲かせてくれたのである。
わたしは幸せな時間を彼女と共に生きたのであった。
ときめきのない生活、それは灰色の人生である。ただ生きているだけである。
生きがいのない細胞は生気をなくし、血行はとどこおり、あっという間に老化してしまう。
このUSB、卒業式で会ったとき返してもらうことにした。あと数日で卒業式だったのである。
ところが卒業式当日、にぎやかな謝恩会などがあって、二人ともUSBのことなどすっかり忘れてしまった。
式典から帰った深夜、彼女からメールが入り、おわびとまた会える日をきいてきた。
都合のいいとき、また中山駅で会おうと返信すると、三日後の火曜日なら何時でもいいとのことだった。もう一度彼女に会えることになったのである。翌日わたしは中山駅に行った。
こんどはお茶か食事を誘おうとおもった。
そのための事前調査である。
用意周到なのである。天気予報だと火曜日は雨のち曇りの予想だった。
昼に会うので、もし雨だったら駅構内のレストランでお茶か食事。雨があがっていたら近くの四季の森公園でお弁当、という計画をたてた。
さいわい適当なレストラン、お弁当屋がみつかった。
帰りは駅から四季の森公園までの遊歩道を走って、事前調査は万全のものとなった。
火曜日当日、朝、もう雨はやんでいて日差しがでてきた。
雨上がりのさわやかな天気で暖かい。途中セーターを脱ぎ、汗をふく。
定刻、Kさんがあらわれた。春らしく清楚な白っぽい服装でまとめた彼女が目の前にたたずんだ。
USBを受けとる。
「今日はあったかいね、お昼ごはん食べない?」
わたしは食事に誘った。
しかし彼女はおそく食べてきたので、おなかがへっていないという。この瞬間、四季の森計画は頓挫した。しかしすばやく気持をいれかえて、
「それじゃ近くの店でお茶でも飲もう」
ということで、駅前のコーヒーショップに入った。
わたしはカフェオレとサンドイッチ、彼女はアイスコーヒーを注文した。
窓際のテーブルにすわると、とりあえずわたしは汗をふいた。何を隠そう、わたしはだれにも負けない大汗かきなのだ。
「自転車で飛ばしてきたらひと汗かいちゃったよ」
照れ笑いしながら言い訳した。
家からここまでどうやってきたか、高校がこの近くだったこと、内定している会社の話など聞いた。
本社が関西の会社なので、研修で来週からしばらく神戸に行くこと、新幹線のキップを送ってきたこと、入社したらまた二ヶ月間関西で研修を受けることなど、彼女は話した。
「いいねえ、ただで関西行けるんだね、帰りにちょっと観光旅行してこれるね」
わたしがうらやましがると、
「わたし、関西方面はまだ行ったことないから、とても楽しみなんです」
といって新幹線のキップを見せてくれた。
「いいデザインをするには、いいデザインをいっぱい見てそれを頭の中の引き出しにしまっておくんだ。そうすれば何か新しくデザインするときにそれらを参考にできるからね。引き出しの中がからっぽでは新しいものは生み出せないんだ」
なんてもっともらしく、先生くさく話してしまった。
彼女と別れると、わたしは一人で四季の森公園に行き、黄色い菜の花畑のまえで酒を飲んだ。
女の子と別れたあとの虚脱感と満足感でしばらくぼーっとしていた。
良寛・一休 老いらくの恋
良寛さん、一休さん。日本人ならだれでも知っている。
村の子供たちと手まりをついて遊んだ良寛さん、とんち話の一休さん、みんなに親しまれたキャラクターである。
その良寛、一休は、高齢になってから恋をして人生を全うした。
良寛は七十歳の時、三十歳の貞心尼とめぐり会い、その後七十五歳で死ぬまで相思相愛だった。
一休は七十四歳で三十歳の森女と生活を共にし、盲目の彼女との愛を綴った「狂雲集」を残して八十八歳で亡くなった。
ひるがえって現代では、かねてから燃えるような恋をしたいと宣言していたあの角川春樹さんが、最近若い女性と再婚 (再々婚?) したそうである。
いくつになっても自由奔放でやんちゃな角川春樹さんらしく、うらやましい。
自分が相手と同じくらい若い時は、若い女の美しさはわかっていない。
自分もつるつるの、しわもない肌をしているときは、当然だと思っている。しかし自分が老年になると、世の中の美しいものがくっきりと見えてくる。美しいものの世界から遠ざかってしまったから、客観的にながめることができるのだ。
美しいものの何物にも代えられない価値がわかるのだ。
美しいもの、神がつくったこんなに素晴らしい造形物、それが毎朝、セーラー服を着て家の前の道をぞろぞろ歩いてくる・・・・
私立女子中高が近くに移転してきてからの風景である。
若い娘は、ありのままで美しい。茶髪は好きではない。
茶髪にすると、黒い髪より柔らかいアクセントになってどうのこうの、という話を聞いたことがあるが、日本人の顔色には合わない。
真っ白な白人だから美しいのであって、黄色人種の我々には、やはり艶々した漆黒の黒髪が最高にセクシーなのだ。
これは花と葉の色の関係と同じである。
わたしは園芸が好きで、種をまいて色々と花を咲かせていた時代があった。「インパチェンス」という東南アジア原産の、日陰でもよく咲く鮮やかな花がある。
この花は、白、オレンジ、赤などの色があるのだが、オレンジと赤では葉っぱの色が違うのである。
オレンジは明るいきれいな緑色であるが、赤い花のほうは紫がかり、それが花の赤い色にマッチして盛りたてているのだ。
その気になって他の花々を見回してみると、どの花もその花を最高にひきたてる葉の色をしている。
自然は偉大なるカラーコーディネーターである。
ふだん、学生を見慣れているせいか、普段着の若い女性のファッションが一番好きである。
Gパン姿がたまらなくすてきな娘や、前髪を左右にたらし、うしろ髪をまとめてくるくるたんこぶにして似合う娘がすきである。白い首筋におくれ毛がたまらない。
よくファッションショーなどで、とんでもない奇抜なデザインの服装を身につけたモデルが登場するが、あんなものは男としてまったく興味がわかない。
それよりも、清潔にきちんと制服を着た女子高生のほうが、はるかにしびれる。
自分の趣味でやっているならしょうがないが、爪に着色し絵など描くネイルアートも、男からみたら全く興味がない、なにもそそられない。ピアスも同じである。
文豪谷崎潤一郎の「痴人の愛」は、素行のよくない若い娘とそれを追いかけまわす中年男の話である。ちょっとあのナボコフの「ロリータ」と似ている。
惚れた若い娘を家にかくまい、なめるようにべたべた熱心にめんどうをみるのだが、娘はそんなことにおかまいなしに家を飛び出し、不良とつきあったり、遊びまわる。
しかし彼女の魔力にとらえられた男は娘をさがしだし、家に連れ戻す・・・・
といったような内容なのだが、わたしは人間の、男と女の真実を物語っている、と思う。
ずべ公でも性格がよくなくても、そんなこと関係ないのである。首すじの美しい曲線、ほっそりとした白い手足、長い黒髪、が男の心を狂わせ人生を狂わせる。
男と女の凸凹は、神様がつくられたのである。神様がデザインされたのである。自然なのである。
悪いものでもなければ、恥ずべきものでもない。これを有効に使わないというのは神の制作意図に反する。
良寛、一休は、人生の晩年この生物としての真実にめざめたのだろうとおもう。
お花見デート作戦
日時、場所を約束しあって異性と会うことをデートというなら、六年ほど前から私は若い娘とけっこうひんぱんにデートするようになった。習慣になった。
それ以前はこんなことは一度もなかったから、人生わからないものである。六十歳を過ぎてからこんな幸福が訪れようとは思ってもいなかった。相手はみんな私の教え子たちである。
そもそもの始まりは六年前、M子だった。
卒業式も終わり、明後日は入社式という三月三十日、秦野の駅で会った。近くの弘法山へお花見に行こうとハイキングに誘ったのである。
誘ったのには、それなりの理由があった。
彼女が一年生の時、午後の授業が終わった帰りがけ、M子が教室のドアの所で振り返り、
「先生、それじゃいつもの所で待ってるからねー、バイバイ」と大きな声で叫んで、大げさに手を振り、おどけて笑いながら帰っていったのである。
まだ教室には大勢学生達がいたから、みんな私と彼女を見比べ、驚きで声も出なかった。
もちろん私もあっけにとられ、ぽかんと彼女を見送った。
そんなことが二、三回あって、クラスの他の女子学生達に、私と彼女は特別の関係のように見られるようになってしまったのだった。
もちろんこれは、彼女の創作した一人芝居で、外で彼女と会ったことなど今まで一度もなかった。
その時は、これが彼女が発信したサインだということが分からなかった。こんなに分かり易いサインはないのに、初めての体験なので状況が把握できなかったのだ。
彼女は小柄で色白の、日本人形のような目鼻立ちの娘だった。
普段はごく普通の女の子で、特別おしゃべりでもなく、変わった行動などすることもなかったのであった。
二年生後期になって、私は彼女の卒業制作の担当になった。
ディスプレイの作品を作るため彼女を手伝った。スチロール板に大きな円を画いて丸く切り抜く。いくつも切り抜く。そしてそれらを接着する。
彼女と一緒に汗を流したひとときだった。
卒業式の謝恩会の時、女子学生の代表から寄せ書きを貰った。
家に帰って見てみると、みんなに色々書いてもらった中でM子は、
「先生の授業はほんとに楽しくて、先生と話すのもとても楽しかったです。いつも変なことばっかり言ってすいませんでした。先生のこと、大本命です」
と書いてあり、ハートマークが回りにぽつぽつ付けられていた。
なにか自慢するようで(実際自慢しているか)、見せびらかしているようで気がひけるが、ここを省くと話が前に進まないのである。
こんなオヤジに好感をもってくれる若い娘がいたのだった。長い教員生活で初めての体験だった。
これを見て私は、このまま卒業して、それっきりにしてはいけない、と強く思った。
この時私は初めて、サインを認識したのだった。
いままでこんなにはっきりとたくさん、私にサインを送ってもらってありがとう。了解です、解読しました、と心のなかでさけんだ。
私は彼女に携帯で電話した。
「ハイキングに行こう」
万一断られても構わないと思った。いや、絶対そんなことはないと思った。「一人で?」彼女は聞いた。
「そう、二人で行かない?」
彼女はOKした。
これが、彼女を弘法山に誘った理由である。
駅構内の店でおにぎり、お茶、お菓子など買い、山に向かった。
山のふもとに着くといきなり登山道が始まり、急な階段が折れ曲がりながら続いていた。
登山道を登りきり、平坦な山道を歩いて見晴らしのいい休憩所に着いた。
期待していた桜はたいしたことなかった。全山、桜に覆われるといった感動的な風景はなく、所々に桜のかたまりが咲いていた。
中高年のグループが休んでいて、わたしたちもその近くのベンチにすわった。
おじさん、おばさんのにぎやかな集団のなかにまぎれこんだ、若い娘と白髪のオヤジのカップル?は少々気恥かしかったが、とりあえずお茶など取り出して休憩した。
林の中のゆるいアップダウンを越えると、登山道をはずれてみかん畑の中に彼女を連れて入っていった。
じつはここは、数日前、下調べに来たとき決めていた場所だった。
まわりをみかんの低木に囲まれ、外界から隔離されている。下心がなかったといったらうそになる。
「大丈夫? 疲れた?」
彼女はうなずいた。
私はみかん畑の中にブルーシートを敷いた。
「おじゃましまーす」といって、彼女はすわった。
買ってきたおにぎりを食べお茶を飲む。お菓子を食べてしばしくつろぐ。
静かである。なんの物音も聞こえない。ときおり遠くで鳥の鳴き声が聞こえるだけだった。
「指圧してあげるよ、疲れがとれるよ」といって彼女の手をとった。
昔、カラー写真で解説つきの指圧の本を買ったことがあった。それを見ながら女房に指圧してあげたことがあった。今でもつぼを憶えているのである。彼女の手の平をにぎり、指を一本ずつ強く握ったり付け根を押したりして、まず手の平を指圧した。小さくかわいい手の平だった。
次にひじのつぼを押していく。腕の三里といって、そこを押すと電気にふれたようにずきんと痛いところがある。
「いたいっ!」
彼女が飛びあがった。
手が終わって、頭と顔になった。頭蓋骨の上、まん中にそって押していく。後頭部首の付け根のあたりをもみほぐす。目、口のまわりはそっと押す。
次に足を押そうとすると、「いい」と断られた。
帰り道、何枚か彼女の写真を撮った。
あとで見てみると、どれもとてもいい表情をしている。柔らかい表情で笑っている。笑ってVサインなどしている。
二人だけのデートの緊張感などまったく感じられない。
彼女も楽しんだひと時だったのだなと思った。
結局私の下心は未遂のまま消滅した。
その後もおりにふれ、彼女とはたびたび会っている。
彼女は温泉の会社に勤めた。自分ではお風呂屋さんといっている。
温泉といっても、温泉地にある従来の温泉ではなく、都会の真ん中に大きなビルを作り、そこに温泉地から元湯をタンクローリーで運んでくる人工温泉である。
彼女はそこでポスターやメニュー、サインなど、グラフィック関係の仕事をしている。
そこの無料特別招待券というのを時々送ってきてくれて、私は何回か行かせてもらった。帰りがけ彼女に会えるのが大きな楽しみだった。
あのみかん畑の真ん中で二人きりでおにぎりを食べた彼女が、制服を着て、広い館内の受付フロアーの奥から現れてくるのは、何か不思議な感じだった。
若い女性と会うのは、心ときめきうれしいものだが、会う時と別れる時がたまらない。
約束の時間が迫ってきて、電車が到着し、どやどやと人が改札口に溢れてくる。
改札の向こうからこちらを見つけた彼女が、手を振りながら小走りで走りよってくる!
この時ほどたまらなくうれしい瞬間はない。
待ち合わせの時、私はかなり早めに行って待っている。一時間近くも早く行って、あたりをぶらぶらしてすごすこともある。
約束の時間までの刻々の時間は、たまらなく甘美なひとときである。時間ぎりぎりに行ったのではもったいない。
サン・テグジュペリの「星の王子さま」で、キツネがいう、
「あんたが午後四時にやってくるとすると、おれ、三時には、もう、うれしくなりだすというものだ。
そして、時刻がたつにつれて、おれはうれしくなるだろう。
四時には、もう、おちおちしていられなくなって、おれは、幸福のありがたさを身にしみて思う。」
また別れの時、改札口の向こうの彼女が振り向いてちょっと手を振る。
こちらもつられて手を振る。
この時の甘酸っぱい思いは心に沁み、いつまでも忘れられない。
就職 ・きびしかった現実
ところで人の運命は様々である。どうしてこの子が、ということもある。
あれはいつだったろうか? たまたまその日、耳の治療で病院に行っていた私は、待合室で携帯に留守電が入っているのに気がついた。
廊下の隅に行って聞いてみる。
「助けて、どうしよう!」
こんな悲鳴のような声が入っていた。
電波の状態が悪いのか声がよくわからない。話はそれだけで、プツリと切れてしまう。
何だろう? 誰だ? 誘拐でもされたのか?
どういうわけか、発信人が確認できなかった。
見当がつかない、少々薄気味わるかった。
しばらくすると今度はメールが届いた。
「先生、どうしょう? 会社くびになっちゃった」
K子からだった。
さっきの留守電はK子からだったのである。
K子は先ほどのM子の二年後輩である。去年就職して今年で一年ちょっとになる。
大変なことになった。おろおろとうろたえているだろう。どうしていいかわからないのにちがいない。
K子も私にたくさんサインを送ってくれた子の一人である。
最初のサインは一年生の時だった。
「先生、手だして」
彼女はそういうと、私の開いた右手に彼女の握った手のひらを重ねた。
「はい、あげる」
見るとビー玉ぐらいの大きさの髑髏だった。モスグリーン色で造形がしっかりしている。陶芸の授業で作ったようだ。
私はそれを携帯のストラップにつけた。
同僚の先生や学生たちはそれを見つけて驚いた。K子は、ふん、といった顔でそれを見ていた。
二年生の初夏の頃、校外学習ということでクラス全員、表参道、青山のデザインショップ見学に行った。
地下鉄を降りて地上に出て来ると、みんなぞろぞろ歩きだした。
女の子、男の子は、たいてい仲良しグループでかたまって歩いている。
私は彼らの間でのんびり歩いていた。
するとK子がグループを離れて私のそばにやってきて、並んで歩きだしたのである。
「どう、 就職活動は」
彼女に話しかけた。面接のこと、遅刻してしまったこと、会社が遠いこと、など聞きながら歩いた。
しかしこれが、一緒に行った同僚の先生や他の学生達からは、我々が二人だけの世界に入りこんでしまったように見えたらしかった。
秋になり、卒制(卒業制作)がはじまった。
中間発表の日、ひとりひとり黒板の前に行って、自分の計画を発表することになった。
私は広い教室の真ん中あたりにすわって、彼らの説明を聞いていた。
するとドアが開いて、K子が入ってきた。遅刻である。
教室をぐるりと見回して私を見つけると、すいすいと歩いて来て、私の前の空いている席にすわった。
彼女は卒制のスケッチをバッグから取り出すと、振り向いて私の机の上にそのスケッチを置き、
「先生、このスケッチで作れますか?」と聞いた。
それは鏡台だった。大きく曲線をえがいた木材に鏡と棚がついている。
私は、工作がむずかしそうな所や、強度的に弱そうな部分を彼女に指摘した。
彼女は振り向いたまま、スケッチを描き直しだした。
この間、他の学生たちの発表は進行していて、またもや私と彼女の二人だけの世界に入ってしまった。
そんなことがたび重なって、ある日男子学生のYに、
「先生、一番好きな学生はだれですか?」
と質問された。
「みんな同じように好きだよ」と答えると、
「でもそのなかで特に好きな人はだれですか? 」
とさらにつっこんでくる。
「みんなおんなじだよ、あはは・・・・ 」
私は笑いにごまかして、その場をのがれた。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
