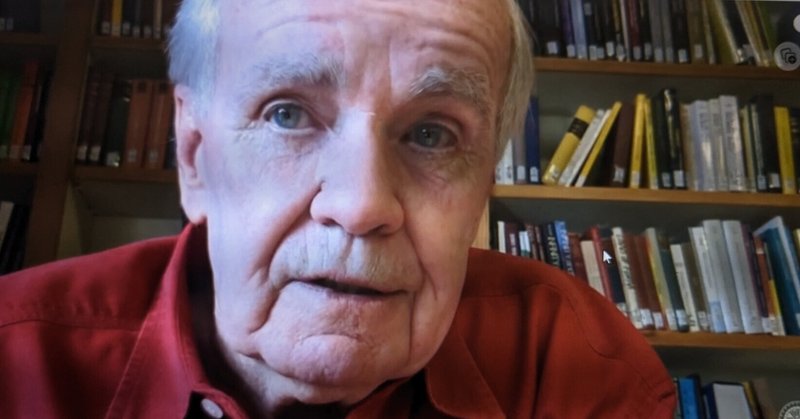
映画日記 よく似た映画を観た。『ノー・カントリー』『クライ・マッチョ』『ランボー ラスト・ブラッド』
よく似た映画を三つ見た。適当に選んで見たのだが、偶然、三つとも似ていたのだ。見たと言っても、自宅でテレビでだから、そんなに真剣には見ていない。それぞれ傾向が全く違う作品なのだが、なにやら同じような映画だった。
三つの映画の似ている点・共通点を並べてみる。
1 まずは、アメリカ映画で、時制は現代だ。
2 馬が出てきて牧場も出てくる。
3 砂漠のような広大な荒野が出てくる。
4 テンガロンハットを被ったカウボーイ風の男が出てくる。
5 銃も出てくる。
6 追跡劇があって、それがなにやら西部劇を彷彿とさせる。
7 舞台がアメリカ南部とメキシコで、国境をまたいで車で長距離を行き来する。
8 主人公が男の老人で、なにがしかの過去を持っている。
9 主要な人物、脇役に、アウトローが出てくる。
10 まるで終活のようなハナシだ。
思いついたものを並べてみたら、10も出てきた。もっと出てきそうだけど、でも、整理したら少なくなりそうでもある。
この文章の頭の写真は、『ノー・カントリー・フォー・オールド・メン』の著者、コーマック・マッカーシーの顔だ。最初に見た映画『ノー・カントリー』の原作者に当たる。必要はないのだが、見つけたので使ってみた。
『ノー・カントリー』(2007)
最初に見たのは、『ノー・カントリー』というコーエン兄弟が作った2007年制作の映画だ。
この映画は観ようと思っていて、見逃した映画だった。確か、賞をいくつも獲っていたと思う。作り手のコーエン兄弟は、二人とも現在まだ60代だ。
この映画の中では、麻薬売買にからむ大金を横取りしたベトナム帰還兵と、それを追うメキシコ人の殺し屋みたいな奴と、それを取り締まる保安官の話が描かれている。逃げるベトナム帰還兵と、それを追う殺し屋の攻防は、西部劇の追いかけっこみたいだった。
ベトナム帰還兵は、銃器の扱いに長けていて、冷静沈着に任務を遂行するタイプだ。サヴァイヴァル能力もあるので、自分でも追っ手を逃れて、うまくやれると思っている。
追っ手の殺し屋は、一度決めたことは完遂する機械のような性格で、常識とか法律とかとは無縁で、自分の作ったルールの中に生きて、行動している。彼のルールに反したものは、雇い主でも殺す。しかし例外があって、コイントスをして、相手が表と言って表が出たら、殺さずに見逃すのだった。わかりやすいのか、わかりづらいのは、よくわからない人物造形になっている。
殺しの手口も独特で、片手に圧縮ガスの入ったボンベを持っている。ボンベの先には、ホースが伸びていて、そのホースは殺し屋の袖口を通っている。そのホースの先から、鉄の棒のようなものが飛び出て、密着した相手を殺傷する。どうやら屠殺用のスタンガンの一種らしい。
ベトナム帰還兵は、お金を持ったことでアウトローになり、追っ手のメキシコ人の殺し屋は、最初からその存在は法律の枠外にあるアウトローだ。
事件を追う保安官をトミー・リー・ジョーンズが演じている。この映画で、私が唯一知っている顔だった。映画がだいぶ進んでから、この警官が、この映画の主人公であることがわかる。
保安官は、動機のない無差別殺人のような事件が、現在のアメリカでは多発していて、もはや自分の理解の及ばない世の中になっていると感じている。
この事件の後に、彼は保安官を引退する。そして、彼が余生を送っている様子が、この映画のラストシーンとなっている。それが妙に不穏なのだ。
一人暮らしの叔父の家に行き、なにやら相談のような親戚同士の昔話のような会話を交わすシーンがある。
その後、自宅で妻と会話するシーンになる。彼は無表情に虚空を見つめていて、見た夢の話をしているのだが、何か自問をしているような様子だ。人生の意味とか人間存在の意味を、映画の観客に問いかけてくるような、そんな終わり方だ。
事件の進行中は、暴力に満ちた衝撃的なシーンの連続だったのだが、別の映画かと思うくらい、最後はとても静かで淡々としている。
と書いてみたものの、実は終わりの方は、半分眠っていた。だから映画の詳細は憶えていないのだ。原作小説では、この部分が意外に長い。数十ページはあったと思う。
原作小説を私が読んだのは、それこそ翻訳が出版された時だから、十数年前だ。その時は、『血と暴力の国』というタイトルだったし、出したのが扶桑社文庫だったから、ノアールとして読んだ。
著者の、句読点のない、会話文にかぎかっこもしない、独特の文体が、やっぱり独特の文体でノアール小説を書いていたジェイムズ・エルロイを凌駕するみたいな言われ方をしていたので、犯罪小説として読んだし、作者のことも、ノアールの書き手として認識したのだった。
その後、著者のコーマック・マッカーシーは、エンタメではなく文学の人で、ノーベル文学賞の候補になっているなんてハナシを知るのだが、ノアールの印象は変わらない。
ちなみに『血と暴力の国』は、先月、『ノー・カントリー・フォー・オールド・メン』という元のタイトルで早川epi文庫で新版が出ている。
原作小説の終章では、保安官が、自分のベトナムでの従軍体験を語っていた。部隊が全滅し、たまたま彼だけが生き残ったのだ。生還後、勲章をもらっている。彼は仲間を助けられなかったことに負い目を感じて、その後の長い人生を生きてきた。
また、追っ手の殺し屋に殺されたベトナム帰還兵の父親に会いに行ったりする。このあたりのことは、映画では描かれていなかったと思う。保安官がベトナム帰還兵だということも映画ではなかった気がする。
小説では最後の最後に、保安官の父親が馬喰だったことが語られる。馬喰は馬を競りにかけて売買する人のことなのだが、アウトローっぽい世界の人に読めた。その前に保安官は、捕まったメキシコ人の殺し屋の裁判に出て、減刑の証言をしている。このことは、アウトローを理解しようとしているのかなとも読めた。つまり、これまで否定し続けてきた父親のことを理解しようとしている、といった意味にも読めた。これは私が読み取ったのではなく、翻訳者の解説に書いてあったことかもしれない。
こうなると、映画は最後の方を寝ぼけてちゃんと見ていなかったし、本を読んだのもだいぶ前のことなので、記憶も曖昧で、映画の感想なのか、小説の感想なのか、私のこの文章も、わけがわからなくなってくる。
ただ、映画の最後の最後のトミー・リー・ジョーンズの顔は憶えている。暴力は突然やってくるし、それから逃れることはできない。同様に、人間にとって老いは必ずやってきて、それは肉体的な衰えかもしれないし、認知症状のようなものかもしれない。それらからは逃れることは出来ないし、そういうわけのわからないものに、今、自分は入りつつある、という、その老いの次元に同化した瞬間の、トミー・リー・ジョーンズの表情は無表情なのだった、という感じの顔だった。
映画を観た人が、意味とか教訓とかを、見つけたかったら自分で考えて答えを見つければいいし、別に見つけなくてもいいよ、という終わり方だ。何も押しつけていない。血なまぐさい殺戮場面が多い割に、静かな印象の不思議な映画だった。でも観終わったら何かを考えさせられるのだった。
そうそう、音楽のない映画だった。
『クライ・マッチョ』(2021)
次に見たのは、クリント・イーストウッドが主演監督した2021年の映画『クライ・マッチョ』だ。
イーストウッドは、この映画を作っていた時は、90歳か91歳。主演もしているが、動作も90代のおじいちゃんに相応しく、背中が曲がってよれよれで、声も細い。ほとんど『眠り狂四郎 The Final 』の時の田村正和のようだった。
タイトルのマッチョというのは、映画に出てくる少年が飼っている闘鶏の鶏の名前だが、男らしさのマッチョもかけている。「マッチョ」と「チキン」が象徴的なコトバとして、頻繁に口にされる。
現代と言えば現代なのだが、時制は、もう少し前に設定されているかもしれない。
イーストウッドは元凄腕のカウボーイで、元の雇い主に頼まれて、雇い主の息子である別居中の少年をメキシコから連れ出す役目を仰せつかっている。だから、少年を連れて車で走るロードムーヴィーみたいに映画は進行する。
少年の母親が、追っ手を差し向ける。この母親が、よくわからない。娼館の女主人のようなのだが、地元の有力者で法律の枠外の存在のようだ。そして、母親が差し向けた追手が、恐ろしく間抜けで、まるでリアリティがない。
イーストウッドと少年は、途中、メキシコ人女性が経営する食堂に立ち寄り、何日か世話になる。女主人と孫娘が四人くらいいる女だけの家だ。そこにイーストウッドと少年は馴染んでいく。
近くの牧場で、二人は荒馬をならしたりして、お金をもらったりする。イーストウッドは高齢のジイさんのクセに、「パパは何でも知っている」(←たとえが古すぎるし、実は私も見たことがない)みたいな頼りになる現役の父親ぶりを発揮する。機械の修理もすれば獣医のように家畜を診ることもできるし、料理もする万能の男で、きわめつけに女性にもてる。
その後、女性の家を離れ、また国境に向かう。その後も、二人に都合のいい展開が多々あって、コメディでもないのに、こんなに簡単でいいのかと思わされた。
イーストウッドもモーロクしたなあと感じた。年齢相応の老いを描いているのではなく、結果的にモーロクが印象付けられるのだ。そして、この映画が、なんとなく「西部劇の打ち止め作品」のように見えてきたのだった。
少年は、無事に父親のもとに辿り着き、老人は彼を慕ってくれるメキシコ人女性の一家の元に戻っていく、みたいな、やっぱり都合のいい終わり方だった。こんなジジイの都合のいい妄想みたいな展開、映画製作中に、諫める人はいなかったのだろうか?
以前のイーストウッドなら、都合のいい終わりも、見る者を納得させる力があったものだが、『クライ・マッチョ』には、詰めの甘いモーロクしか感じなかった。
この映画でイーストウッドが演じる老人には、理想の男が表現されているのだろうか? 男って、なんだか面倒くさい。老いに抵抗してみたけれど、いかんせん、役者の体力が足りなかった、みたいな映画だった。
何気に音楽が良かった。うるさくなく、出しゃばらないで、でも、あってよかった、みたいな音楽だ。
この映画そのものがイーストウッドの終活に見えた。雑というよりは、衰えなのかもしれない。とはいえ、まだ次回作が予定されていて、それが最終作になるというから、相当元気なジイさんだ。
『ランボー ラスト・ブラッド』(2019)
三番目に見たのが、『ランボー ラスト・ブラッド』というシルベスタ・スタローンが2019年に作ったランボー・シリーズの最終作だ。このとき、スタローンは73歳くらいだ。
親が経営していた牧場を引き継いだランボーは、ジジイになっても相変わらずベトナム戦争を引きずって病んでいた。その牧場には、家政婦?とその孫娘と三人で住んでいた。
孫娘が自分の父親を探して、メキシコに行き、事件に巻き込まれ、売春組織に売られてしまった。それを救出に行くランボー。しかし、孫娘は死に、ランボーは売春組織相手に復讐を開始する、というハナシだ。
ランボーは何歳になっても、一人で戦うのだ。暴力を肯定する彼も、対決する売春組織の面々も、みんなアウトローだ。アウトローなんだけど、単純すぎて、深みのない造形にとどまっている。
ハナシの途中で、なぜかランボーを手助けするメキシコの女性ジャーナリストが出てくる。この人、最初はオカマかと思って見ていたら、女性だったので驚いた。
また、なぜか彼女には二度目の登場がある。ランボーが、また助けてくれ、協力してくれと無理強いをして、協力してもらうのだが、何に協力をしたのか、具体的な描写はなく、必要のないシーンを無理やり作ったように見えた。
最後、メキシコの売春組織とランボーが戦うのだが、場所はなぜかアメリカにあるランボーの牧場だ。メキシコから一列の車列になって、敵がはるばるやって来てくれるのだ。しかも牧場の地下には縦横にトンネルが張り巡らされている。
ランボーはトンネル掘りが趣味だったのだ! ベトコンの掘ったトンネルなんかより大きな、アメリカンサイズのトンネルだ。
そのトンネルには、至る所に必殺のトラップが仕掛けられており、売春組織のメンバー達は、次から次へとひっかかって死んでいく。普通に考えたら、敵の作った穴の中に自分から入っていくようなアホはいない。
そんなあり得ない展開ばかりで出来上がった映画だった。
暴力シーンが、あんまり見たことのないシーンの連続で、笑ってしまった。ランボーは、敵の一人の首元に指を突っ込んで、骨(肩甲骨?)を折って、体外に突き出させたりする。素手でこれをやるのだ。
敵のナンバーツーに対しては、殺害後、首をちょん切って、ベッドの上に生首を晒したりしている。また最後は、敵のナンバー1を弓矢(ランボーシリーズの定番だ!)で壁に貼り付け、ナイフで胸を切り裂き、手首を突っ込んで心臓を引きちぎって、取り出したりしている。
一応、リアルな映像にしてあるのだが、滑稽でしかない。人によっては新鮮味を感じるのだろうか? 誰かとめる人、やめさせる人はいなかったのだろうか? 映画の中で流れる曲も、押しつけがましくてうるさい。つくづくセンスのない人なのだと思う。
因果応報的な教訓ならともかく、復讐や報復をこんなにあっさり認めると、暴力の連鎖はいくらでも再生産して止まらない。この映画のようにフィクションにとどまればいいのだろうが、この感覚が現実に持ち込まれると、終わりのない戦争状態を生み出してしまう。アメリカだったら、それこそ議事堂襲撃も肯定されそうだ。私の偏見に満ちた頭の中では、スタローンのファンと、トランプ支持者が繋がってしまった。
それにしても、この映画のランボーが、スタローンの理想とする男の姿、この展開が男の物語なのだろうか?
この映画のタイトルも「ラスト・ブラッド」なので、ランボーのシリーズは、これで打ち止めなんだろうと思う。最期にやりたいことを全部やって、これで終わりにしようという映画だったのだろうか。これはこれでスタローンの終活映画のようにも見えた。
それにしても、粗が目立つ雑な映画だった。ランボー・シリーズは、みんなひどいけれど、その中でも一番出来が悪いんじゃないかと思う。
ランボーのシリーズは、ロッキー・シリーズと違って、バランスが悪い。まるでスタローンの入れ墨みたいに、バランスが悪い。スタローンは、50歳を過ぎてから入れ墨をしたらしい。
ロック・ギタリストのエディ・ヴァンヘイレンが亡くなったとき、ヴァンヘイレンのボーカルだったデヴィッド・リー・ロスが日本で和柄の入れ墨を全身に入れていたらしい、と友人が教えてくれた。ミーハーな私は早速検索して、ロスの写真を見た。その時、並んで出てきたのが、スタローンのタトゥーだった。
映画感想文からただのゴシップ面白バナシになってきた。映画に戻ろう。往生際の悪い映画、というのが『ランボー ラスト・ブラッド』に一番適した表現だろうか。よぼよぼのジイさんが、毛量豊かで真っ黒でツヤツヤのカツラを被っている、みたいなチグハグな映画だった。
何回も書くけれど、誰か止める人はいなかったのだろうか?
本当は、この後、3つの映画について、まとめのような文章を延々と書いたのだが、まるでまとまらなかったので、なかったことにして、ここで終ります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

