竹倉史人「土偶を読む」について
本記事は、NHKのニュースで取り上げられるなど、大々的にプロモーションを展開して話題となった竹倉史人氏の著書『土偶を読む』(晶文社)について、筆者(白鳥兄弟=高橋健)の意見を述べるものである。
本記事の公開に至る経緯
竹倉史人氏の著書『土偶を読む』について、5月下旬に日本経済新聞社にコメントを求められ、取材に対応した。筆者は土偶の研究者ではないが、考古学を専門とする学芸員として博物館に勤務しており、「土偶マイム」のパフォーマンスを行っていることもあって、取材の依頼があったものだと思われる。取材を受けるにあたってまとめたメモが、本記事の原型である。
取材は1時間半以上にわたったが、紙面に掲載された筆者のコメントは百文字足らずであり、また記事全体の論調については筆者の関知するところではない。もちろんこうした新聞記事でのコメントの使われ方については承知しているので、この点についての不満は特にない。だが筆者の意見の全体像を示しておくことにも意味があるだろうと考え、noteとして公開することにした。
日本経済新聞の記事
当該記事は、2021年6月5日(土)の日本経済新聞文化欄に掲載された「ベストセラーの裏側」というコーナーである。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO72585670U1A600C2MY5000/
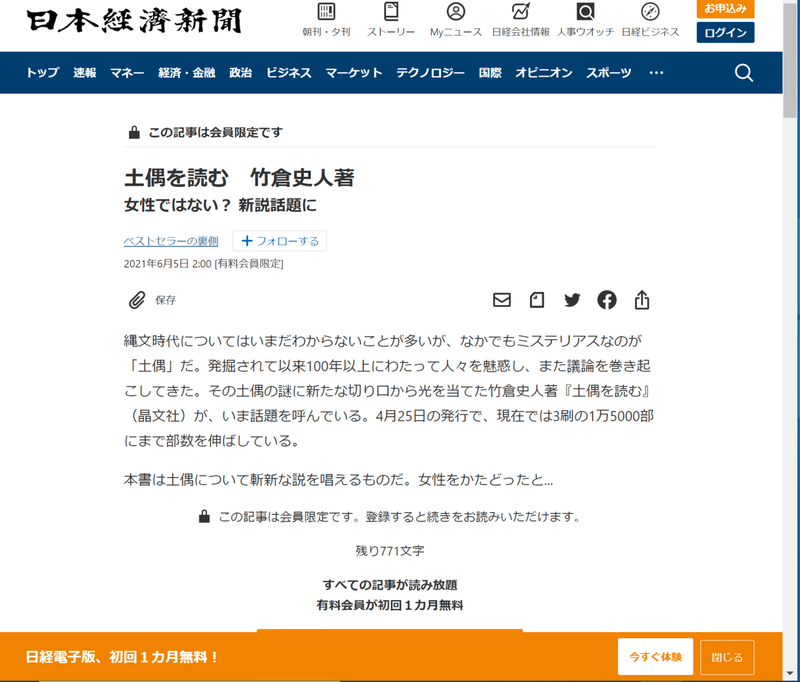
筆者のコメント部分を引用しておこう。
高橋健氏は「従来も土偶を女性、すなわち大地の女神に見立てて豊穣を祈念したとされる『地母神説』など、植物と土偶を結びつけた議論はあった。本書の新しさは植物と土偶の形を直接結びつけている点にある」と述べる。
このコメントには、以下のような文が続く。
だが話題の広がりをよそに、考古学の世界は静観しているというのが現状だ。
これだけを読めば、高橋は竹倉氏の著作の新しい着想を評価している、しかし考古学の世界はこれを黙殺している、という風に読める。しかし、実際に筆者が述べた文脈に即して書き直すと、次のようになる。
竹倉氏は土偶と植物祭祀を結びつけること自体が新説であるかのように述べているが、実際には竹倉氏が否定する従来の説の中にも、いわゆる「地母神説」のように、土偶と植物や農耕に関わる祭祀との結びつきを考えたものはあった。竹倉氏の説に新しい点があるとすれば、土偶は「ひとがた」ではないとした点、植物と土偶の形を直接結び付けた点だといえる。だが、そのアイデアは十分に論証されておらず、反論を呼ぶような水準のものでもない。したがって、おそらく学界での反応はほとんどないだろうと予想するが、それは決して考古学界が閉鎖的で権威主義的だからという訳ではない。
繰り返しになるが、コメントが切り取られることについては承知した上で取材に応じたし、紙面でどの部分が使われることになるのかについても事前に確認の連絡はもらって了解している。このnote記事の目的は、こうした点について批判や不満を述べることではなく、あくまで筆者の意見の全体像を示すことにある。
考古学者以外による考古学研究
取材にあたっては、竹倉氏の著作に対する考古学者としての意見のほかに、「考古学者以外が考古学の理論を打ち立てることに対する感想」も聞かれていた。それに対する筆者の回答は次のようなものであった。
考古学者以外が考古学について議論すること、その結果として新しい理論が生まれることには何の問題もない。学問は開かれたものであるべきだし、そうしたこと(新理論の確立)が起きれば考古学にとってプラスである。ただし、竹倉氏の著作が新しい考古学の理論を打ち立てたとは評価できない。
竹倉氏は、おそらくは自身の過去の経験から、既存の考古学、あるいは考古学者に対する敵対心をもっている節がある。私は考古学が他の学問分野に比べてことさら閉鎖的で権威主義的だとは考えていないが、おそらくそういった側面もそれなりにはあるだろうとも思う。竹倉氏が反発や敵対心をもつような扱いを受けたのだとすれば残念なことではあるが、その扱いが不当なものだったのかどうかは私には分からない。
私にいえることは、おそらく本書は考古学界では評価されないということ、そしてその理由は本書の内容が不十分なためだということである。
竹倉氏の「新説」
竹倉氏はその著作『土偶を読む』(以下、本書とする)で土偶の正体を解明したと主張する。その主張の根幹は、土偶はひとがたではない、さらに植物の姿を具象的・写実的に写し取ったものである、という点である。
本書にはいくつかの問題があるため、おそらく多くの研究者の同意を得る、あるいは反論を受けて議論が進展する可能性は低いと考えられる。以下、それらの問題点をみていこう。
「土偶」とは何か?
従来の土偶の概念を否定しながら「土偶」という枠組みにとらわれている点、これは本書でもっとも根本的かつ致命的な問題点である。
「土偶」は、縄文時代に作られた焼き物の中から、「ひとがた」であるという特徴によって抜き出されたものである。
遺跡から出土する焼き物の大部分は容器の形をしていて土器と呼ばれる。それ以外は土製品と呼ばれるが、用途が分かるものは、土錘や土製耳飾などの名前が付けられている。用途が分からず「〇〇の形をしている」としかいえないもののうち、「ひとがた」のものを土偶と呼び、「ひとがた」ではないものは、〇〇形土製品(動物、亀、猪、犬、イカ、巻貝、アワビ、クルミ、キノコ、三角形など)と呼んでいる。土偶を「人形土製品」と呼ばないのは単に研究上の慣習で、そう呼んでも差し支えはない。
竹倉氏が「土偶はひとがたではない」と主張するならば、まず「土偶とは何か」を新たに定義しないといけない。他の研究者によって抜き出された「土偶」を対象として議論を進めている時点で、すでに「土偶はひとがたである」という前提に乗っかってしまっているのである。
「土偶」に限らず、用語や概念の定義がされないままに議論が進められるのは、本書にしばしばみられる問題点である。竹倉氏は、「土偶はひとがたではない」とするが、他方で植物の「人体化」(p.5)という概念も使っている。人体化されたものが「ひとがた」ではないというのは一体どういうことなのか、という疑問が当然生じる。しかし、そもそも「土偶」や「ひとがた」、「人体化」が何を指すのか、明確に定義されていないのである。
序章では土偶は女性像ではないと断言していたにも関わらず(p.23)、第6章では「ビーナスはやはり妊娠像なのである」と言う(p.225)。人間女性ではなくトチノミの精霊だそうだが、果たしてその妊娠した木の実の精霊のイメージは、「ひとがた」とは無関係に生まれてくるものなのだろうか?
第1章では、クルミの形を模した土器(土製品)が、ハート形土偶=オニグルミ説を補強する存在として扱われている(p.73)。しかしどちらもクルミをモチーフとした焼き物であるならば、両者はどうやって区別されるのだろうか?もちろん「ひとがた」のものが土偶だとすれば話は簡単なのだが、その定義は否定されている。
実はこの土偶の定義に関わる問題だけでも竹倉氏の議論はすでに破綻しているのだが、一応、竹倉氏によって「土偶はひとがたである」という以外の定義が示された、そしてその対象とする範囲が(偶然にも?)これまで「土偶」と呼ばれてきたものと一致している、ということにして話を進めてみよう。
土偶の「正体」は一つか?
縄文時代の土偶がすべて同じ性格をもつという前提に立っている点にも問題がある。われわれが「縄文時代」と呼んでいる時代は1万年以上に及ぶが、地域や時期によって土偶が多く作られたり、少なかったり、あるいは全くなかったりするし、土偶の形や大きさもさまざまである。「土偶」というのは、あくまで現代の研究者が作った枠組みでしかないから、すべての土偶が同じ性格をもっていたとは限らないのである。
ただし、このすべての土偶に共通性を見出すという視点は、実は多くの考古学者も意識的・無意識的に共有している。意識的な場合は、土偶にはこのような共通の性格があるのだという主張となり、無意識の場合は、議論の過程にこうした前提を滑り込ませてしまうことになる。したがって、この点は本書だけの問題ではないともいえるが、土偶の正体を解明したと主張する上では弱点になっている。
また、筆者の個人的な意見としては、多くの人に「共通の何かがあるのではないか」と思わせる点にこそ、縄文土偶の面白さや魅力があるのではないか、とも考えている。そうした意味では、竹倉氏も多くの考古学者と同じ轍にはまったといえるのかもしれない。
竹倉氏の研究方法
本書における議論は、次のように進められる。
1 縄文脳のインストール
2 土偶と植物の形の比較 (イコノロジー)
3 植物と土偶の分布の比較
1の「縄文脳のインストール」は着想を得るための手段、2の「イコノロジー」が論証の中核であり、3の「植物と土偶の分布の比較」は補強手段とされている。
1 縄文脳のインストール
1の縄文脳のインストールについては、率直な感想としては便利な方法だと思う。研究に行き詰ったときに遺跡に行ったり野山で木の実などを拾ったりすると、アイデアが下りてくるらしい。
リンゴが落ちるのを見て万有引力を思いついたという有名なニュートンの逸話のように、仮説を思いつく方法はどんな突拍子もない方法であっても構わない。土偶研究に行き詰って縄文遺跡に行くというのは、かなり穏当なやり方だといえるかもしれない。
ただし思いついた仮説の当否については、別にきちんと検証される必要がある。仮説の検証については後で論じるとして、この「縄文脳のインストール」に問題があるとすれば、それが仮説の補強にも使われているようにみえる点であろう(例えばp.61の記述など)。
なお世間を見渡すと、梅之木遺跡の黒田さんや、縄文大工の雨宮さんなど、相当強力な縄文脳をインストールしていそうな方々もいる。縄文脳座談会など企画してみても面白いかもしれない。
2 土偶と植物の形の比較 (イコノロジー)
議論の中核となるイコノロジー、すなわち土偶と植物との形の比較であるが、この方法には重大な欠点があることは、竹倉氏も自覚している通りである。結局のところ、「似ている/似ていない」という主観のぶつけ合いになってしまうのである。
竹倉氏は上記の3の「植物と土偶の分布の比較」による補強と、いくつものタイプの土偶について解釈の事例を積み重ねることで確からしさを増すことができると考えているようである。3については次節で述べるが、事例の積み重ねについては、場当たり的な解釈を積み重ねているだけのようにみえる。これは竹倉氏による比較の仕方に問題があるためである。
まず特定の土偶だけを取り上げて一般化している。実際には、例えばハート形土偶や山形土偶といっても多様な形のものがある。いろいろな土偶が存在することを知らなければ竹倉氏の主張にも説得力があるように感じるのかもしれないが、都合のいい資料だけをピックアップしている、もしくはその資料しか知らないのではないか、という印象を受ける。
次に、土偶のどこに注目するかが恣意的である。その中でも顔の形(輪郭)に注目している場合が多いが、基本的に写真で比較しているためか、平面形にとらわれていることが多い。
例えば、山形土偶をハマグリやサルボウといった二枚貝に対比しているが、これらの貝は立体的な形状をしており、土偶の頭も立体的である。三次元で比較すれば到底似ているとはいえない。縄文人が見ていた貝は(そして土偶も)、図鑑の写真ではなく三次元だったはずである。
また、山形土偶の頭部形態は極めて多様であり、そのすべてが貝に対比できるとは思えない。もちろん貝の形も多様であるが、その中には土偶に似ても似つかないものもある。もちろん縄文人が利用していた貝種である。
「オオツタノハ」と「星形土偶」の比較についても、やはり三次元で比較すると全く異なる。オオツタノハは笠形なのに対して、「星形土偶」は平坦なのである。竹倉氏はオオツタノハの仲間であるカサガイ科の貝を採集しているから、これらが平らな貝ではないという点はよく承知のはずであるが、上からみた平面形が似ているという一点で押し切っている。
国宝・中空土偶については、頭部の欠損部を無視した写真で比較しているのが致命的である(p.105のカッコ内で言及しているが、これは後付けといわれても仕方ないだろう)。
一部の土偶については、体の形や模様に言及する場合もある。ただ、どの土偶のどこに注目するか、という点は竹倉氏の直感に頼っており、恣意的である。その直感を信頼できるかどうかが、という点が分かれ目となるだろう。また、土偶の体部の模様は土器の模様と共通していることが多いが、それと切り離して、「これはクリのイガである」等の解釈をしても、説得力に乏しいと言わざるを得ない。
これら具体的な比較における問題点については、例えば縄文ZINEによるnoteでもすでに詳しく指摘されており(リンク先は文末)、上記と重複する内容もある。研究者が本気で取り組めば、もっと長大な疑問点のリストを作成することも容易だろう(上で挙げた事例は筆者の作成したメモの一部である)。ただ、個々の対比が妥当か否かということよりも、その背景にある恣意的・場当たり的な比較方法が問題である。
3 植物と土偶の分布の比較
3の植物と土偶の分布の比較は、2の「イコノロジー」によってモチーフと考えた植物について自然分布や遺跡からの出土状況を調べ、それらがある場合は仮説が補強されたとみなすものである。しかしこの手順は不十分であり、竹倉氏の仮説は検証されておらず、補強もされていないと考えられる。
この仮説の「補強」作業を、竹倉氏自身が序章で行っている「統計的データ」による「検証」作業と比較してみよう。土偶が女性像であり出産に関わるという「通説」に対して、「土偶の増減と人口の増減にはある程度の正の比例的な相関がみられることが予想される」(p.50)という観点から検証を行い、否定している。
この検証作業の当否については置いておいて、土偶が植物をモチーフとしたとする仮説にも同様の検証作業を行うと、どうなるだろうか。たとえば竹倉氏は、トチノミをモチーフとしたと主張する土偶(煩雑なので「トチノミ土偶」と呼んでおく)について、土偶が作られた中期中葉にトチノミが利用されていたという考古学的事実を示し、仮説が補強されたとみなしている。
しかし、これは序章において「通説」を否定した「検証」に比べると、ずいぶん甘い。序章と同様に考えるならば、「トチノミ土偶」が作られなくなる時期には、トチノミ利用が低調にならないといけない。だが、実際にはトチノミ利用は、中期よりも後晩期の方が盛んになるのである。
また、国宝・合掌土偶や国宝・中空土偶については、クリの実をモチーフにしたと主張する(以下、「クリ土偶」とする)。これらの「クリ土偶」は縄文時代後期にそれぞれ青森県と北海道南部で作られたものであるが、これらの地域では、それ以前からクリは盛んに利用されていた。たとえば、そうしたクリ利用の証拠が非常に多く見つかっている青森県三内丸山遺跡は、前期から中期にかけての遺跡である。そして三内丸山遺跡からは土偶も二千点以上と大量に出土しているが、それらは「クリ土偶」ではないのである。
このように、竹倉氏が序章で「通説」を否定したのと同様の基準で検証すると、自身の仮説は否定されてしまう。逆に、本書で展開されている程度の議論で仮説が「補強」されるのだとすれば、「女性土偶」が作られた遺跡に女性が存在すれば(そりゃ集落ならいるでしょう)、「女性をモチーフにした」とする仮説が補強されるのだろうか。竹倉氏の議論には、このような二重基準が認められる。
型式編年からの批判
上で述べてきた議論には、土偶の型式編年にもとづく批判は含まれていない。ここでいう土偶の型式編年にもとづく批判とは、「あるタイプの土偶の変遷過程をみると、最古段階ではモチーフとされた植物に似ていない。したがって著者の主張は成立しない」というものである。
こうした議論は、考古学者、あるいは考古学愛好者の間では説得力をもっていると思われるが、実は必ずしも絶対的なものではない。あるタイプの土偶が一系統のものであり、想定される変遷過程が正しかったとしても、「変遷の途中で新たなモチーフを採用する」ことはありうるからである。例えば、木の実に全く似ておらず似せるつもりもなかった土偶が、変遷のある段階から、(縄文人が「あれ、これ木の実っぽいな」と思ったから?)木の実をモチーフとして採用するようなケースである。もちろん、大事な(?)モチーフがそんな簡単に変わっていいのか、という疑問は生じるが、理屈の上ではありうるのである。
したがって、「土偶のモチーフは何か」という問いに関して、特に相手が考古学の方法論を共有していない場合は、型式編年からのアプローチは、必ずしも有効ではないと考えられる。筆者が「2 土偶と植物の形の比較 (イコノロジー)」の節で、土偶の編年ではなく、あくまで恣意的な解釈の適用を問題としたのは、そのためである。
だが、実は竹倉氏の土偶論においても、ひとたびプロトタイプとそのモチーフを定めると、その関係を固定的にとらえている点は同じである。違うのは、考古学者が型式学的ないし層位学的に(共伴する土器との対比から)土偶の変遷の順序を決めているのに対して、竹倉氏は直感的に「プロトタイプ」を選んでいる点である。
したがって、この点については、本書も従来の考古学的な方法論と同じ弱点をもっている。あとは、型式学・層位学的な編年と、竹倉氏の直感のどちらを信じるか、ということになるだろうか。
わかること・わからないこと
前掲の日本経済新聞記事の終わり近くには、(縄文研究は)「わかりそうでわからないのがおもしろいのではないか」という筆者のコメントが掲載されている。月並みなコメントではあるが、本音でもある。
考古学にはわからないことが非常に多い。わからないのは土偶が何をモチーフにしていたかだけではない。土偶の何千倍も出土する土器の模様だって何の意味があるのかわからない。手間ひまかけて飾った土器を惜しげもなく火にかけて煤だらけにしてしまう。いろいろな形の銛や釣針を作るけれど、どんな使い分けをしていたのだろうか。道具を大事に修理しながら使うことがあると思えば、まだまだ使えそうな道具を捨ててしまうのはなぜか。朝何時に起きて夜何時に寝ていたのか。一軒の家に何人住んでいたのかも、一つの村に何軒の家があったのかも、一つの地域にどれだけの村があったのかも、そしてそれぞれの間の関係についても、確かなところはわからない。そもそもこういう風に文章にまとめられる疑問はかなりわかっている方であり、遺跡を掘ればもっとわからないことだらけである。
しかし、だからといって何も手がかりがないわけではないし、わからないから何でもありだというわけでもない(もちろん想像を広げて楽しむのは自由である)。手順を踏んで論証を積み重ねていけば、わかってくることもある。「わからなさ」を認めて、それに向き合いながら、わかることを少しずつ積み重ねていくところに、考古学のおもしろさがあるのではないだろうか。
本書は、知性のある現代人には何でもわかるはずだ、という自信に貫かれている。それは序章の「土偶の正体がわかりません、というのでは形無しというほかない(中略)それはわれわれの知の敗北を意味するであろう」(p.3)という文章に端的に表れている。考古学者が本書に感じる違和感の根底には、おそらくこの「わからなさ」に対する態度の違いがあるのではないだろうか。
ではなぜウケたのか
最後に本書がなぜ「ウケた」のかを考えてみたい。その理由はおそらく、「資料を独占して難解な用語を振りかざし、権威や定説にしがみつく旧態依然たる専門家を、門外漢が新しい発想と研究方法によって乗り越えていく」という構図を、上手く読者にアピールすることができた点にある。こうした図式は痛快に感じるものだし、現代社会のニーズに上手くマッチしていたのだろう。
そうした読者層が一般的な考古学ファン・縄文ファンよりもずっと多かったのだとすれば(本書がベストセラーになったということはおそらくそうなのだろう)、我々がこれまでに行ってきたいわゆる「教育普及活動」というものが果たして適切だったのかという点を、もう一度しっかりと考え直した方がいいのかもしれない。
付記
この文章は竹倉氏の著作『土偶を読む』に対するコメントであり、その出版後に各種媒体で展開された(と思われる)議論はカバーしていないことをお断りしておく。ネット上における主要な書評としては、養老孟司氏による好意的な書評と、縄文ZINEによる批判的な一連のnoteがある。
養老孟司氏書評
https://shobunsha.info/n/n4cae4fc16cff
縄文ZINEによるnote
https://note.com/22jomon/n/n8fd6f4a9679d
https://note.com/22jomon/n/n213f1979a479
https://note.com/22jomon/n/n12c313a766c2
なお、末筆であるが、本書を貸してくれたY市歴史博物館のH氏に感謝したい(すみません、買ってないんです・・・)。
おまけ
それでは本書で示されたさまざまな「見立て」に同意できるところが全くなかったのかといえば、実はあった。最後にそれを紹介しておこう。
竹倉氏は刺突文土偶の肩から胸にかけてみられる突帯状の表現を「腕」の一部だと述べている(p.266)。実は筆者による「土偶体操」というパフォーマンスの最後、砂沢遺跡出土の刺突文土偶では、この部分を腕で表現していたのである。

というわけで、竹倉さん、この点については賛成しますよ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
