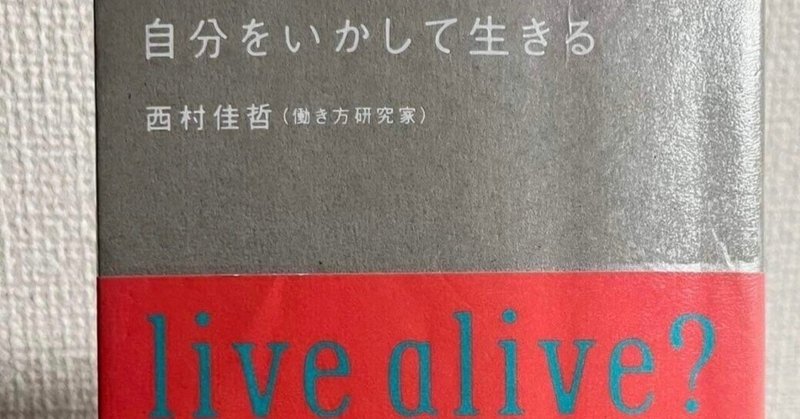
はたらく について~西村 佳哲さんの本を読んで考えたこと~
最近、西村佳哲さんの本に魅了されている、というより、西村さんの本に救われていると言った方がしっくりくる。
西村さんをご存知の方も多いとは思うが、「働き方研究家」であり、その方の本はどの本でも様々な働き方の考え方を持っている大人の事例が沢山出てくるので、読んでいて飽きない。
前提として、私は普段学生という殻に守られていることもあり、来年から社会に出るとはいえど、社会人として働いたことがないので、もちろん働くことがちゃんと分かっている訳ではない。
そんな私が、働くことについての考えをつらつらと述べるのはおこがましい気もするし、このテーマは自分が死ぬまで考えていき、そして死ぬまで答えなんてわからないテーマでもあると思う。
どのように働きたいかを考えることは、
自分がどのように生きていきたいのか、自分が暮らしていてしっくりくる、幸せになれそうな場所はどこなのか、誰と生きていきたいのか、
どんな自分が好きなのか、自然なのかを考えることでもあるかもしれない。
やはり働くということは、辛いことの方が多い(あくまでも考え方次第)。
自分を「働く専用の自分」へと素の自分を隠して仮面を被ることなのではないかと思うこともあるし、そういう側面や場面は少なからずある気がする。(すべての大人がそういう訳ではない。素をいつでもどこでもさらけ出していて、「明日死んでも大丈夫~」とか言ってる人もいる)
また、私には少々アウトローな部分があり、そのままの自分で良いとは思っていても、ごくごくたまに色々な人からの気にしなくても良いような囁きをちょっぴり気にしてしまう時があり、人の考えに一瞬左右される自分が嫌になる。
(人の意見を聞いてゆっくり自分で考えたうえで取り入れるのなら全然良いのだけど、私は即座に影響される。
まあ言い方をポジティブに変えると、いろんな意見を柔軟に取り入れることが出来る。)
「(非正規か正規か悩んでいる場面で)非正規だとボーナスがもらえないよ」
「型にはまったほうがいいよ」
「自分の意見を言うと、会社に扱いにくい人間って思われるよ」
自然体の自分でいれる場所で働きたいと思うことは、我儘な考えだという人もいるかもしれない。
でもよくよく考えてみると、結局働くのはその人の
親でも親戚でも、周りの大人でも大学の教授でも、恋人でも親友でもない、その人自身なのだから、その人にしか決めることが出来ない。
働くとか生きるとか考えてもしょうがないようなことについて考えれば考えるほど、モヤモヤが肥大するような気もする。
そんな中、働き方研究家と自分で名乗っている西村佳哲さんという人の考え方が、働くの根幹にある部分、人間としての生き方を表すのにしっくりときた。
ここでは、一番しっくりときた部分を紹介する。
人間の大仕事の一つは、世界を感じること。
そしてその中で生きている自分に気付くことにある。
「生きている」ことを感じるために生きているといったら言い過ぎだろうか。
生き生きとした・・・という言葉には「生」が二度誕生する。
御飯をたべて、動いて、呼吸してれば生きているわけというわけじゃあない。
ただ生きているような日常の中で、さらにもう一度生きる、
あるいは生まれ直す。
そういう瞬間を「生き生き」という言葉で私たちは捉える。
将来的にどこへ行くか、なにになるかはわからなくても、今この瞬間瞬間の本心に従ってゆけば、おのずといくべきところに向かうだろう。
行き先が見えていれば進めばいいし、分からなくなったときは、本心に尋ねながら歩みを進めれば、その人の本来的な力が発揮されてゆくと信じている。
本心に尋ねる-この文章を読んで思い出したことがある。
今まで何人かの大人と話していて、自分の人生に納得している、幸せと自分で言っていた大人は、自分がどうしたいのかを自分の頭で考えている。
いつ死ぬかわからない中で、とりあえず今は生きていて、その中で働くということを選択するのならば、ただ呼吸をするように働くことも出来る。
それよりも、「生きている」ことを感じるの生き方が、私は幸せだと思うし、その過程で大切にしたい人に考え方が合わない時も大いにあるとは思うが、そのように生きて働いていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
