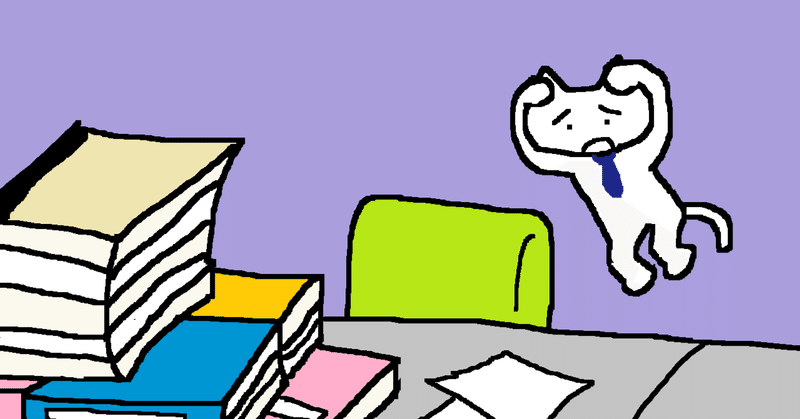
ブルシットジョブの現象学
たとえば1%にも満たないような、場合によってはどうでもいい無視できるレベルのリスクを、なぜひとは真剣に解決すべき「問題」として引き受け、熱心に仕事してしまうのか。いわゆるブルシットジョブを、人々が辛そうに喜んで引き受けるのはなぜなのか。
1%以下のリスクだったら、正直、無視してもいいものが多い。「それはまあそういうこともあるし仕方ないでしょ」というノリだ。しかし、それを(解決できないことがわかっていて)解決すべき問題としてタスク化することの意味について、少し考えてみたいわけです。
結論からいうと、1%以下のリスクや可能性を問題にするのは、そうすると「安心して仕事ができるから」だ。「安心して」というのは、その仕事がなくなる心配が低いということを意味する。
どういうことかというと、たとえば、20点だったものを70点に引き上げたり、50点だったものを80点に引き上げるような「本当に必要で中身のある仕事」というのは、それが人々や社会の役に立つものであるだけに、上手くいけばいくほど、次第にその価値が下がり、やがて不要にされてしまう類の仕事だからだ。
良い仕事は問題を解決「してしまう」ので、上手くいけばいくほど不要になる。働いている人の立場からいえば、失職だ。無職となり、路頭に迷うことになりかねない。
翻って、ここで問題にしているクソどうでもいい仕事、つまりブルシットジョブは、先ほどの例でいえば、99点を100点に引き上げようとしたり、逆に、100点のものをいかに失点させないかあれこれ頑張ったりする雰囲気の仕事である。「万が一のことがあってはいけない」とよく言われたりするが、それはつまり、10000が9999になることすら許されないというわけで、外から見たら依然として99.99%の成功率なのだが、1点でも取りこぼすと何やら厳しく責任を問われるようだ。
そういえば、だれかがラジオで言っていたが、ちょっと前にメディアが騒いでいたマイナ保険証の誤登録の件も、割合にすると0.015%ほどに過ぎず、逆にいうと99.99%の精度で正しく登録されていたことになる(驚くべき正確な仕事ぶりだ)。
20点を70点にする「良い仕事」と比べると、たしかに99点を100点に1点だけ引き上げるだけの仕事だから、数字上はめちゃくちゃ楽勝にみえる。しかし、学校のテストなんかを思い出してみればわかることだが、99点を100点に引き上げることは楽勝どころか、赤点をそこそこの合格点に引き上げるよりもいっそう難しいところがある。
だいいち、99点と100点の差なんてどうでもいいものだ。どちらが偉いとわざわざ言うほどのものではない。逆に、20点と70点の差は明確である。20点の人と70点の人の(そのときの)学力差は、どこからどう見ても明確である。だが、現実には、おそらく20点を70点に上げる方が、99点を100点に上げるよりたやすい。というか後者はそうする意味を感じにくい。99点と100点の学力差は、どこからどう見ても明確、というわけではないからだ。
にもかかわらず、労働者(サラリーマン)としては、むしろ99点だ100点だという瑣末な差異にかかずらう文脈の方がありがたい。というのも、こうした瑣末なことのための努力は、決して「解決」されないし、したがっていつまでも続けていられるからだ。
「万が一のために」「万が一そんなことがあってはいけないから」とはいっても、人間がこの地球上で生きものとして生存しているかぎり、「万が一」を防げないことはみんな最初からわかっている。「そういうことは、ごく稀にであったとしても、起きるものなんだ」と。つまり、「万が一」を防ぐのは原理的に不可能だと考えておかなければならない。そして、原理的に不可能だからこそ、それを「解決すべき問題」と力技で設定してしまうことで、仕事を絶やさないようにできる。労働の世界における「万が一文化」によって、あたかもタスクの永久機関が生成するかのようだ。
あまりに良い仕事は、かえって持続性がない。自分で自分を不要にしてしまうからだ。むしろブルシットジョブのように、どうでもいいことを問題にして、解決できないことをわかった上でその問題解決を図るという労働様式の方が、仕事としての持続可能性は高い。「やってる感」こそSDGsである。
どんな天才でも、つねに100点を取り続けることはできない。というか天才であればこそ、99点だ100点だというレベルの話ばかりしているのを嫌がるものだ。天才は「その努力だとせいぜい60点でしょ」とみんなが思うところで軽く95点とか取ったりするから天才なんだというニュアンスもありますよね。
天才が95点くらいまで引き上げてくれて、あとの5点は凡人が大勢でああでもないこうでもないと突っつき合いながら取り組んでいく。凡人は、このせせこましい領域を、しかも永遠に解決してしまわないこの瑣末な領域を手にして、仕事を失う不安から解放されるのである。ブルシットジョブの価値は、問題を解決することではなく、こうして多くの人々に「正しい居場所」を与えることにある・・かのようだ。
たった1点上げるだけなのになんでこんな忙しい?
ただし、このような仕事は、当然ながらそれ自体では面白いものではなく、うっかり無意味だと感じてしまいかねない。
「この仕事って正直要らないのでは」
「自分は何やってるんだろう」
といった具合に、逆に不安に襲われてしまうリスクを回避することも考えなければならない。
そのために、ひろく行われている習慣が「とにかく忙しくすること」なのではないだろうか。
忙しい、つまり文字通り「心を亡くした」状態であれば、仕事の意味を考える余裕がなくなるので、「ただ目の前のことに朝から晩まで一生懸命取り組んでいる姿勢」そのものが重要になる。こうなれば、自分が社会から不要にされる恐れもなく、また自分がやっていることの意味を突きつけられることもなく、要するに安心して生活ができるというわけだ。
どうでもいい仕事と忙しさは切り離せない。
たった1点上げるだけの仕事なのにこんなに忙しいのは、たった1点上げるだけの無意味な仕事の無意味さを感じなくて済むように、こんなに忙しいのである。こんなに忙しくないといけないのである。もっと忙しくてもいいくらいなのである。
ブルシットジョブは「忙しい」という気分とセットで現象する。この気分に支えられて成立するし、またその正当性を維持するためか、この気分が積極的に求められたりもする。しかし、こうした一連のおかげで、ひとは(サラリーマンとして)、瑣末であればあるほど消滅する可能性が下がるこのブルシットジョブによって、生の安定と居場所を得る。
生活の安全保障としての「99点を100点にするような仕事」。だが生活の権利ということを言うなら、ブルシットジョブ(BJ)ではなくベーシックインカム(BI)の方が適切ではないか、とも考えられる。果たして、BJとBIはどちらが優れているのか。
現代人は根源的に退屈している
ここでは、現代社会の時間感覚について少しく考察することで簡単に締めておきたい。
現代社会は、じつは「それにしても暇」な世界だと考えてみる。
つまり、表面的にはみんな忙しいように見えても、それはより正確には「忙しくしている」のであって、忙しくしないといけないのは、人間が暇と退屈に耐えられないからである。
とりわけ今日のような産業革命以後の世界では、モノやサービスが充実して生活が便利になり、寿命も伸び、時間を持て余すようになった。
時間をゆっくり自分らしく過ごす!とはいっても、「それにしても長い人生」である。寿命も期待できる上に、いろんなことが便利になって時短や省力化がなされているので、「自分の人生を生きるにしても、あまりにその人生が長い」と言わざるをえない。
そうしたなかで、BJはむしろ救い、福音なのだ。
というか、BJもBIも、ともに「時間を忘れさせてくれる事業」だと理解すべきかもしれない。BJにおいて、ひとは無駄に忙しくすることで仕事のどうでもよさをみなくて済むし、時間も勝手に過ぎてくれる。多少意識の高い人は、後者のBI的世界を選好しがちだが、そこでは、「今を生きる」がモットーであり、過去や歴史感覚を戦略的に放棄し、定住農耕民ではなく狩猟採集民や遊牧民をモデルに生活が構想される。いずれも「人生のあまりの長さ」を感じないようにしてくれる道具立てである。
もちろん、「今を生きる」ノマド的生き方のほうが、現代では「高級」な生き方だとは思う。BIもこちら側に近いが、人類は、この高級な生き方を集団として採択するにはまだまだ未熟ではなかろうか。
ノマドは、突然変異の変わり者だけで良い。
現状ではそう考えている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
