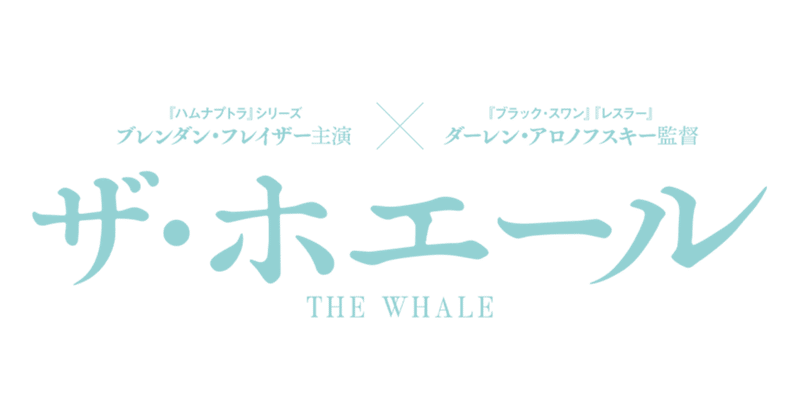
まるで高尚な文学作品のようだった。映画【ザ・ホエール】
ここに前置きを書く。
私は基本的に文学作品の映画化にはアンチで、「やめてくれ」と思うタイプだ。
高校卒業間近からその後の大学生活において、授業中であろうと常習的に文学作品を喰らっていた私にとっては、自分の中にある世界観が壊されるのがただイヤだ、というチープな認識程度でいたが、少々解像度を高め改めて書いてみると、その理由は下記のようなものであった。
「原作からインスピレーションを受けました」と謳って別物にしてくれるのならばまだしも、世間に売るために過度にドラマチックに演出し、原作にはない登場人物をさもキーマンであるかのように登場させ、盛り上げるために誰かがあっさり殺される。「もうこれ別物じゃん」と思う映像を同じタイトルで打ち出しているのを見ると、原作へのリスペクトも愛も感じられない。
私は映像をつくったことがないからおいそれと語れはしないが、文章で平面も空間も未知も…表現するのは簡単ではないのだから、表現、という次元において映像にするのも簡単ではないだろう。そこに描かれる人間たちの歓喜、激昂、逡巡、落胆、懊悩…等の「喜怒哀楽」というざっくりとした言葉では表現し得ない人間の感情や付随する仕草、機微、生々しさや、人間だけではなく取り巻く自然界の美しさ、厳しさ…云々と書き出したら切りがないのだが、文字と余白を駆使して立体的ないし多次元的に物語を織りなし、心に、魂に迫る文学。流行りの俳優やこれから売り出したい俳優を主演に立て、大事なシーンをすっ飛ばして2時間ないし3時間に凝縮した情緒もへったくれもない映画を観たときには、あの一つの作品を描くために茫漠たる時間を要したであろう作家たちの苦労に想いを馳せてしまう。これはきっと私だけではないだろう。作家ご本人が映画化された自身の作品を観たときの、世間体や大人の付き合いなどを無視した率直な本心はいかようなものかと、想像したことがあるのは私だけではないだろう。実際どうであるかは別として、少なくとも一読者、一視聴者として、「そこに敬意はあるのか?」と疑問に思うことはままある。
一方で、原作を愛してやまない監督によって忠実に再現されている映画ももちろん存在するであろうし、加えて私は「創造的誤読」は確かに存在するとも信じていて(オマージュとはまた微々たる差異を感じ得ないが)「創造的誤読」から生まれた別個の「創造」が、人々の感性を良い意味で刺激し、影響を与えるのもまた事実で、一概に文学作品を映像化すること自体が愚かなことと断じることはできないのである。
矛盾しているようであるがこれが私個人の【文学作品の映像化】に対する見解で、しかしながら結局のところ、「原作への愛と個々人の好みの問題」の一言で片付くのかもしれない。
以上は「なぜこんなにも既読の文学作品の映像化作品を観た結果、嫌悪感を憶えるのか?」に関して私個人の「 ”嫌い” という感性」に軸を置いた考察であり、つまらない映画のオープニングくらい、風に攫われて顔にかかった前髪くらい、長くうざったい前置きである。
____________________
恋人アランを亡くしたショックから、現実逃避するように過食を繰り返してきたチャーリー(ブレンダン・フレイザー)は、大学のオンライン講座で生計を立てている40代の教師。歩行器なしでは移動もままならないチャーリーは頑なに入院を拒み、アランの妹で唯一の親友でもある看護師リズ(ホン・チャウ)に頼っている。そんなある日、病状の悪化で自らの余命が幾ばくもないことを悟ったチャーリーは、離婚して以来長らく音信不通だった17歳の娘エリー(セイディー・シンク)との関係を修復しようと決意する。ところが家にやってきたエリーは、学校生活と家庭で多くのトラブルを抱え、心が荒みきっていた……。
『ハムナプトラ』シリーズなどでハリウッドのトップスターに昇りつめながらも、心身のバランスを崩して表舞台から遠ざかっていたブレンダン・フレイザーの奇跡的なカムバック劇。本作でフレイザーが演じたのは、体重272キロの孤独な中年男性。離婚後疎遠だった娘との絆を取り戻したいと願う主人公の“最期の5日間”を、ワン・シチュエーションの室内劇という様式で映し出す。
この映画に原作があるのかどうか、特段調べもしなかったので知らなかった。見終えてこの記事を書く前に調べたところによれば、2012年に初上演された舞台劇の映画化だそうだ。
偶然目にした予告編には既視感があった。はて何に対しての既視感かと思えば、主演を演じた俳優ブレンダン・フレイザーに対してだった。「ハムナプトラ」シリーズは遥か昔に観た記憶があったからとその理由はすぐにわかったが、予告編のみの予備知識だけでなぜだか惹かれるものがあった。
それは、「表舞台から長らく退いていたブレンダンの復活作品!」という謳い文句だけによるものではなかった。久しぶりに「これ、観ないといけない」と、私の内側の奥深いところから、じわじわと時間を要するでもなく、むくむくと膨らむものでもない、ピンと張られた糸の端部から一直線に瞬時に伝わる震えによって、半ば強制的に掻き立てられる類の ”何か” だった。
ハーマン・メルヴィルの代表作【白鯨】が本作の随所に用いられ、この小説が物語の中心といっても過言ではないほど、存在感を持って本作の世界観をつくっていた。
【白鯨】
1851年に発表されたアメリカの小説家ハーマン・メルヴィル(1819~1891)による長編小説。世界十大小説の一つと称される。船長のエイハブはかつて“モヴィ・ディック”という名の白いマッコウクジラに片足を奪われている。その白いクジラへの復讐心、さらに乗組員たちとの捕鯨船での壮絶な航海を描いた物語。鯨に関する当時の知識や捕鯨技術の描写などが多く綴られ、さらに旧約聖書や故事などの引用や比喩も用いられている。
はっきり言って、表面的には「暗い」「重い」と感じる人が多い作品だろうと思うが、私はというと、主人公チャーリーを演じたブレンダンのなんともいえない形容しがたい生々しい演技に、予告編で感じた「半ば強制的に掻き立てられる類の ”何か” 」を見出して、ピンと張られた糸の端部から一直線に瞬時に水滴が伝って落ちてくるように、映画のラストは静かに泣いていた。
さまざまな命題を内包した作品だった。
宗教。同性愛。精神と肉体の患い。懺悔と赦し。求める愛と与えられる愛が嚙み合わずすれ違うことの切なさ。それらがもたらす哀しみ。哀しみが生む怒り。怒りの矛先はいつも定まっているように見えて本当はいつも彷徨っていること。彷徨いに氣づけない人間の愚かさ。誰の中にも裁きがあること。善とは。悪とは。信仰とは。救いとは。……
ワン・シチュエーションの室内劇の中に登場するすべての人が、物が、これら命題を映し出し、会話が、漂う雰囲氣が、この種々の命題を否応なく感じさせた。たとえばチャーリーが残された時間をかけて関係を修復したいと願う一人娘のエリーは、ただ流し見してしまえばそれは、いつの時代にも現れるティーンエイジャー特有の反抗期の象徴かもしれないが、彼女の純粋な渇望による本来求めていた愛が与えられなかったことに対する憤りを悟られないように、己の内を隠蔽し怒りとして表出する様は、どんなにガサツな人間であっても持ち合わせ得る類の人間の繊細さであった。ネタバレを望まないので詳細に書くことは叶わないけれども、これら演者一人ひとりの演技に限らず、ワン・シチュエーションを構成するすべてのもの…部屋のしつらえや外の天氣、燻らせた煙草の煙や去っていく人影、足音…そのすべてが、誰もが自身の内に飼いならす ”白鯨” を投影し、私に突きつけていた。
特にブレンダンの演技は、誰もが自身の内に飼いならす ”白鯨との闘い” そのものであり、彼の演技は最初から最後まで文学的だった。
私は小説の余白が好きだ。読者に訴えかける間合いが好きだ。自由に想像させる優しさが好きだ。物語を読者とつくろうとする作者の愛が好きだ。
小説の余白とは、ただ単に「文字で描かないこと」とは必ずしもイコールにならない。説明を省けば雑になる描写がある。書きすぎれば読者が共に物語を生きる上での自立を奪うこともある。このバランスが取れた(と少なくとも私が感じることができる)余白が好きなのだ。私が否応なく感嘆を漏らす小説とは、余白が優れていると感じる瞬間にあるのだ。
図らずも映像を通して、ブレンダンの演技を通して、私の「好き」を知ることになってしまった。「嫌い」を軸に浅く考察していた私の文学への愛は、この映画によって異なるグラデーションを帯びたのだ。ブレンダンの演技は実に余白が絶妙な、高尚な文学作品のようだった。ブレンダン演じるチャーリーの息づかい、ため息、目配せ、送られた視線、話すときの抑揚、流れる汗ひとつ……その一挙手一投足が、チャーリーに与えられた一秒一秒が、誰もが自身の内に飼いならす ”白鯨との闘い” の過程で人間が味わう人間の生々しさ……それは救いようのない憐憫や諦観がもたらす氣怠さであったり、しかしおぞましくも失われない生への執着等々……であり、彼が最期の5日間を生きる姿は、これまでに喰らってきたあらゆる文学作品が私にそうであったように、人生に立ち向かう姿勢や価値観や生きることそのもの等々への命題を突き付け、物語り、氣づかせ、諭し、余白の中で自由に泳がせ、時に溺れさせ、そして正解のない答えを出させ、私が私を生きる血肉に変えさせた。
こんな演技を観たのは、人生で初めてだった氣がする。
賛否ある作品かもしれないし、前述したように一見すると「暗い」映画であるから、好みは分かれるであろうと思う。この映画が誘う「希望」はおそらく誰の心にもあるはずだが、得てして余白の中でこそ見出せるものかもしれない、とも思う。そういった意味でも、ブレンダンの演技はまさに畏れ慄く白鯨そのものだったと、見終えて興奮止まない私は感じているのであり、普段まったく書きたいとも思わない映画の感想なんかを、長々と指が動くのに任せて書き連ねているのである。
個人的に圧倒的にブレンダンの演技に完全にノックアウトされた私だけれど、最愛の兄を亡くし親友であるチャーリーまで失いそうになるリズを演じたホン・チャウという女優の演技がこれまた個人的には語りたいことが満載なほど好きになってしまった。
____________________
以上は「なぜこんなにも映画【ザ・ホエール】に心揺さぶられたのか?」に関して分析した結果、文学の何を愛して来たのか?に行きつき、最終的に至極単純に自分の「 ”好き” という感性」を知ったという、流れて行くエンドロールを読むでもなくただ茫然と見送る映画のエンディングくらい、誰の役にも立たないかもしれないが、この映画に関わったすべての方を賞賛したい氣持ちと感謝を込めた、しがない職業ライターの映画感想文である。
このエッセイに、チャーリーの添削がなくて良かった。「ご本人に読まれる」なんて恐れ多くてビビる。
書いておいてなんだが、その ”白鯨” に立ち向かえるほど、私はまだ勇敢ではない。
言葉の海 hana
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
