
高橋 美香子 歌集『ぶどうの杖』
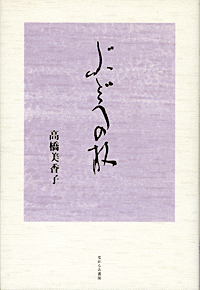
深く考え悩みつつ結論に
綾部 光芳(響)
行く度に親孝行と言われるがまことそうならホームには入れず
「施設に居る僕は終身刑です」父の言葉の刺さりて取れず
「あなたがね家の嫁ならいいのにね」患う姑はわれを見て言う
見舞うたび悲しませぬよう気遣いぬ人であることやめてゆく義母
貰いたる立派な杖をもちたれどそれにはふれぬおトボケの父
一本のぶどうの杖が支えたる父のからだは一枝でよし
歌集『ぶどうの杖』を通読し、先ず強く印象に残った歌を抄出してみた。
一首目は、ホームに預けても見舞う人の少ない現実を詠っているが、そうしたい気持ちはあってもそのように出来ないうしろめたさが背後に隠されていることに気づく。一方、預けられた側の物言いは、冗談で言っていると思うのだが、父が真実を言っているがゆえの作者の辛さが伝わってくる。
三首目と四首目は、長寿社会であるがゆえの避けられない厳しい現実を詠っており、生きるとは何かを考えさせられる歌である。
とは言え、最後の二首からは何か温もりが伝わって来る。ということは、二首目の「施設に」の歌は、父が、優しい作者を信用している発言であることがよくわかる。
肩を寄せ君と見とれる金目鯛捌く間際にいよよ朱増す
一言でへこんだ気持ちもどらざり魔法の溶けぬあなたの言葉
携帯の中に小さな君が居てリモコンとなりわれを操る
知らぬ間に我が細胞の隅々に核となりたる君の存在
こういう歌に出逢うとほっとするが、とは言え、一首目は視点を変えて、金目鯛の側から見ると言いしれぬ奥深さを感じさせるあたり、ただの歌ではないことがわかる。
二首目の、言葉によって魔法をかけられるという発想が、言葉のもつ怖ろしさを感じさせてくれる。
三首目、言葉により操られるという何気ない歌だが、この歌も言葉のもつ力を感じさせてくれる。
四首目は、細胞の隅々に、という意表をついたもの言いに思わずどきりとさせられるが、これも、無言の言葉の存在を感じさせてくれる、という発想に他ならない。
吾亦紅同じ家中に育ちしが何処まで続く争う双子
娘こに貸しし我の靴あり娘の足の形になりて玄関にあり
帰る子は何度も何度も振り返り蝶の髪留めついに消えたり
何れも子を歌った作品である。
一首目は、自らの分身が双子であるがゆえに仲がよい筈だと思っても、二人の間に争いごとが絶えな いということから、所詮、人間は生きている限り争いごとから逃れることはできない、という普遍的なテーマを提示しているものと酌み取ってよさそうである。
二首目の着眼点も面白い。つまるところ、分身であっても、他人にほかならないという物言いに違い無い。
三首目は、詩情豊かな作品である。
高橋さんの作品は、一読して、分かりやすいもの言いをしているが、一首ずつ丁寧に読んでゆくと、それぞれがとても奥が深い作品である、ということに気づく。つまり、対象をよく見て、より深く考え、悩みつつ、最善の結論に到達する、という生き方をなさっているということに、深く感じ入るのである。
家族の時間
春日 いづみ(水甕)
象牙色に葡萄色を配した布地の表紙に金文字の表題と著者名、瀟洒な装丁である。題字は佐田毅氏のもの。さすがに松井如流の弟子、文字が一集の雰囲気を伝えている。ページを繰る手が、目が扉絵に留まった。パステル画に描かれているのは、ひまわりと霞草だろうか、花弁や小花ひとつひとつが光を纏い、生き生きと品位をもって描かれている。見ていると花の精の微笑が感じられ「ようこそ」と誘われている気がした。このような絵を描かれる作者への関心が一気に高まってくる。
五十代からの作品が収められているという。その自立、義母の看取りと死、父の老いなど結婚し築いてきた家庭の膨らみが少しずつ形を変えてゆく時期でもある。
コスモスに薄もそれぞれ風に揺れ振り向きもせず娘は行きにけり
テーブルを囲む夕餉に一つ空く椅子を誰も口にすることなく
双子のお嬢さんの一人が自立し家を出る。双子なので何事も一緒にを心掛けていただけに、一人が出て行ってしまうのは何とも寂しい。コスモスや薄の揺れはお嬢さんの健やかな成長の姿であり、作者のエールを送る手の振りでもあろう。揺れ方の違いに子等の個性も感じられて「それぞれ」の一語が効果的に使われている。家族が揃い囲んでいたテーブル、家を出たお嬢さんの空いた椅子にどうしても心が向く欠落感、家族のだれもが同じ気持ちなのだが、それを口にすることはない。「口にすることなく」との連用形での終わり 方にその心情が滲む。
「施設に居る僕は終身刑です」父の言葉の刺さりて取れず
用事でき電話で行けぬ訳言えばだんだん小さくなる父の声
三が日共に過ごしし老父はリュックを背負い施設に帰る
「あと二年生きさせて貰います」ピシッと囲碁打つ九十一歳の父
一本のぶどうの杖が支えたる父のからだは一枝でよし
「ここからは一人で帰れる」と言いたまう消ゆるまで聞く父の杖の音
一集にはホームで暮らす父を詠んだ作品が多い。一、四、六首目のように父の言葉がそのまま会話体で用いられることで、父の人となりや老いてゆく侘しさを伝えている。「終身刑」とは鋭い言葉だ。ホームを出る時は死の時であり、希望の見えない日々を透徹した眼差しで客観的に見据えている。理性的な父故に作者の心は苛まれるのである。三首目の正月を共にした父がホームに帰ってゆく姿、背中のリュックの揺れが父の心みたいだ。また別の日には杖の音が聞こえなくなるまで見送っている。父が角を曲がってもなお立ち尽す作者の姿が浮かぶ。いずれも老いた父と離れて暮らす切ない思いや心配が感じられる。母を早く亡くした作者にとって、父との日々は濃密であったに違いない。
どの花も我の手に触れ芽吹き出すさみどり色の柔らかな春
片手にてギュッとレモンを搾る時わが常識を一緒につぶす
こうした家族への細やかな情愛や眼差しの行き届いた作品を支えているのは作者の繊細かつしなやかな感覚である。「柔らかな春」を生むマジシャンのような手は紛れもなく豊かな感性を持つ、向日性の作者のもの。また「常識」に捉われまいとの自在さも魅力だ。
家族への眼差し
栗木 京子(塔)
両親や義母、そして夫や二人の娘。家族を見つめるときの作者の歌には、やさしさと眩しさと、そして切なさが感じられる。
待ち合わせの場所を間違えウロウロと赤き帽子の父を見つけぬ
「長生きしてごめんなさい」と胃の検査終えたる父はココアを啜る
一本のぶどうの杖が支えたる父のからだは一枝でよし
歌集の序で佐田毅氏が述べているように本歌集には心に残る父の歌が多い。一首目と二首目からは老いてゆくことの寂しさが伝わってくる。だが「赤き帽子」や「ココアを啜る」の明るさが点景となって歌に体温を与えており、読後にふんわりとしたものが残る。
三首目は「父のからだは一枝でよし」のきっぱりとした語調に、読者も励まされる。
一方、母や義母を詠んだ歌には、もう少しストレートな心情がうかがえる。
母思えば涙流れぬ三秒で十三回忌過ぎたる今も
遠き日に我をどなりしその口にゼリーひとさじ義母に与えぬ
一首目は「涙流れぬたちまちに」でなく「涙流れぬ三秒で」にリアリティがある。急逝した母の記憶は今も生々しいままに在るのであろう。
二首目は義母の「その口」に焦点を絞って表したことで心情に深みが出た。
また、夫や娘の歌は場面の具体性とほのかなユーモアによって魅力が生まれている。
陽の匂い残れる君のシャツ畳む今日の諍い引き出しに入る
迷いつつ二つ買いたるクロワッサン夫も買い来て四つになりぬ
ハッとする冷たき両手で目隠しを吾にせし児をふと思いたり
娘に貸しし我の靴あり娘の足の形になりて玄関にあり
前の二首は夫の歌。諍いはしてもちゃんと夫のシャツを陽に干し、畳んで引き出しに入れる。そのうちに苛立ちは作者から離れていったのだ。クロワッサンの歌も以心伝心と呼びたくなるような仲睦ましさが想像できる。
後の二首は娘の歌だが、
三首目は「冷たき両手」が良いと思う。一般的には目隠しする児の手の柔らかさや温かさを詠みたくなるところだが、作者は事実に即して率直に描写している。児は外から帰ってきてすぐに母親に触れに来たのではなかろうか。「冷たき両手」に、逆に生き生きとした児の動きが見える。
四首目も靴という何気ない物を対象にしながら、「娘の足の形になりて」に新鮮な発見が輝いている。結句の収め方も周到である。
さらに、本歌集には家族だけでなく、伯父や友人、また旅先で出会った人々なども登場し、それぞれに心を込めて詠まれている。
暑き日に帽子を被らぬ伯父の肌大ヤケド負い伏して動かず
冬の海切り取り届く写メールに写らぬ友の病状いかに
がっちりとホテルのゲート施錠され遊ぶ異国人みなメタボなる
犬・山羊・人みなゴチャ混ぜに生きる町を除菌抗菌の日本人行く
広島で被爆死した伯父を悼む一首目からは「せめて真夏でなかったなら」という嘆きの声が聞こえる。
また三首目と四首目はフィリピンのセブ島での歌。丁寧な嘱目がおのずから文明批評につながっているところに作者の歌境の深化を見て、頼もしく感じた。
愛を支えに
関根 和美(地中海)
葡萄の色を偲ばす美しい装丁の紫は、絵を描く父上のお好きな色とか。タイトルの書体と同様、上品で趣のある設えである。実や葉や蔓ばかり浮かぶ葡萄棚だが、そこにはたおやかに見えて実はしっかりとした木があり、すべてを支えている。「わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です」(ヨハネ15・5)を思い起こしつつ家族、特に父娘の愛の象徴としての『ぶどうの杖』を辿ってみたい。
「施設に居る僕は終身刑です」父の言葉の刺さりて取れず
兄とともに父愛用の杖選ぶあれこれ迷いほどよき疲れ
若き日の父の憧れチャップリンの杖の姿をまねて歩きぬ
一本のぶどうの杖が支えたる父のからだは一枝でよし
九二歳になる父を見守る巻末の作品群は特に印象深い。兄も加わり父の杖を選ぶ風景の何と愛に富んでいることか。お洒落でモダンな父親像も浮かぶ。入所を「終身刑」と宣い気に入らない杖には知らんぷり。ぶどうの杖に出会って悦び、おどけてチャップリンの真似とは見事である。「一本の」「一枝で」の呼応の美しい一首は一巻の象徴であろう。
「団欒で食べるご飯は美味しいね」そう言った母次の朝倒る
亡き母は朗らかなるを名に持ちぬ遺影も明るき笑顔の「郎子」
山の端に落つる夕日は我を包む亡母の命の色に似ており
遠き日に我をどなりしその口にゼリーひとさじ義母に与えぬ
今ならばもっと仲良く暮らせたと初空に浮かぶ亡き姑の顔
動きや実体を伴う父と違い、若くして世を去った母の姿は追憶の声や遺影に偲ぶだけだが、時には浄土の光となって著者を包んでくれる。倒れる前夜、家族の団欒を心から慈しんだ母の言葉はどれ程著者のその後を支えたことだろう。また別れとはこのように突然来るという現実に、改めてはっとさせられる。
続く二人は同一人なのか紛らわしいが義母と姑を詠んだ作品の一首目。上句の生なまの表現を受けて下句の現実はあまりに切ない。柔らかいゼリーがやっと一口、この私の手から運ばれるものを今はただ大人しく受け入れている。取り返しのつかぬのも歳月だが、歳月を経て初めて受け入れられる賜物もある。
知らぬ間にわが細胞の隅々に核となりたる君の存在
満開の花のトンネルに消えゆきぬ何処へ行きしや子の乗る車
丘の上の海軍塚のカラスウリ命あかあかと弾けだしたり
犬・山羊・人みなゴチャ混ぜに生きる町を除菌抗菌の日本人行く
ギックリとまた突然に痛み来る身体じゆうが腰になる日々
若き日に歌と出会いこんな相聞歌を沢山詠んで欲しかったと思わせる一首目。一方で溢れる想いを込めようとする分、殊に夫の歌などに見る饒舌が惜しまれる。言葉の選択が必要かも知れない。巻頭歌の花びらと観音像に先ず絵筆を持つ人を感じたが、この二首目も美しい構図と余韻に子の独立を描く。折々の 歴史詠は故郷に繋がる海や船、軍人などの素材のものに惹かれたが更なる大作を望めそうだ。また独自な視線と感覚に貫かれた海外詠 や日常詠も次歌集の武器となることだろう。
父の夢に生かされて
歌集『ぶどうの杖』が孕む世界
千々和 久幸(香蘭)
わたしは今、昭和24年(1949年)に公開された小津安二郎の『晩春』の一シーンを思い出している。それは鰥夫の父が娘と旅先 で枕を並べて眠るシーンである。今日でもあの名高いシーンは、娘が父に対して抱くエレクトラ・コンプレックス(女の子が父親を慕い、母親に反感を持つ気持)ではないかなどと、父と娘の間に横たわる見えない性的なイメージ(究極は父娘相姦のイメージ)を巡って、議論が絶えない。
わたしもあのシーンでは父娘の間にただならぬ気配を感じ、思わず背筋がゾクリとした記憶がある。その心理的な体験をいま的確に言い当てることは出来ないが、このたび高橋美香子さんの歌集『ぶどうの杖』に詠まれた父の一連にまずそのことを感じたのだった。
1, 三が日共に過ごして帰る父張り切っていた父振り向かず
2, 金盃の月に寄り添うひとつ星光を放つ父の面影
3, もの憂くも見つむる先にいつも在る風と過ぎるやひとり居の父
4, 一本のぶどうの杖が支えたる父のからだは一枝でよし
父を詠んだ歌の中で陰影の濃い作品を挙げてみた。
1番目の歌、眼目は結句の父の不機嫌とも見える表情にある。振り向かなかった理由を言わないところに、歌としての膨らみが出た。
2番目の歌、作者は穏やかな月にではなく、異彩を放つ星にこそ父を認めたのだっ た。
3番目の歌、父もまたいつかは風に攫われ風になって、わが手を離れると言い聞かせている。
4番目の歌、もう壮年の父ではない、衰えた父を凝視する目が痛々しい。
こう見てくるとこれらの作品には、エレクトラ・コンプレックスの危うさより、堅実な娘としての父恋いの気持ちが横溢している。 危うさと言えば、むしろ夫との関係の方により微妙なこころ揺らぎが見てとれる。
5, 知らぬ間に我が細胞の隅々に核となりたる君の存在
6, 遠き日に娘等弾きしピアノ曲ポロンポロンと夫が弾きおる
7, あなたのみの私の心を組み立てるジグソーパズルの最後のピース
8, ゴンドラに揺れつつ君にこっそりと甘き言葉を吐いてみようか
これらの作品のうち6番目の歌を除けば、それぞれ「君」「あなた」「君」は、夫と読むよりボーイフレンドか恋人と読んだ方がイメー ジが広がり、哀切さが増そう。
5番目の歌、「細胞の核」とは放胆によくぞ言ったものだ。
6番目の歌、夫の背に漂う孤独感が胸を打つ。
7番目の歌、男女の愛は どこかゲームに似てもいる。8番目の歌、照れ隠しの恋ごころはここに極まる、か。
最後にこの作者の今後を占う作品を挙げ、その詩才のさらなる成熟を期待したい。
9, コスモスに薄もそれぞれ風に揺れ振り向きもせず娘は行きにけり
10, マンションの自動ドアよりいっぱいの春光曳きて子の帰り来る
11, ホワホワの黒い毛付きのブーツ履き枯葉を踏めば江東区もパリ
9、10番目の歌、成長した娘を眩しく見詰める母の気持の良く出た歌、11番目の歌、歌集の随所に散見する、こんな軽妙な一面にも作者の得がたい資質を感ずる。
このように作者は父の夢に生かされ、父の夢の尖端に生きて屈託がない。
批評特集―覇王樹2016年3月号転載
ー 覇王樹公式サイトへ ー
