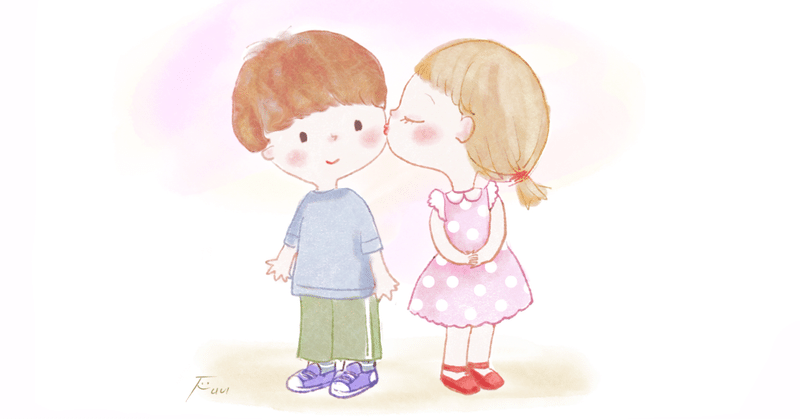
「今も生きる私の初恋」
みなさんはご自分の初恋を覚えているだろうか。
私の初恋は小学校6年生の時だった。今までにも父の同僚や、兄の同級生に恋心を抱くことはあった。しかしこの小学校6年生の時の恋愛は「あこがれ」ではなく、自分の全てを捧げてもいいほどに好きだった。朝から晩まで彼のことを考え、彼と話をする女子に嫉妬をして不安になり。全てが彼を中心にまわっていた。
彼はRくんといい、私が小学6年生の時に一つ下の学年に編入してきた転校生だった。
私が暮らしていた地域はコンビニも信号もないような村で、市内から転入してきたRくんは随分とあか抜けて見えた。
Rくんは小柄でお調子者で周囲をよく笑わせ、その一方で時々、どこか誰も信じていないような暗い目をするような男の子だった。後から知ったのだが、転校も家庭の事情があったとのことで、それも関係していたのかもしれない。
Rくんは卓球が上手で、彼が来てから小学校では卓球ブームが起き、みんながこぞって卓球をするようになった。彼はまたたく間に私たちの小学校の人気者になった。
小さな学校だったこともあり、私とRくんは自然と親しく話をするようになっていった。毎日追いかけっこをしてふざけ合って。休日は神社に集まって、自動販売機でジュースを買って大人の気分を味わいながら何時間も話をした。
林間学校では狭いテントの中で遅くまで話をし、いつもより近い距離感にドキドキしたのを覚えている。
あの頃、私たちはお互いの好きな人を当てるゲームをしていた。
一日中「誰?」「誰々くん!」「本当?」「うそー」のようなやり取りを繰り返していた。
ある日の放課後、私は一世一代の勇気を出して彼の下駄箱に「R」と書いたメモを残し、逃げるように走って帰った。もう大丈夫だろうと思って足をゆるめた時、
「おーーーーーい!」
と叫びながら走って追いかけてくるRくんの姿があった。逃げようと思ったが、
「待てって!」
というRくんに観念し、私は足を止めた。
R「これ、本当?」
私「……」
R「なあ、本当なん?」
限界だった。私は「うそ! 明日本当の人言う!」と言って逃げ帰った。心臓が飛び跳ねていたが、自分の心臓から逃げる場所はなかった。
その後どうなったのかは覚えていない。何もなかったということは、私は言わなかったのだろうと思う。
私たちの日課は追いかけっこだった。
走って逃げて追いかけて、捕まえて叩く。キスをしたり抱きしめたりという方法を知らない子どもにとって、それは最大のスキンシップだった。
卒業式の日、私たちは最後の追いかけっこをした。出会った頃は私が勝つことが多かった追いかけっこだったが、1年が経ち男女の差が出てきて、私は彼に追いつくことが難しくなっていた。最後に私はどうにか追いつくことができたが、今思えば手加減してもらい追いついたのではないかと思う。
最後に捕まえたRくんの体温や、伸びるセーターの触感、叩いたときの笑顔を昨日の様に覚えている。
追いかけっこが終わって、Rくんは私の親の車まで送ってくれた。
珍しく始終無言だった私たちは、結局言葉を交わすことなく別れた。
中学校に入るとお互いの世界も広がり、私たちは疎遠になっていった。
挙げるともっともっとエピソードはあるのだが、これが私の淡い初恋の話だ。
もう少し器用だったら実らせることができたのかもしれないが、初恋を実らすには小学生の自分は不器用すぎた。
伝えたかったけど、伝えなかった言葉がある。
生きる時間が長くなるにつれ、様々な自分を過去に残してくる。
悔しかった自分、悲しかった自分、嬉しかった自分……
色々な自分が集まって「私」ができている。
色々な自分と一緒に生きていくこと。
それが、大人になるということかもしれない。
そして恋はいつまで経っても慣れない。
怖くなったり自信がなかったり。嫉妬したり嫉妬させたくなったり。
普段はなりを潜めている私の中の大事な一部が主張し、無視できない存在になっていく。
どうして人はこんなにも面倒なことをするんだろうと思うこともあるが、せっかくこうして人間として生まれたものだし、たまには頭で理解できないことがあってもいいかなとも思ったりする。
恋は何億通りもある。正解はない。そして毎回が不器用な初恋である。
この先誰といたとしても、不器用な初恋を続けて行きたいと思う。
Rくん、結婚おめでとう。
≪終わり≫
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
