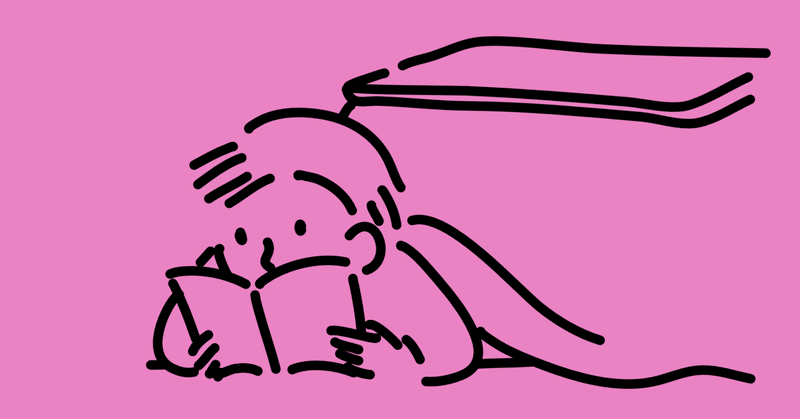
「怖い本を読んでいる手」怪談ウエイトレス
「怖い本が苦手なんですよ」
メニューを見ながらそのお客さんは言った。その表情が、さして怖そうでもなくのんびりとしていた。年のころ三十後半というところの女の人で短い髪に、やたらぼわぼわした服を着ている。
「だのに、怖い話を聞くのは好きなんです。人づてにこの店の話を聞いて来たんです」
「そうでしたか」
野木が一人で喫茶まりもの店番をしていると、決まってこんな客が現れる。そして、やたら甘いものを注文して、少し怖かったり少し奇妙な話をしていくのだ。でもなんとなく、この人は違う気がした。コーヒーを頼まれたらどうしよう。まあいいか。
「 オレンジジュースあります?」
「ありますよ」
甘くも苦くもなく、まんなかか。野木は、オレンジをふたつ冷蔵庫から取り出し、絞り器にはさんで、しぼって、冷やしたグラスにそそぐ。
グラスを手元に引き寄せると、お客さんがじっと中を見つめてから顔を上げたので、野木はさっきの話をぶり返してみた。
「怖い本がだめというのは、怖いのが苦手とは違うんですか?」
「苦手じゃないんです。こう見えて、百物語にも参加したことがあるし、お化け屋敷も怖い映画も好きなんですよ。でも、怖い話を読むことはできなくて。実話でも、小説でも」
「活字だとかえって想像力がかきたてられてしまうとか?」
「いえ、だめなのは文字や言葉じゃないんです」
お客は、オレンジジュースをすすって、あまいというのかすっぱいというのかなんともいえない顔をした。
「問題は、手なんです」
「手、ですか?」
野木が眼の前にやたら甲がひろくて指が短い自分の手を広げていると、お客がそれより私おなかがすきましたというので、メニューにはないけれどマスターがいつも冷蔵庫に常備している麺と野菜で焼きうどんを作った。
「それで、手がどうしました?」
うどんをすする客に野木は話の続きを催促をした。やたら食べるのが遅いのだ。最後の一本をすすりきると水を一口飲んでから、話は再開された。
「あるとき怖い本を両手に持って開いて、文字を追いかけていたんですよ。その本はやけにぶあつくて、すごく怖くていっそのこと読むのをやめようかと思っていたんだけども、続きが気になるからちょいちょい飛ばしながら読んでいたわけ。両手で抑えていたんだけど、時折何かの拍子にぱたん、と閉じちゃう。あれ、何ページだっけとなってあわててページをめくって開いてを繰り返していたら、自分の手がやけに目に入るでしょう。ひどくかさついていて。そのうち本を読んでいるんだか手を見てるんだかって感じになって、ふと気がついた。なんか手が違うって」
「違う?」
「手が、少しだけほんの少しだけ大きかったの。右手の甲のところにあるほくろとか、静脈のうきぐあいなんかはまったく同じなんだけど大きさが違う。輪郭にして、数ミリくらい。手って、自分の体の中でいちばんよく見るところでしょ。顔は鏡で見るけど、直にみるのは手で。炊事しているときもずっと手を見てる。意識はしていないけれども、そこは自分の手だし様子が違えばすぐわかる。なんか大きくないか?って、本を閉じたらまたしてもばたんって音がして、明るい窓のそばによって見てみたらなんと…」
「なんと?」
「いつもの手だった。大きさに間違いはなし」
「なるほど…」
正直、思っていたような話ではなかったと思いながらも、野木はほう、という顔をした。
「あー、私の見間違えだと思ってるでしょ」
「いやいやそんなことはないですよ。で、その後はどうしました?」
「その本は図書館で借りていたからすぐに返して、まったく違うタイプの本を借りたのね。子供向けの本。家に戻ってすぐに読んだけど、手はなんともなし。やっぱり見間違えだと思って、今度は買ったばかりの本を開いてみたら」
「ら?」
すぐには答えてくれない。
「その本は、実際に起きたことをもとにした怖い話だったんだけど、しばらくはなんともなかったの。紅茶をすすりながら、ソファに座って読んでいたらなんだか妙な気がして、ページをおさえていた手を見てみたら」
「またですか?」
「そ、また。文庫本だったしページ数も長くはなかった。文章も私の好みだった。だから今度は気分のせいじゃないと思って、しみじみ手を見てみたら…」
答えはわかっていたが、目を大きく見開いて尋ねた。
「元通りですか?」
「そう」
「つまり怖い本を読んでいる間だけそうなると。でも、それって気分的なものじゃないですか。怖い話だし」
「でも、怖い話を聞いてるときには変わらないんだけど」
「あ、そうですよね」
「人間って、体を動かす前に本当は頭が予測しているっていうじゃないですか。もしかすると、怖い話のときだけ頭よりも手が存在感を増すっていうか、先に動き出すかんじなのかな。でも、それが怖い本のときだけってのいうのはなんなのかと思って」
「ゲシュタルト崩壊というやつじゃないですかね。手は、毎日眺めていますから」
お客さんは肘をついてまだ悩んでいるようなので、野木は何気なく思いついたことを口にした。
「デジタルならどうなりますかね」
「デジタル?ああ、ネットで見るやつ」
「無料のがありますから。著作権の切れた話が載ってるんですよ」
野木は自分のスマホを操作して、岡村綺堂の書いた鰻の話を見せてやった。古い話だがシンプルに怖い。タイトルを見るとお客さんは、ああこれ読んだことある、怖いけど洒落た文章だよねと言いながら、手をテーブルの下におろして読み始めた。
しばらくして、野木はおかしなことに気がついた。お客さんの目が、上から下にいったまま上に戻らないのだ。一点にくぎ付けになっている。よほど怖い場面につきあたったのかと画面をのぞくと、話はまだ佳境ではない。テーブルの片づけをよそおってカウンターから出ると、野木はお客さんの手を探しに行った。ぶらんとわきにたらしてある。もちろん、ふつうの手だ。
「お客さん、だいじょうぶですか」
声をかけようとすると、急に顔を上げて、「こわかったー」という。
「え、もう読み終えたんですか?」
「久しぶりに怖い話を文字で読んだわ」
「でもまだ、真ん中ですよ?」
「読み終わったよ?」
「じゃあ、どんなお話か教えてくださいよ」
野木が言うとお客さんは、つらつらと要領よくあらすじを語った。聞いているだけで怖くなる。
「さっき、この話は知っていると言いましたよね」
「ざっくりね。でも、こまかなところは忘れてた」
「手はどうなりました」
「ああ、手。忘れてた」
お客さんは笑いながら自分の手を見て、なんともないやと言った。まあ、読み終わったのだからもう遅いのだがなんだか怪しい。大体、怖い話を読んでいると手が少しだけ大きくなるなんて、はったりにしても怪談にしてもあんまり微妙過ぎやしないか。
手の大きさなんて、よほど親しい人間にしかわからないだろうから、そうだと言われればうなづくしかない。これが怖い話なら、瞬間的に指が一本増えているとか、手の甲に見知らぬ女の顔が浮かび上がったりと、もっと象徴的なできごとが起こるだろう。
試しにほかの話も読んでくださいよと言おうとして、 少し考えて、マスターが書いたものを読んでもらうことにした。近所のつぶれかけた文房具屋から仕入れた原稿用紙にマスターが何かを書いていたのは知っていたが、ついこの前ちょっと読んでよと言われたものだ。
なんで原稿用紙と聞くと、そっちのほうが感じがでるからとか。書き損じが多くて、店の原稿用紙が尽きておやじに仕入れを頼むほどだったが、都合四十枚、なんとか書き上げたという。どんな話ですか。読めばわかるじゃん。いちおう、先にざっくり聞いておきたいんですよ。えー、まあ怪談。怖いんですか。怖いかどうかは読んだひと次第。なんですかその読者頼みは。まあいつか読みますからそこに入れておいてください。で、暇なときに読んだ。
それを差し出した。
「今までは本だったわけですよね。これで試してみたらどうです」
「原稿用紙とか懐かしいな」
「さっきは手を下に垂らして読んでいたでしょう。それだと私には変化がわかりませんから、ちゃんと出しておいてください」
まるで試験監督のようなことを言ってしまったが、お客さんは素直にうなづくと、両手を原稿用紙に沿えるようにした。
「では、読みます」
上から下、下から上と目玉が上下する。いかんいかん、目にとらわれている場合ではないと視線を手に移す。見る限り異変はないと思っていたら、お客さんの目がぴたり、と止まった。そっと覗いてみたが、なんでもない場面だ。主人公とその恋人が公園を歩いて雨に降られる。そこから怪異がやってくるのだが、まだ何も起きていないし日も暮れていない。
このあと雨が降ってきて二人は木の下に駆け込むのだが、お客さんがあんまり一点を凝視しているので、だんだんそこに何かがあるんじゃないかという気がしてきた。
そのうちに、お客さん自身は動かないんだけれども手がすこしずつ動きだした。原稿用紙から離れてカウンターのうえを滑って、すうっと持ち上がったと思ったら、ぱっと目の前に細い白い指が広げられた。
野木は思わず、のけぞってしまった。別に何かされたわけじゃない。ただの手だ。でも動けない。その手はしばらく目の前で静止してから、ふっと、もとの位置に音もなくおさまった。そして、
「読み終わった」
とお客さんが言った。
「どうでした」
「今回はなんにも起こらなかった」
そう言って、自分の両手をまじまじ見ている。野木は物語のほうはどうでした、とは終いまで聞けなかった。そんなに怖くなかったかと、お客さんの帰ったあとで読み返してみると、果たしてそれはまったく違うお話になっていたのだった。
あれからマスターはまた、文具店に原稿用紙を買いに行ったようだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
