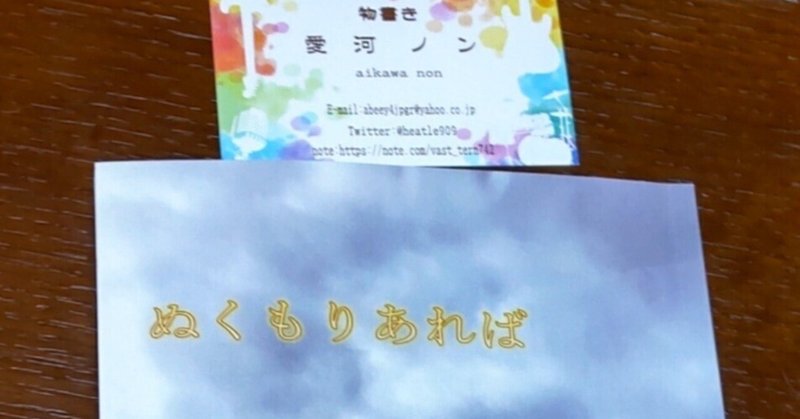
『ぬくもりあれば』感想
モラトリアムだったあの頃
モラトリアム――人生の猶予期間。
一般的に大学時代をこのように表現することが多いですね。
といっても私が大学生だったのはもう二十年ほど前なので、現在は価値観が変化しているのかもしれませんが、受験戦争から離脱し社会に揉まれるまでの、自由でお気楽な時期といえるでしょう。
もちろん、熱心に勉学や研究に励む大学生、将来に向けて自己研鑽を積む大学生も多数いらっしゃるでしょう。が、すくなくとも我々の時代は、大学生(特に文系)とは「遊んでいる人」というイメージが横行していたことも否めません。レポートの提出やらアルバイトやら忙しくはありますが、いっぽうで、やれサークル仲間との飲み会だの、やれ合コンだの、華やかで賑やかな集まりが一気に増えることでしょう。
……などと説明していますが、私はそんなパリピ的な集会には一切縁のない学生でした。一人で図書館にいたり、家に引きこもっているのが好きな人種であったため、具体的には漫画を描いたり小説を書いたり、ホームページを開設して拙作を載せたりして、自分の世界に浸っていました。…いや、文芸部と漫研を兼部していたため、ありがたいことに定期的なお茶会や飲み会はありましたが…あっ、文芸部の部室で毎日ダベったりとか、…あっ、漫研の部長になって飲み会の幹事したりとか、…したけど基本は一人で創作活動をせっせとね、こう、何か形にしようとね(執筆がんばってましたアピールをしたい人)…
まあ、そこで出版社に目をかけていただけたら違う人生が待っていたのでしょうが、特別な才能も努力も運も持ちあわせていなかったので、就職したら社畜コースというよくある船に乗ってしまいましたが(それはそれで受け入れているので、今さらやり直したい欲もありませんが笑)
なんにしろ、大学時代は人生の猶予期間として、好きなことをできた時期でもあります。制約はあれど、勉強漬けの小中高校生時代と比較しても、圧倒的に自由でした。
同時に、将来について考えず(考えなければならないのに先延ばしにして)、目の前の楽しいこと、目の前の悩みごと、目の前のレポートに対処しているだけの日々でした。
要するに、高校生までは大人に課された問題をこなしていた生活だったため、自分を律して自立するといった修行を積んでこなかった子どものまま、ある程度の自由を手に入れた状態だったともいえます。自己管理できない自由は堕落につながりやすい。今思い返すと、馬鹿だったなあと後悔も多いですが、まあ当時は当時で必死だったわけですけれどもね。
そんな当時の自分を回顧しつつ拝読した作品、『ぬくもりあれば』について、語っていこうと思います。
あらすじ――孤独な大学生が家出少女と……
『ぬくもりあれば』
著者:愛河ノン様
(以下、文学フリマ京都のWebカタログより。著者による紹介文)
モラトリアムを生きる孤独な大学生の主人公が、河川敷で出会った家出少女を部屋に泊まらせたのを機に、周りの学生らに翻弄されながら退廃的になっていく長編小説。
第49回文藝賞一次選考通過作。

いやあ、大学生が少女を拾っちゃいますよ。それだけでなんだか、禁断の関係を妄想しませんか…… 春谷さん、いったい何を想像しているんだい。
いやいや、ここで訂正を――「拾う」というのは語弊がありますね。本文でも「拾う」などといった表現はありませんし、主人公も拾ったつもりは一切ないまま、気がつけば少女との生活が始まっていたわけです。
まあでも、十八、九の大学生が、中学生を一人暮らしの自宅に泊まらせてお世話をする。こういう、はたから見れば未成年誘拐事件になりかねない「拾っちゃいました」ストーリーが、個人的に好みであります!w
『ぬくもりあれば』感想
まず、紹介文にもあるように、主人公が退廃的になっていく物語です。
愛河さんの作品は多数読ませていただきましたが、一見すると善良な性格の主人公が堕ちていく様を描くのが上手い。関西弁をまじえた独特のユーモアと毒を含む文体で、誰の心にもひそむ嫌な部分を率直に心の声としてさらす反面、主人公の行動はまわりに流されやすく、結果として犯罪に加担しがち――人間が堕落していく様子を、わかりやすく、読みやすく、おもしろおかしく表現されている作品が多いです。
本作も例に漏れずではありますが、こちらの主人公は関西人ではありません。関東出身で、大学生になって関西で一人暮らしを始める、という設定。なので、まわりの人々が関西弁。この関西弁のやりとりがテンポよく、何の違和感もないのが、関西人としては嬉しいですね。
あまりネタバレするつもりはありませんが、主人公はモラトリアムな大学生、家出少女は受験生です。ともに、将来を先延ばししてはいけないけれど考えたくない身分。主人公のまわりは大学一年生ですから、まだ就活もしていないわけで、だいたいが「今が楽しければいい」的な態度。さて君たち、将来どうしますかと冷静に分析してみるものの、結局は目の前の悩みに翻弄される主人公。
なんとも初々しい閉塞感にほほえましくなるけれど、本人にとっては切実なんだよなあってことも痛いほどわかる。
大人になるということは、そういう閉塞感と折り合いをつけていくことだよ、なんて思ったり。そんな私も大人になれているのか、よくわかりませんけども(ただの中年おばさんだよ……w)。
あと、男女のすれ違いあるあるも、わりと共感して読みました。主人公の青年が、家出少女に対する自分の態度をキモイキモイと自己嫌悪する場面があるんですが、女の私としてもキモかったです(笑)(褒めてる)。男の人がよかれと思ってすることが女の側からすると「キモいな」と冷めた目で見てしまうことって、たぶん多くの人が経験していると思うんだけど、なんとも上手い具合にそれが描かれていました。
でも自分でキモイとわかって自己嫌悪している主人公には共感したし好感も持てたし、人間臭くて良かったです。
私としては、愛河さんの作品の中でも本作が最も味わい深く印象に残っているのですが、ラストシーンの雰囲気が余韻たっぷりでなんともいえないです。せつない、泣ける、とかそういうのではないんですが(衝撃的、放心状態、というのでもない)ほんとにただ「なんともいえない」、まさにモラトリアム。
「希望」とも「絶望」とも捉えられるラストシーンで、主人公の心境としては、「虚無」に近いのかもしれない。なんともいえないけど、あえて言葉を選ぶなら「深い」。
以上が私の感想です。
読む人によって千差万別な感想が出てきそうなので、他の読者さんの感想も聴いてみたいです。
#文学フリマで買った本
順次感想を載せていきます
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
