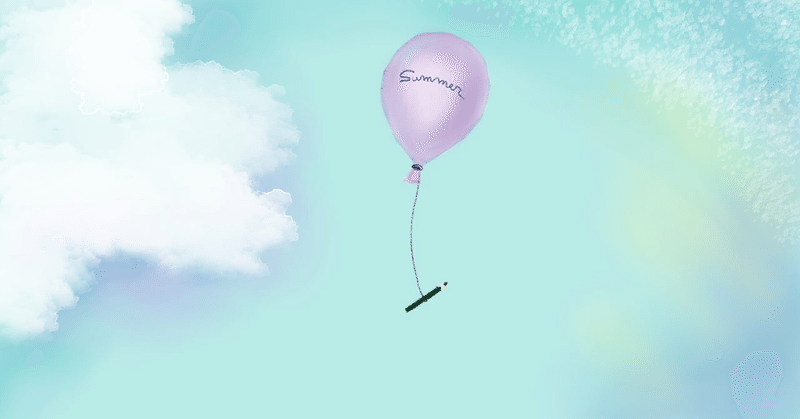
『バルーン』
【前書き】
皆さん、こんにちは。早河遼です。
本作は大学のサークルで出している部誌の2022年度2月号に掲載してもらった作品です。かなり昔に書いた作品なので当然文章は拙いですが、当時の面影を残すために改稿なしで掲載しようと思います。
ここで裏話をすると、実はアイデア自体は部誌掲載以前から組み上がっていまして……笑
本来monogataryのお題用に書き始めて時間の問題でポシャったアイデアをそのまま流用していたりします。まさかこんな所で活きるとは思わなんだ。
それでは、Have a nice flight!
(作品の世界観に肖って)
僕は、風船だ。
とあるショッピングモールの片隅で、たくさんの兄弟たちと一緒に売られている、何の変哲もない風船だ。日光に照らされて光る、赤いボディが自慢だった。
そんな僕のもとに、二人の人間がやって来る。大人の男の人と、年端もいかない女の子。女の子は、僕を見るや否や、満面の笑みで指を差した。
どうやら、僕の買い手が決まったようだった。
男の人──恐らくお父さんと思しき人物は、店員さんに小銭を渡すと、僕の身体に結ばれた紐を取った。それを受け取った女の子は、これまたとびっきりの笑顔を浮かべて、その場で何度か飛び跳ねた。それに合わせて、僕の身体も上下に揺れる。
やがて、二人は仲睦まじそうに手を繋ぐと、ショッピングモールの中へと歩き始めた。春が近づく白んだ青空。多種多様の人が行き交う道。いっぱいに広がる物珍しい光景は、お腹の中でヘリウムとは違う何かを膨らませた。
それはきっと、僕の紐を掴んでいるこの子にとってもおんなじことなのだろう。さっきからお父さんの手に引っ張られながらも、あっちへこっちへと視線を向けていた。見るもの全てが珍しく見えるのだろう。この子とはとても気が合うな、と心のどこかでそう思った。
けどその思いは、この子と共有できぬまま終わってしまった。
ふとした瞬間だった。女の子の手に留められていた僕の身体は、ふわりと上空へと浮かんでしまう。何かの拍子に、女の子が手を離してしまったのだ。
「あ、ふうせん……!」
風船が飛んで行ってしまうことに気づいたのだろう。一拍子遅れて女の子が声を上げる。掴もうと手を伸ばしても、その小さい背丈と腕ではもう届かなかった。
僕の身体は抗うこともできぬまま、みるみるうちに高度を上げていく。女の子の今にも泣き出しそうな顔も、徐々に小さくなっていく。
誰かに支えられないと浮くことしかできない僕は、ただ風に身を任せることしかできなかった。
北風に流された僕は、高い建物がいくつも建ち並ぶ場所へと辿り着く。
空に突き刺さるほどまでに高い、角張っていて青空を反射する建物。よく見ると、その中に何人もの大人が一点を見つめて作業をしていた。どこか苦しそうで、必死になっている様子だった。
この人たちは何をしているのだろう。どうしてこんなに焦っているのだろう。何故、そんなに辛そうにしているのだろう。そんなことを考えているうちに、自然に流れゆく僕の身体は高い建物の合間を通過した。
何やら騒音が聴こえる。下に垂れ下がる紐の方を見ると、いくつもの鉄の塊が煙を吐きながら走っていた。さっきの人たちと同じように、どこかせわしかった。
この街にあるものは、みんな落ち着きがない。何かに取り憑かれたかのように、動き回っている。もっとマイペースに行動すればいいのに。
そんな想いが届くことはなく、僕の身体は変わらず風に乗って、建物の群れを抜けていく。
北風に流された僕は、たくさんの檻のある場所に辿り着いた。
檻の中にいるのは、人間とはまた違う生き物たち。鼻の長いもの、首の長いもの、口が大きいもの、角が生えたもの、鬣の生えたもの。それぞれの檻の周りには、人間の子供たちが大勢いて、みんなその生き物たちに首っ丈だった。
何で生き物が閉じ込められているんだろう。どうしてそれを子供たちが興味深そうに観察しているんだろう。一つ、また一つと疑問と興味が膨らみ、弾けた。
そんな風に下を眺めていると、徐々にその景色が大きくなっていくことに気づいた。すぐに気づいた。僕の身体は段々と浮力を失いつつあったのだ。
僕は少しずつ檻へと接近する。やがて、その中でくつろいでいた一匹の生き物が、こちらへと視線を向けていることに気づく。黄色の体毛に黒い縞模様が付いていて、鋭い爪と牙を持っていて……体内のヘリウムがキュッと締まるのを感じた。
身の危険を感知し、必死に上へ逃げようともがく。上がれ、上がれと自分の身体に念じ、とにかく陸地から離れることだけを考え、必死にもがいた。
あとちょっとで生き物の目の前に来る。そう思ったその時、一陣の強い風が走り、僕の身体をふわりと浮かした。再び気流に乗り、上空へと流されていく。
ひとまず、助かった。
風に運ばれながら、僕は安堵する。表面をひりひりさせる北風は、やはり宛てもなく白んだ空の下を自由気ままに流れるのだった。
北風に流された僕は、煙突と無機質な建物が建ち並ぶ場所へと辿り着く。
赤と白の縞模様をした煙突。それ以外は、無色。温かみも、冷たさも、何の感情も感じられないその建物群は、ただ黒く淀んだ煙を吐き続けていた。
ここ一帯は、嫌いだ。空気が不味い。生理的にというか、本能的に嫌悪感を覚える。身体の表面がヒリヒリして、体内の空気が収縮して、むず痒くなるのだ。人間はよくこんな環境で生活できるなあ。
そう考えているうちに、僕の身体は煙突から吐き出された、煙の柱へと近づいていく。これはまずい。あんなのをまともに受けたら……逃げないと。さっきみたいに自分の身体に強く念じて踏ん張ってみたものの、今回は風の方が強く、抗えぬまま直撃してしまう。
痛くないけど、いたい。身体がピリピリする。不味い。気持ち悪い。苦しい。苦しい。くるしい。
煙の柱を通過した後も、妙な悪寒と不快感に見舞われる。それに比例して、体内の空気の圧が徐々に緩くなっていく。飛び続ける気力が、薄れてしまったのだ。
僅かな差だけど、徐々に高度を落としていく身体。そこに、上空へと投げ出された時の軽々しさはない。錘を付けられたような、重圧感。そんな身体を、北風は文句の一つも言わずに支え、僕の足となってくれた。
北風に流された僕は、鬱蒼とした森の中へと辿り着く。
最初は木々を見下ろせるほどだった高度も、段々と樹冠に触れるほどまで近づき、気づけば幹と並ぶほどの高度まで降下した。まるで僕の心情を、そのまんま表しているかのようだった。
空気の圧も緩み、足となってくれた北風も弱まり、速度も徐々に低下し、やがて陸地へと近づいていく。
そして、湿っていてぬかるんだ地面に紐が触れ、僕の身体が静止した時。
女の人が一人、泥だらけで倒れ込んでいるところを目撃した。
その人は、ひどく疲弊していた。服も、背負っていた大きな荷物も、泥だらけになっている。頭と膝の部分が赤く滲んでいて、苦痛がこちらにも伝わってくる。
この人、何で倒れているのかな。しかも、こんな場所で。
僕の紐を掴んでいた女の子のような、溌剌さは微塵もない。
建物の奥にいた大人のような、必死さもない。
例えるなら……そう。あの煙を吐いていた無機質な建物。
その表情に、生き生きとした色はない。まるで、もうすぐ死を迎えるかのような……死ぬ? 死んじゃうのかな、この人は。こんな場所で、一人で? どうしよう。どうしよう。どうするべきなんだ。いや、そもそも風船の僕にできることなんて……。
「……ふう、せん?」
そう焦燥に駆られている最中、ふと女の人が目を覚まし、上体を起こした。しかし、その動作の途中で顔を歪めた。苦痛によるものだろう。顔を顰め、歯を食いしばっていた。
良かった、生きてた……。決して喜ばしい状況じゃないけど、その僅かな幸福に僕は安堵する。
「……そうだ。良いこと思いついた」
しばらく呆然と僕を見つめていたその人は、やがて表情を変えて、背中に背負っていた荷物を何やら探り始めた。紙切れとペンを取り出して……何をする気なんだろう。想像もつかなかったが、ただ一つ、色を失った彼女の表情に微かながら変化が生じたことは確かだった。
紙切れに何かを書きなぐり、それを束上に巻いて、僕の元へと這い寄る。そして、紐を手に取ったかと思うと、紙を紐に結び、「よし」と呟いた。
「お願い……誰でもいいから、届きますように……」
誰にかけたわけでもない、弱々しい祈り。
それが森の霧の中に溶けていくのと同時に、僕の身体は女の人の手によって、ふわりと浮かんだ。
彼女の細く、傷だらけの手は、最後の力を振り絞ったかのように確かなものを感じて、僕は再び木々の葉を抜けて上空へと辿り着く。けど、その微かな力も虚しく、徐々に下へと下がっていく。
流石に、駄目か。
そう諦めかけたその時、一陣の風が木々の上を勢いよく通過した。木々の葉がざわめく。僕の身体も、ぶるぶると小刻みに震えた後、風に乗って進み始める。
急ごう。紙に書いてあることは分からないけど、すぐに渡さなきゃいけないのは確かだ。あの紙を渡さないと、あの人は力尽きて孤独に死んでしまう。そんな予感がした。
無関係な人だけど、そもそも本来無機質な存在である風船が人を救うなんて変だけど、僕が何も出来なかったせいで人が死んでしまうなんて、そんなの嫌だ。僕が望むのは、屈託もなく眩しい笑顔なんだ。あんなに苦しく、悲しそうな表情で人生を終わらせてしまうのは、自分のポリシーが許せない。
鬱蒼として霧に包まれた森を抜けた。
灰色の煙を吐き続ける建物群の地帯を抜けた。
生き物たちが檻の中で眠る区域を抜けた。
天を刺す高い建物が建ち並ぶ街を抜けた。
けれど、それらの光景はぐんぐんと横切っていく。それらが記憶に残らないほどまで、焦っていた。
さっきの生き物たちに紙を渡しても意味がない。あの大人たちに渡しても、知らん振りされるだろう。もっと関心を持ってくれそうな、心優しい人。そんな人たちが集まる場所。そこを探さないと。そこに、向かわないと。その一心で、街を抜けた。
体内の空気が少しずつ萎んでいく。浮力も落ちていく。意識も朦朧としてくる。満身創痍な僕に追い打ちをかけるように、強い向かい風が身体に吹きつける。
もう、駄目なのか。諦めたくない。けど、もうこれ以上、飛べない。どんなに身体に念じても、どんなに踏ん張っても、身体が言うことを聞かない。空気は風船の生命線。それが少なくなった今、飛ぶことも意識を保つこともままならない。ここでくたばるわけには、いかないのに。
空気が極限まで減り、意識も途切れ途切れになり。
向かい風に押し付けられるように、僕は地面へと落ちていく。
黒い素材で固められた地面。その上に力なく着陸する。
見ると、そこは白い建物の前だった。
「あれ、このふうせん……」
聞き覚えのある声が聞こえてくる。声のした方を見ると、そこにいたのは年端のいかない女の子と、父親らしき男の人。その顔、格好、間違いない。ショッピングモールで僕を買った、あの家族だ。
「ねぇみて、ぱぱ。てがみ、ついてる」
女の子は紐に結ばれた紙を取り出し、広げて読んだ。しかし、読めなかったのか顔を顰め、すぐにお父さんに手渡した。
彼は訝しげに目を通したが、やがて目を見開いて、女の子の手を取って建物内へと走りゆく。
あの焦った様子、何かに気づいたような表情。
もしかしたら、あの女の人の想いが、届いたのかもしれない。
良かった。
けど……気持ちが晴れ晴れとしない。
それどころか、意識も、気力も、空気と共に消沈していく。
ああ……そっか。
僕はもう、ここまでなんだ。
身体のどこかから、空気が少しずつ抜けていく。何かの拍子に穴が開いたのかもしれない。これじゃあ空気を入れ直しても元に戻らないよな。まあ、風船なんて寿命が短いから、元々覚悟はしていたわけだけど。それでも何だか……やるせないな。
けど、一日だけだったけど、良いひと時だったな。
色んなところに行った。興味深い場所にも、二度と行きたくない場所にも。最終的には女の人の願いも叶えられたわけだし、結果オーライじゃないかな。
ああ……意識が薄れてきた。
死んじゃうのかな、僕。
本当はもっと過ごしたかった。兄弟が言うには、長くて一週間は生きられると聞いたんだけどな。
それでも、良いかな。悔いはない。
それに僕が死んでも、誰かが悲しむわけでもないし、今更嘆いたところで──。
「ふうせんさん」
その時だった。
暗くなっていく視界の中で、さっきの女の子が明るい声をかけてくる。
「……ありがとう」
どこか寂しげで、けど心から感謝しているかのような、そんな言葉。僕が受け取るには勿体なさすぎる言葉。
そんな言葉を受けて、僕の体内でヘリウムとは違う、温かい何かが膨らんでいくのを感じた。
そっか。僕も、そんな言葉を受け取っていいんだ。
何の変哲もない。人と意思疎通もできない。
そんな僕でも、受け取っていいんだ。
もしそうなら、僕は。
なんて、幸せ者なんだろう。
体内の空気と同じように、僕の意識も萎んでいく。
やがて、黒に染まる僕の意識。
だけど……その最中でも。
女の子のあの言葉が、最後まで自分の中で鳴り響いていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
