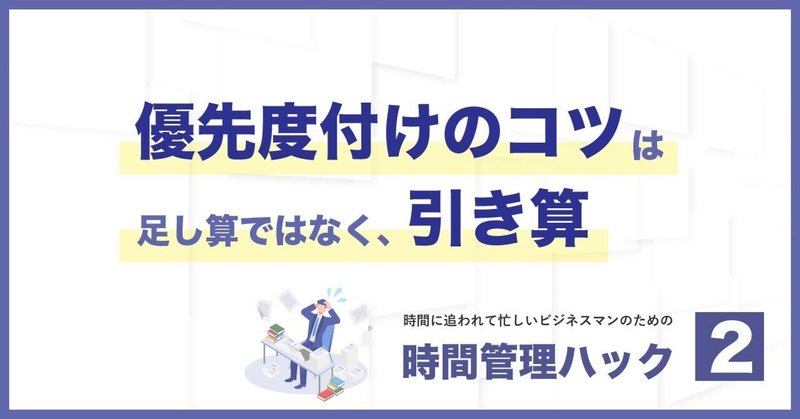
優先度付けのコツは、足し算ではなく、引き算!【時間管理ハック②】
前回の「「時間に追われて忙しい」から脱却するためのマインドセット【時間管理ハック①】」では、そもそもの時間管理をする上で意識したい、時間の大前提についてお話ししました。
「時間に追われる人」は小手先のテクニックではなく、まずは根本的に考え方を変えないと変われません。
少し概念的、哲学的ではありましたが、非常に重要な部分なので、きちんと抑えておきましょう。
続いて、今回は時間管理を行う上で重要な「優先度付け」について、その具体的なやり方などについて解説していきます。
※前回の記事はこちらから
自己紹介
事業投資家の林周平(@HayaShu88)と申します。10社のグループ企業の経営と林経営塾を主催しています。
僕のプロフィールは以下をご覧ください。
時間管理のコツは「足し算」ではなく、「引き算」で考得ること!

時間管理のコツとして、一番先に押さえておきたいことが、「時間管理のコツは引き算」という事です。
例えば、時間管理をしたいから時間管理ツールを導入しよう、ガントチャートを作って管理しよう、など「足し算」で解決しようとする方が多いように思います。
しかし、時間管理ツールやガントチャートを導入したはいいが、タスクを登録したり、更新したりする手間に、逆に追われて、かえって逆効果になってしまっているという方も多いのではないでしょうか。
このように、時間管理は「足し算」では本質的には解決しません。
時間管理のコツが足し算じゃなくて、引き算が重要です。引き算とは、つまり、「やらないことを決める」ということです。
「プロジェクト管理するな」と言いたい訳ではなく、足し算をするのではなく、基本的に時間管理をしたいのであれば、引き算をしましょうというのが言いたい事です。「時間は有限だ」という前提を持つということです。
「時間が無限だ」と思ってるから足し算してしまうんですが、有限だと思った瞬間、「泣く泣く引き算をする」という風に、行動が変わってくると思うので、僕は、引き算っていうのは時間管理のコツとしては一番重要だと思ってます。
「引き算」するのは、実は「足し算」するよりもずっと辛い

ただ、「引き算」ってやろうとすると辛いんです。
上記図の左の人みたいに、人間だったら誰でも「あれもこれもやりたい」という風になります。
例えば、子どもの場合、「あれもやりたい、これもやりたい」ってなるのが普通ですよね。
そのため、「引き算」は辛いんですが、「意識的にまずはこれをやりきろう!」という風に思えるかどうかなんです。
実際に、上記図の右の人だって、心の中では「本当であればあれも、これもやりたい」って思っているんです。
「やりたいんだけれども、まずはこれをちゃんとやろう」という風に、引き算して考えられるかどうかがポイントです。
上記図の左の人は、子どもみたいに「あれもこれも食べたい」と言って、いざ何かお菓子とかを食べてたら、晩ご飯ときにおなか一杯になってご飯が食べられなくなって、みんなが晩ご飯終わったあたりに、おなか減ってきて、母親に「だから言ったじゃないの!」と叱られてしまうイメージです。
動物的に考えたり、反応的に捉えてると、誰でも左の人みたいに簡単になってしまいます。
時間管理をして、「時間に追われないようにする」という事を実現したいのであれば、上記図の右の人のように、引き算の発想を持つようにしましょう。
また、もう1つ、上記図の右の人のような引き算の発想を持つメリットを説明すると、「やりきった達成感が得られやすい」という事です。
上記図の左の人は色々やりたい事が多すぎて、大体、全てが中途半端になってしまって、やりきった感覚がないことがほとんどです。
振り返ってみると、ただ何とかなっただけ。
何とかなった事の積み上げでその人の人生、つまり生命が形成されてるって事になるので、やりきった感がないんです。
上記図の右の人は、一つの事を成す達成感があったり、一つひとつのプロジェクトにちゃんとけじめをつけて、良かった事や悪かった事、分からなかった事も、きちんと結論を一つひとつ付けてやっていくので、経験が一つひとつ積み上がっていくような人生になります。
なので、上記図の右の人のように、引き算の発想をもって一つひとつ着実にやっていこうとというのが、時間管理の最大のコツであって、時間に追われなくなる第一歩になります。
ただ、1つ勘違いしがちなのが、「やることやコミットを減らそう」という意味でないという事です。
「時間の量は有限である」という前提を持ったときに、どういう意識を持って物事に取り組みますか、という事を言いたい訳で、「余剰をどんどん作って仕事の数減らしましょう、コミットを減らしましょう」と言いたい訳では全然ありません。
具体的にどう時間管理すればいいの?押さえておくべき4つの時間管理ノウハウ
時間管理のコツは足し算ではなく「引き算」という事をお伝えした上で、具体的にどんな場面で、どんな風に「引き算」をしていくべきなのか、押さえておくべき次の4つのノウハウについて、まずは「1.優先度付け」について解説していきます。

※他の「2.集中力」「3.ワーキングメモリ」「4.効率性」については、別記事にてそれぞれ解説していますので、上記リンクから、ご覧ください。
優先度付けが上手くなる3つのコツ
どの仕事から優先的に行えば良いのか、優先度付けが上手くなると、時間管理が劇的に変わってきます。
では、どのように優先度付けを行って行けば良いか、優先度付けのコツを1つひとつ解説していきます。
<優先度付けのコツ1>優先度「高」ではなく「低」を増やす

優先度付けのポイントは「優先度高」じゃなく「優先度低」を増やすという事です。
これができるかどうかです。優先度を高にするのは誰でもできます。
だからこそ優先度低にする決断ってすごく精神的に辛いんです。「あれもやりたい、これもやりたいし、重要だけど…」という感じで泣く泣く優先度低にするという感じです。
この、優先度低の決断をいかにしていくかが優先度付けのポイントです。
余談ではありますが、「至急」という言葉を口癖みたいに使う人がいます。これは、一番格好悪いなと僕は思います。
「至急」と言ってても、実際に「至急やらなかったらどうなるの?」と聞いてみたら、「いや別に困らないよ」って言う事が非常に多くて、「だったら至急って言うなよ」と思います。
「至急」という言葉は、スペシャルなヘルプカードなのでできるだけ使わないようにした方が良いと思います。
言ってはダメという事ではなく、「至急」という言葉を使うと、自分の信頼残高が減ると思って、「本当ごめんけど、至急ちょっとお願いします」と、そのカードを、大事な局面で大切に使うのが大事ということです。
逆に、「至急」という言葉を使ってくる人がいたら、ちゃんと確認した方がいいですね。「これ、本当に急ぎなんですか?」とか、「至急の理由ってどういうことなんですか?」とか、もしくは「至急と言われても、こちらちょっと対応できないんですけども」とか一回跳ね返したり、受ける側も「至急」という言葉の圧力に流されないようにしましょう。
<優先度付けのコツ2>「保留」という意思決定を下す

優先度の付け方のコツは、いかに優先度低を増やすかというお話をしましたが、「これは優先度低なのか…」と困ってしまう時には「保留」という決断をするというのも1つのコツです。
「保留」というのは、実質、優先度低という事なんですが、「今はやらないけど、いつかやる」という事ですね。
例えば、タスクリストを作って運用していると、「2ヶ月ぐらい着手してないタスク」などが出てきたりしませんか?それは2ヶ月やってないから「やらない」という事なんですよ。
ポイントは、そういう「いつかやるけどやってないタスク」をズルズルとそこに置いておかない事です。これは、次の時間管理のコツのキーワードになりますが、「ワーキングメモリ」が取られてしまうんですね。
「いつかやるけどやってないタスク」が残り続けることで、毎回「これもやってない、これもやってない」という風にワーキングメモリが取られ続ける上に、やってないという事で自尊心が若干削られるわけです。
そういう時にはもう、「そうか、俺はもうやらないってことなんだ」と思って潔く「保留」に入れることです。実際やってない訳ですし、行動は嘘つかないですからね。もう、「俺の潜在意識はこれをやらないって言ってるんだな」と思って保留に入れるという決断をした方が良いと思います。
「保留」を使いこなせるようになると、気がだいぶ楽になります。「優先度低」よりも、まずは「保留」を使いこなせるようになる方が、改善が早いと思います。本質的には「優先度低」が一番大事ですが、優先度低という意思決定をするのはなかなか精神的に辛いんです。
心に優しいテクニックとして、まずは「保留」のテクニックの方が使いやすいかと思います。
<優先度付けのコツ3>業務レベルで捉える

優先度付けをするコツの3つ目が「業務レベルで捉える」という事です。
具体的に言えば、「タスク管理をあまり細かく積み上げてマネジメントしようとすると、物事が見えなくなっていくので、タスクレベルではなく業務レベルで捉えてマネジメントしよう」という事です。
例えば、「ペットボトルの水を飲む」という業務があったとします。その業務をマネジメントしようとして、次のようなタスクに分解して他の人に業務遂行を指示したとしましょう。
ペットボトルを机の前に置く
左手で持ち、左手で抑えながら右手でキャップを開ける
左手で口に運ぶ
このタスクだけを見ると、どんな業務なのか分からなくなりませんか?
なので、こういう場合は「水を飲む」だけでいいという事です。それ以上粒度を細かくタスク分解してマネジメントする必要はないという事です。
例えば新人で何もわかってない人や、全体像を1回も説明していない人であれば、粒度細かく指示を出す必要がありますし、ある程度わかってる人や、分かってくれよという人にはある程度粒度を大きく出すなど、相手によって変える必要はありますし、ここはプロジェクトマネージャーのセンスとも言えます。
しかし、「このタスクの粒度を細かくすればするだけ良い」という雰囲気が世の中に蔓延しているので、これは大きな間違いですという事を言いたい訳です。そもそも、タスク管理をするという事は足し算ですからね。
タスク管理をするという事は、管理コストをわざわざかけるという事なので、粒度を細かくすればするだけ管理の手間もコストも上がります。だからこそ、「できる限り管理をしなくても良いように、引き算をしましょう」という事がここで僕が言いたいことです。タスク管理の際に、粒度という観点を持っていただけたらと思います。
ここで言う、業務というのはタスクが複数入っているものをパッケージしたものを指します。
なので、例えば先ほどの「ペットボトルの水を飲む」で言えば、「ペットボトルを机の前に置く」「左手で持ち、左手で抑えながら右手でキャップを開ける」「左手で口に運ぶ」というのが1個1個のタスクですが、それをまとめると「ペットボトルの水を飲む」という業務になるという感じです。
また、タスク管理においても、1ページ目に表示される量を超えると効率が悪くなります。
例えば、スマホで開いた1ページ目のアプリは見ても、2ページ目以降って一気に見なくなりますよね。
Google検索でもそうですが、検索結果の1ページ目はよく見ても、2ページ目以降はほとんど見られないわけです。同様に、タスク管理ツールでも1ページ目だったり、上の方に表示されてるものはちゃんと見ても、下の方は見ないんです。
これは、ワーキングメモリと一緒なんですが、結局1ページ目から外れてるタスクって見ないですし、タスク管理の効率が下がるんですよ。それならば、そこを引き算した方が効率上がるってことです。
1ページ内で処理をできるようなセルマネジメントした方が、タスク管理の効率は上がります。
ここは、特に指示してる側の人間が、気遣ってあげてほしいところです。「こんなにいっぱいタスクがあるけど、正直この辺は全然着手もできてないし、そもそもそこまで重要ではないのでは?」と、保留への意思決定を促すという感じで、マネジメントをしてあげるというのが良いと思います。
【参考】優先度付けの基準

優先度付けの基準の例についてですが、まずは、「優先度高」については、「これをやらないと仕事がどうにもならない。やらないと炎上して爆発して終わってしまう」ぐらいの本当にマストのものだったり、「これをやらないと、日々仕事をしている意味がない」というほど。未来的に重要なものが適切です。
「俺たちはこういう事をしようという旗振りで集まった団体だよね。これをしなくても、別に今すぐは死なないんだけれども、これをしなかったら俺たち存在意味ないよね」という、やらなければ存在意義が否定されるぐらい重要だというものを優先度高にしましょう。
これは、正直極端に言ってます。なぜか、というと、みなさんに引き算をして欲しいからですね。誰でも優先度高にはできるので、あえて極端に表現しています。
「優先度中」は、「もうやらないとまずいよね。これクレームなっちゃうよね。炎上するよね」というものだったり、もしくは、「さすがに絶対にやっておいた方がいいよね」みたいなものが優先度中です。
「優先度低」は、やらなくてもどうにかなるものです。
極端に言えば、「掃除」とかです。
「よし、今度こそ俺はあの綺麗なデスクで仕事するんだ」と思って、みなさん「優先度高」に入れるんですよ。みんな入れるんですが、それがもう1週間もやってないんやったらもうやらないという事だと、潔く優先低とか保留にするという風に泣く泣く「優先度低」にしていくんです。
「やりたい」という気持ちは大切ですが、そういう願望に流されずに、「やらなくてもどうにかなる、もしくはやりたいと思っている程度の話」は全部泣く泣く優先度低にしましょう。
なるべく優先度低にする。このセンスが良くなると、タスク管理が非常に上手になっていくんじゃないかなと思います。
【事例】プロジェクト管理ツールの運用例

これは僕がプロジェクトマネージャー的に関わっている実際の案件でのASANAというタスク管理ツールを使ったタスク管理の例です。
週次ミーティングを行い、その場でこのASANAのタスク管理ツールを綺麗にするという事を行っているので、日々更新しなくてOK、いつも最新の状態ではなくてもOKとしています。
なぜなら、別に毎日コミュニケーションする必要がないプロジェクトだからです。だからこそ、できる限りお互いの管理の手間がないように、管理した方が良いタスクがあれば最適な粒度で「新規タスク」に追加したり、週次ミーティングのみで「この件はどうなっているのか」のような感じで、PDCAの状況を管理しています。
常に最新の状態に更新するという管理を省き、このプロジェクトに合った「引き算」の管理を徹底している訳です。
このタスク管理表の中でまず、見ていただきたいのが、まずステータスを「新規タスク」「進行中」「確認待ち」「完了」「マイルストーン」「保留」という6つに分けているという点です。
「確認待ち」というのは、担当者から見て「自分じゃない人たちが今ボールを持っている状態」のことです。つまり、担当者自体としてはもう作業完了してる状態のものは、確認待ちに入れます。
「確認待ち」のものが確認後、「進行中」や「新規タスク」に戻ったりします。また、タスクを完了するのは基本的に、依頼元の人、つまりプロジェクトマネージャーや上司が行っています。
みんなでタスクを登録し管理している会社は、タスク完了した本人が完了にするよりも、依頼元(プロジェクトマネージャーや上司)の人が「タスク完了しましたので確認お願いします」という報告を受けて、「ありがとう。タスク完了してきますね」という返事をしながら、タスクを依頼した人が完了するという方が、必ず一旦確認のフローが入るのでいいのかなと思いこのような取り決めをしています。
しかしこれはあくまでこのプロジェクトに関しての最適なマネジメントであって、そこの取り決めはプロジェクトによって変えると良いと思います。
例えば、僕の場合であれば、もし、タスクの粒度が細かかったら、「確認しなくていいから、自分で確認し、OKにしていいよ」というマネジメントもあり得ると思いますし、粒度がざっくりしていたり、業務レベルの粒度であるならば、一応その依頼元や、上層の確認が基本的には必要なはずなので、そういう意味で、完了にするのは、その依頼元の人がするというルールにしています。
「マイルストーン」と言うのは、今季の重要な目標と課題の事です。
「もう、今季は絶対これやるぞ」と言った、事業計画に沿ったような目標の事です。別にここになくてもいいんですが、これがあることによって重要度の設定に意識が向くので、そういう良い意味合いを狙ってやってます。
少しここで、管理をスムーズにするポイントを挙げます。まず、新規タスクの期限についてです。みなさんタスクを管理する時に必ず期限を入れるのですが、大事なことは、その期限に意味があるのか、という事です。意図をもってその期限入れてるのか、という事なんです。
とりあえずタスクを設定したんだからと、期限を当たり前のように入れていく人が多いんですが、意図のない期限は入れない方が良いです。ノイズです。
よく僕が言うのが「言ったらやる、やらないなら言うな」ということです。
なぜかと言うと、人はそれをベースにして人を信じたり、そこをベースにして他の人が動くので、意図がない期限をわざわざ切ってやらないぐらいだったら、他の人に迷惑がかかるから、最初から期限を入れないというのが結構大事です。
また、もう一つポイントとして上げたいのが、重要度高のタスクをしっかりとプロジェクトマネージャーや上司の方が「重要度高からやったらどうか」や「重要度低のものにばかり期限が入っているけど、別に急いでないから後でもいいよ」などを定期的に業務のバランスを調整してあげることが大切です。
そうしないと、基本的に人は重要度低の、やりやすいものからこなしていくからです。重めの重要度高のものは後にしようという気持ちが働くので、そこはプロジェクトマネージャーや上司役の人がしっかり促してあげるというのが大事です。
最後が、先ほども優先度の付け方において一番重要なポイントとして説明した「しばらく新規タスクで着手されずに滞留しているものは、潔く保留に入れる」ということですね。ただし、保留は「今すぐやらないけど、できる時にやる」という事であって、一生やらないということではないという点を勘違いしないようにしてください。
僕はこのように各プロジェクトの管理を、ASANAというタスク管理ツールを使い、うまく引き算しながら効率的に管理をしているという事例でした。
まずは、業務・タスク管理において「保留」の意思決定をするところから始めよう!
仕事をする上で、業務やタスクの管理は必ず発生します。足し算になりがちな業務・タスク管理を効率的に進める上で大切なのが、「優先度付け」です。
特に「優先度高」ではなく、「優先度低」という意思決定をいかにしていくのかが大切だということをお伝えしました。しかし、実際は優先度低にするという決断は、なかなか精神的には辛い…。だからこそ、まずは「保留(すぐにはやらないという意思決定をしたが、いずれやる)」という意思決定をして、保留を増やしていくという事から着手してみるのがおすすめです。
次の記事では、本記事に引き続き、時間管理の4つのノウハウのうち2つ目の「集中力」について具体的な事例も交えて解説していきます。
※次回の記事はこちら
↓こちらは私の詳細な経歴やプロフィールの紹介です。
↓経営塾で伝えている中心となる考え方はこちらにまとめています。
↓Podcastでは「仕事と幸福論」を雑談形式で配信しています!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
