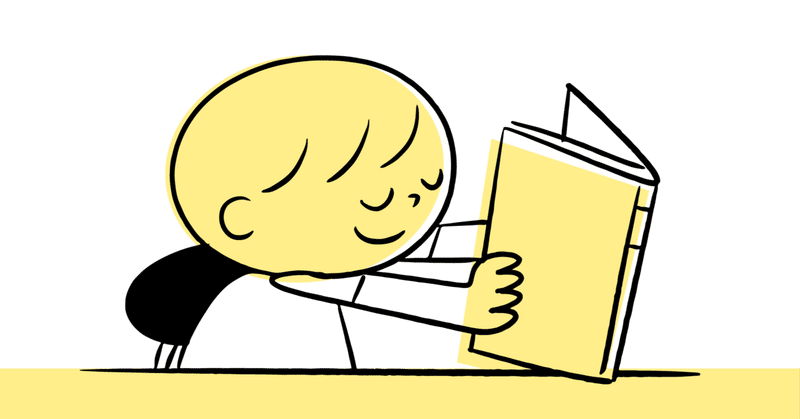
後見制度の今後 ~介護と癒し~
「一度後見人をつけたら亡くなるまで」
「後見人と相性が合わなくても、他の人に変更してもらえない」
「家族は後見人にはなれない」
10月から「後見制度」のオンライン講座を受講していますが、受講前まで、私は、後見制度に、どちらかというとネガティブなイメージを持っていました。
ただ、制度や現状を詳しく知ることによって、ひとり世帯にとっては、心強い存在でもあるし、「知って、必要があれば活用」させていただくことの意義も感じるようになりました。
一方で、ご本人に家族がいらっしゃる場合、「不動産売買」や「相続」などが発生しない限り、ほぼ制度を活用することもなく、「家族が対応する」のが日本の現状でもあります。
実際どうなの?
◆一度後見人をつけたら亡くなるまで
↓ ↓ ↓
原則として途中でやめることは認められず、被後見人が亡くなるまで、後見人業務は続きます。(それまで、後見報酬が発生するということでもあります)
◆後見人と相性が合わなくても、他の人に変更してもらえない
↓ ↓ ↓
家庭裁判所の決定事項なので、「好きじゃない」「気が合わない」では、残念ながら変更の理由にはなりません。
後見人の横領、あるいは後見人自らが「辞める」という意思表示ない限り、変更なしが現状です。
◆家族は後見人にはなれない
↓ ↓ ↓
実際、誰が後見人に採用されているか統計を見ると、「親族」は約20%。
ただし、「家族はなれない」ということではないようで、後見人の候補者として申請することも可能です。
一方で、最終的には、家庭裁判所が後見人を決定することにはなるので、必ずしも、その候補者がなれるわけではない、ということになります。
一市民として、感じること
認知症高齢者の方も含めて、成年後見の対象者であろう方々は「1,000万人以上」。
ところが、実際の利用者は「25万人」(2.5%)。
確かに勉強をしてみて、一人の人生をほぼ引き受けて支援を行う制度ですので、緻密で分かりにくい部分がある。
また、いろいろな情報が錯そうして(私のように知らないのに、よくないイメージを持つなど)、利用が進まないという現状は、正直納得できるところがあります。
◆一度後見人をつけたら亡くなるまで
↓ ↓ ↓
「終わらない後見」を「終わる後見」に。今後の法改正によっては、「必要な時だけ」の「スポット後見」の可能性もあるかも?
ひとり世帯であれば、亡くなるまで後見人にいてもらう必要がありますが、ご家族がいらっしゃる場合は、「不動産売買」など、その案件に対して後見人という存在がいればいいのでは? ということです。
◆家族は後見人にはなれない
↓ ↓ ↓
これまでは、家族による虐待などがない場合、財産の金額や申立ての書面によって「専門家をつけたほうがいい」というような慣習があったそうです。
が、今後は、親族が排除されるのではなく、ご本人にとって、誰が本当に後見人としてふさわしいのか?
そういった方向性も模索中のようです。
家族として、少しばかり介護に携わる機会をいただき、それ以前とは比べものにならないレベルで、こういったことに真剣に向き合えるようになりました。
家族単位では悩ましいことでも、制度として整っていれば、社会として「すでにそう」であれば、多くの人の安心感につながっていくと思います。
一方で、まだまだ市区町村でも、こういったことの扱いは格差が存在するとのこと、個人個人が意識を高めていくことは、そのスタートかな?
と感じます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
