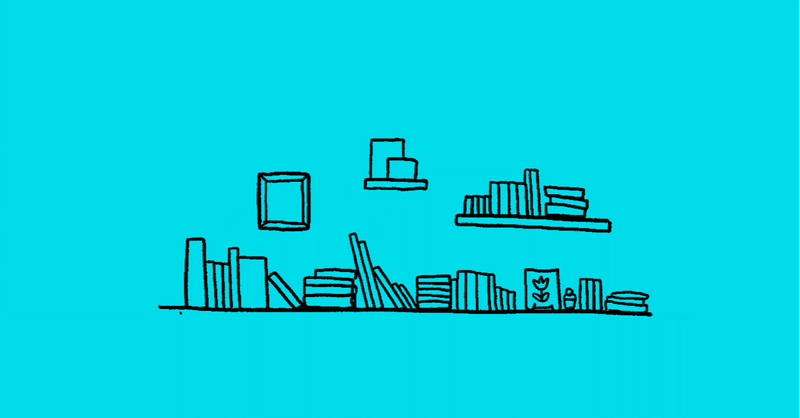
伝わる文章を書くための参考書
まったくの別分野から今の仕事を始めて右も左もわからなかったころ、大変お世話になった本があります。
なんとかかんとか取材を終え、はーやれやれどっこいしょとおもったのもつかの間。私の仕事としては、これを「記事」にしなくてはいけません。
えっ どうやって?
どこかで書き方の勉強なんてしたこともありませんし、趣味の小説だったりブログだったり学校の論文だったりは書いたことはありましたが、雑誌に載せるような記事となるともう完全にお手上げ。
とりあえず文字起こし(あるいはテープ起こし。録音した音声を、文字通り文字にすることです)をして、さあこれをどうまとめたものか、と頭を抱えてしまったとき、これらの本に助けられました。
「」の中は。で終わらないとか、!や?のあとは一字下げるとか、そういう技術的なことはさておき、今回は内容についてです。
まず、池上彰先生の『伝える力』シリーズ(PHP)。
会話でのコミュニケーション術が主なのですが、文章の書き方も載っています。
取材してきた事柄を雑誌に載せる場合、取材したことをすべて載せることはできません。(中略)そこで求められるのは、どの事実を拾い、どの事実をそぎ落とすのか、という取捨選択の能力です。(中略)たとえば、1000字程度のスペースに、テーマを3つも4つも盛り込んで書いてしまったりします。これでは、内容が散漫になり、何を言いたいのかわからない原稿になってしまうでしょう。 『伝える力』(PHP)
これ、もともと書ける人には当たり前のことなのかもしれませんが、私には目から鱗でした。
短いスペースにどれだけ情報を詰め込めるかが勝負だと思っていた節があったので、情報を取捨選択する意識がなかったの。
これをきっかけに、これまで取材で聞いた話は全部盛り込まなくてはと思っていた考えを捨て、テーマを2つ、多くても3つに絞ってまとめてみるようにしました。
おかげで、自分の以前の記事と比べて、ではありますがずいぶんスッキリ読みやすい内容になったように思います。
本自体も、伝え方の本にふさわしく大変読みやすいのでおすすめです。
もう一冊が、副島隆彦先生の『説得する文章力』(KKベストセラーズ)。
副島節とも言うべきバッサバッサ斬り捨てるような文章の書き方を、技術面から教えてくれる本でした。
ついついまろやかな言い口で逃げようとしてしまうのを叱られているような気分になるけど……笑
今でも書き終えた自分の文章を、同著内の「説得力のある文章を書くための20カ条」「やってはいけない書き方10カ条」に照らして修正すると真っ赤っ赤になるので、まだまだ全然だめだなあと反省するためにもとてもありがたい一冊です。
結局、要は「難しい話をどれだけかんたんにわかりやすく書くことができるか」で、文章の伝わりやすさは決まります。
難しい漢字を使いすぎないことや、数字の表記などは共同通信の記者ハンドブックを参考にしています。
ふ〜〜なんか真面目な文書いちゃったぜ!たまにはね。いいわよね。
ちなみに他にもたくさん書き方の本は買ったけど、結局買って満足してしまって読んでいないという……。
またちゃんと読んだらご紹介するかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
