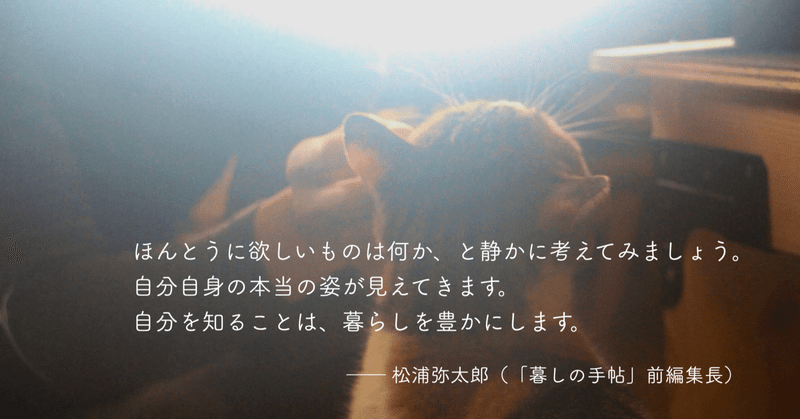
暮らしはもっと、多様でいい。人々の暮らしをめぐる8ヶ月間の旅を通して知ったこと (後編)
そんなこんな*で、突然千葉県いすみ市の古民家で暮らすことになった僕(※そんなこんなはこちらの記事から!)
これは、後に僕や周りの人たちの人生に影響を与える、めちゃめちゃ大きな選択だったと思う。
そこで共に旅をすることになるパートナーのWakanaと出会えたし、今まで思い描いたこともなかった将来の暮らしのビジョンが見えたからだ。
パートナーとの出会いと旅の始まり
ボランティアスタッフを招き入れて、共に暮らしをつくることは、『パーマカルチャーと平和道場』初の試みだったそうだ。
そして、僕を含めて3人のスタッフが採用されて、その内の一人の女性と意気投合。
彼女と僕は性格や人との接し方、表現の仕方は違うけれど、「これ、いいね!」と思うものはなんだかいつも似ている(性格が違いすぎて互いにイラッとすることも多々あるけど、だからこそ許し合い、学び合い、尊敬しあえる大切な人だ)。
元々、自分で暮らしを手作りすることに関心のあった彼女(会社員生活の合間を縫って自宅でソーラー発電したり☀️、古着や布を縫い合わせて服をリメイクしたりしてたらしい👚)は、有機農業を営む農家さんや農的な暮らしを巡る旅をするためにここにきたという。
僕は、ここを出たあとは横浜で友人たちと立ち上げたマンションに住むことを予定していたんだけど⋯⋯
農的暮らし、めっちゃ興味ある⋯
この人と一緒に旅したらぜったい愉しい⋯
ごめん、横浜のみんな⋯
たくさんの貯金もなければ、旅の仕事の両立がうまくいくあてもなかったけれど、このタイミングを逃したらあとで後悔で悶え苦しむということだけは分かっていた。
相手の人生も巻き込む、大きな決断だ。
僕は丁寧に言葉を選び、一緒に旅をするお誘いをした。
少し考えた彼女は「ワクワクするね。しよう、二人旅!」と答えた。
そして僕と彼女は、日本中の暮らしを巡る旅をすることになった。
旅は、11月にスタート
二人で旅を始めたのは2021年の11月からだけど、実質的にはボランティアスタッフをしていた2ヶ月間を含めるともう8ヶ月くらい旅をしたことになる。
僕たちは、いいとものテレフォンショッキング的に、数珠繋ぎでさまざまな場所を訪ね、暮らすことになった。
● 僕たちが訪ねた場所(一部抜粋)
・パーマカルチャーと平和道場 @千葉県いすみ市
・ブラウンズフィールド @千葉県いすみ市
・エコビレッジUMIKAZE @千葉県南房総市
・古民家うつわ @千葉県夷隅郡御宿町
・ぴたらファーム @山梨県北杜市
・ビヨンド自然塾 @山梨県北杜市
・京都の庭師さんの家 @京都府綾部市
・菜音ファーム @淡路島
・楽音楽日 @徳島県神山町
・Zion Valley Farm @高知県香美市
濃密すぎる日々だったため、すべては書ききれないけれど、各コミュニティ、農家さん、ご家族の暮らしをご紹介するね。
実は、これらの場所以外にも二人で野宿をしていたり、初めて道端で会ったおじさんの家に泊めてもらったりもしたんだけど、それはまた別の機会に(笑)
パーマカルチャーと平和道場

旅の原点になった平和道場。ここでは、井戸水をポンプで汲み上げて生活水として使ったり、雨水をフラッシュ浄化して飲み水として飲んだり、太陽光だけで料理をしたりと、自然のエネルギーを暮らしに取り入れることを体感的に学んだ。
それだけでなく、コンポストトイレを通じて僕たちの排泄物が土の中の微生物や野菜たちのためになることが、自然たちから存在意義を与えられたようでとっても気持ちよかった。
人間だけが、種まきせずに、うんちを水にながしているのさ
ブラウンズフィールド

この日は、食べて、飲んで、歌って踊るブラウンズフィールドの収穫祭。一泊二日で祭りの運営をお手伝いさせてもらった。
食や音楽が人を結びつける力ってほんとうにすごい!
ちなみに、ブラウンズフィールドが存在する千葉県いすみ市は、学校給食のお米を無農薬無化学肥料の有機米にした日本初のオーガニックタウンだ。
エコビレッジUMIKAZE

大学生時代に繋がった現代の侍みたいな友人が立ち上げた南房総のキャンプ場。
パーマカルチャーの概念を取り入れた環境に優しい暮らしを実践するエコビレッジとして、気軽に自然体験ができる施設を目指している(UMIKAZEは今月、クラウドファンディングを実施し、5日で100%を達成した🎉)。
とっても温かな雰囲気で僕たちを迎え入れてくれたスタッフの武藤くんには心から感謝!
古民家うつわ

同世代の友人3人が暮らす、千葉県夷隅郡の古民家。
田んぼや畑、焚き火などの昔暮らしを体験できるだけでなく、彼女たちの専門分野である「プロセスワーク」や「NVC」などのコミュニケーション手法を活用したリトリートも開催している。
大家さんのキウイ畑で数百個のキウイを収穫したのはいい思い出🥝
ぴたらファーム

山梨県北杜市にあるぴたらファームは、自然循環型の暮らしを実践、提案するオーガニックファーム。
世界中の調味料、マニアックなスパイスを取り揃えていて、食の自給率はほぼ100%。
メンバーの持つそれぞれのスキル(編み物や建築、お菓子作りなど)を分かち合いながら、僕たちのようなWWOOFerをみんなが心地いい形でうまく暮らしに取り入れる仕組みには美しさすら覚えた。
ビヨンド自然塾

同じく、山梨県北杜市にあるビヨンド自然塾。
広大な敷地内にあるのは、自然農をベースにした畑、設計図やメジャーなしでつくられた小屋(通称:小人の家)、一歩間違えたら怪我をするスリル満点の手作り遊具。
そう、写真からも察していただける通り、代表の方がいい意味でぶっとんでいる人なのだ(ちなみに、写真は土室に焦げ後をつけていい感じのデザインにしているところ)。
誰もが知る一流大学を出た後、大手精密化学メーカーで研究者として働いていた方なんだけど、経済活動に一切興味がなくなってからこのビヨンド自然塾を一人で切り開き始めたそうな。
そのパワフルさの裏にあるエッジの効いた哲学はいつも僕たちを感動させてくれた(話がおもしろすぎて、ほとんど笑ってたけど)。
興味のある方は、ぜひ会いに行ってほしい。
ビヨンド自然というか、ビヨンド人間みたいな人だ。
京都の庭師さんの家

京都の山村でひっそりと暮らす庭師さんの家に一週間ほど滞在させてもらった。
彼は、たまたまタイの山間民族と暮らしていたことがあり(そんな“たまたま”ある?)、そこからあらゆるものはその土地にあるもので作ることができるということを体感したそうだ。
そして造園会社に勤めたあと、特殊伐採(高木や巨木を根元から倒さずに伐採すること)を専門とする庭師として独立し、古民家を買って自給自足生活を愉しんでいる。
僕が一番理想に近い暮らしを送っていたのが、彼だった。
道具を大切にすること、暮らしと遊びと生業は一つにできるということ、できないかもしれないことも意外とやってみたらできるということ、たくさんのことを学ばせてもらった。
菜音ファーム

カフェとキャンプ場を営む農園、菜音ファーム。
2011年の震災をきっかけに関東から淡路島に移り住み、開かれたこの場所では、無農薬無化学肥料でお米と野菜を育て、味噌、梅干し等、発酵食品を手作りしているだけでなく、島で採れるワカメやヒジキも手間ひまかけて商品にしている。
ある日、代表のMUDOさんが語ってくださったことが印象的だった。
引っ越してきた当初は、「なんでも自分たちでできた方がいい」と考えて、塩作りやパン作りもやっていたけど、めちゃめちゃ手間がかかるし、時間と労力がかかる割にはできあがる量はそんなに多くない。
でも、そのうち自分たちよりも美味しく塩やパンをつくる人たちと出会えたんだ。
全部自分たちだけでやろうとしなくても、この島全体をコミュニティとして捉えて、みんなで得意なことをGIVEし合えばそれでいいんじゃないかな。
奇しくも僕たちの旅のテーマは「自給他足(じきゅうたそく)」だった。
「自給自足(じきゅうじそく)」をもじったこの言葉は、自分たちの大好きなことや得意なことを通じて他の誰かにギフトして“優しさの流れ”をつくるようなイメージを込めた造語なのだけど、それを実践する人と出会えたと感動した。
何もかもはできなくても、みんな何かはできるはず。
それを分かち合えば、僕たちはもっとリラックスして生きられるんじゃないかな。
楽音楽日

徳島県神山町、水が美しいこのフィールドで約20年間暮らしを手作りするご夫婦がいる。
ご夫妻は、自分たちのやっていることを「実家業」だという。
誰もが気軽に来て、そこにあるもので豊かに暮らし、また旅立ってほしいという願いを込めてそう表現しているそうだ。
実際に、ふらりと来た若者を2年間泊めてあげたこともあったそう。
20年間、この土地で育った自然栽培のすだちを使った『スダチスコ(すだち × タバスコ)』は絶品なので、機会があればぜひ食べてほしい😋
Zion Valley Farm

親御さんから引き継いだブルーベリー農園を高知の山奥で営むご家族のもとに2週間滞在させてもらった。
無農薬、無化学肥料で野菜をつくり、工夫さえすれば愉しく豊かに暮らしを創造ことが可能であることを改めて実感した。
僕たちはここで、生きた鹿を殺め、解体するという経験もさせていただいた。

生きること、命をいただくことを肌で学ばせていただいた Zion Valley Farm の皆さんに感謝申し上げます。
滞在先で、どんなことをしていたのか気になる人はこの記事を読んでみてね!
多様な暮らし方を愉しむ
料理はアートだと知る
当たり前だけど、上にあげた全ての場所は、それぞれ気候も違えば土も違う(だから旬の食材も違う)。
土地の資源やニーズも違えば、そこに集う人たちの性格や能力も違う。
何もかも材料が違う中で、暮らしをつくれば、多様になるのが自然だと思う。
僕は旅をする中で、料理をするのが大好きになった。
「料理=レシピ通りに作らないといけないもの」という思い込みがあったときは、料理はなんだか退屈でできれば誰かに任せたいと思っていた。
でも、よく考えれば料理にレシピなんて初めはないはずで、どこかの誰かが作った創作料理や偶然の産物が長いときを経て、「うん、これは間違いのない組み合わせだね」だと大勢の人たちが合意したものに過ぎない(ちなみに、チーズは旅人がラクダに牛乳を乗せて運んでいたら、日光の熱で発酵して偶然できたらしい🥛🐪)。
旅先で出会う多くの人たちは、「どれだけレシピに忠実につくれるか?」よりも、「今あるものでどれだけ美味しいもの、美しいものがつくれるか?」というチャレンジを愉しんでいた。
僕も彼らにならって、自分の感性のまま、今まで見聞きし、味わってきた食の経験を織り交ぜながら料理を作ると、わりと毎度好評をもらえるし、個人的にも合格点を超えるものを作れることを知った(これが続くと天狗になりそうなので誰か鼻を折ってほしい👺)。
「料理って、白いキャンバスにのびのびと自由に絵を描くようでめっちゃおもろいなぁ」としみじみ感じる。
暮らしだってそうだ。

不動産会社や広告会社のプロフェッショナルが提案する生活様式、暮らし方だってその人に合っていれば最高に愉しいと思う。
でも、すべてが他の誰かがつくったものでまかなわれるとちょっともったいないとも思う。
自分が少し手を加えるだけで、暮らしがオリジナルのアート作品になるのに、その愉しみを捨ててしまっていることになるからだ。
電車から見えた景色
昨日、電車に乗って高知の田舎町から都心に向かうとき、夜の街にポツリ、ポツリと光って浮かぶマンションの部屋がいくつか見えた。
キッチンの場所や壁の質感、カーテンやライトの色はどこか似通っていて、少しだけ違和感を感じた。
そこで営まれる暮らしをアートと捉え、その地域にあるもの(食べ物だけじゃなくて、たとえば捨てられるはずだった衣服や廃材でもいい)を活かして人々が生活していたら、アパートやマンション、町全体が展示会のようになって、人間がもっとイキイキと愉しくと暮らせるだろうなとワクワクした。



社会は暮らしの集合体だから、そこにあるものを活かす人が増えれば、自然と過剰な消費は減ると思う(=ゴミも減る)。
そうなると、「もっと、もっと」とお金を無理に稼ぐ必要もなくなる(もしくは、稼ぐ目的ができるかもしれない)。
違うことを愉しめたら、人と違うことに恐れを抱く必要もなくなる。
そして、暮らしの知恵を分かち合う理由ができるから、人々がもう一度つながれる。
「暮らしをつくる」って、(手間はかかるけど)割といいこと尽くしかもしれない。
最後に言葉のおすそ分け
最近、心から共感するこんな言葉と出会った。
未来でもっとも評価される高等技術は、狭い土地で快適に生活する技だろう。
決して広くない住処でも、僕たちは人間は創造的に、びっくりするほど豊かに、快適に生きられる。
それを実践する人たちと出会っちゃったもんだから、信じるしかない(笑)
しれっと発表するけど、実は僕たちの移住先が決まりそうなんだ。
暮らしや生業をつくる舞台が決まったら、やりたいことが山ほどある⛰
(山ほどあるけど、急がず焦らず、かしこく力を抜いて愉しく軽やかに🍃)
そんな暮らしの様子も、ゆっくり何らかの形で発信できたらと思っているよ。
いつもありがとう。
おかげさまで、生きています。
また逢う日まで👋
Hide
P.S.noteでサークルを始めたよ🐑
僕たちが移住先と出会うまでの旅のプロセスをほぼリアルタイムで、一緒に愉しめるコンテンツをつくっているので、ご興味があったら見てみてね👋
noteを読んでくれてありがとう! 僕らしく、優しさのリレーをつなぐよ。
