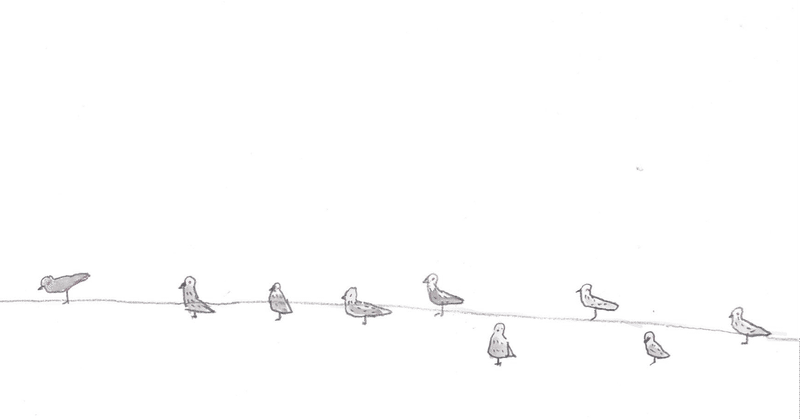
あこがれる文体と、「好きなことを仕事にするか」という命題への一次回答
文芸誌を手に取った
遅いタイミングとは思いつつも、文学ムック「ことばと vol.7」を読んだ。2023年11月上旬に刊行済。「第五回ことばと新人賞」の受賞・佳作作品と選評が掲載されている。
先に断っておくと、私はこの新人賞に応募したわけではない。経緯としてはちょっと回りくどいが、私は朝日新聞ポッドキャストの熱心なリスナーだった。朝日新聞つながりで本の情報サイト「好書好日」も知っており、そのなかのインタビュー記事「小説家になりたい人が、なった人に聞いてみた。」で、ことばと新人賞の池谷和浩さんへのインタビューを読んだ。読んだタイミングが、長編物語を書き上げて、物を書くことについていろいろ考えをまとめていた時期と重なっていたので、印象に残ったのだった。
物語を書いているが、文芸誌といったものをあまり読んだことがない。でもいざ開いてみると既視感があった。友人が作っていたミニコミ誌の豪華版だな、と思うことにした。と言うとどちらに対しても失礼なのかわからないが、秒単位で情報を伝えようとする世の中にあって、投げ手にしても受け手にしても時間をかけるという世界で、真っ向勝負をはかっている意味ではどちらにも敬意がある。
初めは新人賞の受賞作ってどんなもんかな、という好奇心で手に取ったが、選考座談会(江國香織、滝口悠生、豊﨑由美、山下澄人、佐々木敦)にもかなりのページ数を割いていた。
偶然が重なった経緯から、まったくの傍観者として読む選評は、それでも物を書く者としてかなりスリリングだったし、言い方が許されるのであれば、抱腹絶倒だった。というのは、自分だったら立ち直れないかもしれないと思うほど辛口批評だったからだ。
普段、本の帯に書かれている推薦文は、歯が浮きそうなほど褒めちぎられているもので、オブラートに包みながら痒いところに手が届くような評価が羅列してあるのを想定して読んだので、切り刻まれている最終選考者方に同情を禁じ得なかった。
受賞作「フルトラッキング・プリンセサイザ」、佳作「おとむらいに誘われて」以外の作品は本誌掲載はされていないので、選考委員の方々の用いる単語や選評内容から推しはかるしかない。それだけに抽象化されて自分の作品にも重ね合わせることができた。先にも申し上げた通り辛口というか真剣すぎる講評なので、苦し過ぎて逆にもう笑うしかなかった。
目指す文体、文学形式
「ことばと」という誌名に相応しく、新人賞以外に掲載されているどの作品も作者ごとに「言葉」と向き合ったものだった。もはや言語学の森だ。
自分はここまで「言葉」を拠り所にして全振りはできないだろう。私にとっては言葉は絵筆や絵の具のようなものではないかもしれない。あくまで工具(ツール)寄りだ。「赤」と言ったら赤以上の赤を表したつもりはなく、読者に対しても赤以上の赤として受け取ってもらうことを期待しない。期待しなくても、読者の記憶の中で「赤」は多様に広がり続けるからだ。
自分の文体が生み出す説得力はほとんど論文調になったらいいなとさえ思っている。ファンタジーではあっても、このファンタジーがいかに自分にとって現実なのかを説明できたらいい。noteの文体は物語よりもさらに硬質寄りになるように実験してもいる。
そこまで考えて、自分の目指す文体はスウィフトの「ガリヴァー旅行記」に近いかもしれないと思った。あくまで日本語訳から推し量るしかないのだが。
若干不本意ではある。スウィフトが緻密に風刺をこめていたとしても、印象としては無骨だからだ。まだ私には、現代にあって「ガリヴァー旅行記」がどれくらい褪せてないのか判断できるほどの読書経験がない。それでも「女性の乳房を顕微鏡的に至近距離で見たらすごいグロテスク」と表されている描写力というか、インパクトというか、納得感というか、とにかくハッとさせられてしまった。
「ことばと」の世界観と、自分の目指すところは違う。それが分かっただけでも文芸誌としてある文学形式をまとめてあり、それを発見できた経験は大きい。
文学形式としてもはや手がつけられていない領域はないだけに、ただやってみたとか、これをやればセンスがいいと思われるだろう、という姿勢では通用しないということは、選評からびしびし伝わってきた。選考委員の方々でさえ、なんとか言葉を駆使して、「読んだけどなんかモヤモヤした」というところで評価を終わらせずに形にしようとするグルーヴ感がとても面白かった。
自分の作品で、踏み込みきれなかった、こだわりきれなかった、「まいっか」と思ってしまった言葉や符号へのこだわりに攻勢を緩めてしまったという意識に容赦無くグサグサと刺さってきた。
そんななかで、自分が何を書きたいのかを、それこそ瞳孔がバキバキに開き切るくらいに目を逸らさなかったということを、誰よりも自分が知っているというのが最後の拠り所になった。
「好きなことを仕事にするか」という命題
作家を目指すかどうかを、「好きなことを仕事にするか」という命題とつなげて考えられることがある。「しない」理由は、好きなものごとに真正面から取り組んだら、人生がそれ一色になったら、「好きなことを楽しむ」ことができなくなってしまうかもしれないという心配からだ。自分の核にあることで傷付いたら、自分の逃げ場がなくなってしまうから。
ある側面ではそれも真実だろう。自分を守る必要のある局面や、次の局面まで自分を連れていくための乗り物として、今の興味が存在していることが確かにあるからだ。だからそういった思いに対しては、いま目の前にあることをやる、というよくある回答に尽きるのではないだろうか。
それが物足りない場合には、「楽しんでいる自分」を守ってくれるのも「これ以上ないくらい本気の自分」だったりもする、自分を差し出さないと得られない愉しみもある、と私はここに証言しておきたい。
何者でもないアラフォー女性が、35万文字の物語を完成させるためにやった全努力をマガジンにまとめています。少しでも面白いと思っていただけたら、スキ&フォローを頂けますと嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
