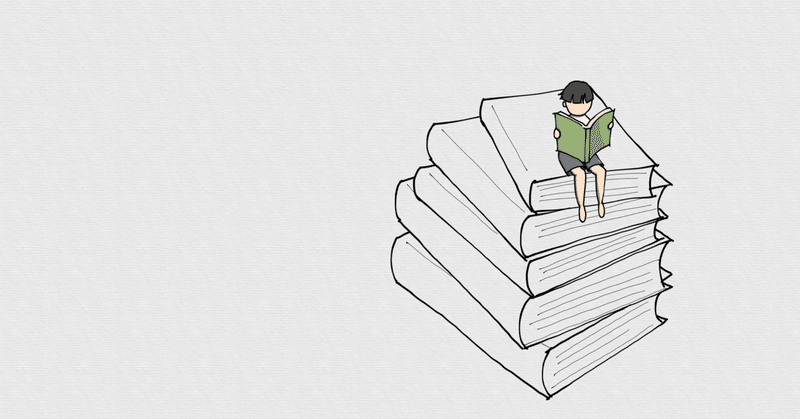
第三稿。テーマやオマージュとのすり合わせ
テーマをどう設定するか
35万文字の物語を作り終えて、2作目に取り組み始めている。次は10万文字以内で仕上げたいものだ。ただし1作目を補完するような物語にしたいとは考えている。
つまり根源的なテーマは変わっていない。根源的に語りたいテーマとしては私は狂信的と言っていいほどに「掴んで」いる。少なくともそう思い込んでいる。
ただその超大テーマを語るための、派生的なテーマは変えられる。切り口をどうするか考えるために資料をあたる。
他の人はテーマ探しをどんなふうに行うのだろうか。読んだ本の一節や、町で見かけた風景、書いてみたいシチュエーションから膨らませていくのだろうか。
私は一つのボールを投げられると十個〜数十個の発想が、四方八方に火花のように広がる。学生時代から五感を使って作ることを訓練してきた癖のようなものだと思う。収拾がつかないほど広がる妄想を楽しんでもいる。だから、小さな発想の種を育てて行って、ひと繋がりに物語を作るのは本当に向いていないと思う。どこまで行っていいのかわからないから、どこまでも振り切ってしまう。
まずは発想のハブだとか枠組みを作ってしまうところから始める。サッカーで言うとフィールドの白線を引くようなものだろう。
第一作目で概念のハブとなるものの一つに「樹」があった。「樹」といえば地面から上に生えているものを思い浮かべるが、それが植物の全てだとは思えないので、ちょうど執筆開始時に話題になっていた、スザンヌ・シマードの『マザーツリー 森に隠された「知性」をめぐる冒険』を読むことになった。何となく気になった、という程度で手に取ったけれど、この本を選んだことが作品作りの成功を決定づけたと言える。成功というのは、まとめ上げた、という意味で。
2023年発行の新刊だし、線を引きながら読みたいしで、新品を買うしかなかった。痛い出費である。
結果として私は植物のみならず、植物と菌との共生関係や、菌が媒介する植物同士のネットワークを学ぶことになり、物語の舞台裏にも強固な支柱を建てることができた。
成功体験を元にして、二作目も論理の拠り所にできる、それなりに体系化された本を設定しようと思っている。
手持ちのカードで戦うことと、限界に挑戦することの均衡
誰にも知られていない、完全なる自主制作で、どうしてここまで気合を入れ、私財を投入して打ち込むのか。
誰にも頼まれてもいないのに……私が情熱を傾ける理由はまさに、誰にも頼まれてない、誰も私が作ることなんて求めてないことにこそある。
ちょっと前の私は、胸の中にこんな妄想を抱いていた。
ある日道の向こうから、身なりのいい老紳士が歩いてきて、自分の前で立ち止まって曰く
「なかなかいい目をした若者じゃないか。どれ、ひとつ私の手伝いをしてはくれんかね?」
彼は知る人ぞ知る大会社の、引退した創立者だった──。
自分はその幸運を掴み取る野心や能力を、今は燻らせているだけなのだ。誰かに見つけられ、選び出され、能力を開花させられるのを待っているだけなのだと。
──生まれて数十年。そんな老人は現れなかったし、これからも現れそうにない。その前に、道を歩く向こう側に老人が突っ立ってたら、身なりがいいかどうか判断できないほど離れているうちに、道を変えるか、反対側に移動して早足に通り過ぎるような臆病者だってことを忘れていた。まして私はもう若者だと胸を張って言える年齢ではない。
何が言いたいかと言うと、私が生きるべき世界は、解くべき問いが用意されていて、できるだけ高得点で解いたもん勝ち、というものとは違っていたことに、やっと気がついた。
誰もそれが面白いと思っていないところに、自分で問いを立てて挑んでいく。その着眼点がいいか悪いかも、ある種のギャンブルなのかもしれない。
あまりお金をかけず、自分の知っている範囲で話をまとめ上げる力も必要だと思う。知りすぎることは必ずしも発想を広げることにはならないから。一方で、自分が立てた問いそのものが、もはや誰かが一度は考えたことがあることで、知ることでより一歩問いを深めることもできるのだ。あらゆることの境界線を探っていくのはスリルがある。そこに挑戦を見出すから、物語制作が単なる現実逃避ではないと、胸を張って言えるようにもなる。
第三稿でテーマに立ち返る

第二稿は紙→Wordに移し替えていき、その過程で補足や修正を行なった。三稿は全ての原稿をプリントアウトし、片手に赤ペンを持って推敲した。
普段はPILOTのJuice up 0.3mm極細ペンを偏愛しているが、推敲用のペンはZEBEAのSARASA CLIP 1.0に落ち着いた。滑らかで、ノック式なのでどこでも作業ができる。太いので句読点を補った箇所も目立つ。
二稿まではとにかく「作り上げる。完成させる」ことに熱量を傾けた。三稿は全体を再度見返して、テーマがぶれていないか、オマージュした作品を毀損していないかを丹念に検証した。オマージュ作品を再度読み返しもした。致命的な勘違いがあれば、自分の作品も全て破綻するからだ。
あらゆる手をつくし、35万文字を3周もしているのだ。書き終えた今、ちょっとやそっとのことでへこたれる必要はないと感じるようになった。
我を誰と心得る。たった一人で35万文字も書き終えたアラフォーぞ?
なぜ物語制作に情熱を傾けるのか
アラフォーは働き盛りである。私だって、40歳までに自分のやるべきことが見つかり、しかもそれが社会の歯車を回している実感を持てることであればいいと願ってきた。平凡な人間だ。
……とは思ってきたけれど、おそらく私は何かが決定的に違ってしまっている。人がこうすればうまくいくと言うことで、うまくいくことができない。
自分には言いたいことがある。当然、それが真実だと思っている。多くの人がそこまでこだわる必要がないことを信じている。
私は多くの物事に「あと一歩」のところで「まいっか」となってしまう。本当はその「まいっか」を踏み込めば、すでに人がこれと認めた枠組みに属することができたような気がする。でも、その「まいっか」とは「人生なんてこんなもんよ」の「まいっか」ではない。いわゆる、釈然としない物事に留まるために「まいっか」を使えない。
なにかを作り上げる下拵えをするにあたっての、「とりあえずここはこれくらいでいいか」の、離れるために「まいっか」を使っている。人間関係や、社会生活に、最後の最後で重きを置けないのはそのためだと思う。
物語を作ることは、そんな私が唯一「これだけはまかりならん」と思えることの集積である。そして、これでさえ「まいっか」となってしまったら、もう私にはいよいよ何もなくなってしまうのである。
これが私にできる残された最後の何かだったらいいなと思っている。とは言えそれがもし違ったとしたら、一旦はその失意を受け入れて、何年か飼い慣らした後、痛みとともに過ごした時間のことを、また語りたくなるんだと予想する。だから、物語を作ることが私に残された最後の一つだと信じている。
何者でもないアラフォー女性が、35万文字の物語を完成させるためにやった全努力をマガジンにまとめています。少しでも面白いと思っていただけたら、スキ&フォローを頂けますと嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
