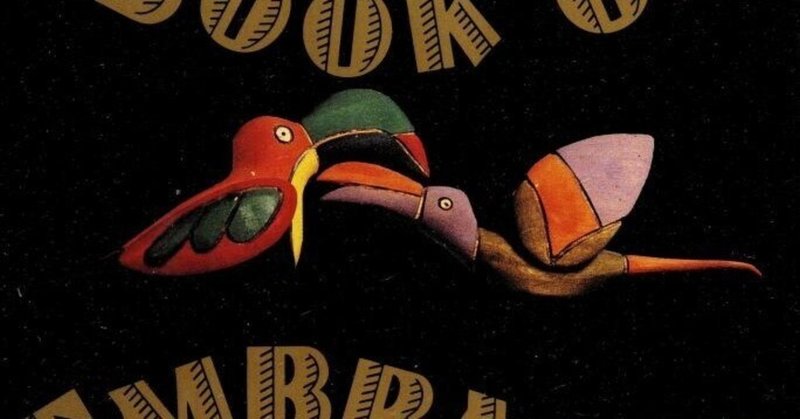
Christmas Eve By Eduardo H. Galeano
毎年、クリスマスが差し迫ると、エドゥアルド・ガレアーノというジャーナリストによって語られた短い話のことを思い出す。彼がフェルナンド・シルバというニカラグア人の医師から直接聞いた話であるようだ。それが「クリスマス・イブ」という題で文章化され、英語に訳されたものが『The book of embraces』(1991)という本に収められている。現在ではInternet Archiveで閲覧可能になっている(p.72)。とても短い話なので、ここに和訳しておく。
マンガグアという町にフェルナンド・シルバという男がいた。彼は町のこどもたちのための病院を営んでいた。
あるクリスマスイブの日のことだった。彼は夜遅くまで働き詰めていた。外から爆竹の鳴るのが聞こえ、花火の夜空を照らすのが見えたときになってようやく、彼は仕事の収めどきだと思った。家に帰ってお祝いをしなければならなかった。
万事が平常であるよう、彼は最後の巡回をした。そのときのことだった。 背後から足音がした。消えいるようにやわらかい足音だった。ふりかえると、病気のこどもがひとり、あとをつけてきた。ほのぐらい灯りのなかにくっきり浮かびあがったその顔には、死相が刻まれていた。もう死から逃れられない。ゆるしを請うような目をしていた。
フェルナンドが歩みよると、男の子は手をさしのべて、口をひらいた。
——だれかに知らせほしい。
声は、ささやくように口走った。
——ぼくはここにいるんだって。だれかに知らせてほしい。
クリスマスまで残すところわずかになった。けれども、今年だけはクリスマスがやってくる気がしない。やってきたとしても、それがもはやクリスマスだという気がしない。クリスマスというのは、暗闇や寒さのなかで人のぬくもりが際立つ日である、と思う。クリスマスには、小さく寄り集まる人のぬくもりを世界そのもののぬくもりのように錯覚させるような魔力がある、はずだった。世界が闇に包まれたとしても、求めればぬくもりは与えられる。どこかに必ずぬくもりはある、と思わせるような。
しかし、今年はただ、身も蓋もないほど暗く寒い。もはや人のぬくもりが人のぬくもりではない。たしかに、人がいまこうして悲痛な形で大量死をしていることは、それ自体としてはそれほど驚くべきことではないのかもしれない。普段は見えてこないだけで、本当はこの世界にありふれていることなのだ。けれども、それが重大な国際問題として世界中の目に晒される形となり、それでいてそれをだれも止めることができないのは、いったいなぜなのだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
