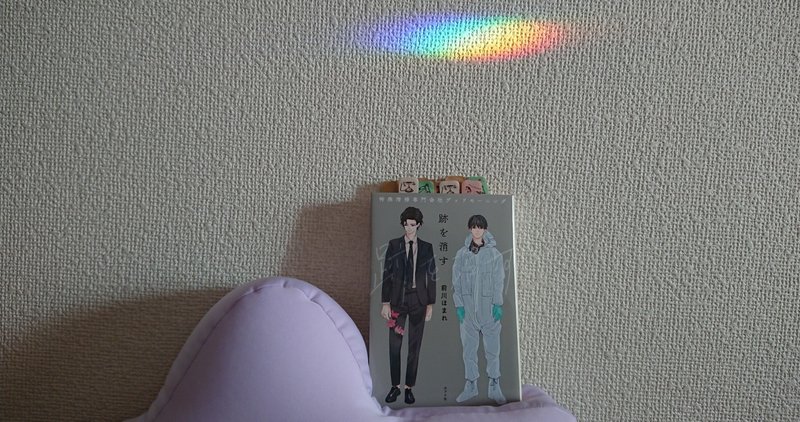
「骨のないクラゲと骨のあるクラゲ」死者と生者が交差する現場の物語を読んで
読書感想文なんて高校生以来だから、約20年ぶりのことで要領がつかめない。まずは本を選ぶところから始まった。課題図書56冊にさっと目を通す。一番今の自分にピンときたのが前川ほまれさんの『跡を消す 特殊清掃専門会社デッドモーニング』(ポプラ社)だ。最近はマンガでもこの手の話は多い。興味本位でちらっと見たことがあった。この手の話というのは、わけありの死に方をした人たちの部屋の清掃、つまり死の痕跡を消す仕事の話だ。(※以下、多少引用やネタバレあります。)
物心ついた頃からあの世とかオカルト系、怖い話がなぜか好きで、特に死にたい願望はないけれど、死に関しては定期的に考えていた。死にたい願望がないことについては、この本の中にまさに理由がズバッと書かれている。
「人生への過度な期待は、毒になりますから」
「確かに、期待さえしなければ、落胆することもない。過度な希望がなければ、大きな絶望もないね」
「僕は、あの日から全てを捨てた。もう、あんな悲しみを味わいたくないんだ。身軽になれば、大切なものがなければ、期待しなければ、生きていける……」
この物語の主人公・浅井航とそのバディとなる笹川啓介の会話だ。この会話こそ、私が死にたくならない理由で、人生に期待なんてしていないから、何かに挫折して死にたいとか考えずに済むのである。フリーターの浅井は夢や希望なんて持たずにクラゲのようにぼんやりと漂いながら適当に生きていた。特殊清掃専門会社・デッドモーニングを経営する笹川と出会って、彼の人生は少しずつ変化していく。
読み始めた時、笹川はいつでも冷静で、正しい判断ができて、やさしくて、心が広くて、紳士な大人という印象を持った。けれど、物語が進行するにつれて、良いイメージしかない笹川はどんどん崩れていった。逆に、浅井の方は当初、典型的なフリーターらしく、何も志すものもなく、堕落した生活を送っていて、魅力を感じない人間だったのに、浅井の仕事を手伝うにつれて、どんどん人間味が出て来た。魅力的なクラゲに成長していった。過酷な仕事上で、仕事帰りのプライベート飲みで少しずつ距離が縮まって、二人が仕事仲間ではなく人間として向き合った時、完璧に見えた笹川の心は実はとても繊細でもろくて、逆に浅井にはそんな笹川を救いたいという強い志が芽生え、やさしくたくましい心の持ち主に成長していた。
いきなり二人の出会いから最終場面までの印象を書いてしまったが、死んだ人が残した痕跡を消すことは並大抵のことではないということがこの本を読んで、一番の収穫だったと思う。故人が残した生活用品などは物だから、まだ片付けやすい。故人の身体の痕跡は特殊薬品を使わないと、なかなか消すことは難しいらしい。遺体の発見が遅れれば遅れるほど、体液が染み出して、床下にまで広がってしまう場合もあるらしい。それは強烈なにおいも伴う。実際、笹川の仕事を手伝い始めたばかりの浅井もその悪臭に耐えきれず、逃げ出してしまうシーンもあった。自分の身体に染み付いていないか、仕事の後は自分のにおいを嗅いでしまう癖もついた。
においは記憶に残りやすいと聞いたことがある。においとセットでにおいがした場面も蘇りやすいと。自殺や孤独死で亡くなってしまった人たちの部屋を毎日清掃していたら、そのにおいと共にその部屋の光景も目に焼き付いてしまうだろう。笹川の会社では何人ものバイトがすぐに辞めている。ある意味、それが当然で、その方が人間としては自然で、特殊清掃業を長く続けられている方が異常だ。そう、まともそうに見えていた笹川はとっくに病んでいた。救命士なのに自分の娘を助けられなかったという無力感、後悔から人の死と向き合うようになった。人の命を救うことに誇りを持っていた男は、今度は死んだ人たちを救うことによって、永遠に明けることのない夜の闇の中で娘の死と向き合い続けていた。まるで罪滅ぼしのように、亡くなった人たちの痕跡をキレイに消し去り、最後はちゃんと弔った。仕事の時以外は日常的に喪服を着て過ごす。娘の死から立ち直れずにいた。そんな笹川の事実を知った浅井は「命あればクラゲも骨に会う」ということわざの通り、大切な信念をみつけて、次第に本当に骨のあるクラゲとして浅井の分厚いカーテンに閉ざされた心を救ってしまう。
主人公が退屈な人生を過ごしていた当初はスローペースで読めていたのに、笹川との距離が縮まるにつれて、人生に意義を見つけ出した途端、ゆるやかに感じていた物語自体が加速して行って、読み進めるスピードも速まった。この辺は、話の展開上手な著者の力量だろう。著者は看護師だったということで、専門的な医学知識も随所に散りばめられており、読んでいて為になった。幻肢痛にはミラーセラピーが効くとか、前頭葉は人間の感情を司る大事な場所とか。一見、仕事の依頼者や職場の同僚の話に過ぎないけれど、実はそれらは笹川の心情を表していたのかもしれない。大切な人の死は幻肢痛みたいなもので、実際はもう存在しない箇所が痛むから痛み止めさえ効果ないってまるで娘を亡くした笹川の心情だ。よく例えられる、身内が亡くなって右腕をもがれた気分になるっていうあれだ。それから前頭葉がやられてしまって、自分の感情がコントロールできない。認知症のように怒るとか物忘れがどうとかではないけれど、娘の死によって喜怒哀楽の中で、喜びも楽しみも消え失せて、彼には哀しさしか残っていなかった。魂の抜け殻のように。生きているのに、笹川はまるで死体みたいだと思った。
笹川と出会ったばかりの頃のクラゲみたいな浅井もある意味、死体みたいなものだった。期待も希望も持たない生き方は死んでいるみたいな生き方だから。つまりクラゲという比喩そのものが死体を象徴しているのかもしれない。クラゲに骨を持たせれば生きた人間になれる。死体の痕跡を消すことを生業とした二人こそ、死者みたいな生者だった。様々な死の現場と向き合うことによって、現場で故人の小さな骨の欠片をみつけて苦労して洗浄した浅井はいつしか自身の骨もみつけ、笹川は娘を亡くした過去から浅井の手を借りて脱却し、未来に向かって進めるようになる。
死の現場で生をみつけるってなんだか皮肉な話だけれど、人間が生きるってこういうことなんだと思う。誰も死からは逃れられない。それが自死であっても、老衰であっても、生まれた限り、死はいつか必ず訪れる。死を悟って少しずつ身辺整理をして、生活用品を最小限に生前、片付けておくことはできないことはない。でも最後までどうしても手放せないのが身体という所有物で、身体だけは残ってしまう。家族や同居人がいて、すぐに死に気付いてもらえたら、腐敗が進む前に埋葬してもらえるから良いけれど、孤独死などで気付かれない場合は悲惨で、そんな時は笹川や浅井たちの出番となる。自分の身体って物と同じで借り物なんだなと死をみつめることによって気付いた。自分自身と思い込んでいるけれど、死ぬ時、残るってことは抜け殻というか、物なんだなと。自分って一体何なんだろう?実体はどこにあるんだろう?と考え出すと大幅に脱線してしまうので、それは割愛するとして、身体をあの世に持っていけないのは生きている人たちに申し訳ない。片付けてもらうことになるから。
人間以外の野生の生き物は、捕食者が死体を片付けてくれるらしいから、自然ってうまくできていると思う。人間だって虫が湧いて、虫が捕食してくれると考えられなくもないけれど、自然界の生き物と比べたら、痕跡が残ってしまう。残ってしまうというか、残しているのかなとも考えられる。生に執着するみたいに、この世に生きた痕跡を残すみたいに、身体は置いて死んでいくのかなと。身体を置いていけば、虫の栄養源になり、体液が染み込めば大地や自然に還れる。つまり地球の生の営みの一部として循環できると考えられなくもない。しかし現代社会の都会においては自然に還るまで放置することは難しいので、特殊清掃が必要になるのである。
つまり特殊清掃は人間社会ならではの文化というか、もしも大自然の中での死なら捕食者や自然の雨風のおかげで風化できるからそんな仕事自体必要ないわけで、人間が文明を築き上げてしまった負の遺産とも言える。でも痕跡が残りやすい状況だからこそ、浅井も笹川もそんな現場から、死人の痕跡から生きる力や骨をもらえて、心救われたとすれば、負とは言い切れないか。
「全く同じ死なんてないということだけ。死を迎えた状況も違うし、遺族の反応だってバラバラだ。」
「どうして同じ死はないんだと思う?」
「全く同じ生き方なんて、ないからだと思います。どんな人生にもそれぞれの苦悩があって、孤独があって、悲しみがあって、そして幸福があります」
同じ生き方も同じ死もないけれど、形は違っても死は誰にでも平等に訪れる。死者の痕跡、死をみつめることでその人の生前まで遡り、ひとりひとりの人生を顧みる作業までするのが笹川と浅井の生業だ。単純に悪臭を消したり、生きた欠片を片付ける仕事ではなく、人の人生を見つめ直す最後の番人というか、お寺の住職さん並みに尊い仕事で、だから結局は清掃した人たちの心まで洗われてしまうのかなと思う。
死は生き物が生き物に残せる最強で最後のプレゼントみたいなもので、悲しいし、つらいし、遺体は腐敗して臭くなるし、死に場は壮絶な環境には違いないんだけど、でも故人の人生と向き合うことによって、自分自身のこれからの生き方を考え直せる点で、これほど人生経験が豊かになることはないと思う。まさに身をもって生きるとは何か、死ぬとはどういうことかということを生きている人たちに示してくれて、死とはどんな死に方であっても尊いものであると考えられるのである。できれば大切な人たちや自分の命は失いたくないけれど、いつかは必ず訪れる避けられない死を改めて考えるきっかけをくれた本だった。
最後に社名が「デッドモーニング」=「死んだ朝」から「グッドモーニング」というたった一文字違いだけれど、真逆なイメージの社名に変更された時、個人的には「デッド」のままで良かったなと思った。浅井が「今年は、この事務所を朝日が差し込むような明るい場所にしたいです」と意気揚々と言っていて、あの自堕落だった浅井が笹川を救うために急に明るくやる気のありそうな人間に変わって、骨のないクラゲみたいな浅井推しだった私は、一気に彼から心が離れてしまった。逆に「僕は、あの夜の中で生きていればいいんだ。これからも、ずっと。」と喪失感から抜け出せない笹川の本性が見えた時、私は笹川推しに変わっていた。どうしても陰鬱とした雰囲気のキャラの方に惹かれてしまって、同じく、素敵な朝を迎えられなくても、長い長い夜の中で微かな蛍の光みたいなものを頼りに生きていたっていいじゃないかと浅井に反抗したくなったから。死んだ朝の中にいても、死なずに生きているなら、それでいいじゃないかと。
そっか、浅井が救命士だった笹川の頃を救命したことになるから、特殊清掃のおかげで心の救命士になったということになるのかな。骨のないクラゲ(死者)フリーターから他人様の骨を拾って自分の骨をみつけて特殊清掃業を誇りに思えるようになって、ついには上司の心を救う骨のあるクラゲ(生者)救命士になったということか。
骨のあったクラゲ(生者)みたいな笹川は救命士で挫折して、特殊清掃業で死を理解したくてひたすら死と向き合って、でもどんなにたくさんの死と向き合っても自分の心は救えなくて、自分の殻に閉じこもってある意味ニート時代の浅井と同じように心を押し殺したような暗闇の海を漂う骨のないクラゲ(死者)としてひっそり生きていた。
出会った時、真逆のような二人は話が進むにつれて実はとてもよく似ていて、立場が入れ替わっていくような展開がおもしろかった。
ここからは趣味の音楽の話も交えて、少し余談になってしまうけれど、本編第四章「私たちの合図」はクリスマスイヴの物語で、世間がクリスマスムード一色で妙にキラキラ華やぐ日に、一年前のイヴに事故で亡くなった同居人の片づけを依頼した女性の話とそれから、こんな日に飛び降り自殺の現場の清掃依頼が舞い込む話と、それから笹川の大事な娘の命日という三つの死が巧妙に展開するのだけれど、ここにこそこの物語の神髄があると思う。何を言いたいのかというと、生きるも死ぬも時間は選べないということだ。お正月だってクリスマスだって生まれる人もいれば、死ぬ人もいる。特に自死の場合、そんな世間が賑やかそうな時期だからこそ、自分が惨めに思えて死にたくなるというのは当然のことだろう。たとえ幸せの象徴みたいな時期だって死は避けられないんだということをあえてクリスマスを登場させることによって強く印象づけている。
そして趣味の話というのは、SEKAI NO OWARIの新曲「silent」がこの章にぴったりなので、この章を読む時のBGMにお勧めしたい。クリスマスを否定するようなサビの歌詞、雪で静寂に包まれる日は心の声が聞こえてしまってうるさいとか、スノードームとかこの章にも登場するモチーフが歌詞に登場するので、併せて聞いてみてほしい。
もうひとつ、趣味の話だけれど、全編を通して、著者はフジファブリックの楽曲を意識したのかな?と思える言葉遣いがあったことが実は何よりもうれしかった。
「笑ってサヨナラですか……?」
「桜の季節って残酷じゃないですか。周りを見れば、どこもかしこもサヨナラが溢れているから」
「グッドバイが溢れているならさ、また新しいハローを探せばいいじゃないか」
サヨナラってカタカナ表記までまるで『笑ってサヨナラ』って楽曲だし、『桜の季節』って楽曲もあるし、『Hello』って楽曲にはハローとグッバイが登場するから。
亡くなったボーカル・志村正彦もクリスマスイヴが命日だし、クリスマスの死が描かれた第四章が個人的には一番印象深いものとなった。
#読書の秋2020 #跡を消す特殊清掃専門会社デッドモーニング #前川ほまれ #跡を消す #ポプラ社 #読書感想文 #SEKAINOOWARI #silent #フジファブリック
この記事が受賞したコンテスト
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

