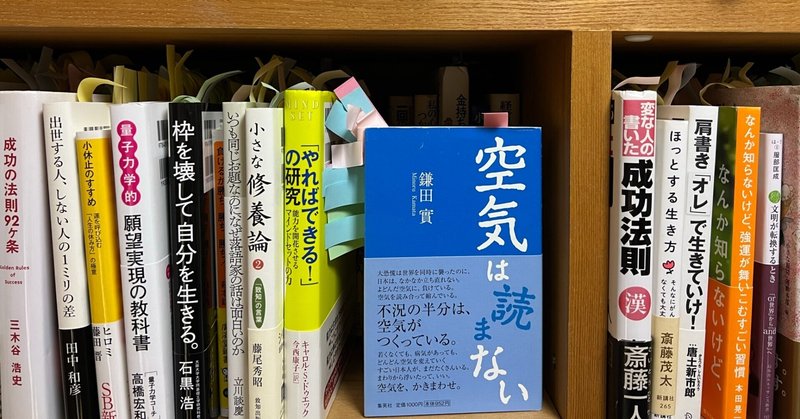
病院でのチェロの演奏
今日のおすすめの一冊は、鎌田實(みのる)氏の『空気は読まない』(集英社)です。その中から『「当たり前」病』という題でブログを書きました。
本書の中に「病院でのチェロの演奏」という心に響く文章がありました。
2002年の春、突然、山口さんという夫婦から電話がかかってきた。面識はない。話を聞くと、どうもコンサートの“押し売り”らしい。ヴラダン・コチというチェコのチェリストのコンサートを開いてくれないか、という。突然の申し出に、ぼくの態度は煮えきらなかった。
山口夫妻は食い下がってくる。すばらしい音楽家だ、と熱く訴える。何度か電話をもらううち、彼らは書籍のプロモーションが本業で、押し売りなどではないことがわかってきた。知人から紹介されたチェコ人チェリストの音楽と人柄に惹かれ、ボランティアで協力しているだけ。
コチが病院や福祉施設でチャリティコンサートを開けるよう、交通費から何からすべて持ち出しで奔走し、通訳やアテンドも引き受けているらしい。山口夫妻をこんなにも魅了したチェロを、ぼくも聴いてみたいと思った。コンサートの日がやってきた。
ヴラダン・コチは40代なのに少年のような顔をしていた。吹き抜けになっている病院のロビー。ふっと一瞬、天を仰ぐと、彼は弦に弓をあてた。初めの一音を聴いたとたん、ああ、すごいと思った。澄んでいる。音があたたかい。力強く、重く、それでいて、やわらかい。不思議なチェロだった。
コンサートは大成功だった。これほどの技量をもった男が、なぜボランティアでコンサートをしているのだろう。不思議に思いながらも、豊かなチェロの音色に、ぼくの心はわしづかみにされていた。
一年ほどして、また山口夫妻から電話をいただいた。今度は二つ返事で承諾した。そのころ、病院の緩和ケア病棟に、がんの末期を迎えた51歳の女性が入院していた。彼女は、蓼科の森のなかで小さなフランス料理店を営んでいた。お店ではいつもクラシック音楽を流していたという。
ロビーでホスピタルコンサートの話をすると、彼女はその日を楽しみに待った。しかし、彼女のがんは体じゅうに広がった。日に日に衰弱していった。コチの二度目のコンサートの日、ロビーに下りていく体力は残されていなかった。
どうしても彼女にコチのチェロを聴かせてあげたい、とぼくは思った。病院の二階にある緩和ケア病棟の、彼女がいる奥の部屋まで音が届くように、ドアをすべて開け放った。コンサートがはじまる一時間ほど前、ロビーでピアニストと音合わせをしていたコチに、彼女のことを話した。
「二階の病室で、あなたの音楽を聴いている人がいる。そのつもりで弾いてあげてください」すると、コチの目の色が変わった。即座にチェロを手にすると、彼女の部屋へ案内してほしいと言う。
「私は音楽を欲している人のために、音楽を届けにやって来ました。その患者さんのところで弾かせてください」病室に入ると、コチは柔和な笑みを浮かべて、彼女の手を握った。そして、チェロを奏ではじめた。言葉はいらなかった。バッハの『無伴奏チェロ組曲』に続いて、『浜辺の歌』が静かにはじまった。
まさか日本の歌を弾いてくれるとは思わなかったのだろう。彼女の目に涙があふれてきた。心にしみいるチェロの調べに浸りながら、自分の人生を振り返っているように見えた。演奏が終わると、コチは彼女にハグをして病室を出た。二人とも、いい笑顔を浮かべていた。
彼女は、かたわらにいたご主人に「ありがとう」と言った。すべてを受容したのだと思う。がんが末期であることも、自分の命がつきようとしていることも。そして、がんが見つかってからの半年、世話をしてくれたご主人に「さようなら」を伝えた。
それから、横にいたぼくの手を握った。「ありがとう。幸せです」命がつきようとしていることを自覚してなお、この女性は幸せだと言う。遠い異国からやって来た男の音楽が、病室の空気をあたたかく包み、一人の人間を「受容」へと導いたのである。すごい音楽家だと思った。
マザーテレサは、「死を待つ人の家」を開設し、行き倒れの人や、道端で倒れている瀕死の病人を見つけると、ここに連れてきた。
マザーは、「たとえ、人生の99%が不幸であったとしても、最後の1%が幸せならば、その人の人生は幸せなものに変わる」と語り、最後の瞬間を安らいだ気持ちで過ごしてもらうよう手厚く介護した。そして、ほとんどの人が、息を引き取るとき、「ありがとう」と言って亡くなったそうだ。
最後に、「ありがとう」と言ってあの世に旅立てる人は幸せだ。途中がどうであれ、この世を離れるとき、よい波動だけを残していけるからだ。「ありがとう」の言葉はどこまでもあたたかい。
本日のブログはこちらから☞人の心に灯をともす
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
