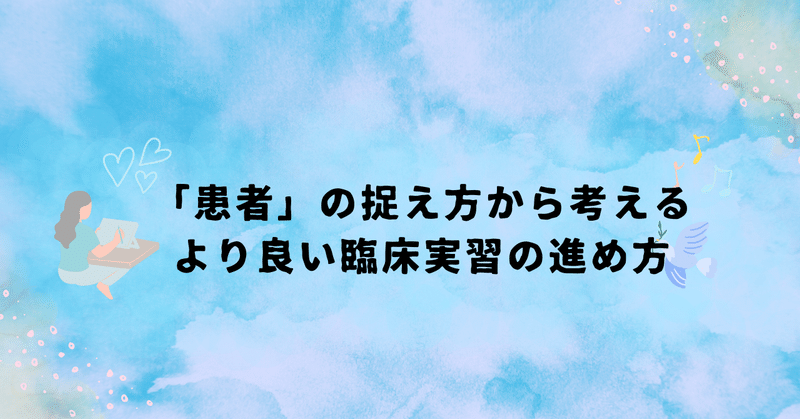
「患者」の捉え方から考えるより良い臨床実習の進め方
今回は自分が臨床実習に向かう前の学生に対して何回か話した内容ですが、医療従事者として、対象となる方の日本語と英語の視点の違いを整理しながら、臨床実習で良く学生の問題となる事象について考察と自分なりの解決策を提示していきたいと思います。
「患者」・「patient」:捉え方の違い
日本語:「患者」
日本語の「患者」と言う言葉は読んで字のごとく「病気や怪我を抱えている人のこと」を指します。
当然ながら、医療機関においては、患者は医師や看護師が治療やケアを行う対象となります。
この表現方法で言えば、患者の人は病気や怪我を抱えているので、医療従事者からすれば、一目見れば判る・もしくは検査結果から判断できると言えます。要するに外から見て判断できるとも換言できます。
英語:「patient」
日本語の「患者」に対して、「patient」と言う表現方法は、同様に病気や怪我をしている人を指しますが、それ以外の意味として、辛抱強く待ち続ける人を指すことがあります。また、派生語として"patience"は、辛抱強さや忍耐力を表す言葉であり、"impatient"は、辛抱強さがない、我慢できないという意味を持ちます。
これは一言で言うと、その人の心・気持ちの持ちようであり、外見や検査結果だけでは判断できない場合もあると言うことです。
視点の違いから言えること
上記の2つの用語はどちらも「病気や怪我をしている人」を指していますが、日本語の「患者」は外からの視点(医療従事者から見た視点とも言えるでしょう)に対して、英語の「patient」はご本人の内側からの視点であることが決定的に違っています。
同じ理学療法士・リハビリテーション専門職であったとしても、どちらの視点で目の前の対象者を捉えるか次第で問題点の立て方や目標設定が異なってくるはずです。同職者であれば、ICFで考えれば納得してもらえるかと思います。「患者」の視点で捉えてばかりだと、心身機能・構造や活動に偏り易くなりますが、「Patient」の視点で対話が出来ていれば、背景因子(環境因子・個人因子)や参加の項目まで広く対象者の状態を考えられるはずです。
学生には臨床実習に向けて、折に触れて英語の「patient」の意味を説明しながら、見学させていただく「患者」はどんな苦しみや不安・痛みに辛抱(耐えて)いるのか考えられるようにと伝えています。
臨床実習の常套句
臨床実習で学生が言われる常套句は以下の通り
疾患や病態ばかりを見て、その人自身を見られていない(見ていない)
学生(もしくは実習地訪問で教員)が一度は実習指導者に言われるこの常套句、自分ももしかしたら臨床で仕事していたときは一度は言っていたかも知れません。
確かに真面目な学生ほど学内で学んだ病態や疾患に関する知識をまとめて質問するでしょう。でもこれは果たして学生だけの問題なのでしょうか?
学生にこの常套句を言う前に、実習指導者としてやるべきことが出来ているのか、ここで問題提起をいくつかしていきたいと思います。
問診で目の前の患者から引き出しているか?
まず初めに、そもそもその実習指導者は目の前の患者から内面の悩みや葛藤を聞き出せているのか?と言った問題です。学生は実習中は基本的に見学を通して、介入中の内容や対象者の様子をメモに起こし、質問内容を考えている筈です。
一方で、介入中の対象者との会話がたわいも無い世間話に終始しているリハビリテーション専門職が少なくないことも事実です。信頼関係を築くために世間話から入ることを否定する気は全くありません。しかしながら、臨床実習で学生が来ている、その学生指導に当たっている場面においてもその様な世間話に終始していないか?ということがここで提示している問題点です。
個人的には学生が臨床場面を見学している時の対象者(ご本人が会話できない状態であればそのご家族など)との会話では、世間話では無く、問診の要素を取り入れながら会話をするべきと感じます。そうすることで初めて、見学中の学生が対象者の悩みや葛藤と言った内面にアクセスすることが可能になるのではと考えています。
学生が患者との対話に参加できているか?
見学中に問診の要素を取り入れて会話しているとして、次のstepとしてその会話の中に学生を参加させてもらえているか?が問題となります。
可能であるならば、介入中の会話に学生を参加させてもらいたい。それは、この会話が学生と対象者との対話の入り口となるからです。
直接対象者とコミュニケーションを取ることで、ただ見学でメモを取るだけでは考えられない内容(深さ)まで学生が考えられる様になるきっかけとなります。要は学生が自分事としてその対象者の不安や悩みを聞き取ることが出来る機会となるのです。
このように、可能な範囲から実習できている学生を診療場面の一部に参加させることを正統的周辺参加と呼びます。この正統的周辺参加の機会を増やしていく目的で、昨今言われている診療参加型臨床実習への移行が進められてきているのです。
正統的周辺参加の機会を増やすことで、状況に埋め込まれた学習の機会の創出に繋がり、その見学や体験を振り返りながら経験・教訓に落とし込むことが何よりも臨床実習で求められていることになります。
そのための第1歩として、普段の対象者とのやり取りから学生へ参加させることは臨床実習指導として重要なことと言えます。
この辺りの理論的背景は下記の書籍にまとめられています。興味があれば少しご覧ください。
一緒に考える時間を取っているか?
指導者が対象者の不安や悩みを会話から引き出せている、その会話に学生が参加する機会を造り出せている。そうだとして最期に、まとまったフィードバックの時間の中で学生-指導者間でその内容について考える時間を作れているか?が最期の問いになります。
ここまで来たら、学生と指導者で一人の対象者について議論することが大事になります。そして可能であれば、この議論は学生・指導者の立場を超えて、フラットな立場で対話が出来ると一番良いでしょう。
対話については下記の書籍が非常に参考になりましたので、ご紹介しておきます。
もちろん、学生の習熟度によって指導の質も変えなければ行けません。学生へ問を投げかけたときに、学生自身で考えを述べてくれるようであれば良いですが、いきなりそれは難しいでしょう。言語化が可能なところから焦点化するなり、部分的にでも指導者側の考えや意見を伝えながら関わる必要があるでしょう。つまりこの対話においてはティーチングからコーチングへの段階的な指導が求められます。
まとめ
ここまでの関わりをすることで初めて、学生は一人の対象者について全体像を捉えながら考えることが出来てくる筈です。
逆に言えば、ここまでの教育的な関わりをして初めて、先に挙げた臨床実習の常套句「疾患や病態ばかりを見て、その人自身を見られていない(見ていない)」に対する学生の到達度が議論出来るようになるのです。
一方で、学校で普段の授業を進めるだけではこのように実際の対象者を想定してここまで深く考えられる機会は造り出せません。
診療参加型臨床実習への移行する過渡期において、その大きな目的は先にも挙げた正統的周辺参加の機会を増やすこと、そこで得た体験を経験・教訓に落とし込むこと、その過程を通して臨床に必要なスキルを身につけることにあります。レポートの有無がどうこうと言ったことは手段の1つに過ぎません。
今後、教育に興味を持つ臨床家が増えていき、養成校と臨床現場が一緒に後進の育成について考える機会が増えていくことを期待しています。
ここまでご一読いただき誠にありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
