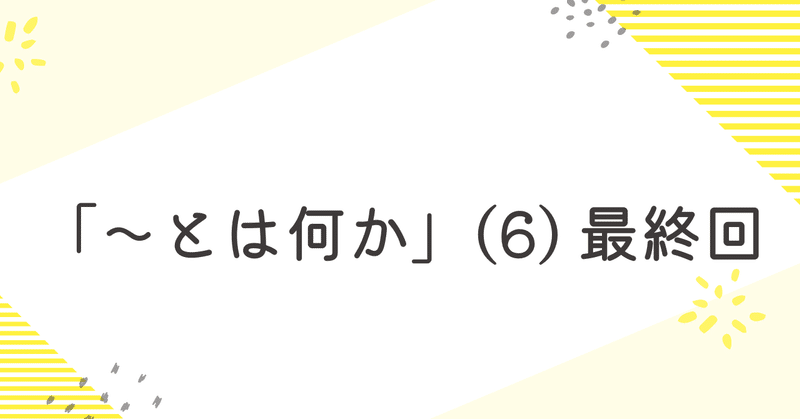
「~とは何か」(6) 最終回
本質観取
本質観取の方法は、基本的には、認識問題の解明のために内在的意識における事象の確信形成の構造を観て取るための(内的洞察の)方法である。
したがって、現象学が「確信成立の条件の解明」として理解されなければ、つまり「構成」や「ノエマ」の概念が正しく理解されなければ、「本質学」という理念も適切に理解されえない。
本質観取と言語ゲーム
本質観取は、そもそも「認識の謎」の解明のために、対象の確信構成の構造を観取する方法である。しかし、これはそもそも哲学の基本方法、つまり哲学の「言語ゲーム」の方法を原理化したものと考えることができる。
「言語ゲーム」は、ウィトゲンシュタインの『哲学的探求』に現われる概念だが、その主旨は、言語の「意味」は、「言語」に内在するものではなく人間どうしの言葉のやりとりの中で、相互に関係的な了解性として生成する、という点にある。
哲学者は何らかのキーワード(原理)をおいてこの「本質」を示そうと試みる。つまり哲学の原理とは、どのような言葉が「ことがらの本質」をもっともうまく説明できるのかを求めるものであって、何が真理であるかを示すことではない。
科学の観察と測定の方法は、事実(事物)の領域ではきわめて優れた客観認識を生み出すが、これを人文領域にそのまま適用することができない。
たとえば、「認識の謎」を解くためには、われわれ自身の内在意識における「確信構成の構造」を把握しなければならないが、この構造は実験装置によっては捉えられない。
各人の内省による内的な洞察を「言葉」に置換え、これを各人の間で(間主観的に)吟味してどういう言葉が誰にも納得できるものとなるかを確証するほかはない。
ハイデガーによる不安の本質観取を展開する
ハイデガーは『存在と時間』で人間実存についての優れた本質観取を行った。それは情状性、了解、語りという三契機で取り出したというものである。そこでは情状性、つまり「気分をもつこと」が現存在(=人間)の第一の本質とされたが、さらにハイデガーは「不安」の気分を人間の「根本情状性」と呼びその本質観取を行っている。
ハイデガーによる考察は以下である。
恐れは、たとえば強盗や病気、台風などという対象をもつ。
だが、不安は恐れと違って明確な対象をもたない。
不安の対象はいわば世界そのものである。
不安の主体は人間自身であり、不安の内実は、われわれの実存可能性(よりよく生きられること)に対する不安である。
不安の気分の本質は、「不気味さ」の気分、慣れ親しんで安心している世界から引き離されるという情動にある。
そのことから、その最も底には「死の不安」があることがわかる。
死の不安が差し迫るとき人間は日常的な世事から切り離されて「単独化」される。
こうして不安は、われわれを「平均的な居心地のよさ」の世界から引き離し、人間の存在の根底にある「寄る辺なさ」を露呈するものである。
竹田氏によれば、これが「本質観取」といえる理由は下記であるという。
第一に、ここで不安の本質は、外的な知識や情報に依拠せず、ただ自身の内的経験への内省だけから洞察され観取されていること。
第二に、他の情動である「恐れ」と対照しつつ、その特質が取り出されていること。このことで何が「不安」の本質と言えるかについて、誰にも納得される形で記述されていること。
第三に、誰であれハイデガーの内省による洞察を自分の内省によって追検証できるということ。
最後に、これがとくに重要だが、ハイデガーの洞察が不安の本質の最後の結論というのではなく、誰もが自分自身の内省によて不安のより深い特質を、これに付け加えてゆくことができるということだ。
量的研究と質的研究の本質連関
現在、量的研究/質的研究という区分が臨床心理学、教育学、看護学、介護学などの領域で行なわれ、量的研究が実証主義にもとづくデータ(エビデンス)を基礎とした研究を意味し、これに対して質的研究は、データでは捉えきれない人間的側面をカバーする方法とされている。そしてここでは現象学の応用ということがしばしば言われている。
この区分は、人文領域が、事実学的な実証主義だけでは捉えきれない側面をもつことについての自覚の高まりといえる。ただ質的研究における現象学の応用という点では、そもそも現象学理解が十分とはいえずーーー 一般には、本体論の解体、認識論の解明、本質観取といった現象学の根本方式はほとんど理解されていないーーーそのため質的研究のためのさまざまな方法が提案されてはいるが、基本的に主観的な解釈理論の域を出ていないように見える。
Kindle 版.
【哲学は、個人的な思考に耽っているだけで、何も社会の役に立っていないと言われている中で、現象学は広い分野で応用されている。それが適切に応用されていないということであれば、竹田青嗣、西研たちの現象学解釈を採用されていないからなのではとさえ思っています。】
【基本的に、ハイデガー流の「解釈的現象学」に基づいて刊行された放送大学の教材『現代に生きる現象学ー意味・身体・ケア ー』について数回以上投稿記事を書きました。それは、本書にも書かれていたように、看護については、ハイデガーの後期思想である彼独自の存在論的形而上学である「本来性」に踏み込まない範囲で応用するということであったので、竹田解釈とのズレを感じていなかったからです。
竹田氏も、ハイデガーの後期思想については批判的ではあるが、人間実存の本質観取については優れているということでしたので、問題ないものと、個人的には解釈している。】
引用図書:竹田青嗣著『哲学とは何か』
今回で「~とは何か」を終了します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
