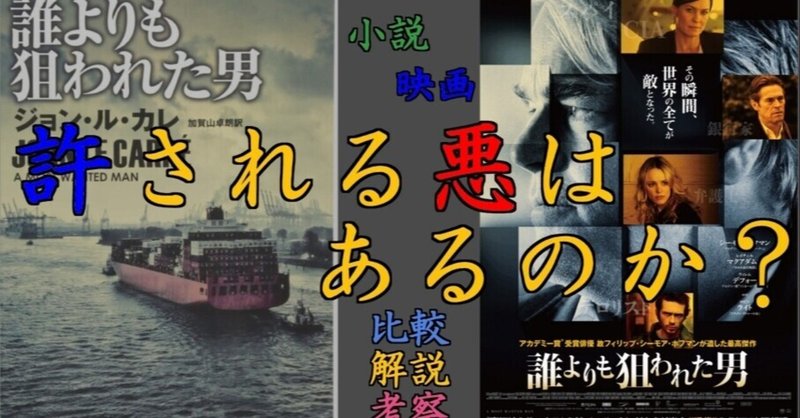
【You Tube】誰よりも狙われた男の原稿【スパイ映画】
という事で今回はマイナー作品…なのかな?アントン・コービン監督、主演、フィリップ・シーモア・ホフマン
そして原作、ジョン・ル・カレのスパイ映画。誰よりも狙われた男の小説版との比較、解説、ちょっと考察
といった事でやっていこうかと思います
で、この映画、ちょっと評判を見てみたのですが、あんま良く分かっていない人が結構いるのかな?っていう印象がありまして
まぁようはこの映画「何かが判明する」とか「何かが解決する」といった事を描く類の話じゃないんですね
じゃあ何を描いているのか?というと、我々の生きている日常、この作品の舞台はハンブルクな訳ですが
そのハンブルクの街中で、テロリストらしき人物を見つけた時のスパイ組織の反応、行動、思考
テロ容疑者発見から逮捕までの経過を再現している作品なんですね
「こいつテロリスト…?」ってのを見つけたら皆さんどうしますか?
やっちまえばいいんだよ!って人は日本の警察からすれば頼もしい人材かもしれませんが
まぁようは人権で固められている現代社会においてそんな事は出来ない
しかし、テロが発生してからでは遅い!
人権に最大限に留意しつつも、テロの発生だけは絶対に阻止しなければならない
それが現在の諜報機関の立ち位置である、という事になる訳です、となるとどうするか
観察し、情報を集め、どうにかして決定的な証拠を掴み、そこで逮捕する
という展開になっていくのは言うまでも無いのでしょうが
とはいえ昨今の世界情勢、といってもこの小説10年前の作品ですけれども
テロリストもそうそう簡単に尻尾は出しません。でも当然ですがテロを起こさせる訳には絶対にいかない
という極限状況の中でのやり取りを描いた作品って事なんですね。
だから本当に、捕まえた奴、マークしていた奴が本当にテロリストなのかどうか分からないんです。
分からないけど…、分からないけれども…っていう映画なんですね
って事でまず映画のあらすじをざっとおさらいしていきましょう。
主人公のバッハマンは小説によると【ドイツ連邦憲法擁護庁 外資買収課 課長】という肩書きのようですが
ご存知の通りそれは仮の肩書であり、彼はドイツのスパイですね
で、彼は過去に大きな失敗をして、現在ではドイツの中心であるベルリンではなく
港湾都市ハンブルクに左遷されていますが、まぁ当然、返り咲きを狙っている
小説版の表現によれば彼は職業にスパイしか選べない男、と表現されています。
映画版とはちょっと印象が違いますね。そして返り咲きのための目星はガッツリと掴んでいるようで
イスラムの学者であるファイサル・アブドゥラという博士がテロの資金提供者であるという情報を完全に掴んでおり
しかもその息子まで抱き抱えているという状況。お膳立てはバッチリです。
そしてそんな状況の中、ハンブルクの街にイッサ・カルポフという謎の青年がたどり着く事になります
ちなみに説明が前後しちゃいますが、このハンブルクという街。この街で911のテロが計画されたという字幕が
一番最初に出てきますが、何だってこんな事になったのか?というと
実は第二次大戦、ナチスの蛮行が発端なんですね
どういう事かというと、ドイツってのはご存知の通り戦争に負けて、戦争責任を徹底的に追求された国な訳です
日本はその辺まだちょっと曖昧にしていますが、ドイツはもう完全に自分達の非を徹底的に認める方向に舵を切り
【二度とナチのような蛮行を赦してはならない!】みたいな話になっているのはまぁ皆様もご承知の通りでしょう
ようは国家権力に対する監視の目、つまりスパイ活動みたいなものに対して非常に厳しくなってしまったという歴史があるらしく
しかもハンブルクというのは港湾都市であり、外国人は別段珍しいものではない。
行き過ぎた…ってのとはちょっと違うんでしょうが、しかし強い人権意識やリベラル思想の中で
皮肉にもテロリストがやりたい放題やれる土壌というのが形成されてしまっていた、という事らしいんですね
マジかこの国、やりたい放題やんけ!っていう
日本も実はスパイ天国みたいな事言われていますけど、敗戦国ってのは悲しいもんですね
で、一周回って911が起きてしまった反省って事で、ハンブルクは現在では結構過剰な監視体制が敷かれており
そのレーダーにこの作品の最重要人物、イッサ・カルポフは引っかかる事になります。
そして調べれば調べるほどコイツは怪しい、という事になる訳なんですが
そこに「ナチの蛮行を繰り返してはならない!」とばかりに人権弁護士のレイチェル・マグアダムズが現れて話がややこしくなります
これは小説版の話ですが、彼女は以前悠長に構えていたらクライアントが目の前で警察に一瞬で連れ去られるという経験をしており
クライアントの扱いにかなり過敏になっています。今回のクライアントであるイッサは【イスラム過激派の可能性有り】という情報が出ますが
彼女は「そんな事より国家権力の方が怖い。奴らはまだナチなのよ!」みたいな感じで、その辺りの事はあまり真剣に考えようとしません
そしてイッサの代理人としてイッサの父が持っていたとされるある銀行のリピッツァナーという口座に預金されている金を
イッサの代わりに引き出すとか引き出さないとかいう、なんだかよく分からない話に巻き込まれる事になります
で、このリピッツァナーというのも説明がややこしいというか、結局のところ話の全貌は明かされずに終わる訳ですが
このウィレム・デフォー、扮するトミー・ブルーという人はスコットランド系で、父親がドイツに移住してきて、銀行業を始めたんですね
映画だとこの銀行は結構デカイ銀行ですけど、小説版だと小さな個人バンクなんですね
スコットランド人が始めた個人銀行って時点で「誰がそんな銀行使うんだ?」という話になる訳ですが
当然、経営には四苦八苦していたらしく、そこに目をつけたのがロシア人のカルポフだったようなんですね
ようは「俺の汚い金を保管しておいてくれれば多少甘い汁を吸わせてやるよ」みたいな取り引きだったのでしょう
そこにイギリスの諜報機関も絡んでいるらしい、みたいなややこしい話があったりもするんですが、そこは無視します
真面目一辺倒であったはずのブルーの父は、仕方が無く彼等の資金を預かる、まぁいわゆるロンダリングに手を染め
銀行業を続ける事が出来た、そしてその金を、カルポフの息子を名乗る謎の人物
イッサ・カルポフが引き落としに来た、という話な訳です
何故ロシア人の金をイスラム教徒のチェチェン人がおろしにきたのか分からないという人もいるでしょうが
それは正しいんです。意味不明なんです。本当に息子かどうかも相当怪しい、全くもって怪しすぎるんですね
そういう男が凄まじい大金をおろしに来て、しかも「父の金は汚い、私はそんな金はいらない」とか意味不明な事を言っている
話しを戻しましょう
イッサが入国した時から彼を張っていたバッハマン達は、イッサの金が預けられているらしい銀行員と接触し、先手を打ち
かつレイチェル・マグアダムズを拉致し、せっせとイッサ包囲網を完成させていきます
しかしイッサはどうにも【コレだ!】という決定的証拠を出してはくれません
考えようによっては「一切何も持たせない」という事がテロリスト達の手口、手法という事なのかもしれませんね
身分証明書とか持ってればそこから色々追跡するんでしょうが、何も分からない相手には何も出来ない、という
で、どうしたもんかなぁ…という感じですが、そうと決まれば作戦変更
もともとバッハマンの本丸はファイサル・アブドゥラ博士。コイツを捕まえるためにイッサを利用しよう、という事になります
イッサはテロリストに金を渡したいのかもしれないが、延々とマークしてきたアブドゥラ博士を経由させれば
イッサがどういう人物であれ、テロリストへの資金の提供は阻止する事が出来るでしょう
なんやかやでこの作戦はベストのように見えますよね。テロさえ阻止出来ればあとはまぁどうにかなる
イッサも引き続きマークし続ければいいわけです
という訳でイッサにはドイツの市民権とパスポートを渡す、という事でレイチェル・マグアダムズも説得完了
イッサという餌を使って、アブドゥラ博士をハメ、バッハマンの計画は見事に成就した!かに思われた矢先
突如としてアメリカ人が急襲
トンビに油揚げをさらわれるが如くアブドゥラ博士とイッサをもろとも連れ去っていってしまい
バッハマンの努力と苦労が一瞬で水疱に帰してしまいました、というような話ですね
で、ここから小説との比較をやっていこうかと思うのですが、まぁコレが結構全然違います
*************************************
まずこのイッサという人物、これが猛烈に印象が違うんですね
映画版は拷問を受け、そこそこハンサムで、非常に内向的で、敬虔なムスリム、という感じで演出されており
映画版の製作者の意図としては、好感を持てるように、というか
「この人本当にテロリストなのかなぁ?実は違うんじゃない?」
と思わせるようなキャラクターになっていると思うんですが、ハッキリ言って小説版は真逆です
なんというか、一昔前のコメディドラマに出てきた変な外国人みたいな描かれ方なんですね
もう完全に、ひとっかけらも信用出来ない
むしろ近くにもしいたら嫌悪感しか感じないだろうな、って感じのキャラクターなんですね
まずそもそもが不法入国者ですから、出自が全く分からないし、聞いてもはぐらかす
話しを聞いているとチェチェン人だチェチェン人だと言う訳ですが、それもどうやらロシアとのハーフで
トルコ、スウェーデン、ロシアの刑務所でそれぞれテロリストとして扱いを受けていて
そして拷問の末に…という注釈は入りますが、自分がイスラム過激派である事を自白している
どうやってハンブルクまで辿り着いて。然るべき情報屋に情報を聞いて、他人の家に潜り込み
人権弁護士を雇う事になったのか良く分からない。何処から逃亡資金が出てきたのか訪ねても説明に矛盾がある
ここまでで十分真っ黒に思えてくる訳ですが他にも胡散臭さ満点で
「なんで拷問を受けたんだ?」とか「なんで刑務所に?」という質問をするとコレがすごくって
「チェチェン人だからですよ!チェチェン人の事皆イジメる!世界中の何処に行ってもイジメられる」
とか相当答えになっていないんですよね。チェチェンってのはイスラムで、まぁロシアに虐められているってのは僕も知ってて
そこに関しては気の毒だなとは思う訳ですけど、この作品はそういうチェチェン人の悲哀とかいう話じゃなくって
現金にして10億円という金を、何の身分証明書も持っていない、ジハーディストの疑いもある不法入国者に渡す渡さないという
そういうような話な訳で「憐れなチェチェン人にお恵みを」で話が通る訳が無いんですよね
映画版と同様に小説版もイッサが結局本当にテロリストなのかどうかというのは最後まで分からないんですけれども
コレだけ状況証拠揃っていて信用するのは不可能だってくらい全然駄目なキャラクターなんですね
ハッキリ言って読んでてどう足掻いても真っ黒にしか見えないし、読んでてマジでムカついて来るんですよね。
こんなの国外追放しろよ、みたいに僕でも思ってしまう感じです
更にコレが極めつけなんですけど、何かにつけて「神の思し召し神の思し召しインシャラーインシャラー」と言う訳ですが
コイツがメッカに向かって祈っているのを見た事が無いし、コーランを平気で床に放り出していたとか
僕もイスラムの戒律なんて良く知りませんけど、どうやらコーランを床に置くみたいなのはありえないっぽいんですね
で、しかも片手で、まぁ普通の本のように扱う、というのもありえないそうです。みなさんも気をつけましょう
つまりまともなムスリムから見るとコイツは絶対にムスリムでも何でも無い。こいつは完全な嘘つきだ、という描写が出てくるんですね
さらにチェチェンってのはイスラム教スンニ派が殆どだという話なんですけど
コイツはスンニ派のモスクとシーア派のモスクの区別が付かない、と
更に言語道断な事に、レイチェル・マグアダムズに対して
「いずれあなたがイスラムに改宗したら僕が結婚して色々教えてあげます」みたいな事をほざく始末
てめぇこの野郎って話ですよね。俺のレイチェルを!みたいな
で、つまりこの小説って、こういう「どう見ても真っ黒にしか見えない男を巡る話」って事になるんですね
読みながら終始「嘘つけこいつ!」みたいな事を思いながらページを進める事になります
特にレイチェルに「結婚してあげます」とかほざくシーンで僕の堪忍袋は完全に切れてしまいましたね
「こんな奴拷問だ!」ってなもんですよ。当然の報いですよ。俺のレイチェルを
ちなみにここまで聞いて「小説は小説、映画は映画でしょ」って感じの人もいるでしょうけど
映画版でもコイツ明らかに偽ムスリムだ、と示されているシーンが実はありまして
ここですね。イスラムはキリスト教以上に偶像崇拝には厳格ですから
金のコーランのブレスレットなんてもっての他。相当ありえないものって事なんですが
敬虔な信者であるイッサはコレを「敬虔な信者であったチェチェン人の母の形見」として肌身放さず持っていた訳です
少なくとも【敬虔なムスリム】では無い、というのは映画、小説共に確定事項と言っていいんですね
まぁ「敬虔なムスリムでは無いならテロリストじゃないんじゃないの?」みたいな話があってややこしいんですけど
もしかしたら金で雇われた本当に訳の分からない人だったのかもしれません
次に我が愛しのレイチェルですが、まぁこの人は映画小説、共に大差無い感じではあるんですが
イッサが大差ある感じに仕上がっているんで、それに引っ張られる感じでかなり厳しいキャラクターになってしまっています
早い話が「この嘘つき野郎がもし本当にテロリストだったらどれくらいの被害が出るのか?」みたいな事を
これっぽっちも考えているように見えないんですよね。左翼って本当にこういう感じなんですかね
原作者のジョン・ル・カレはMI6にいた事があったような人なので
ル・カレから見た人権左翼ってのもこんな感じなんでしょうか。だとしたら僕としてはかなり恐ろしいですけどね
そして銀行員のブルー。映画版だとなんかあんまりパッとしないこの人の役回りなんですが
小説版だとレイチェル・マグアダムズに一目惚れしてしまって
それはまぁ僕も似たようなもんだし、まぁ仕方の無い部分だと思うんですが
それによって色々と厄介な事態に巻き込まれていく結構出番の多い、味わい深いキャラクターだったりしますね
この人はイッサの事を「全くもって全然信用できない」と感じつつもレイチェル可愛さで首を突っ込んでしまった事で
ウルトラ厄介な状況に追い込まれていく訳で
映画版のなんか状況に対処しているだけで精一杯って感じとはまたちょっと違っています
そしてバッハマン
僕はこの映画って実は結構思い入れがあってですね。というのもこのバッハマンを演じたフィリップ・シーモア・ホフマンですが
彼の訃報を聞いたのがこの映画を見た直後だったんですよね。「いやぁ…やっぱフィリップ・シーモア・ホフマンはいい訳者だな」
とか思っていたら薬物中毒で死んだ、みたいな話がニュースで流れて、ちょっと呆然としてしまったんですが
ですのでこのバッハマンというキャラクターとフィリップ・シーモア・ホフマンが強烈に結びついてしまっていたりするんですね
映画のバッハマンは状況をコントロールしていたと思ったら最後の最後にアメリカにオーバーライドされてしまった
気の毒な人って感じに見えますが、小説版はどっちかというと「あれ?あれ?なんかやばいぞ?あれ?どうなってんだ?」と
自分の描いていたシナリオが色んな登場人物の出現によって徐々に徐々に侵食されていく、みたいな
そういうキャラクターになっていますね。あの映画の唐突なラストとは違って
「嫌な予感がする…嫌な予感がするぞ…絶対あいつら何かしてくる。絶対何か企んでる」
ほら~~~~~!
みたいな感じの切迫感が読んでて味わえますね。このクライマックス付近で
不安定な状況に放り込まれたキャラクター達が焦りに焦りまくる、みたいな描写を描くのが
ジョン・ル・カレは好きだったんでしょうかね。裏切りのサーカスでもそういう感じの部分がありましたね
では最後にラストの話しをしましょう。
この作品のラストを最初に僕が見た時
【許される悪はあるのか?問題】っていう、一時期流行った倫理的問題のある種の回答になっているのかな?
と僕は思ったんですね
ドイツの諜報組織が人権とかを最低限に遵守し
「これは悪なのだろうか?許される悪はあるのだろうか?あったとして、この悪は許される悪に分類されるのだろうか?」
などと延々と逡巡していたら、
アメリカが「許される悪?あるに決まってんだろw」と全てをご破産にしていくような展開で
まぁ多分「アメリカってひどいよね」みたいに見ている人が多いんじゃないのかと思っていて
僕も初めて見た時そうでしたし、間違ってはいないんでしょうけど、小説読んでいるとちょっと印象が変わった部分があります
まず映画でもファファっと出てくるこのモアという人なんですけど、この人はドイツの国外諜報担当
まぁようはスパイ組織の右派に当たる人で、そしてバッハマンは左派、あんな感じでも実は極左に当たります
バッハマンが極左というのは相当違和感ある人もいるでしょうが
諜報組織ってのは最低限の愛国心が無ければ務まりませんので、ある程度右っぽく見えるのは仕方が無いんでしょうね
何が言いたいのかというと、この映画は恐らく多くの人が思っているであろう【アメリカとドイツ】という構図というより
【ドイツ内部のアメリカ派とリベラル派】の権力闘争という印象が小説版では強いんですね。
しかも小説版ではここにイギリス諜報部も小悪党みたいな感じで絡んできて結構こんがらがる感じだったりして
ジョン・ル・カレはイギリスの人なので、イギリスのこのゴミみたいな扱いってのはなかなか凄いな…と思う訳なんですけど
つまり我々日本人は自分達を【アメリカのポチ】とか言って結構卑下したりする訳なんですけど
なんの事は無い、世界中の西側諸国は多かれ少なかれアメリカの傘の下で活動していて
最終的にアメリカのオーバーパワーに対抗する術をもっている国なんてのは何処にもありゃしないって事なんですね
アメリカ嫌だアメリカ嫌だって、僕も思ったりするんですけど、結局最後の最後に頼る先はアメリカなんだっていう
で、コレを持って「どっちにしろアメリカが酷いじゃねぇか」ってのも分からない意見じゃない訳ですけど
アメリカの認識としては「アメリカで計画された911がアメリカで起こった」ってのならいざしらず
「ドイツで計画された911がアメリカで起こった」ってのは普通に考えて相当笑えない事態であり
我々が住んでいるこの消費大国日本で、未だに目立ったテロみたいなのが起こっていないってのは
我々の日頃の行い、ってのもあるにはあるんでしょうし、僕もそう思いたいですけど
実際はアメリカが、自業自得とはいえ一手にヘイトを溜め込んでくれているから、という側面もあったりするかもしれない訳です
で、そうなってくるとアメリカとしては
「お前等の怠慢のせいで飛行機に突っ込まれる訳にはいかん」と考えるのはこれはコレで当然と言える訳で
逆に言えば劇中で起こったイッサとアブドゥラ博士の拉致に関しても
まぁ彼等はこれからグアンタナモとかに連れて行かれて、なかなか手酷い拷問を受けたりする事になるのだろうと思われる訳ですが
アメリカからすると「俺達が勝手にヘイト溜めて何が悪いんだ。国家主権?知るかタコ」って理屈は
滅茶苦茶といえば滅茶苦茶ですが、筋が通っていると言えば筋が通っているとも言えるような気が僕はしてしまいました
劇中でバッハマンは人権弁護士のアナベルに対して
「お前等みたいに血を流す覚悟も無い温室育ちのボンボンが偉そうに指図して来んじゃねぇよ。こっちは身体張ってんだ」
みたいな事を言うシーンってのが出てきますけれども
コレは特大ブーメランとしてバッハマンに帰ってくる訳なんですね
「俺達は実際に血を流したんだよ。大した被害も出ていねぇどころかテロリストの温床になっているような国の分際で
俺達に指図すんじゃねぇよ。こちとら万人単位で人死が出てんだよ」っていう
まぁようはそういう「対テロ戦争」ってのは地域、宗教、人権、主権、などが様々に絡み合って
もはや地獄の様相を呈しているという事を教えてくれる名作、名著であると僕は感じました。
僕は相当面白く読めたので、興味ある人は是非ともご自分でも手にとって
誰よりも狙われた男、読んでみたらいかがでしょうか?
それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
