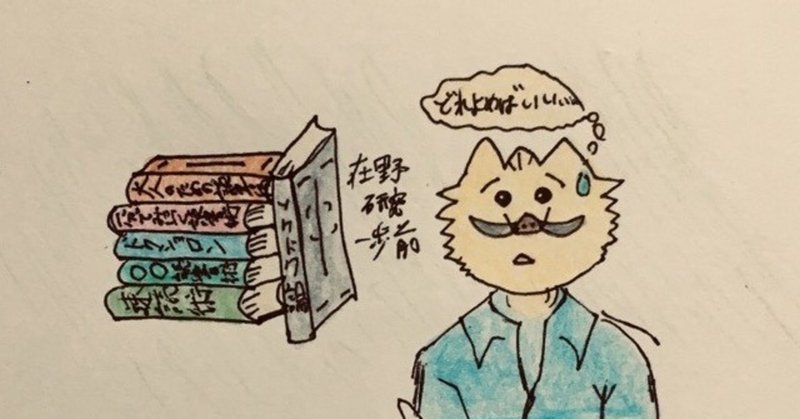
在野研究一歩前(18)「読書論の系譜(第四回):澤柳政太郎編『読書法』(哲学書院、1892)④」
前回に引き続き、澤柳政太郎編『読書法』(哲学書院、1892)の「読書論」について見ていきたい。今回は「第四章」の内容である。
「第四章」(該当ページ:P34~41)↓
●「讀書の第一則に曰く讀書は注意を以てす可しと、此法則たる讀書法の綱領にして之を擧くれは他の小規則は盡く是に從ふものなり、實に此法則は讀書法の金條と稱するも敢て不可なきか如し」(P34)
⇒「読書法」は、その第一則として「読書は注意をもってすべし」があげられる。ぼーっと本を読むのではなくて、意識を集中して本を読むことが、種々の「読書法」を実践していく上での前提条件となる。
●「一時間なりとも充分の注意を以て讀書するときは、一週一月の間数多の書籍を漫讀するよりも其効果尚ほ多しとす」(P35)
⇒「注意」(意識の集中)をもって読書に励むことができれば、たとえその取り組んだ時間が長いとはいえなくても、一週間・一カ月のスパンでぼんやりと数種の本を読むよりかは、充分効果があると言える。
●「或ハ曰く讀書するに當りては常に筆を執りて其要點を抄記すへし、或ハ曰く再三熟讀すへし、或ハ曰く閲讀したる所を以て他人へ講話すへし、或ハ曰く全巻の分解圖を製すへし」(P36)
⇒ここでは、「読書」に取り組む上で、実際に心掛けると良い点が幾つかあげられている。
「常に筆を執りて其要點を抄記」とは、つまり「メモをとる」こと。
「再三熟讀」とは、何度も同じ本を読み直すこと。
「閲讀したる所を以て他人へ講話」とは、読書を通して知り得た情報を、きちんと構成し直して、他の人に分かるよう説明してみること。
「全巻の分解圖を製す」とは、読み終わった一冊の本の内容を「図」にして纏めてみること。
●(読書を趣味とし、面白みを覚えるための方法)
「一、自己の學はんと欲する所の事項を記述する書籍を讀むへし」(P37)
「二、自己の業務と直接間接の関係ある書籍を閲讀すへし」(P37)
「三、確實の目的を以て讀書すへし」(P38)
「四、專讀の書籍を定め置き濫りに變更すへからす」(P40)
「五、閲讀せんとする書籍の順序排列を一定すへし」(P40)
「六、凡そ讀書するに際しては必す是によりて智識を進め利益を得んとの念を想起して亡失せさらしむへし」(P41)
⇒一つ目では、自分が学ぼうとしていることを設定して、それに関連した本を選び読み進めていくことの重要性が示される。つまり「学びたいこと」を設定することが、「読書」に取り組む上では大切になってくるということである。
二つ目では、「自己の業務」=「個々人が日常生活において関わっている仕事や作業」と関連する内容の「書籍」を選択することが勧められている。自身とは一切接点がない内容の書籍よりも、踏まえている基礎知識の割合が高い書籍を選んだ方が読書効率がよく、また読み始めるための「モチベーション」を持ちやすいと言える。
三つ目では、「なぜこの本を読むのか」という何らかの「目的」を意識して、「読書」に励むことの重要性が示されている。
四つ目では、「一、自己の學はんと欲する所の事項を記述する書籍を讀むへし」と関連して、自分の学びたい分野を「自身の専門とする分野」に位置付けて、その分野を無暗に変更しないようにすることが説かれている。
五つ目では、四つ目と繫がる形で、自身の専門とする分野がある程度身についてくるまでは、その分野に関する書籍を集中して読んでいくことが大切であり、他の分野に手を出すべきではない、とする。
六つ目では、「読書」という行為の先には、常に「知識の獲得・発展」「利益の獲得」が意識されているべきである、とする。
以上で、「在野研究一歩前(18)「読書論の系譜(第四回):澤柳政太郎編『読書法』(哲学書院、1892)④」」を終ります。お読み頂きありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
