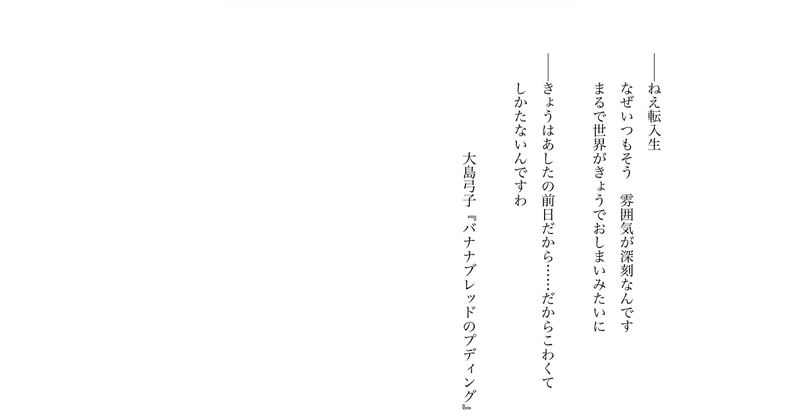
「バナナブレッドのプディング」と川上未映子(その1)〜まずは「春のこわいもの」
書店の新刊棚には、気になる二人の作家の新作が並んでいる。一冊は角田光代、5年ぶりの新作長編「タラント」、もう一冊は川上未映子の「春のこわいもの」である。
先日は第160回芥川賞受賞の砂川文次「ブラックボックス」について書いた。川上未映子は2008年第138回の芥川賞を「乳と卵」で受賞した。私は、この作品を読んだが、「ふーん」という感じで、よく分からなかった。
ところが、翌年出た「ヘブン」が素晴らしく、「あこがれ」そして2年半前の「夏物語」と独特の感性で表現された小説を世に出している。こういう時、芥川賞の選考プロセス・選考委員が才能を見出す能力に感心する。
彼女の2年半ぶりの小説「春のこわいもの」は、短編集だが、個々の作品の長さにはバラツキがある。一方、コロナ禍が始まった頃(なんだか遠い過去のような気もする)を背景としていて、全体に統一感のある空気が流れ、一つの組曲のような作品になっている。
なお、本作は新潮社とAmazonのオーディオブック Audibleの共同制作として書き下ろされ、音声版は昨年夏に先行配信された。私は、書籍が刊行された後、Audibleを聴き、その後、書籍版を読んだ。
全編に漂うのは不安感であり、何か恐ろしいことが起こりそうな予感である。短い3つの小説「青かける青」、「花瓶」そして「淋しくなったら電話をかけて」が、そうしたトーンを醸成する。
序曲のような「青かける青」の後に続く、「あなたの鼻がもう少し高ければ」は、この短編集の中で最もエネルギーを感じる一編である。登場する女性、私の位置から最も遠い位置にいるであろう彼女らが見据える未来は、ある意味はっきりしていて、彼女らはそれに向かって力を使う。しかし、その行き着く先には何があるのだろう。
不思議な余韻を残して閉じられる「ブルーインク」に続いて、本書のコアとなる「娘について」が始まる。ここには、作者の分身のような作家志望の女性が登場する。彼女とその友人、そして友人の母の話である。コロナ禍により、誤魔化していた現実を直視せざるを得なくなった人も多いだろう。あるいは、忘れていた過去を呼び覚ますきっかけにもなっただろう。
作家という仕事は、<自粛要請が出ても、わたし個人の生活には大きな変化が見られなかった>。仕事のキャンセルもない、<でもそれは、わたしの仕事にその価値があるからというわけではまったくなく、べつに書かれても書かれなくてもどちらでもいいというか、出しても出さなくてもどこにも何にも影響を与えないものだからだ>と、作家志望のよしえは考える。
そして彼女は邪悪な過去に向き合わされる。
川上未映子は書かざるを得なかった。コロナ禍によって産み出されたわけではなく、感染症に浮かび出された、ずっとあった現実を。そんな風に私は感じた

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
