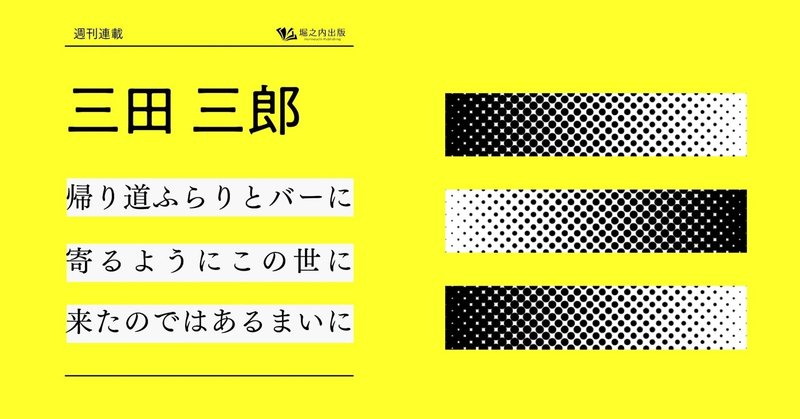
【三田三郎連載】#004:何もかも分からなくなりたい
※こちらのnoteは三田三郎さんの週刊連載「帰り道ふらりとバーに寄るようにこの世に来たのではあるまいに」の第四回です。
他の記事はこちらから。
何もかも分からなくなりたい
私が酒を飲む理由は数多く存在するが、その一つに「何もかも分からなくなりたいから」というのがある。別に私は、社会の構造や他人の心情が分かりすぎて困っているというわけではなく、むしろそのあたりについては鈍感な方だと思うが、それでも色々と中途半端に物事が分かったり、分かった気になったりするのが不快でならないのだ。その不快感に対処するため、大量に酒を飲んで泥酔することによって、一時的に自らを何もかも分からない状態へ導くという、強硬手段を採用しているのである。
泥酔状態に限らず、私は昔から何もかも分からなくなるのが好きだった。例えば、高校生のときの話である。数学の授業中、ひどい寝不足だったのか、早い段階で居眠りをしてしまった。目が覚めたときには授業がかなり進んでいて、黒板一面に書かれた数式が一つたりとも理解できないという事態に陥っていた。その瞬間、私は焦るどころか、なぜかその分からなさに恍惚としたのである。それからというもの、私はしばしば数学の時間に居眠りをして、何もかも分からなくなることの愉楽に浸るようになった。目が覚めたときに授業内容が理解できると、安堵するどころか悔しさを覚えるほどに、その陶酔感に病みつきとなった。
また、英語のリスニング試験も私の大好物だった。私は英語の聞き取りが非常に不得手で、ほとんどの言葉が耳から入ってはそのまま反対の耳から出るような有様だったので、何もかも分からなくなることの快楽を存分に味わえたのである。学校の試験ではリスニングの時間が短くて不満だったが、TOEICの試験を受けたときは、45分間にわたって何もかも分からない状態が続いたため、もう少しで忘我の境地に達するのではないかというほどに快楽を堪能することができた。
そんな私が大人になって飲酒にのめり込んだのは必然であるように思える。数学の授業も英語のリスニング試験も、大人になればなかなか経験できるものではないが、酒をたくさん飲みさえすればいつでも、酔っ払って何もかも分からなくなれるからだ。極限まで泥酔すれば、自分が何者なのかも、今が何時なのかも、ここがどこなのかも、一緒にいるのが誰なのかも、一切合切が不明になる。何もかも分からなくなりたければ、酒を飲むのが一番手っ取り早いのである。
そういえば、私は以前に京都で飲み過ぎて泥酔し、何もかも分からなくなった結果、神戸の自宅までタクシーで帰ってしまったことがある。後で聞いたところによると、とんでもない金額になるからやめておけという友人の制止を振り切ってタクシーに乗り込んだらしい。どうやら私は、自宅の近くで飲んでいると錯覚していたようだ。そのときのことはほとんど覚えていないが、どうしてワンメーターで帰れるのにタクシーに乗ってはいけないのかと、友人の制止を訝しんだ記憶はうっすらとある。翌朝目が覚めて、京都からタクシーで帰宅したことに気付いた私は、冷や汗をかきながらスマートフォンで想定料金を調べ、その金額を見て膝から崩れ落ちたのだが、そのあたりについては何も分からないままの方がよかった。やはり何かが分かってしまうというのは不快感の源泉である。願わくはずっと何もかも分からない状態でありたいものだ。
次会っても顔は覚えていないから知恵の輪の片割れを手渡す 三田三郎
著者プロフィール
1990年、兵庫県生まれ。短歌を作ったり酒を飲んだりして暮らしています。歌集に『もうちょっと生きる』(風詠社、2018年)、『鬼と踊る』(左右社、2021年)。好きな芋焼酎は「明るい農村」、好きなウィスキーは「ジェムソン」。
X(旧Twitter):@saburo124
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
