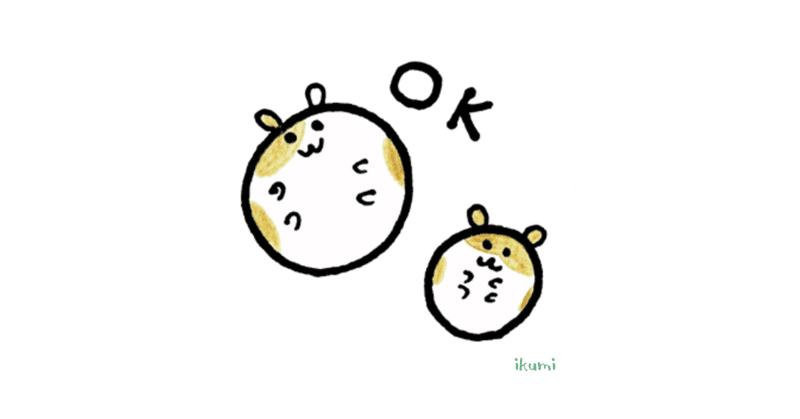
#38僕もあなたもみんなOK牧場!~交流分析の真髄はめちゃくちゃシンプル~
こんにちは、人馬交流分析士のりょーじ(@Horse Value)です。人馬交流分析って何?りょーじって誰?それをやって何になるの?という疑問への答えは#1をお読みください!
#31~33と#35~37では、人と馬との交流分析ではなく、人と人との交流分析についてお話してきました。この「交流分析」というのは心理学の1つの手法なんでしたね。今日は#31~33と#35~37の続きなので、まだ読んでないよ、という人は#31から読んでください!
馬と人との交流体験から人々が役に立つことをお伝えするというのが僕の役目なのですが、今回も含めて数回かけて、この心理学的手法「交流分析」についてお話ししています。
というのも、僕の経験に基づく解説だけではどうしても学びがぼんやりとしてしまいがちだからです。#29まででお話してきたH.O.R.S.E.理論は僕が馬との交流の中で発見した「人間本来のあり方」なんですが、「そう在れたらいいけどどうしたらいいか分からない」となりがちで、どうも具体的な提案に欠けてしまいます。
でも、世の中には、人と人との交流を細かく分析することを通じて「人間とはこういう在り方」なのだ、というのを発見し、在り方だけではなく行動にまで落とし込んだ学問があるんです。それが心理学の「交流分析」です。
じゃあ、それとの一致を見ていかない手はないよね、ということで「交流分析」をまず皆さんにご紹介したいわけです。
さて、前回は、自分がどんな自我状態でいることが多いか、という「自我状態の傾向」を知ることのできる「エゴグラム」という手法を紹介しました。
その中で、自分の見る自分のグラフと他人が見る自分のグラフが同じではないことがあるよ、というお話をしました。今回はその理由をお話しします。
今日のラインナップはこちら!
・ライフポジション~OKか、OKじゃないか~
・自我状態とライフポジション
・僕もあなたもOK牧場!
このライフポジション、とかOKとかどういうことでしょうか。自我状態とどう関係するのでしょうか。今日も丁寧に説明していきます。早速行きましょう!
ライフポジション~OKか、OKじゃないか~
「ライフポジションとは自分、そして他者に対してどう感じ、どんな結論を下しているのかという基本的な構えのことです。」
と教科書的に言われても中々分からないですよね。そこで分かりやすくするために出てくる言葉が「OK/not OK」です。余計分からなくなりましたね。大丈夫、しっかり説明していきます。
「あなたはOKですか?」と言われてあなたはどう反応するでしょう?
言葉を変えると「あなたは自分を自分でOKだと思いますか?」という質問です。

これってめちゃくちゃ深い質問ですよね。でも直感的にOKです!と答えられる人が「私はOK(I’m OK)」のポジションにいる人です。
これは「自分が自分をどう捉えているのか」という質問です。OK、と思える人は「自分はこのまま、ありのままで良い!」と思うことができている人です。
「あなたの周りの人はOKですか?」と聞かれたらどうでしょう?
なかなか自信を持って「OKです!」と言える人は少ないです。

「この人はOKだけど、あの人はOKじゃない。」だから人による、というかもしれません。「みんな本来は悪い人なんだ!」という考えを持っている人もいるかもしれません。
そんな人は「You’re not OK」のポジションです。
OK/not OKの意味が分かってきましたかね?自分と相手について、どう感じ、(OKかnot OKかを)結論づけているのかがライフポジションでした。つまり、ライフポジションには下の図のような4つのパターンがあるんです。

図の中の言葉は参考程度にしてください。とにかく、「I’m OK」の人は「自分は自分のままでOKなんだ!」と思えている人で、思えていない人が「I’m not OK」です。そして、「You’re OK」の人は「どんな人もその人のままでOKだ!」と思えている人でそれ以外の人は「You’re not OK」である、ということを覚えてください。
ざっくり言うと、自分に優しく、相手に厳しい人は「I’m OK, You’re not OK」です。逆に自己肯定感が低くて周りの人はすごい人ばかりだと思っている人は「I’m not OK, You’re OK」です。
自我状態とライフポジション
さて、この考え方は「交流分析」の中でどのような役割を持っているのでしょうか。実は自我状態を説明する上で、ライフポジションはとても大事な考え方です。
自我状態の傾向を表した図であるエゴグラムについて前回お話ししました。
もし、エゴグラムが全く同じグラフの形の人がいたとします。でも、その2人は似ても似つかぬ性格です。どういうことでしょうか?
こんな疑問にお答えするのが、ライフポジションです。
分かりやすい例でお話しします。
今あなたの目の前にいる2人は両者ともCP(批判的親)が高いエゴグラムのグラフ(他の要素もとても似ているグラフ)で、「今ここ」でもCPであるとします。
でも2人は全く違う感じがします。1人はとても攻撃的で、1人はとても礼儀正しいです。2人とも「ルールを大切にする」という同じ自我状態を持って行動しているはず(そしてその行動も確かにCPの行動)です。
この2人が同じ自我状態で存在しているとは信じられない!この理論は間違っている!ということではないのです。そこでライフポジションが登場します。攻撃的な人は「I’m OK, You're not OK」で、礼儀正しい人は「I’m not OK, You’re OK」だとします。
つまり、CPの態度で「ルールを守らなくてはいけない!」の向かう先と表れ方がライフポジションによって変わるのです。

「I’m OK, You're not OK」の人にとっては「自分はちゃんとした人で、周りの人はルールを守らなければいけない人達なのだ!」という感じです。
逆に「I’m not OK, You’re OK」の人にとっては「周りはしっかりした人ばかりだから、自分はいつもしっかりルールを守らなければいけない。」という感じです。
同じ自我状態なのにこのように変わるのはとても面白いですね。
実は、自我状態の表れ方には肯定的に働く場合と、否定的に働く場合があるのでした。その肯定・否定的な表れ方はこのライフポジションに大きく関連します。OKであれば肯定的に、not OKであれば否定的に表れることが多くなる、というわけです。
どの自我状態でいるか、という良し悪しはないのですが、どのライフポジションにいるべきか、という良し悪しはあります。「交流分析」という学問においては「I’m OK, You’re OK」に留まり続けることが大事、と言われています。
僕もあなたもOK牧場!
今日の題名でもあったこの言葉。交流分析の発する最も強いメッセージです。自分もあなたもOKのライフポジションのことを指しています。
そんな在り方でいられたら素晴らしいですよね。

ただ、それって難しいです。自責の念にかられたり、誰かを責めたりせずに生きられるようになること、それが理想だと分かっているけど、それが難しいんです。
実は、エゴグラムを作った時に、自分で思っている自分のグラフと他者から見た自分のグラフとが違う、というのもこのライフポジションによって起こります。
例えば、僕は自分自身ではCP(批判的親)>NP(養育的親)としていました。でも、フォームで答えたものではCP(批判的親)<NP(養育的親)でした。
ここで何が起きているかというと、自分自身に対して批判的で常に懐疑的な自分がいるんだけど、他者に対してはそうではない、ということなんです。これはまさに「I’m not OK, You’re OK」のライフポジションにいることが多い、そういうスタンスで物事を見ている、ということです。
交流分析においてそんな自分を責めるポジションにいるということは良くない、とされています。常に自分に厳しく追い込むことは大切ですが、それは「ありのままの僕」を認めないということでもあります。

さて、理想の「I’m OK, You’re OK」というポジションでいるにはどうしたら良いでしょうか。
実は、大切なことは「自我状態について知る、そして自分について知る」ことです。
というのも、誰もが持っている自我状態のパターンについて知れば誰かの発言や仕草も冷静に、当たり前のものとして受け入れられるようになります。これが「You’re OK」への第一歩です。あなたにとって誰かの在り方は理解可能なものとなるからです。
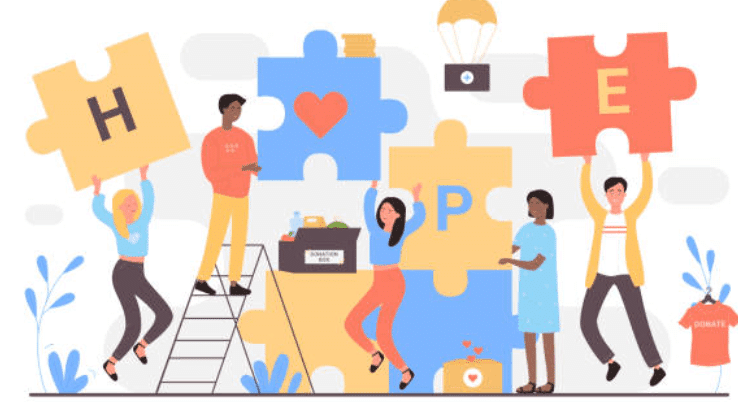
それは自分についても同じです
そして、自分がどのようにいるか、ということをエゴグラムや自分での振り返り、周りの人からのフィードバックを通じて知ることが「I’m OK」への第一歩です。自分を知らなければ漠然と自分を疑い続けることになります。
もし、自分を知ることができれば、それはつまり自分がどう変わりたいかも知ることができる、ということです。どんな自我状態でいることが多いかの傾向は、「行動」で変えられるんでしたね?つまり、自分を知ることが自分の好きな(I’m OK)な自分になる第一歩なのです。
自分と相手の自我状態を知り交流を自分にとって理解可能なものにする。
そして、それによって自分も相手も当たり前に変化し続けると信じる。
だから、どんなときも「I’m OK, You’re OK」でいられる。
今日覚えてほしいことはこの3つの文章です。これが交流分析の真髄です。
交流分析について解説していくのは今日で一旦区切りとして、次回からはまた馬との体験、そしてH.O.R.S.E.理論にお話を戻していきます。
鋭い人ならH.O.R.S.E.理論と交流分析がものすごく近いことに気づいてもらえたと思います。この2つが繋がっていってより理解しやすくなっていくのを楽しみにしてください!
明日も一日頑張りましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
