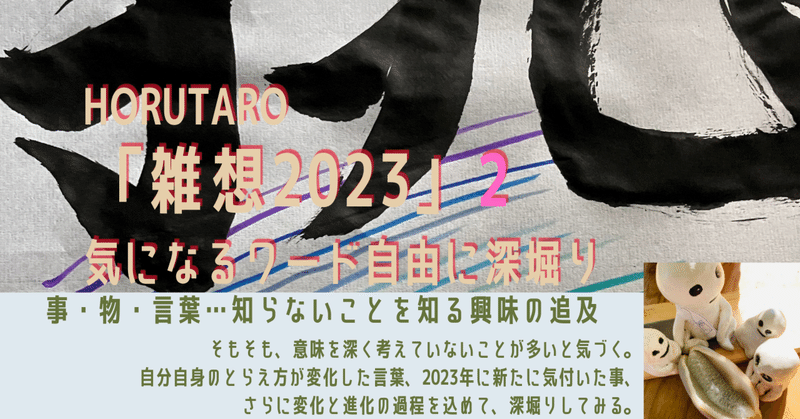
「雑想2023」-2-タイパの雑想
コスパそしてタイパと、いかに短時間で効率よく、業績、評価、知識等を得ようとする流れになっている。
情報量が多い中、短時間でいかに理解し、価値を見出し、業績を残すことだけになっていないだろうか?と、何か引っかかる「モヤっと」がある。
自然や空の写真は相変わらずクオリティは目指さず、適当に良い加減・好い加減。おまけに文章も好い加減のHORUTAROです。
「雑想2023」として、インプットからのアウトプットまでの記録にしていくために残していきます。
自由に考えてイメージをそのままなので、「雑」です。
思考が行ったり来たりの「雑」感覚満載で綴ります。
折角なので、タイムパフォーマンスの意味を知ろうとしたとき以下の記事を知った
「Z世代はなぜ時間があるのに時短を求める?「タイパ消費」の実態」
久保田進彦氏:青山学院大学経営学部マーケティング学科教授。
真島加代:清談社
Z世代での「タイパ消費」について、新しい気付きになった。
世代が異なることでタイパとの認識「時間の消費感覚」が違うようだ。
Z世代ではリキッド消費という消費スタイル傾向があり、その逆としてソリッド消費がある。後者では50代ぐらいから、ソリッド消費の傾向があるということだ。
自分の中での瞬間の楽しみ方、価値のとらえ方、物・事・場等へのリキッド消費という感覚を知ることが大切ではないだろうか。
単純にタイパという言葉にもやっと。
流れのままに流した情報だけで「納得」していないだろうか、反対に「抵抗や反発」、さらに「無関心」になっていないだろうか。
そして、自分自身はどうだろうか?
タイパも時に必要なことだと思っているが、意味を理解してタイパと発言しているか…
そもそも、リキッド消費ばかりでいる事ができるのだろうか。
私もリキッド消費やソリッド消費を適当に行き来しているなと思っている。
消費する行動としてはなんとなく理解できる。
別の記事では、
タイパ記事はnoteでもよく出てくる言葉なので、検索すると数が多い。
そこから、目についた以下の記事を読んでみた。
知り得たい情報は知りたいと思う事、知る行動時間が無限ではない。
情報において、「どこまで」「どのように」「どうしたい」情報が必要かを考えての行動をしているだろうか?
タイパ意識であれば、自分の中で必要な事を、自分の中でふるい分け、自分の最良の情報として取り込めるかもしれないと、その方が必要な気がしてきた。
しかし、気を付ける事として、「自分自身が興味があること」だけにしない事を限りなく意識していないと、情報の偏りが起きる。
タイパ=「短時間」を考えてしまった。
短時間で効率よく情報を知り、処理していこうとすることを続けることで、判断に要する時間「隙間時間」はどうするのか。
以前も紹介したと思うが、思い出す本が「ファスト&スロー」。
この本では、早い思考、遅い思考があると説明している。
タイパを意識しながら、短時間で自分の思考は何をしているのだろうか?
経験も知識も感覚もないことをタイパ意識で受け止め解釈することで、自分の変化や行動がどうなるか。
できるのだろうか
今までの私にはない思考で、知識を得るには、文字(見る)・音(聴く聞く)・行動(動く)が大まかにあるけれど、そこで時短でできることと言えば、「見る」「聞く」になる
書籍の文字を追って「字を読む」ことは、速読をしないとタイパにならない気がする。
文字を早く読み理解するには、よほどの速読体得者じゃないかと思ってしまった。ネットにしても文字を読むことに時間を要する。
(ネットでは1ページ内の全テキストを読んでおらず、瞬時にエリアごとに見て、重要なキーワードのみ読むという状態もあると、どこかの研究があったような…)
紙書籍の速読はできないHORUTAROです。
動画だったら、視覚から入るので理解できそう。
2倍速に音声も加わり、ざっくり理解はできそうだ。
(やっぱり2倍速は無理だった(笑))
次に、音声書籍、朗読データを聴くことで、2倍速で聴くことにする。
今では時々、他の作業をしながら聞くことがある。
朗読速度は、アプリは2倍速までの設定が多く、試しに最速2倍速で聴いたが思考が間に合わず理解不能。
さらに、「聴こうと意識」集中するため、なんだか疲れる。
「疲れる」ということで聴くことが楽しくない。精神的に疲れているわりには内容の理解がないので2倍速拝聴は中止した。
音にしろ、動画にしろ、速度に慣れることも必要で、聴き始めは速度を変えつつ調整、ある程度理解でき、疲労感のない限界スピードが「1.6倍速」だった(1.5倍速が落ち着く速度)。
音声で聴いていくうえで気を付けることもあり、図表が多い場合は、先に資料を見ておくか、聴きつつ資料を都度見るか、紙書籍を買って読み直す、という方法もある
音声で「図○○参照」と聴いても図の内容がわからないな。
図まで理解することはさておき、音で聴くことは数多くの書籍の理解に私にとっては比較的な進化と感じている。
どうしても紙書籍でじっくり読み理解したいときは、本を手に入れることにした。
書籍を読むことに抵抗があったことは、今まで紙書籍(漫画は多い(笑))を読まないことも原因があるようで、速読せず、1文字1単語1文章ごとに理解しようとして読書時間に隙間時間ではなくなってくる。
(途中で寝るというどうしようもない結果…あるあるです(笑))
タイパからそれてしまった。
タイパで常に過ごしていこうとすると、早い思考への判断は経験や知識が大切であり(本能的判断は別)、逆に、無意識の意識で情報を受け取った時、タイパ思考と思いつつも、ゆっくりと考える時間(遅い思考)があると思った。
タイパへの処理対応の理解
常に「タイパ」でいる事が、自慢・自信・能力というステータスにならないように、判断の処理能力が早いことがよい事であると、勘違いしないように、「遅い思考」の中で自分自身の思考パターンを理解することで、自分の中の状態で、タイムパフォーマンスが上がる(時短と効果を得ること)が何か、それはどういう時か、が「タイパ」と表現できることになるかが実感できるようだ。
タイパに意識する
言葉の響き、かっこいい感覚でタイパ意識しているときは、何かに追われていないかな。
穏やかになる気持ちを取り戻して、時短と効果が必要か「遅い思考」で考えてみよう。
慌てて過ごさなくてもいいんだよねって、思ってしまった。
私は私。
では。
ーー読者様へおねがい--
あくまでも、私個人の投稿時点での認識・感覚での表現です
できる限り正確な情報での文章にしようと思いますが、認識違いや事実が異なる場合もあります。
note読者様の新しい気付き等、ご意見等あれば、コメントを頂けますと大変うれしいです。
私自身も、今後のかかわりや学びの中で成長し、新しい気づきで変化していくような気がしています。
後日、誤記・誤認識等あれば、発見次第修正分を本文へ追記します。
あなたのサポーで、好い加減、良い加減をひたむきに続けます!ひと息ほっとなりますように!
