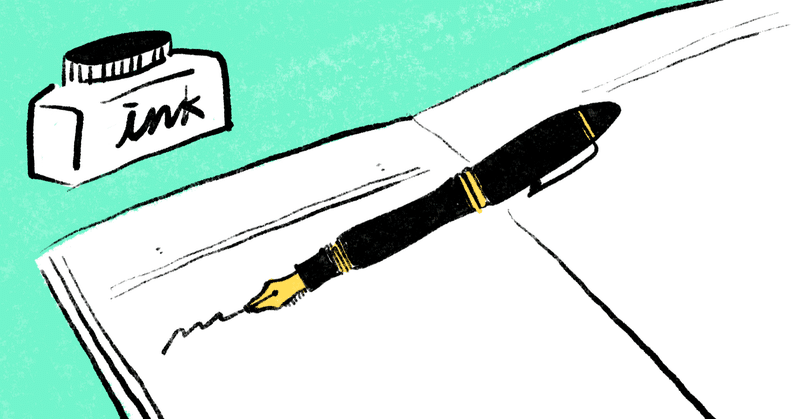
「随筆」ということば
「随筆」、あえて読み下すならば、「筆の随に」「筆に随う」とでもなろうか。
私は、この言葉がとても好きだ。どうしようもないくらいに。だから、「随筆」ということばについて、少し考えてみたい。
「筆に随う」ということは、すなわち「何を書くか決めないままに文を書く」ということだ。つまり、「随筆」とは、用意しておいた「既製品」としての文章を筆を使って紙に書き起こす作業ではない。「いま」考えたことを、「いま」紙に書く。これが「随筆」ということばの意味だろう。
脳内で論理をくみ上げた文章を書く、ということが必要な場面はもちろんある。しかし、それはしばしば退屈で、没刺激的で、心がときめかないものでもある。この原因は、筆を文字を書くためだけの「道具」として扱っているからではないか。
随筆はそうではない。随筆にとって、筆は単なる道具ではなく、むしろその営みの中心となる存在である。文を書く人は、筆に自分自身を仮託して何ものかを表現する。つまり、「筆に随う」ということは、「自分自身に随う」ということでもあるのだ。筆の持つ魔力によって、自分自身が明らかになっていくと言ってもいい。
また、随筆にはもう一つ大事な側面がある。それは一言でいうと、「双方向性」だ。
筆を持ち、紙に文字を書き連ねる。この一文字一文字を書いているとき、もしくは一旦筆を止めたとき、私はその自分がさっきまで書いてきた文字からの訴えを目にする。
今まで私が書いてきた文の中には、「その時自分が考えていたこと(≒過去の自分)」が宿っている。それを少し後の自分、すなわち今の自分が見たとき、それは図らずも客観的な目線になり、私に重要な啓示を与えてくれることさえある。そして、過去の自分が書いた文から受け取ったメッセージに応えるようにして、私の思考は次々に変化し、書く内容も変わっていく。
これが「随筆の双方向性」の正体だ。考える➡書く➡考える➡書く➡……ではなく、書く➡見る➡気づく➡考える➡書く➡……という過程を経て、私の思考はどんどん成長していく。「考えてから書く」のではなく、「書くことによって考えを変える」のだ。
もう一つだけ、言っておきたいことがある。さっきから筆だ筆だと言っているが、パソコンやスマホなどの技術が生活に完全に組み込まれた今、筆で何かものを書くということはほんとうに少なくなっている。両者には、どのような違いがあるのだろうか。
筆によって紙を彫っていくという点で、随筆はきわめて物質的、実存的な営みである。言い換えると、そこには確固たる「重み」がある。容易には消しえない、力強い存在がそこにはある。しかし、スマホで文字を打つとき、そこには物質的なものはほとんどない。あるのは「スマホ」という電子機器だけで、現れる文字はデジタルな空間に閉じ込められている。
こう比べてみると、筆で書かれた文字と、スマホに表示された文字との差は歴然だ。そこには計り知れない質的な断絶が横たわっている。いくらスマホで表示される文字が筆で書かれる文字に似ていようと、その深淵を飛び越えることは絶対にできない。
筆によって現実世界と交渉関係を結ぶとき、そこには緊張が生まれる。原研哉が書道を「後戻りできない不可逆性への跳躍」と表現したように、随筆という営為には、書道ほどの不可逆性は含まれていないにしろ、「びっしりと聴衆で埋まり、静まり返ったコンサートホールで、ソロ演奏のバイオリニストが最初の一音を発するときのような緊張」をもたらす力があるのだ。この緊張こそが、簡単に書いては消し、書いては消しを繰り返せる電子空間における「記述」との大きな差異である。両者の「質的な断絶」というのは、この一文字一文字の重みの違いに端を発するのだろう。
ここまでだらだらと随筆のことを語ってきたが、皮肉なことに、私は今この文章をパソコンで打っている。本当は、シャープペンシル(または万年筆)をもち、文字たちの声に耳を傾けたいし、最初の一文字を書くまでのあの何ともいえない心のざわめきを感じたい。でも、悲しいかな、この文章をあなたに読んでもらうためには、私はこうするよりほかなかったのだ。
「画面に表示される文字」という完全に均質化し個性を失った文字、しかしその一方で広く普遍性を持ちえたデジタル世界におけるメディアとしての文字。一長一短だが、この文章を読んでくれたあなたがいたということは、私が「指の随に」打ち込んだこの文章に、少なくともそれだけの意味があったということではないだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
